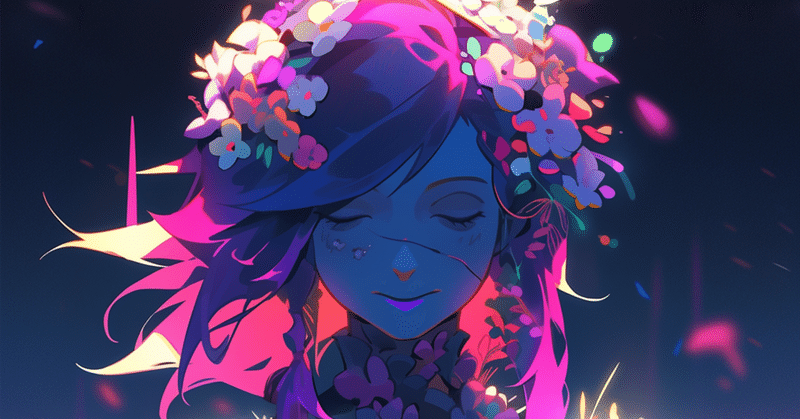
悪霊を追い出せ!―福音派の危機を克服するために(1992/6/1)/奥山実【読書ノート】

「悪霊はいない」という考えは非聖書的であり、サタンの罠に見事にはまっている者の考えである。著者がインドネシア宣教師時代の豊富な体験をふまえ、実践と理論の両面から悪霊の追い出しをとらえる。
はじめに
最近、悪霊の問題について、電話や手紙での問い合わせが実に多い。この文章を書く直前にも、東京から自動車ではるばるやってきた三人の兄弟姉妹たちに対しての奉仕を終えたところである。
この人たちは、クリスチャンのご夫妻とその夫人の妹さんであった。妹さんは宮城県のある福音派のA教会の会員なのであるが、何年にもわたって、日曜日の礼拝に出席するたびに、必ず頭痛がする、また時に吐き気をともなう。何と聖日毎に必ず頭痛がするのである。それも礼拝の最中に。
この場合、月並みな考えで「ああそれは教会牧師からのプレッシャーだろう」などと言う素人判断は誤りである。彼女は教会も牧師も愛しているのだ。精神科医にまで相談したが、理由がわからない。
クリスチャン・ホームに生まれた彼女は幼い頃から日曜学校に通い、主イエスを信じ、中学生のときに受洗した。しかしほどなく右のような状態になってしまった。彼女のお姉さんは嫁いで東京に行き、夫と二人である福音派のB教会に通っているのだが、私がある教会で説教した悪霊についての説教をテープで聞いたとき「妹のケースはまさに悪霊だ」とわかったそうだ。
と言うのは、妹さんはオカルト関係の本が大好きで、たくさんのその種の本を買い集め読んでいたこと、また心霊体験などがあることなどを、妹さんから聞いたことを思い出したからである。精神科医の説明で納得がいかなかったが、今やその理由がはっきりとわかったのである。
そこですぐに所属している東京のB教会の牧師に「先生、妹がへんな具合になる理由がわかりました。テープを聞いて、悪霊だとわかりました」と言ったら、「悪霊などいないのでは――」と言うような歯切れの悪い返事であった。しかし、とにかく妹を救いたいと私に電話をして来たのである。そこで私は「妹さんが所属している宮城県のA教会の牧師に、率直に話して、妹さんが「礼拝のとき、頭痛がするのは、悪霊が原因とわかりましたので、奥山牧師のところへ連れて行って、見てもらいたいのですが、いいでしょうか」と相談するように」と答えた。そして、すぐに許しを得て、私のところへやって来たというわけである。
そのときその妹さんは、すでに自分がどのようなオカルトをやったのか、何とメモ用紙四枚にわたるオカルトの数々、幽体離脱の体験まで書いてきた。知らぬは大人ばかりなり、子どもたちが今や、オカルトの犠牲になっている。重症になって来ると、誰がみてもおかしな行動をするようになり、精神病院に入れても治らない。精神科医の知らない原因だからである。彼女の場合、幻聴や幻覚が現われている。まさに危機一髪あった。いま彼女はきれいにされて、頭痛も起こらず礼拝に出席している。普通の精神病と悪霊による場合の差については、本文の第二章にあるのでよく読んでいただきたい。
さて、それにしても、「悪霊などいない」と言う考えはどこから来たのであろうか。聖書をまともに信じてないリベラルならまだしも福音派の牧師、聖書信仰者にかなりいるのであるからどうにもならない。これらのことについての学問的、神学的アプローチに興味のある方は「第二部」をよく読んでいただきたい。
それにしても、「サタンは認めても、悪霊は認めない」と言う変な神学はどこから来たのであろうか。実は悪霊については学問の世界からの誤った情報によるものである。アジアやアフリカの未開の人々が山にも川にも、木や石にも悪霊が住んでいると信じて、恐れおののいているのは、無知から来るもので、科学が進歩すればひとりでに消滅するもの、悪霊などもともと存在しなかったことがわかるはずだ、と言うものである。
しかしこれは学者たちが、ものの見事にサタンの罠にはまったのである。
つまりそれがサタンのやり口なのである。聖書は明らかに「終末」を警告している。そのときサタンは、この聖書の終末論を人々の目から隠すために、種々の「偽りの終末論」を人々に見せるのである。
終戦直後、璽皇尊(璽光尊じこうそん)という変な教祖(長岡良子)が出現して、信仰宗教を起こし、数々の有名人も参加したが、「○月○日に東京に大災害が来る。世の終わりじゃ」と終末を告げたのである。当時、いまの千代の富士よりも勇名をはせた名横綱の双葉山までが、防空ずきんをかぶって大騒ぎしたのである。しかし、そんなことは起こらなかった。これを見て人々は、「終末なんて馬鹿らしい」と終末論の全面否定となり、聖書の終末論まで否定するようになるのである。これがサタンの罠である。
悪霊も同じこと、未開の人々が、何でもかんでも悪霊と言うので、悪霊の全面否定となるのである。そして、そのような考えが神学にまで侵入して、「悪霊なぞいない」と言う神学をつくりあげるのである。これがサタンの罠である。学問々々などと言って、聖書もよく読まないで、かたよった神学書ばかり読んでいると非聖書的になるのである。もし「悪霊つき」と言うのが、「精神病の表現にすぎない」などとリベラルと同じようなことを主張するなら、「使徒の働き」一六章一六~一九節をどのように解釈するのであろうか。聖書信仰者であるならば、まともに聖書を読んでいただきたい。
パウロとシラスがピリピの町に行ったとき、占いがよく当たる女がいて、ある一団の男たちに利用され、男どもは「多くの利益を得」ていたのである。この女の占いが当たらなければ、客はこない。当たるので大儲けしていたのである。なぜこの女の占いは、よく当たるのか、「占いの霊」につかれていたからであると聖書は明らかにしている(一六節)。このように占いは当たるのである。もし占いが、全然いいかげんなものなら、とうの昔に姿を消している。もちろん、当たらないのもある。しかし当たる者がいるから困るのある。そのあたる占いは恐ろしい。「占いの霊」つまり悪霊によるからである。だからこそ占いは罪なのである(申命記一八・一〇~一二)。
主イエスが地上に来られたとき、ユダヤ人たちは、主イエスをせいぜい宗教教師(ラビ)、あるいは預言者の一人ぐらいに思っていたが「悪霊につかれた者」たちは主イエスを見抜いて「あなたは神の聖者(マルコー・二四)いと高き神の子(マルコ五・七)」と呼んだのである。そのとき主イエスは「黙れ(マルコー・二五)」と口を封じられた。そのときがまだ来ていなかったからである。だからこそマルコの福音書一章三四節には「悪霊どもがものを言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである」とあるのだ。
一般のユダヤ人たちが主イエスの本当の姿を知らないときに、悪霊つきたちはすでに主イエスをよく知っていたのである。これが霊の力(悪い意味での)である。このことがわからないと使徒の働き一六章一七節は解釈出来ないのある。なんとこの女占い師は、パウロとシラスを見抜いたのである。
「この人たちは、いと高き神のしもべたちで、救いの道をあなたがたに宣べ伝えている人たちです」と叫んだのだ。まさに正しくパウロとシラスを言い当てたのである。単なる精神病患者が、どうしてこのようなことが出来ようか。
聖書の言う通りこの女は「占いの霊」につかれていたのでパウロを見抜いたのである。悪霊つきが主イエスを見抜いたのと同じである。悪霊どもが「イエスをよく知っていた」(マルコー・二四)ように、悪霊はパウロとシラスをよく知っていたのである(使徒一六・一七)。
そこでパウロとシラスは、主イエスの御名によって、その悪霊を女から追い出した(一八節)。「即座に、霊は出て行った」のである。つまり「占いの霊」が出て行ったのである。そうすれば誰でもわかることだが、当然に占いは当たらなくなるのである。
だから聖書は言う「彼女の主人たちは、もうける望みがなくなった」(一九節)のである。だからこそ、男どもは怒ってパウロとシラスを捕らえたのだ。
これ以外の解釈が出来るであろうか。もしこの女が単なる精神病患者、気違い女とするなら、男どもが大儲け出来るわけがない。パウロとシラスが逮捕されることもない。聖書の記述を曲解する以外に手はないのだ。
「悪霊はいない」と言う考えは、非聖書的であり、サタンの罠に見事にはまっているあわれな者の考えである。もっと学問的に言うなら一九世紀の唯物論、進化思想の誤った奥行きのない狭い世界観の影響によるものである。
今やエレクトロニクス、ハイテク産業の基礎となっている量子力学の主流(コペンハーゲン学派に由来する)は、原子を構成する素粒子の振る舞いに、人間の「意識」が多大の影響を与えることから、「意識」とは何かと言うことで、哲学者、宗教家の意見に耳を傾け、「量子力学と意識の役割」を中心に、ノーベル物理学賞のジョセフソン博士をはじめ、まさに「世界最高峰の知性」によるコルドバ国際シンポジウムをもったのである。その全記録が出版されつつある。
その緒言のところで、「ハイゼンベルグとボーア、そしてもっとわれわれに近いところでベルの業績をうけて、量子力学は観察者と被観察物のあいだの諸関係を疑問に付し、おそらくはさらにわれわれが現実世界について抱懐していたところの観念そのものまでを根底から揺るがせるにいたった……」とあるように、今まででの科学のような客観的観察ということ自体が問題となるようなところへ来ているのである。
引用文の中に「ハイゼンベルグとボーア」とあったが、本来は、ボーアとハイゼンベルグと言うべきところであるが、この二人こそ量子力学の主流となった人々である。そして今やトップレベルの物理学者たちが「月があるから月が存在するのではなく、観察されるから在る」と言うようなことを真剣に論じ合っているのである。まさに「唯心論」の復活なのである。
前世紀に「唯物論」をとり上げてとうの昔に捨ててしまった「唯心論」が息を吹き返しているのである。科学者たちが一生懸命に真理の山を上り、やっと峠をこえたと思ったら、宗教家たちがニコニコ顔で、科学者たちを歓迎した、と言われているのである。科学の定義さえ変わってしまったと言われているのだ。
そして今や、物理学者たちが東洋神秘思想(オカルト)に走って行っているのである。まさに危機である。だから今こそ我々は、聖書から科学とは何かと言うことを主張しなければならないのである。そこでエジンバラ大学のトーマス・トランスが『科学としての神学の基礎』と言う名著を世に出したのである。これらのことに興味のある方は「第二部」を読んでいただきたい。
このようにして「悪霊はいない」という考えは、啓蒙思想が生み出した一時のあだ花であったのだ。そのようなものを神学の中にとり入れた罪は大きい。そしてそれは非聖書的であり、非科学的であり、現実の問題も解決しない神学のお遊びである。「新アカデメア派」が象牙の塔に立てこもって哲学思想をもて遊び現実の問題にとり組もうとしない姿をトランスは「エキュメニカル運動(WCC)においてよく問われるような類いのもの……」と笑っている。WCCが、本当に人間の問題を解決しないように、「悪霊はいない」と言う神学も、現実のなま身の人間の問題を解決しない。それらの聖書解釈上の誤りも本文の中にしるしておいたのでよく読んでいただきたい。
特に第五章の「雨は二度降る」は福音派の神学、デスペンセーショナリズムの根本をひっくり返すようなところなので、注目していただきたい。まさに「パラダイム転換」なのである。オカルトの氾濫、占いの氾濫、種々な悪霊の働きに対して、教会は勝利出来るのである。もし御言葉にかたく立つならば。
「私たちの格闘は……悪霊に対するものです。」(エペソ六・一二)
「ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ去ります。」(ヤコブ四・七)
一九九二年二月十四日 那須にて 奥山実
重要部分抜粋『第二部:神学に興味をもつ人のために』より
三、パラダイム転換(常識破り)
古典物理学が通じない世界、ニュートン力学では説明できない世界、それは常識の通じない世界である。今世紀の物理学が、かの有名な「相対性理論」と「量子論」によって著しい発展をし、人類に大きな貢献をしているとは周知のことであるが、「相対性理論」がアインシュタインによって発表された時、当時それを理解できるものは、世界で十人もいない、と言われたという。
だから当時、日本の大学で物理学を学んでも教授の中にその理論を説明できるものはいなかったのである。今でも大学で物理をやったからと言って、量子力学を本当に理解して卒業したとは限らないのである。このように当時は相対性原理を理解できるものは十人もいないと言うことは、つまり当時の常識では理解できなかったのである。しかし今にいたるも常人にはなかなか理解しがたいことであるが、量子力に至ってはもっと理解しがたい。
量子力学を支える二本の柱は、「不確定性原理」と「相補性原理」(相対性原理ではない、相補である)。
相補性原理は、量子力学の主流派となった「コペンハーゲン派」の元祖ニールス・ボーア(NieIs Bohr 1885-1962)が主張したもので(一九二七年)、原子を構成する素粒子のようなミクロの世界では、古典理論とは矛盾するが、物質には「波動」と「粒子」の両方の性質があるというものである。ちなみにこれはニュートン力学では、あるいは常識では絶対に認められないものである。
粒と波はまったく別のもの、別の性質である。粒とは野球のボールみたいなもの、波とはすでに何か、たとえば水などが、すでにある場所を占め拡がっていて振動するものである。学問的表現では粒は「局所化」されているが、波は局所化されていない、と言う。だからこそ、光は波であるということが常識であった十九世紀の終わりごろは、光の媒介をするエーテルの存在が考えられたわけである(結局は存在しなかったのであるが)。
さて、相補性原理は、アインシュタインの相対性原理の法則ほど有名ではないが、量子力学の基本であって、すでに数々の実験で証明されている。しかしニュートン力学とは全く矛盾している。つまりニュートン力学には限界があって、それに固執していたのでは、科学はそれ以上一歩も前進できず、真理の探求もできなかったのである。完璧と思われていた古典物理学も乗り越えられなければならなかったのである。
同じように、まばゆいばかりに輝いているカルビン主義神学も、聖書の光にはなお劣るのである。いかに完璧に見えようとも、神学は聖書と同列ではない、誤りも不足もある。それは「誤りなき」聖書によって絶えず改革されなければならない。カルビニストなら、それらのことは百も承知である。しかしいつの時代にもパラダイム転換は生命がけである。勇気がいるのだ。皆が平安に過ごしている土台をひっくり返してしまうからである。
プトレマイオスの天動説を、コペルニクスが地動説としたが、それに賛同したガリレオ・ガリレイは裁判にかけられた。パラダイム転換がいかに困難かおわかりだろう。それはカトリックの公認の教義であるアリストテレスの哲学に矛盾していたからである(聖書によって裁かれたのではない。むしろ彼は同時代のケプラーと文通し、聖書にかたく立っていた)。このようにしてカトリック教会は、教会の組織力で科学者たちを裁き、今に至るまで大きな痛手となっている。このようにコペルニクス的転換をパラダイム転換と言うのであるが、まさにニュートン力学から量子学への道もパラダイム転換であった。つまり常識破りである。 皆が平安だと思っている近代カルビン主義神学の修正も、パラダイム転換となるほどの出来事である。それをする人間は、あらゆる非難中傷を覚悟しなければならない。
実は物理学の輝かしい発展も、固定観念にとらわれた保守的な物理学者たちの壁に何度もはばまれた。「物質波」を提唱して、その後の量子力学に著しい貢献をし、ノーベル賞を受けた(一九二九年)フランス貴族のド・ブロイの場合も、その考えは「狂気のさた」といわれた。
と言うのは、当時は電子は、光とは異なり、絶対に「粒子」と考えられていたからである。しかしド・ブロイは、電子のボーア軌道を定常波の波形で置きかえ、アインシュタインの光量子仮説が、電子についても成立すると考え、革命的公式をつくり上げた。そこでは電子は常識をうち破って、波としての性質で表されていた。ド・ブロイの天才を見抜いたのは、同じ天才のアインシュタインであった。「これは狂気のさたと見えるかも知れない。しかし、真実、健全なのだ」と言ってド・プロイを支持したのである。
そしてアメリカでド・ブロイの物質波が発見され、ド・ブロイはノーベル賞を授賞した。やがてこれがシュレーデンガーの波動方程式となって、量子力学の骨格が作り上げられ多大の貢献をしているのである。現在にいたるも。
しかし今では誰もが感謝しているド・ブロイの公式も、当時の保守派にとっては「狂気のさた」であったのだ。マックス・プランクの場合も、前述したように極めて保守的な物理学者で、静かにベルリン大学で教鞭をとっていたが、はからずも量子の世界に足を踏み入れ、信じきっていた古典物理学では説明の全くつかない事実に直面し、それを乗り越えてミクロの世界に入って行ったのであるが、いぜんとして、保守的な物理学者たちはこれを認めようとしなかった。
その時もプランクの偉大な業績を発見して世に出したのはアインシュタインであった。実にアインシュタインこそ天才の名にふさわしい人物であったのだ。しかしその時、保守的な物理学者のかたくなさを見たプランクは『科学者の自伝』(一九六八年)の中で次のように語っている
「新しい科学的真理というものは、論敵を納得させ、彼らにその正しさを理解させることによって勝利をおさめるのではない。むしろ論敵たちが少しずつこの世を去り、新しい見方に慣れ親しんだ新たな世代が育ってくることによって勝利を獲得するのである……」
自然科学の華とも言われる物理学でも、真理にかたくなな人間が、組織の中で力をもち、真理をはばむのである。そして類いまれなる発見を葬り去ろうとするのである。だからプランクは、そのような人間が世を去ってくれないと、科学も進歩できないと言うのであるが、教会はそのようなことを言っておれない。
悪霊の問題は、いずれそのうちわかってくれる、などという悠長な問題ではない。世界的なオカルトの氾濫によって、子供たちが甚大な影響を受けている。教会員の子供、いや牧師の子供でさえもその影響下にある。
大人の世界にエロ本が氾濫しているように、子供の世界にはオカルトの本が氾濫している。オカルトを通して働く悪霊の影響を受けたものは、聖書の御言葉を拒否するようになる。そしてその心に御言葉が根をおろさない。悪魔に御言葉がうばわれていくからである(ルカ8:12)。
"道ばたに蒔かれたものは、聞いたあとで悪魔が来て、心の中からそれを取り去り、信じて救われることがないようにする人々のことです。"
子供たちはどんどん成長していく。そしてこのように聖書の御言葉に養われない、むしろ御言葉を拒否する者たちが福音派の教会をひきついで行くのである。これが福音派の危機である。
教会員の子供たちが、いや自分の子供たちが、そのような悪霊の影響下にあり、すでにあちこちで犠牲者が出はじめているのに、「悪霊など存在しない」などという誤った神学に安住していてはならないのである。
日本はスパイ天国だと言われている。平和ボケしていて政治の厳しさを知らないのだと誰かが言ったのを読んだことがある。スパイにとって、スパイなど存在しないと考えている国ほど活躍し易いところはない。それと同じように、悪霊などいないと言っている教会ほど悪霊にとって活躍し易いところはないのである。
サタンは認めるが悪霊は認めない(神の存在は認めるが、天使は認めない、とでも言うのだろうか)こんな変な考えがいつカルビン主義神学の中に入ったのかわからないが、すべてのカルビニストがそのように考えているわけではないだろう。しかし日本の場合、悲劇的なほどに悪霊については無知である。アメリカの場合、福音派ではトップクラスのトリニティ神学校(Trinity Theologica1 Divinity School)でさえも、「パワーエンカンター」、つまり悪霊との対決のしかたを教えている。
「悪霊は存在しない」という考えは、学問の世界からの誤った情報による、と序文に書いた通りであるが、このような思想に影響されて神学をつくり上げ、聖書解釈をすると、聖書の真理を歪曲してしまう。
次も、あるカルビニストたちの、そのような誤りの一つであるが、「Ⅰコリント八・四」の解釈で、「……世の偶像の神は実際にはないものであること、また、唯一の神以外には神は存在しないことを知っている」のところで、パウロが「世の偶像の神は実際にはない」と言っているので「悪霊など存在しない」と解釈しているのを読んで、あきれ果ててしまった。コンテキストを全然無視しているのである。これでは新興宗教やリベラルの聖書解釈と同じである。
聖書の御言葉を、文脈から切り離してバラバラにしてはならないのは誰でも知っていることであるが、このコリント第一の八章は、一〇章まで同じテーマなのである。八章一節を読めばわかるように、これは「偶像にささげた肉」についての質問に対する答えとしてパウロがコリントの教会に書いているのである。そこで八章、九章、一〇章を読んで行けば、明確にわかるように、パウロは「悪霊が存在しない」どころか「彼らのささげる物は、神にではなくて悪霊にささげられている、と言っているのです」(二〇節)と言っているのである。
一九節二〇節と分脈を追えばわかるように、パウロはコリントの人々に、「あなたがたは、偶像の神にささげた肉だ、と言っているのであるが、偶像の神にささげているのではなく、悪霊にささげているのだ」と言っているのである。つまり偶像の神なんかいない、「いるのは悪霊だ」と言っているのだ。だから八章~一〇章の文脈でわかることは、八章四節でパウロが「世の偶像の神は実際にはない……」と言っているのは、人を雄弁にしてくれる神(ヘルメス)、とか狩猟に役に立つ女神(アルテミス)などはいない。日本流にいうなら、学問の神とか、お産の神様など都合のいい神などいない、と主張しているのである。
このように八章四節は、一〇章一九、二〇節との関係から解釈されてはじめて全体像をつかむことができるのである。こんなことは聖書解釈の基本の中の基本で、言うのも恥ずかしいことである。このように「悪霊は存在しない」という前提で、聖書解釈をしているので大きな誤りをおかすのである。さすがに偉大なるカルビニスト、チャールズ・ホッジは素晴らしい。彼はこの八章四節の釈義で、一〇章一九節との関係を明確にし、「偶像の神とは悪霊のこと」と明言している。これが正しい聖書解釈である。
また誰が解釈してもそうなるはずであって、パウロは悪霊否定者である、などの結論になるわけはないのである。
だから、どうやら「悪霊は存在しない」という歪んだ解釈は、カルビニストの間に、最近になって入ってきたようである。リベラルか、新正統主義あたりの悪影響であろう。
危機的なことは、このような誤った考えが、福音派や近代カルビニストのパラダイムになっていることである。そして前述したようにパラダイムに挑戦することは大変なことなのである。
「常識破り」というレッテルをはられる。だからそれはおかしいと思っていても皆沈黙しているのである。そしてそれは一つの固定観念をうち破ることである。だからそれは革命的なことなのだ。しかしパラダイム転換はどうしてもやらなければならない革命である。そうしなければ福音派の危機はさけがたいものになるからである。
私のやろうとしているパラダイム転換は、誤った聖書解釈と神学で「悪霊など存在しない」と考えている誤った常識をうち破ることである。そしてその非聖書的、非現実的観念を、聖書的なもの、現実的なものにすることである。このようにして教会を救うことである。
四、 古くて新しい聖書と科学の深い関係
しかし実は、もう一つ大きなパラダイム転換がある。それはリベラルも福音派も共にもっている常識「聖書と科学は別のもの」を打ち破ることである。
これこそ人が「狂気にみちている」というであろうパラダイム転換である。私はこの『第二部』で、いたずらに「量子力学」のことを書いたわけではない。量子論がニュートン=デカルト的パラダイムを乗り越えて、人類を新しい世界に導き、驚くべき科学の進歩を果たしてきているが、それは「科学革命」と言われるほどの大変化で、「科学の定義は変わった」とも言われている。今や科学者が宗教家の助けを必要としているのである。「聖書と科学は別です」などという時代は過ぎたのである。
この点で、序文に紹介したエジンバラ大学の教義学教授トーマス・F・トランス(Thomas Forssyth Torrance)の『科学としての神学の基礎』(The Groundand Grammenof Theology)は極めて重要な本である。
ただしこの本は、少なくともプラトンとアリストテレス、そしてカント、量子力学、さらに最新宇宙物理学の基礎がわからないと読み進むのが困難な本である。知人に東大で生物学をやり、その後献身して牧師になった方がいるが、半分も読み進むことができずにギブアップしたそうである。しかしある意味でこの本は革命的本である。一読をお勧めする。福音派の常識、そしてリベラルの常識も、吹き飛ばしてしまうような内容である。つまりパラダイム転換である。なぜならカント的テーゼが量子力学によって粉砕されてしまったからである。その中で彼は次のように主張している。
「前講において、私は全体像が変化してしまったことを示そうとした。なぜなら新しい世界が、科学における根本的変化を伴いながら出現し、決定論さえも論破されるか、あるいは少なくとも相対化されてしまったからである。なぜなら決定論は、比較的低次の実在にだけ、それもいくつかの厳しい限定の枠内でのみ妥当するにすぎないからである。今日の講義で私が明らかにしたいのは、神学が自然科学に基礎づけられるのではなく、それどころかその逆がより真実に近いのだ、ということである。……」(六四頁~六五頁)
何と科学こそ神学に基礎づけられるべきである、と主張しているのである。
啓蒙思想、特にその完成者であり、また同時に克服者とも言われるカントの影響を受けて、聖書と科学を分断して、聖書は聖書、科学は科学などと考えてきた神学者にとっては、まさに「狂気の沙汰」と見えるであろう。「神学が科学を基礎づける、聖書によって科学をみちびく」などというのは常軌を逸するものだと言うであろう。しかし最新物理学、量子力学を知っているものにとっては、至極当たり前のことである。いや、量子力学などやらなくとも、「聖書こそ最高の真理の規範、究極の権威」と信じてきた者にも当たり前の話である。実に我々はそう信じ、告白してきたはずではなかったのか。それとも科学だけは別であったのか。科学だけは聖書の上にあるのか。結局「聖書は最高の真理の規範」と意味もなく、唱えていただけなのか。
ちなみに、トランスはバーゼルでバルトのもとで学び、教父思想の専門家であるが、スコットランド神学は「改革派神学とともに自然哲学(物理学)の伝統」があると知らされて、彼の驚くべき最新物理学への造詣の深さの理由を知った。
バルトのもとで学びながら、そのスコットランド神学のゆえに、バルトに「反逆者」と言われそうなことを平然とやりとげたところにトランスの偉大さを見る思いがする。右の引用文の中でトランスは、「決定論は比較的低次の実在だけで……妥当する」と言っているのは、ニュートン力学の限界のことで、量子力学を理解しているものにはよく知られていることである。つまり、かつて「宇宙のすべての事象を、完全に記述することができる」(ケルヴィン卿)と思われていたニュートン力学に大きな限界があって、存在のごく一部にしか妥当しないと言うことがわかったのである。見えない量子の世界には全く別の物理法則があったのだ。
同じように、ほぼ完璧に見えた近代カルビン主義神学にも、限界があって、手も足も出ない領域があったのである。これらの限界は、完全な聖書が示すより大きい、より深い宇宙観によって修正されなければならないのである。さらにまた啓蒙思想の悪しき影響からも、きよめられなければならないのである。「我々は啓蒙思想を通過した」などとつまらないことを誇ってはならないのである。むしろ、それによって受けた精神的ダメージのために、まともに聖書も信じられないでいるのである。面白いことに、リベラルは「福音派は啓蒙思想を通過していない」と嘲笑し、福音派も同じ言葉をペンテコステ派にあびせているのである。そのような意味のないことを言っているよりも、トランスの鋭い批判に耳を傾けるべきである。
「しかし、科学的認識を観測可能で現象的に確定したものに限定することによって、カントは科学と信仰との関係を切断し、信仰からいかなる客観的あるいは存在論的な指示(reference)をも奪いとって、信仰を実在的な認識内容をまったく持たない空虚なものとしてしまった」(トランス、43頁)
そして周知のごとく、カントの人間主体の哲学の思想界に与えた影響は大きく、ドイツ観念論やロマン主義にも及んだが、カントの形而上学批判の手法に学んだウィットゲンシュタインの影響による分析哲学や、その西欧の科学主義文明の結論的成果と言われる論理実証主義(ウィーン学派としても知られている)は、二十世紀に入り、科学の分析論をつくり上げた。それは現代の常識人にまことに納得のいくものである。
「科学的知識は、それが経験的に実証できるがゆえに、他のいかなる知識よりも優れている。科学者は帰納的に仮説を提示し、実験的手段によって仮説の論証あるいは検証を行う。その結果、仮説から自然に関する一般原則が導き出され、科学法則として理解される……」
このようなわけで、科学的知識こそが最も優れている知識であって、それは「経験的に実証できる」もの、であり、「観測可能で現象的に確定したもの」(カント)なのである。それならば、実在は経験的に実証できるものだけ、観測可能で現象的に確定したものだけであろうか。我々人間(この不完全なるもの)が経験的に実証できないものは実在しない、と言うのだろうか。
この疑問に答えたのが量子力学であり、それまでの古典物理学における科学の定義、常識を吹き飛ばしてしまったのである。
というのは、量子力学が、ミクロの世界に入って行った時、目に見えない素粒子を観測するためには、観測装置を使うのであるが、何と観測によって、観測対象が変化してしまうのである。
古典物理学では全く経験したことがない事柄である。観測が対象物を変化させてしまうなど、考えも及ばないことであった。「宇宙に手をのばし、さわった時、宇宙を攪乱することになると、誰が知っていただろう」(F・A・ウルフ)と物理学者が述懐している通りである。
しかし実は、マクロの世界でも、はなはだ微小ではあるが、観測が対象物を変化させることは経験していたのである。たとえば、体温計で体温を測ろうとして、その体温計をわきの下に入れた場合、その体温計の冷たさが、体温に影響を与えたのである。ヒヤッとしたあの感覚をみんな経験していると思う。しかし、その影響はあまりに微少なので、大した影響はなかったのである。
しかしミクロとなると話は別で、観測が大変化を与えてしまって、観測そのものが困難な対象物が山のようにあって、実在に手が届かないのである。そして客観的な観測ということまで大問題となってしまったのである。
日本にはじめてノーベル賞をもたらした物理学者の湯川秀樹は、この辺の事情を次のように語っている。
「なるほどわれわれの頭の中では、物質はすべて原子とか電子とかいうものからできていると考えている。それは正しいに違いないが、しかしわれわれが相手にする物体の中にある原子や電子の数は、非常に大きなものであって、現実にそれらの原子や電子の一つ一つについての完全な情報を得ることは、とうてい不可能である。それらの多数の原子や電子の中のごく少数のものについて、われわれがとくに注意して観察してみることは可能であるが、しかしその他の大多数の原子や電子について一々観察することは、不可能である。それは人間の力の及ばないことである。」(『科学者のこころ』朝日選書:50頁)
我々の目に見えるマクロの世界は、我々の体も、地球も、宇宙も結局は目に見えない原子、そしてそれを構成している素粒子からできているが、その実在の真の振る舞いを知るために観察しようとしても、その数があまりにも多いため「大多数の原子や電子について一々観察することは、不可能である。それは人間の力の及ばないことである」とある通りである。つまり観測不可能なのである。大雑把なマクロの世界は観測できるが、目に見えないミクロの世界は観測が無理になってくるのである。また観測しようとする素粒子、たとえば電子だが「非常に考えにくい、常識ではちょっと理解できないようなふるまいを、電子はする」のである。
また原子や素粒子は、我々一般人が考えているものとは全く違うのである。我々は原子の構造が、太陽系のようになっていると思っている。学校で学んだように。しかし湯川秀樹が言うように「そういう模型は、文字どおり正しいとはいえない。そういう軌道というようなものを、原子核の中の電子について考えるのはおかしい」のである。
ではどのように考えるべきかと言えば「今日では、電子は原子核のまわりになにか雲のようにひろがっていると考えるのである」
もうこうなったら一般人はとてもついてゆけない。しかしこれが現実なのである。そこで原子の構造については、一般人があまりにも理解できないので、現在にいたるも一九一三年のボーアの原子像が用いられているのである。実に約八十年前のもので原子像を説明する他ないのである。
あるエレクトロニクス関係の本に目を通した時もボーア原子像で説明されていた。実はボーアの「ボーア軌道」を否定したのは愛弟子のハイゼンベルグなのであるが、このあたりにボーアの心の広さがある。そしてこの二人が量子力学の主流派となって、現在の驚くべき成功を見たのである。そしてこの二人が初めてゲッチンゲンで会った時、ハイン山を散歩しながら話し合ったが、その時この二人の天才が了解し合ったことは「原子は物質ではない」ということだったのである。
原子が物質でないなら、いったい何なのだ。つまり、このミクロの世界は常識は通じないのである。これが量子力学のトップの考えなのである。一般人がついていけるはずがない。
さて、古典物理学では、運動している物体の運動の状態を正しく知るためには、どこで、いつどのようなスピードで、ということを知らなければならない。また、ある物体の運動量を知りたい場合、その運動量をpとし、速度をvとし、質量をmとした場合、その物体の運動量(運動の勢い)は、有名な数式p=mvで表される。そしてそれは我々でも納得がゆく。
しかしミクロな量子の世界では、全く別の法則が働いているので、ある素粒子の位置(x)と運動量(p)を知りたい場合、これもあまりにも有名なΔx・Δp=hで表される。Δ(デルタ)は言うならば、ある幅であって、不確定性を示す。hはプランク定数である。つまりプランク定数(h=6.62×10^-27[エルグ・秒]、エルグとは1ダインの力の下で1cm変位した場合を1エルグとする。記号はergである。1ダイン[dyn]とは1gの質点に作用して1cm/sの二乗の加速度を生じさせる力のこと)を越えないようなミクロの世界では、位置と運動量を同時に正確に知ることはできないのである。
数式を見てわかるように、電子のように小さな粒子の位置(x)を正確に決めようとすると(Δxは小さくなる)、Δpは大きくなる(運動量の不確定性が増大する)。逆に運動量Δpを正確にしようとするとΔxが大きくなる(位置の不確定性が大きくなる、つまり位置がわからなくなる)という矛盾に遭遇するのである。もっとわかり易く説明すると、物を見るのには光が必要である。暗いところでは何も見えない。光があって物が見えてくる。つまり観測ができる。
ところで光とは、一〇万分の三・八センチメートルから七・八センチメートルの波長をもった電磁波のことなのであるが(光は粒でもあり波でもある、これも古典物理学ではわからないこと)、電子のように小さい粒子粒子を測定する場合、波長の短いX線を用いなければならない(長い波長だと回折を起こす。
波の特徴として、大きな波は対象物が小さいと、あまり影響を受けないで、そのうしろに流れて行く)。ところで、この線の光子が、さぐっている電子に衝突して散乱波が対象物にあたると散乱波を起こす)してくれて位置がわかったのだが、その衝突の衝撃で、電子は飛ばされて、運動量が変わってしまうのである。つまり観測のためにγ線をあてるだけで、電子の運動量が激しく変化し、結局もとの運動量はわからないのである。逆に運動量を変化させないように波長の長い電波をあてると、電子の位置がわからなくなるのである。「あちらを立てれば、こちらが立たず」と大いに物理学者を悩ませているのである。これが有名なハイゼンベルグ(Wernen Heisenberg 1901-1976)の不確定性原理であって、量子力学を支える二本の柱のもう一本の重要な柱なのである。
さて、そのような訳で、古典物理学によれば、ある瞬間における物体の位置と運動量は、正確に観測し計算できる。それさえわかれば、その物体の次の瞬間の状態が予測できるわけである。
ところが不確定性原理では、ある粒子の位置と運動の状態を同時に、正確に知ることは絶対にできない。というのは前述したように観測が粒子に影響を与えてしまう、つまり観測によって対象が変化してしまうのである。これは「客観的観測」というそれまでの科学の最重要概念が否定されてしまうことになるのである。
前述したように湯川秀樹は素粒子が「常識では考えられないような振る舞いをする」と述べているが観察者(主体)と対象物(客体)が、ミクロの世界では相互作用を起こすのである。たとえば光に対して粒子としての実験を行うと、光は粒子としての性質で振る舞い、波動としての実験をすると、何と波動として振る舞うのである。素粒子に意識があるのかとさえ考えてしまう。まさに常識では考えられない行動をするのである。このようにミクロの世界での実験は「観測者」が極めて大きな問題になる。つまり光を粒子とするか波動とするかは観測者が決定権をもつことになるのである。これでは科学の常識であった客観的観測の土台がくずれてしまうのである。オーギュスト・コントの実証主義もひっくりかえされてしまうのである。
「おそらく、不確定性原理は一般相対性理論と並ぶ……あるいは、我々の世界認識に与える衝撃の大きさという点では、それをはるかにしのぐ、二〇世紀の科学史上最大の収穫のひとつといえるだろう。この原理によれば我々の世界認識の基盤である客観的観測という概念そのものが根本的に否定されてしまうのである……」
量子論には主流派もあれば反主流派もある。しかし、人間の観測が対象物を変化させてしまうことはあまり認めざるを得ない事実なのである。だからそれについてはあまり議論しない。だから人間はこの宇宙の「観察者」(オブザーバー)ではなく、「関与者」(パーテシペーター)と呼ぶべきであると言われている。
それでは人間の観測の何が対象物をかえてしまうのか、については大いに議論がある。その問題を徹底して究明しようとした最初の人は、ハンガリー生まれのノイマンである。そして一九三二年に『量子力学の数学的基礎』という本を書いた。そして「観測者効果」(観測対象が、観測者の意識の関与によって、波動関数が収縮する)を提唱した。
つまり人間の意識が、対象物を変えてしまうということであって、ここから人間の意識の問題が取り上げられ、発展してきたのである。だからこそ、序文に書いたように、現在の「世界最高峰の知性による」と言われるコルドバ国際シンポジウムは、まさに『量子力学と意識の役割』というのが中心的テーマであったのである。
そのシンポジウムの中で行われたバークレー大学素粒子物理学教授F・カプラ(Fritjof Capra)と、ノーベル物理学賞にかがやくケンブリッジ大学教授ブライアン・ジョセフソン(Brian,D.Josephson)との討論の一部をご紹介する。現在のトップレベルの物理学者たちが、何を考えているのかが良くわかるが、それは驚くべきものである。何故に最新物理学が、宗教家や哲学者の助けが必要なのかが良くわかる。
F・カプラ「意識については伝統的に二つの意見があります。第一に、唯物論の立場から意識は、物質がある程度の複雑性に到達した段階において獲得した物質の所産であると考えられています。もう一つのアプローチでは、反対に、純粋意識という表現をとり、これがあらゆる実在の根底にあると見ております。そこでお尋ねしたいのですが、物理学の世界で言われる相補性の意味でこの二つのアプローチを相補的なものとして扱うという発想について、どうお考えになりましょうか?」
B・ジョセフソン「まったく同感です。あなたのお考えは私の個人的態度ともぴったり当てはまります。緒現象の説明のしかたについて私は、意識経験の観点からもそれを説明できるし、物理学の立場からもそうできると考えておりますから。二通りの考えをそのまま認めてよいでしょうし、おそらく両者は互いに一致することでしょう。」
(『量子力学と意識の役割』67頁~68頁)
カプラ教授の言うように、一般に現代人は唯物論の線にそって「意識」というものを考えている。つまり物質の所産である副次的なもの、はじめに物質ありき、である。物質なしに意識もない。ところが、その逆に「純粋意識」というものがある。物質があってはじめて意識が生まれるというのでなく、ある意味で、別に物質と関係なく、独立して意識というものがある。この二つを相補的に取り扱ってよいか、と質問したのである。
相補的ということは前述したように、AとBという互いに矛盾に見えるものを両者とも受け入れて理論を構築することである。
光子の粒としての性質と波としての性質を、たとえ矛盾と見えても、現実を受け入れることである。そのように、物質あっての意識という考えと、物質と関係のない純粋意識の存在の考えの両方を受け入れてよいのか、との質問である。それに対して、ノーベル賞物理学者のジョセフソン教授が「まったく同感です」と答えているのである。
これは何を意味するのか。
現在のトップレベルの物理学者たちが「純粋意識」の存在を確信しているのである。
そしてジョセフソン教授は、「物理学の立場からもそうできると考えております」と答えているのである。
この「物理学の立場」というのは、エベレット、ウィーラー、グラハムら三人の「多世界解釈」と思われる。この解釈は、この世界と並行して存在する別の世界を認めて、波動関数が表現している可能性がすべて実際に起こりうるとする解釈である(コペンハーゲン派は可能性のうちのただ一つだけ実現可能とする)なんと物理学者たちが見えない別の世界を前提にして物理をやっているのである。
では、物質から離れた純粋意識とは何であるのか。
それはいつから存在し、どこに存在の場をもつのか。量子力学の種々の実験によって、「意識」の役割の重大さは意識できても、手も足も出ない領域である。そこで今や、トップクラスの物理学者が、東洋神秘思想(オカルト)に急接近しているのである。これも危機である。
エリサベツ・アン・ラウシャー(Elizabeth Ann Rauscher)と言えば、バークレー大学とジョン・F・ケネディー大学の両校で天文物理学と原子物理学の教授をつとめている「現代キューリー夫人」とでも言うべき、新進気鋭の女性物理学者であるが、物理学者と東洋思想研究家からなる総勢四〇名にものぼる研究グループを組織して研究を励んでいる。それほどに最新物理学にとって、宗教の問題は大きく、宗教家の助けが必要なのである。天安門広場事件の時、民主化運動の中心人物とみなされた物理学者の方励之教授とその夫人がアメリカ大使館に保護を求めたことを、記憶力の良い人ならおぼえていると思うが、その後イギリスへ出国を認められて亡命した。彼が道教思想を基本にして宇宙生成を論じているのを、ふと読んだことがある。彼も中国が生んだトップレベルの物理学者であるのだ。
エリサベツ・ラウシャー女史も、世界最高峰の知性として、コルドバ国際シンポジウムに招待されたが、その時、彼女は次のような発言をしている。
「一個の物体の何たるかについては、現実に何らかのコンセンサスといったものが存在し、これを発展させていくことが可能です。つまり私たちは、あたえられた世界の中の一個の物体というものを定義することができますし、これについて何人かの人々がそれぞれ別個に語りながら実は同じことを言う、ということもできます。瞑想においては追求されるものは個々まちまちの体験ですが、しかし、その細部についてやはりその同じ程度の特性にいたるまで論じることも可能なのです。
たとえば《瞑想の青真珠》と呼ばれるものについて、それは、目を閉じていながら眼前に見える何らかの物体であるということが、広く人々のあいだに知られるところとなっています。したがって、出現が生ずるのは自分たちの視野と呼ばれる領域内のことだと言って大過ありますまい。
瞑想者たちは、彼らが見、また視つめるこの青色について、ありありと正確にそれを描きだすことができますが、そのことは私たちが日常眼前にするさまざまの「客観的」色彩について自由に述べたてることができるのと何ら変わりないほどです。
事ここにいたっては、主観的経験といわれるもののなかに、いかに同時に、不思議なほど客観的な何ものかが含まれているか、身にしみて人はそれを味あわずにはいられません。主観性との関係における客観性の定義が、どうしても解明すべき意義甚大の問題と私が考えるのは、そのようなわけからなのです。
科学において定義されるような客観性というもののおかげで、われわれは、自然に関する諸々の知識を満足すべきやりかたで総括してくることができました。しかしながら客観性の効用もどうやら限界に来たようで、意識の諸状態を研究するうえに新しい規矩を探しもとめねばならない地点にわれわれは到達したように思われます。」(『量子力学と意識の役割』70頁-71頁)
この引用文の中で、ラウシャー女史は二つの重要なことを主張している。
一つは、神秘主義者が行う「瞑想」の時、意識にのぼるものは、目を閉じているにもかかわらず、あたかも客観的に同じものを見ているように、瞑想者たちが、共通のものを正確に描き出すことができる、という事実のことを語っているのである(これは聖書に禁じられていること。申命記一八章)。
一八世紀、一九世紀なら、啓蒙思想や、唯物主義におかされた世間知らずの自称インテリたちがあざ笑うであろう。同じように、啓蒙思想や、時にはマルクス主義までをも、無批判に受け入れて、聖書の直理を軽んじてきたリベラルには、霊的盲目のゆえに何のことかさっぱりわからないであろう。そしてまた霊的な事柄よりも、知的なことを求めて、啓蒙思想や、古典物理学の科学観に影響されて、奥行きのない世界観、宇宙観でものを考えている福音派も、ラウシャー女史にはとてもついて行けないだろう。そして「聖書と科学は別なのです」などと言っていては誰にも相手にされないのである。最新物理学は今や聖書の宇宙観、天国と地獄、意識の世界―を知りたいのである。
しかし近代プロテスタントは、初代教会や宗教改革時代と違って、聖書と科学を分断してしまったのである。だからこそ最新物理学者たちは、東洋宗教に走るのである。それゆえにこそ、コルドバ国際シンポジウムには、プロテスタントの神学者は誰も招待されなかったのである。
トップレベルの最新物理学者と共に心理学者、文化人類学者、宗教学教授、哲学者、精神分析医、などなどオールラウンドであるが、そしてオラトリオ会神父(カトリック)やイスラム学者まで招かれたが、プロテスタントは誰もいなかったのである。「聖書と科学は関係ありません」などと言っている者を呼んでも何の役にも立たないからである。
ここまで来たら、エジンバラ大学の教義学教授トーマス・トランスが、なにゆえに「神学によって科学を基礎づける」べきことを主張しているか、わかって来たと思う。「狂気の沙汰」と思われた彼の主張は、量子力学を知るものには当たり前のことなのだ。また、本当に「聖書を最高の最終的真理の規範」と信じている者にも当たり前のことなのである。
聖書は本当に真理の最終的よりどころであるゆえに、「科学は聖書によって基礎づけられなければならないのである」と科学者に言わねばならないのだ。本当に聖書をそのように信じているならば、である。恥ずかしくてとても言えないと思うが、言うべき時が来たのである。トランスのような勇者がもっと出現しないと駄目である。とくに日本は真理よりも人間関係を大事にするお国柄である。
文化人類学者は言う。「韓国や中国の方が、日本よりもヨーロッパ的である」と。なにゆえか。それは「原則社会」だからである。つまり、韓国人、中国人にとって大事なのは、原則、真理、なのである。
ところが日本人にとっては、真理よりも「人間関係」の方がより重要なのである。だからNHKが、東京のある地域でアンケート調査した時、36%の人々が「どうせ宗教もつならキリスト教」と答えたと言う(ある地域では50%を越えたこともある)。ではどうして教会へ来ないのか。「人間関係がこわい」のである。近所の人から、友人から、身うちから「変なこと言われたら嫌だ」と恐れるのである。つまり、真理よりも人間関係を選ぶのである。ところが韓国や中国は、原則や真理の方がより重要なのである。だから「キリスト教には真理がある」。それだけで教会へ来る。
何も十字架の福音の奥義や聖書のすべての教理がわかったからではない。中国も共産主義に失望して人生の土台を失った若者や学生がどんどん教会に集まって来る。原則社会の人々は、しっかりした原則、真理がないと人生をやって行けないのである。ところが日本は人間関係社会(悪い言葉では部族社会)であるので「真理などどうでもよい」と思っているのである。人間関係さえうまくやればそれでいいと思っている。これで人生やっていける。だから他人に合わせて、他人の顔を伺って生きているのである。「百万人といえども我行かん」などと言う意気のいいのはあまりいない。
その点、韓国は素晴らしい。160名もの最新物理学者……宇宙物理学者、量子力学者、さらには生物学者などが「創造科学研究会」の会員として堂々と活躍している。つまり聖書によって科学をしているすばらしいグループである。大学教授や博士たちで、まさに韓国の最高の知性の集まりである。ところが実はアメリカでは、近代カルビニストたちは、この創造科学研究会を軽んじているのである。つまり、「聖書と科学は別」と信じているからである。科学にだけは聖書は最高の真理の規範とはなり得ないと考えている神学者たちである。そして量子力学を知らず、古典物理学にしがみついている者たちである。しかし実はアメリカの創造科学研究会も、かつてアメリカで、進化論の教科書を書いたゲーリー・E・パーカー(Gary E Parker)博士など、最高の知性の集まりで、パーカー博士はクリスチャンとなり、聖書の創造論に立って、かつて自分が主張したことを、くつがえしているのである。この様な実体を神学者たちは知らない。
このようにして、啓蒙思想や、古典物理学の影響を受けた近代カルビン主義は、修正されきよめられなければならないのである。
トーマス・トランス博士は、その著書『科学としての神学の基礎』の中で、
「もちろん、現代人の多くは神学と科学とを関係づけることを恐れ、それぞれがもつ、知解可能性と正当性との自律的領域を両科学に所属させながら、両科学を実用的に隔離することによって仕事を進める。例えば、この事態がキリストへの信仰を史実のイエスから切り離すに至るときに、これが悲劇的なことになるように、この事態は我々の現代的状況について多くのことを語っている。すなわちこの事態から、この種の現代神学が神と空間―時間の世界との間のきわめて重要な関係から遊離し、切り詰められた神人関係に閉じ込もり、それによって被造的宇宙の知解可能性における一切の共通基盤を失ってしまった、ということが示される。きわめて多くの現代の神学者たちが自然科学との真剣な対話を交わすことができなくなっている背景には、明らかにこのような事態が存在している。なぜなら、神学者たちは、科学者たちとの関係を確立するための共通基盤を持っていないからである。他方、科学者たちの間では、これとはまったく違った事態が起こりつつある。彼らは信仰者の間でますますその数を増してきている。実際私の知る少なからぬ大学の科学者の間では、大学外よりも信仰者の比率が高い。これは、神学者たちが適切には理解してこなかった、ものの見方の深い転換が、科学自体の前進に連関して起こったことを示している。これまで長い間、西洋文化において支配的であった制限的で抽象的な思惟様式から我々が自由になるにつれて、認識の基本的習慣が変えられつつある。かつては排除されていた実在のさまざまな諸次元が、今やいっそう接近可能なものになる。これらの次元が指示する多層宇宙(amulti-leveled universe)は、宇宙の驚くべき知解可能性により深く本来的根拠づけられるとともに、より開かれた思惟の諸概念と諸構造が、われわれの側で発展させられることを要求する。」(30頁-31頁)
と言って「神学と科学の分断」の悲劇を語っているが、コメントを加える紙数はないので、彼の主張を読んでいただきたい。ただ「かつては排除されていた実在のさまざまな諸次元が、今や……」というところに注目していただきたい。つまりニュートンの機械論的宇宙観では排除されていた諸次元が、物理学者の前に現れてきたのだ。つまり今や物理学者の方が、啓蒙思想に影響された神学者よりも霊的なことをよく知っているのである。
「悪霊などいない」と言っている神学者がいかに非聖書的で、非現実的かおわかりだろう。
同じく、現代のプロテスタント神学が、いかに時代おくれであり、リベラルが役に立たないかについて語っているところを紹介するので一字々々よく読んでいただきたい。
「現代神学において我々が今直面しているのは、次の問題である。すなわち、科学者たちがラプラス主義とマルクス主義の狭い機械論的決定論をはるかに越えて、宇宙の偶然的秩序における知解可能な諸関連をより深く、より統一的に把握する方向に進んできているのに対して、神学は、大体は過去の極端な二元論に根ざす蒙昧主義的な思惟様式にいまだ固執する傾向にある、という問題である。いわゆる自由主義神学は、人間の宗教的および道徳的経験の入念に保護された自律的地位の内側で自由な思考(free-thinking)を営むが、何らかの神秘的な超越論によって補われる場合でさえ、この神学は容易に空虚な人間主義的な主観主義に陥る。自由主義神学が自然科学との知解可能な関係を確立したり、また唯一なる三一的神の秩序ある創造としての空間と時間についてのより深く、より統一的な理解に向かって共に前進することなどまったく不可能である、ということは明白である。」(35頁)
最新物理学、そして現代の科学者との対話において、なぜリベラルが役に立たないかは、すでにわかっていただけたと思う。一九世紀の唯物論を含めて、時代遅れの狭い、薄っぺらな世界観、宇宙観にしがみついているからである。しかも聖書を言葉どおりに信じない悲劇によって、塩気のない塩となって、人々に捨てられているのである。福音派も「聖書を最高の最終的真理の規範」と告白しながら、古典物理学にしがみついて「聖書と科学は別のものです」などと言って言行不一致をやっていると、リベラルと同じ運命になる。
トランスは、実は古代教会、教父学の専門家であるが、「古典的キリスト教神学の基礎」に再び帰る(芦名定道)ことを目指している。
そして古典的神学というのは「ニケア神学とそれに続く二世紀間に生じた神学の全体とを指す」のであるが、それは「聖書と科学が一体であった頃」である。
もともとキリスト者は、聖書を創造主なる神からの啓示の書として信じているので、「聖書は最高の真理の規範」であるのは当たり前で、プラトンやアリストテレスの世界観、宇宙観に、「三位一体なる神の創造」という驚くべき聖書的真理によって挑戦していったのである。
プラトン哲学にとって、この見える感覚的世界は真実の存在ではなく、イデアこそが実在なのである。それに対して教会は「神による世界創造」という驚くべき、聖書の真理で立ち向かったのである。この天と地は影のようにはかないものでなく、創造主なる神の作品なのであり、明確に実在するものであるという主張である。
プラトンの二元論に対して、アリストテレスの哲学は、もっと自然哲学(物理学)的である。
自然を可能態から現実態へと向かう運動変化としてとらえ、その運動の究極の第一原因(不動の第一動者)としての神を置いた。このようにしてアリストテレスの哲学では、神学は宇宙論の項に入れられた(思惟の思惟としての神と矛盾しているように見えるが)。そしてアリストテレスにとって、自然は永遠から存在していたのである。ところが、初代教会並びに古代教会は、「神による無からの天地創造」という、聞いたこともない聖書の真理によって挑戦していったのである。宇宙は永遠ではなく、「はじめ」があったのである。「永遠者は主なる神のみ」なのである。このようにして、当時の人間がつくり出した種々の哲学を打ち破って、世界を変えてしまったのだ。この点で教父学の専門家であるトランスの文章は実に明快である。そして心おどるものがある。
「厳密な意味での神学が成立したのは以上の発展経過においてであった。ここでいう「厳密な意味での神学」とは、「教義学」(dogmatics)のことである。この点について説明しよう。古代世界において、プラトンとアリストテレスの学派は、いわゆる「新アカデメイア派」によって継承された。
この学派の哲学者は(間もなく懐疑派と呼ばれるようになったが)、際限もなく問いを発するのには専心したけれども、積極的答えを受け入れる用意がなかった。彼らの問う問題は、エキュメニカル運動においてよく問われるような類いのものである。すなわち、決断と変化にかかわらせるような解答を生み出さないような問題である。
この類いの問題が今でも単なる「アカデミックな問題」と称せられるのは、いうまでもない。しかしキリスト以前と以後の各二世紀の間に、ある点で経験科学の先駆者となった思想運動を開始した、新アカデメイア派とは異なる哲学者たちが現われた。彼らはアカデミックな問題だけを問う偉ぶった人々によって「独断論者たち」(dogmatics)とあだ名された。
彼らは積極的な答えを生み出す問題に、従って現実的で有用な認識に導く探求に専心したからである。「独断論者たち」に従えば、彼らは象徴的で無用な問題ではなく、周囲の現実世界についての問題や、諸事物の本性が否応なく彼らに与えるような答えに関心を持った。すなわちこれを受け入れ、これに従って行動するのを差控えることができないような、そういった種類の答えである。このように「ドグマティック」な人々とは哲学者ではなく、科学者、すなわち自然の客観的で固有の諸構造によってそう考えざるをえないという仕方でのみ思惟する人であることになる。
キリスト教神学者たちが取り上げ発展させたのは、この思想運動であった。その際彼らは自然固有の諸構造を神による無からの創造に関係づけることによってこの運動とその基礎を発展させた。これをアレクサンドリアのキュリルスはドグマティケー・エピステーメー(dogmatike episteme)、すなわち「教義的科学」と呼び、この語をキリスト教神学に適用した。まさにこれこそが、我々が教会の偉大な諸公会議に見出す種類の神学なのである。
これは神学的な自由思想といったものではなく、神と神の創造した宇宙との現実的な相互作用によって、またこの相互作用における神の知解可能な自己啓示によって我々に押し迫ってくるような、神とキリストについての神学なのである。そこで聞かれ、見出されるものの支配に自らの精神を委ねるとき、我々は神と世界、キリストと聖霊および教会について根本的な事柄を語らざるをえないことに気付く。教義的科学すなわち神学は、このようにして成立し、科学の全過程を変化させるようなある根本的観念を発展させた。今日私はそのことについて語りたいと思う。」(70頁-72頁)
当時の神学者たちが、世の思想家たちから「独断論者たち」(ドグマティックス)とあだ名されたことをよく覚えることである。啓蒙思想やこの世の科学に影響されるような腰ぬけではなかったのである。
初代教会も古代教会も、神の啓示である旧約聖書と使徒たちの手紙(新約聖書)にかたく立っていた。天才プラトンの二元論を打ち破り、アリストテレスの自然哲学に勝利した教父たちのキリスト教神学は、まさに「聖書のみ」から来たものである。人間のつくり出したもろもろの哲学、それらの影響を受けて教会の中に侵入してきた異端的教説に対して、聖書からの教理によって勝利していったのである。
三二五年のニケア会議は、そのキリスト論において、周知のごとく「ホモウシオス」か「ホモイウシオス」か一文字イオータ(ι)をめぐっての天下分けめの戦いであったのである。それは「神の啓示である聖書」によればどうなのかということであり、いかに聖書的かというミクロの戦いであったのだ。このようにして聖書から与えられたキリスト教神学が、この世の哲学を、異端を打ち破っていったのである。そして科学の基礎づけをしていったのである。このようにして聖書と科学は深い関係をもっていた。ところがそれを分断したのは、中世カトリック教会である。
五、聖書と科学の分断の罪
誰でも知っているように、中世のカトリック教会は、宗教改革が必要であったほど、多くの問題をかかえていた。神学の面でも、初代教会、古代教会のような聖書信仰は失われていた。そしてアリストテレスが再び教会の中に侵入して来たのである。
「中世の西ヨーロッパの大学で、アリストテレスの著作は論理学と自然哲学の教育の基礎となり、彼はゆるぎのない権威となった。カトリック教会もまたアリストテレスの著作を『聖書』の記述を補強するために用いた……」のである。
それに対して、すでに聖書の世界観に養われていた人々は反対を表明した。とくにパリ大学は1210年にアリストテレスの哲学を禁ずべしとした。しかし、かの有名なトーマス・アクイナスが「アリストテレスとキリスト教神学は矛盾しない」として、カトリックの公認の神学に組み入れたのである。
このようにして、地動説のコペルニクス体系は、アリストテレスの宇宙像に完全に窒息させられていたのである。そしてそれを取り上げて、その正しさを一般人にも理解してもらうためにガリレオは「天文対話」(一六三二年)をイタリア語で書いたのである。
これは常識破りであった。というのは、当時はこの種のものはラテン語で書くならわしであったからだ。ガリレオの心のぬくもりが伝わって来るようである。これによって彼は宗教裁判にかけられた訳であるが、「彼は聖書によって裁かれたのではない」。アリストテレスの宇宙観によって裁かれたのである。アリストテレスの宇宙観と合わなかったからである。むしろガリレオは聖書に立っていたのである。同時代のケプラーと文通し、著書を交換して励まし合っていたのだ。そして彼はこの宇宙を「第二の聖書」と呼んでいた。そしてまた「もし人々が正しく聖書を読んでくれたなら、私の言っていることを理解するはずだ」と言っていた。
つまり、ガリレオにとって「聖書と科学は一つ」であったのだ。ガリレオはアリストテレスの哲学によって裁かれた、ということをしかと知ることである。そしてこの時、カトリック教会は「聖書と科学を分断」し、聖書なき科学―アリストテレスの宇宙像に立っていたのである。換言すれば、科学は人間の思弁である哲学のもとにおかれていたのである。
宗教改革は、再び教会が聖書を取り戻し、そしてまた、その「聖書と共に近代科学が生まれた」のである。宗教改革は、再び「聖書と科学を一つ」にしてくれたのである。クリスチャン学者の渡辺正雄氏などが強調するようにガリレオも、ケプラーも、そしてニュートンも、聖書に立って科学をしたのである。ケプラーも、ニュートンも、たまたまキリスト教世界に生まれたので有神論者で聖書中心なのではない。二人とも、熱烈なるキリスト者であったのだ。ケプラーはチュービンゲン大学で神学を学び、聖職者となる準備をした人である。
天文学に進んだ時も、「この宇宙は、神による創造であるので、きちんとした法則があるに違いない」とかたく確信して天文学をやり、惑星運動三法則(ケプラーの法則ともいう)を発見したのである。神の存在を基本にして科学したのだ。ニュートンの場合も、イギリスの司祭が「我々(司祭)が束になってかかっても勝ち目がないほどに聖書の知識をもっている」と語っているほどに聖書に精通していたのである。
そして知るべきことは、ニュートンには科学書よりも、神学書の著作の方が多いのである。こうして近代科学は聖書と共に幕を開けたのである。これも万人が認めるところである。その成果は、宗教改革に負うところが大きい。というのは「改革者たちは中世の教会に入ってきたギリシャ、ローマ的異教の要素を一掃し」(『進化論を斬る』126頁)たからである。
ところが、近代プロテスタントが、再び「聖書と科学を分断した」のである。それは前述したように啓蒙思想の影響によるのだ。そして今や、福音派にまでその影響は及び、「聖書と科学は別のものです」などと言っているのである。
このような時代遅れ、時代錯誤がなぜ生じるのかをトランスは見事に指摘する。
「さてしばらくの間、上述の再構成と現代起こってきたことを対比してみよう。今日、キリスト教思想は現代文化のさまざまな形の思想の内で、またときには一時的な流行の内においてすら解釈される傾向にある。トーマス・S・クーンは彼の著名な書物、『科学革命の構造』において次のことを示した。すなわち、科学者は通常、彼が生きている共同体あるいは社会において優勢な、一定のパラダイムの内で思考を展開しようと努める。
しかし創造的思想を企てるときは常に例えば科学上の大発見や進歩におけるように、社会の思想世界を飛び越え、新しい諸概念を発展させる。それらの概念は共同体のパラダイムと根本的に対立するものであって、革命的な変化あるいは転換なしには共同体のパラダイムと同化できないものである、と。
科学がその主要な進歩をなし遂げることができるのは、新しい概念が人々の思想のパラダイム的構造を変化させるときに限られる。さてこのような観点から考えると、現代神学は逆の仕方で活動してきたと認めざるをえない。説教者、学者、そして神学者たちはその全世代にわたって、社会と文化のパラダイムを試みるどころか、どのようにしたら福音を伝達し、それを現代世界に対して理解可能で適切なものにできるかと問い続け、そしてこれに答えてキリスト教のメッセージを共同体のパラダイムに適合させようと試みてきた。
こうしなければ、今日の人々はキリスト教が何にかかわるものであるかを理解しないであろう、というのが彼らの主張である。このようにして科学が我々の思想を変えることによって前進するのに対して、教会の説教と教えはますます時代遅れのものになっていく。このようなわけで、最近の数十年間に我々が福音を時代に適切なものにしようとすればするほど、福音は現代人にとってどうでもよいものになってしまい、他方神学は現代の分裂した文化の中に口を開けた深い裂け目にはまり込んでしまったのではないのか?
しかし古代教会を振り返って、ガリラヤの人イエス・キリストにより古代世界が驚くべき仕方で征服されたことを考えるとき、次のことに気が付く。すなわちこの事態が生じたのは、古代キリスト教神学が単に古代の異教世界のパラダイムの内で作業しようとする代わりに、人間の哲学と科学と文化の基礎そのものを再創造するという途方もない課題を引き受けたまさにそのときであった、ということである。」(同書68頁~69頁)
科学が「狂気の沙汰」と言われたり「常識破り」というレッテルをはられたりしながらパラダイムに挑戦して、人々の常識を打ち破って真理を求めてきたのに、教会は、とくにリベラルは、人々の常識やパラダイムに、聖書の真理を曲げてでも従おうとして、結局は、塩気をなくした塩になって、人々に捨てられてしまったのである。しかし初代教会や古代教会は、世の人々のパラダイムを聖書の真理によって変革して行ったのである、文化と科学を……
それは古代教会が、本当に「聖書を真理の最高の規範」としていたからである。
このようにして教会史の中で、聖書と科学の分断の罪をおかしたのは、中世カトリックと近代プロテスタントである。
一、初代教会/古代教会:聖書と科学は一つ。プラトン、アリストテレスの哲学を一掃する。全く聖書的立場(「独断論者たち」dogmaticsとあだ名された)
二、中世カトリック:聖書と科学の分断。アリストテレスを受け入れる(ガリレオ裁判)
三、宗教改革:聖書と科学は一つ。ギリシャ・ローマ的異教の要素を一掃する。全く聖書的立場(近代科学の誕生)
四、近代プロテスタント:聖書と科学の分断(聖書と科学は別のもの)。啓蒙主義と進化論の影響を受けて聖書の真理を歪曲する
五、創造科学研究会/トランス教授:聖書と科学は一つ。啓蒙主義と進化論を一掃する。全く聖書的立場
それにしても、何故にかくも近代プロテスタントは科学主義に対して弱いのか。進化論学者たちが、証明できない仮説「存在は偶然による」に立って「創造主はいない」と神を否定しているのに、ただ沈黙をまもっているだけである。そして何と福音派までが、宇宙の年代一五〇億年とか、地球の年代四五億年など、学問的根拠はまことに薄弱で、その道の専門家なら、でたらめもいいとこであることを知っているのに、それに甚大な影響を受けて、聖書解釈や、翻訳まで聖書の真理を曲げて進化論に従っているのである。
創世記一章の六日の創造について、チェーン式聖書でも「しかし天地創造が六日間でなされたと考えるには難点が多いため……」と解説しているように、こんな単純なことにいろいろな解釈をしている。最も多いのは、ヘブル語のヨームは、長い期間をも意味するからと、ほとんど六日間の創造を信じていない。
なぜ素直に六日間と信じられないのか。進化論の影響によるのである。しかし、聖書解釈の原則は何か。「聖書は聖書によって解釈される」のである。そこで出エジプト記二〇章一一節に「主が六日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを造り」とある。「六日のうちに」とある。これで解決である。ところが近代カルビン主義者及び福音派の多くは、聖書解釈の原則をふみにじっても、六日を信じないのである。「長い期間」が常識である。進化論に合わせているのである。
リベラルを笑えないのだ。もっとひどいのはヨブ記四〇章一五節の「さあ、河馬を見よ」である。
その河馬が一七節で「尾は杉の木のように垂れ」とある。誰でも知っている通り、河馬の尾はまことに小さく可愛いのだ。とても杉の木のような尾ではない。この動物は原語ではベヘモス(בְּהֵמוֹת)と言う、尾が杉の木のように垂れている巨大なる動物である。尾が杉の木のように垂れている巨大な動物なら恐竜しかいない。
しかしそれは絶対に認められない。なぜなら一五節に「これはあなたと並べてわたしが造ったもの」とあるからである。つまり、主なる神は「人間と恐竜を同時代に造った」と言うことになり、進化論の主張と合わないからである。これほどまでに進化論を恐れているグループもないであろう。そして進化論学者は笑っているだろう。というのは進化論学者の方が、進化論があてにならないことを良く知っているからである。
私が京都福音自由教会で、神学生の時から副牧師として奉仕していた時に、京都大学で進化論を教えていた生化学者の小牧助教授がクリスチャンになった。救いの喜びにあふれて、彼は私にこう言った。「奥山先生、キリスト教は進化論と真っ向から対決すべきです。並んではいけません。進化論は土台がぐらぐらなのです。先生、進化論と対決してください」
何と進化論をやっている専門家が、進化論はあてにならない、と言っているのである。そして「進化論と並ぶな」ということは有神進化のようなことをするなと言うことである。今や「進化論は自然科学でない」と言う学者さえいる。上智大学の渡部昇一氏であるが、それに対して進化論学者は沈黙したままである。未信者の学者でさえこの位の勇気がある。
とにかく、進化論があてにならないという資料は山ほど手元にあるが、枚挙にいとまがないので一つだけにする。いまだに堂々と教科書に必ず載っているエルンスト・ヘッケルの「反復説」は学問的に大問題であるが、実はヘッケル自身、人格的に問題のある人物で、平気で偽物造りをやったのである。
反復説で彼が提出した資料も、学者たちから、それが人工的なものであることを次々と暴露されたのである。逃げ場のなくなった彼はついにそれを認めたが、一九〇八年に臆面もなく、次のような一文をベルリンの新聞に書き送った。それによって我々は、進化論学者たちがグループで偽物造りをしていたことを彼の暴露で知ることができる。
「この不快な反論を手短かに切り上げるために、まずわたしは、わたしが示した数多くの胚の図のうちのごく一部(おそらくは6~8%)は確かにある意味で偽物であることを認め、それに対して悔いていることを告白する。が、それももとをただせばとりもなおさず、現時点での観察資料が不完全かつ不十分であることが原因なのである。すなわち、資料が不足しているために、進化の各段階をつなぐ段になると無理を承知で溝は仮説で埋め、失われた環は比較に基づく総合判断によって復元しなければならないのである。
……それでもなお、わたしの罪が問われるのなら、最高と言われている教科書や学術雑誌に載っている図版の大多数も同様に「偽物」の責めを受けるべきである。なぜなら、それらはみな必ずしも正確ではなく、大なり小なり手が加えられており、模式化され、構成し直されているからである。信頼され尊敬されもしている生物学者を数多く含む何百人ものひとたちがわたしと同じ被告席に並ぶことになるのだ。これはわたしにとって大いなる慰めである。」
これほどに衝撃的なことがあるだろうか。「最高と言われる教科書や学術雑誌に載っている図版も……必ずしも正確ではなく、大なり小なり手が加えられ、模式化され、構成しなおされている……」と暴露しているのである。また、この自分を「偽物造りをした」と言うなら、「信頼され尊敬されている生物学者を数多く含む何百人もの人たちが被告席に並ぶことになるのだ」と言っているのだ。つまり集団強盗をやった犯人が逮捕された時、「オレ一人じゃない、みんなでやったんだ」と仲間をばらしたようなものである。
ちなみに、どの博物館にもある、サルから人間へある。つまり地層の古い進化したような画がかかげられているが、何の学問的根拠もないものである。つまり地層の古い順に出てきたものではないのだ。画家が描いたものである。
進化論者たちの「モンキー・ビジネス」(偽物造り)は、学者として恥ずべきものであるが、彼らは信じられないほど偽物造りをやっている。
一本の歯から「ネブラスカ人」をつくり上げ、ヘスペロピテクス・ハロルドコーキ(Hesperopitecus haroldcokii)と仰々しく学名を付けたが、何と後でわかったのは、それはイノシシの歯だったのだ。「ピルトダウン人」は事件にもなった偽物である。その他、ネアンデルタール人、ジャワ原人、北京原人など、学問的に問題だらけのものばかりである。これほど甘やかされた学問もないだろう。だからこそ、トップレベルの進化論学者が進化論を捨てるのである。物理の世界でこんなことはない。突然、湯川秀樹が「物理は訳がわからないので、物理学を捨てます」などということはない。
このような進化論に、聖書の真理を合わせようなどとしてきたことを恥じて、悔い改めるべきである。根なし草のようなリベラルは、めっぽうにこの世の学問に弱い。我々福音派はもっと聖書を信じることである。本当に「聖書を最高の最終的真理の規範」と信じることである。
ということは、聖書を科学の上に置くことである。量子力学がカント的テーゼを粉砕しまったように、聖書信仰によって啓蒙思想の悪影響を吹き飛ばし、本当に聖書に立つことである。科学者でさえも、ラプラス主義やマルクス主義の狭い機関論的決定論をはるかに越えて、多層宇宙(amulti-leveleduniverse)にその思索のメスを入れている時、福音派がいぜんとして一八世紀の啓蒙主義や、一九世紀の進化思想の影響を受けて、底の浅い、薄っぺらい宇宙観、世界観にしがみついて、聖書を解釈し、霊的盲目となり、「悪霊などおりません」などと非聖書的なことを言っているようでは、まさに塩気をなくした塩である。人に捨てられ、踏みつけられるだけである。
六、誤った弁証
リベラル派は、処女降誕しないキリスト、奇跡を行なわないキリスト、復活しないキリストをつくり出して、キリスト教(と言うよりむしろ宗教)を近代人に弁護しようとして失敗した。つまり非聖書的キリストをつくり上げていったのであるが、近代カルビン主義(福音派も含めて)は「聖書と科学は関係ありません」と言うことによって、近代科学に対して自らを弁護してきたのである。それがつまずきのもとである。一方では、「聖書は真理の最終的規範」と告白しつつ、科学を特別扱いしたのである。このような言行不一致を平気でやりながら、わが神学は最高などと思っているとしたら喜劇である。実はこれは広い意味でのカルビン主義神学とさえも合わない。
というのは、カルビン主義というのは、その信仰の働く領域が、全生活であるからである。カルビン主義者がカトリックを批判して、カトリック信仰は、教会とこの世の生活を分離し、信仰は教会生活のみに限定している。しかしわがカルビン主義は、その生活の全領域に信仰が生きて働くのである、と誇るのである。しかしこれは偽りである。科学を除外しているからである。本当のカルビン主義は、科学も含むのである。
しかしある人は言うであろう。我々は科学を除外している訳ではない。ただその方法論にだけ限って言っているのだとしかしいかに方法論であろうと、信仰から切り放しているのであるから、生活の全領域とはなり得ないのである。
もはやカルビン主義ではない。実は「方法論」さえも信仰が働くのである、ということを後に示したい。いずれにせよ、「聖書と科学は関係ありません」と聖書と科学を分断して、近代人に対してキリスト教を消極的に擁護しようとしたのには訳がある。それはガリレオ裁判をはじめとして、教会が科学者を弾圧してきた罪を言い逃れるためである。
「あの時は、聖書と科学を一緒にしてしまって、つまらないことをしたものです。実は聖書と科学は別のものでして、信仰は信仰、科学は科学、やっとそのことがカントたちの教えによって最近わかりましたので、今後あのようなことはやりませんので、以後よろしくお願いします」と頭をさげたのである。クリスチャンは従順である。しかしこの場合は無知と不信仰による従順である。
この種の裁判で、最も目立つものはガリレオ裁判であるが、前述したように、ガリレオが裁かれたのは、聖書によってではない。カトリックの公認の教義であるアリストテレスの哲学(宇宙観)に合わなかったからである。むしろガリレオは聖書にかたく立っていたのである。
だからガリレオ裁判については、聖書と科学を分断して自己弁護する必要などさらさらないのである。むしろ「聖書と科学が一つだったので、カトリックに裁かれたのだ」と言うべきところなのである。つまり聖書ではなく、教会がガリレオを裁いたのである。このポイントを忘れてはならない。
それから、ダーウィンのブルドッグと言われたトーマス・ハックスレー等の進化論学者たちとの論争において、結局、教会側が不利になったのも、あまりにも教会側が不勉強でただ教会の権威によって、これらのものを圧しつぶそうとしたからである。この教会の体質はカトリックもプロテスタントも同じで、真理についての戦いで、「教会の権威をもち出す大きな過ちを犯す」のである。本当は聖書をもちだすべきなのだ。神の啓示の書であり、真理の最終的規範である聖書によって静かに論じれば良いのだ。それを教会の組織力で弾圧しようとする誘惑にかられるのである。これはサタンの働きである。だからガリレオ裁判にしろ、ハックスレー論争にしろ、神の栄光をけがし、歴史の汚点となるのである。
しかし今や、聖書を中心にして静かに論じ合えば、韓国の場合のように、進化論を撃破できるのである。今や進化論は危機的情況にあり、『進化論・危機にある学説』(マイケル・デイトン、川島誠一郎訳どうぶつ社)などと言う専門的な本がどんどん出版されているのである。
ハーバード大学で法学博士号を取得したノーマン・マクベスは、長い病気療養中に、『種の起源』の百年祭(一九五九年)があったので、暇にまかせて百年祭記念論文集を一冊たまたま開いて読んだ。それがきっかけで、十年にもわたって専門書を読んで、すっかり進化論への確信を失ってしまったのである。彼は有神論者でも何でもない。ただ進化論に興味をもって学びはじめただけのことである。そして進化論学者でも信じないことが、学校の教科書に載っていたり、人々の常識となっている事実に驚き、またジュリアン・ハックスレーほどの大生物学者が全く首尾一貫していないことを主張しているのを知って「これほど明白につじつまが合わないからには、しろうとが自分なりの意見を立てても許されるでしょう」と思って『ダーウィン再考』という本をあらわしたのである。
進化論学者たちの真理に対する不忠実さは、「モンキービジネス」のところで紹介したが、進化論学者とは、その進化論を専門にやっているものたちのことで、科学者一般のことではない。
トーマス・クーンの有名な『科学革命の構造』(the Structure of Scientific Revolution)の中にあるように、科学者は普通はパラダイムの中で、「通常科学」に従事しているのであって、パラダイム科学を聖書のもとにおくか、教会のもとにおくかは天地の開きがある。
そのものを問題にはしないのである。パラダイムを問題にする時は、「科学革命」となる。このように今でも、ノーベル賞をとるほどの学者でも、別にパラダイムは問題にしないで、その専門分野だけの研究をしている訳である。そして進化論は、現代のパラダイムになっているので、一般に科学者は、進化論が真理かどうかは問わないで、自分の専門の研究をしているだけである。
ところが、そのパラダイムをつくり上げた進化論学者たちがパニックなのである。そこで、世界的な進化論学者の今西錦司や、ゲーリー・E・パーカー博士たちのように良心的学者は、進化論を捨てたのである。ある進化論学者たちは偽物づくりに励んでいる。パラダイムにもなっている進化論であるので、偽っても固持して行きたいのである。ジュリアン・ハックスレーのように、オカルト宗教の会員になって「進化論は事実である」と呪文のように唱えている者もいる。だからこそ、稲垣久和氏は「進化論のパラダイムの廃棄」を声を大にして主張しているのである。
ところが、今だに「聖書と科学は別です」と言いながら、あてにならない進化論の影響を受けて、聖書解釈や、翻訳までも、進化論に合わせている始末である。進化論学者たちが「存在は偶然による」という今だに証明されない仮説に立って、「創造主はいない」とまことの神を否定しているのに、ただ沈黙しているだけである。沈黙どころか、前述したように、影響までされて、聖書の真理を曲げて、進化論に迎合さえしているのである。
この進化論の非科学的、そして偽りに満ちた、とても学問ということができない行状を、いかんなく暴露しているのは、何とノン・クリスチャンの良心的学者たち、科学ジャーナリストたちである。せめてジェレミー・リフキン『エントロピーの法則』(祥伝社)、フランシス・ヒッチング『キリンの首』(平凡社)、マイケル・デイトン『反進化論』(原書の「進化論・危機にある学説』の方がよい。どうぶつ社)のうち一冊でも読んだなら、進化論の実態を知って驚くであろう。
未信者でさえも、義憤を感じて進化論の偽りを暴露しているのに、リベラルや福音派は時代おくれの神学書に書いてある進化論などを読んで、進化論と取り組んでいるのだからどうにもならないのである。アメリカの友人に聞いたのだが、あるデータによると、何と、科学者グループよりも、神学者、牧師のほうが進化論を信じているパーセンテージが高かったと言うのである。あきれてものが言えない。
主なる神を否定する理論に迎合していては、本当の神学をきずくことは決してできない。実はクリスチャンのグループで、学問的に進化論の非科学性と偽りを、正面から堂々と暴露し、論陣をはっているいるのは「創造科学研究会」である。このグループは、その道の最高の知性の集まりであって、進化論学者が恐れている生化学者のデュアン・T・ギッシュ博士、所長のヘンリー・M・モリス博士、かつて進化論の教科書を書いたゲーリー・E・パーカー博士などなど、その道の専門家であり、「彼らは熟練した科学者であり」とフランシス・ヒッチングも認めざるを得ないでいるほどの学者たちである。
ヒッチングはノン・クリスチャンの学者であるので、あまりにも聖書中心のギッシュに不快感を露骨にあらわしているが、その学者としての真価は高く評価し、「非常に知的で、正統派進化論に対抗するのに必要な知性を十分に備えている」と告白している。
このように未信者の、その道の専門家でも、その実力を高く評価しているのに、何と福音派の多くの神学者は、この創造科学研究会を蔑視しているのである。この福音派の神学者たちの高慢はどこから来るのであろうか。
第一に進化論の実状を知らないことである。
第二に、進化論に関してクリスチャンの本よりも一般の本を読み過ぎているからである。と言うのは現在、進化論学者がこの世のマスコミを牛耳っているので、彼らに都合のいい様に真理を歪曲して報道しているのである。とくに創造科学研究会については根も葉もない報道をいている。
神学者たちはこの様な偽りの情報に影響されて創造科学研究会を誤解するのである。
第三に、創造科学研究会をファンダメンタリスト(根本主義者)と軽蔑して、耳を傾けようとしないことである。
未信者のヒッチングでさえも、その主張にしっかりと耳を傾けて論じ合っているのである。何故に耳を傾けないで批判しているのか(この非科学的態度よ)。それは、「聖書から科学について語れるはずはない」という不信仰からである。つまり、その種の神学者にとっては、聖書は最高の真理の規範ではないのである。そして進化論と真っ向から論陣をはって闘っているクリスチャンのグループを支援しようともせず、また自ら進化論と闘う実力もなく逃げ回っているのである。あまつさえ、進化論からの影響さえ受けている。未信者の学者でも、「進化論は自然科学ではない」(渡部昇一)と堂々と正面きって論じている時にである。
なぜこのように進化論と対決する気力がないのか、我らの神が否定され、あざけられているのに。それは前述したように、ガリレオ裁判の誤解と、進化論との論争の初期において、教会が組織力で圧し潰そうとして失敗したこと、そしてまた一九二五年の有名なスコープス裁判においてファンダメンタリストが嘲弄される場となった事であろう。実はこの場合もファンダメンタリストが、教会の組織力によって論敵を押さえつけようとして失敗したのである。
このスコープス裁判を境として、啓蒙主義の影響の強い近代カルビニストたちは、もう二度と進化論とは議論できないと、逃げるか妥協か(有神進化などで)の道をとってきているのである。
勝てる試合で逃げ回っているボクサーみたいな姿である。試合の始めの方のラウンドで、なめてかかって、ガードをさげてパンチを出したら、思わぬパンチを喰って、気力をなくし、あとは逃げ回っているだけのボクサーである。二度とパンチを出そうとしないで、ガード一方である。これでは弱い進化論にも勝てる見込みがない。
何故に偽物造りのヘッケルの「反復論」が教科書に載り、モンキー・ビジネスと言われるほどの「偽物」を造っている進化論が、学問として許されているのか。それは近代の時代精神に合っていたからである。文芸評論家であり牧師の資格もある佐古純一郎氏は「近代文学の精神は、神のアリバイ(不在証明)を立てることであった」と言っているように、進化論は、神否定の理論、もっと正確に言えば、聖書の神を否定する理論で、まさに時代が要求していたものなのである。
マルクスとエンゲルスが、進化論に狂喜したことを本文に開いたが、まだ証明されない仮説「存在は偶然による」に基ずく進化論を自分たちの理論の基礎にすえたのである。そして「社会ダーウィン主義」が発展した。これらの社会学者にとっては、進化論は仮説では困る訳で、絶対に真理でなくてはならないのである。だからこれらの社会主義者や学者たちが、さかんに進化論を真理であるかのように宣伝し、人々を洗脳していったのである。
左翼学者たちの「偽物造り」も進化論学者たちに劣らず一流である。周知のごとく、日本のほとんどあらゆる大学の経済学部で、左翼学者たちは、ソ連や中国が天国のようなことを我々学生に教えてくれたものである。平等どころか、共産党幹部たちだけが貴族のような豪華な生活をし(ノーメンクラトゥーラ)、人民が物不足で行列をつくり、秘密警察におののきながら生きていた時にである。右翼よりも恐ろしい全体主義に自由を奪われていたのに、である。この左翼学者たちも、偽りの天才である。共産主義が崩壊するのは当たり前のことなのだ。そしてその理論の基礎となった進化論も崩壊の危機にあるのである。
さきに紹介したフランシス・ヒッチング(HrancisH itching)は、イギリスで大変に名の知れた科学ジャーナリストで、多くの著書と共に、テレビの科学教養番組の制作者でもある。無神論者で、創造論者ではないが、しかし進化論についても膨大な資料を駆使して正確な批判を行なっている。その彼の本を読んで、何故にこれほどまでに偽りに満ちた進化論が、一般の人々に信じられているのかがわかる。例えば、「化石証拠は進化論を否定する」のであるが、何とその逆に、進化論学者は、一般人に「化石が進化論を証明する」というようなことを平気で書くのである。
化石証拠は、実は進化論学者にとって、生命とりになるほど困難な問題である。
「主要なグループの間をつなぐ化石をいくら探しても、そんなものはほとんど、あるいはまったくと言っていいくらいにない――博物館の標本棚は、中間的な生物の化石でいっぱいになってもいいはずである。
つまり両者の特徴がわずかずつ混ざり合っていて、どこで無脊椎動物の時代が終わり、どこから脊椎動物の時代が始まるのかがはっきりわからないような化石が、大量にありそうなものである。
しかし現実はそうではない。不思議なことに突如として、完成された形態のものが、もっともダーウィン流ではない仕方で登場してくるのである」
つまり「種から種へ」の化石など出てこないのである。化石はまさに聖書的に「種類にしたがって」出てくるのである。化石証拠は何の無理もなく、進化論的仮説を否定し、聖書を支持するのである。
ところがである。進化論者たちの一流の「偽物造り」が始まるのである。
「進化に関する一般向けの入門書や教科書などを見てみればたいていの著者が、化石の欠落にはなるべく触れないようにしながら調子よく自信満々に話を進めているため、読者にはそのような問題が存続することなどほとんどわかりようがない。彼らは、化石の証拠も示さずに、いかにももっともらしいお話を書いてしまっているのだ。適当な突然変異が決定的瞬間に偶然生じて、そうしてやがて進化は新しい段階へと突入していった、という具合にである」(『キリンの首』)
これはもはや犯罪である。黒を白と言っているのだ。上智大学の渡部昇一教授が、「進化論は自然科学でない」と言ったのは何も大げさでないことがわかったと思う。このような進化論学者たちの偽りをよく知っていた世界的進化論学者今西錦司は、「我々進化論学者は、進化論に不利な証言を隠してきた。これは学者としての良心に恥じる」と告白し、その後しばらくして「科学者廃業」を宣言し、進化論を捨てたのである。
余計なことだが、実はダーウィン自身、この中間形態の存在については、自信がなかった。そして実に歯切れの悪いことを言っている。
「自然淘汰の理論によれば果てしのない数の中間形態が存在していて各群のすべての種を現存変種と同様の細かい漸進段階によって互に連結しているはずだから、次のように問われよう。
何故われわれはこれらの連鎖形態をわれわれの周囲の到るところに見ないのであるか。何故に一切の生物は解き難い混沌の中に混ぜ合わされていないのか、と。現存形態に関しては、われわれは(稀な場合を除いては)それらの間のつなぎ環を直接に発見することを予期する権利はないのであって、ただその各々と或る押しのけられた絶滅形態との間にそれを予期する権利を持つだけであることを想起しなくてはならぬ。」(『種の起源』下巻、堀伸夫訳、槇書店337頁)
このように「つなぎ環を直接に発見することを予期する権利はない」と変なことを言っている。さらに中間形態の「化石証拠」については、「地質学的記録は大抵の地質学者が信じているよりも遙かに不完全である」と言って、化石証拠のないことを地質学者の責任にしている。
しかし地質学の発展と進歩によっていよいよダーウィンの仮説は危機をむかえているのである。状況はダーウィンにとって、遙かに悪くなっているのである。もし現在ダーウィンが生きていたら、恐らく自分の仮説をとりさげていたであろう。
私が進化論学者たちに騙されなかったのは、三〇年前、京都大学の生化学者小牧助教授との出会いによる。その後、宇佐神先生や、堀越先生との交わり、そしてギッシュ博士や、パーカー博士との出会いによる。面白いことに創造科学研究会の会員は、はじめは「進化論に反対するなどとんでもない」と思ってた人が割と多い。しかし、その後進化論とまともにとり組んでみて、「なるほど、これはとんでもない学問だ」とわかったのである。
しかし普通は化石の場合のように、一般人だけでなく、神学者まで騙されているのである。良心的な進化論学者はこのようなことに耐えられるはずはなく、昆虫生理学者で著名な日高敏高教授は、率直に進化論の疑問を述べている。とくに朝日新聞社発行の『世界動物百科』の中で。それに対して「あれは今の生物学者がだれでも思っていて、じっとがまんして、いわないでいることだ。それをまあ、君はヌケヌケと書いて……」と非難された。
このように専門家たちは皆知っているのである。そして「いわないで」隠しているのだ。「それをなぜ暴露したのか」と責められた訳である。これが進化論の実態なのである。これは外国も同じ事で、ハーバード大学のスティーブン・グールド教授は、化石の欠落のことを「古生物学の商売上の秘密」と呼んでいる。こんな進化論者たちに騙されて、影響されて、聖書解釈や、翻訳まで歪曲して、進化論に合わせているとは、そして学問的だ、などと考えているとは、本当に情けない話である。われわれ近代カルビニストはどこかで間違ったのである。だからスコットランド神学できたえられたトランス教授は、古代教会に帰ろうと言うのである。
進化論も、啓蒙主義も遙かに飛び越えて、最も聖書的だった時代へ!
七、ドグマティックス(独断論者たち=教義学)とあだ名されよ
もし初代教会や古代教会が、プラトンやアリストテレスの哲学の影響を受けながら、神学をつくり上げたら「三位一体」の教理など生まれはしなかっただろう。ニケア会議のような「ホモウシオス」も確定しなかったであろう。ただ神の啓示である聖書のみから導き出された教理なのである。近代カルビン主義のように、啓蒙思想や、進化思想の影響を受けてでき上がった神学とは訳が違うのだ。カルビン主義を本物にしたければ、もう一度聖書を読み直すことである。
ところで、神の三位一体の教理は、周知のごとく、そして前述のごとく全く聖書にのみ聞くことによってしか与えられないものであった。そしてこの教理は、何かのたとえでは説明することができない。人間の理性を越えたものである。そして、この聖書からのみ聞くことによって与えられた神の教理は驚くべき真理である。
例えば、哲学の永遠の命題と言われる「一と多」の問題がある。人間はこれに明確な答えを得ることはできない。ちなみに個人主義と全体主義の問題、個人を強調する国家は全体の力を失ない、全体を強調すると個人が犠牲となる、というように「一と多」の問題は、量子力学の不確定性原理のように、まさに「あちらを立てれば、こちらが立たず」なのである。人間が永遠に解決できない問題の一つである。しかし、永遠なる神においては、見事に解決されているのである。
三位一体の一と多の完全な調和よ!最新物理学者が耳を傾けたいのはこのような事柄なのである。
「神の主権」と「人間の自由意志」の問題も全く聖書から聞くことのみによって珠玉のような真理を得ることができるのである。結論から言えば、神100%、人間100%である。聖書においては、神の主権は明きらかであって、神はすべてをなし給うのである。つまり神の主権は100パーセント主張されている。「では人間は何パーセントなのですか」と聖書に問えば、「人間も100パーセント」なのである。アダムは自分の罪に全責任を負わねばならなかったのである。
人間の救いは「神の選び」によることは明らかである。エペソ人への手紙一章4節など「世界の基の置かれる前から」予定されていたのだ。善も悪もする前から、である。つまり神の主権が100である。しかしまた人間の救いはわれわれの決断による事を聖書は明らかにする。「主イエスを救い主と信じれば救われる。信じなければ滅びる」(ヨハネ三・三六、ローマ一〇・九)のである。つまり人間も100である。100と100では理性を越えているが、聖書がそのように言うので受け入れるのである。三位一体と同じように、信仰で受け取るのだ。ちょうど、最新物理学者が「光が波でもあり粒でもある」という事実を、ニュートン力学――人間の常識には合わないけれども、事実として素直に受け取るのと同じである。
だからある日、ある人が「神の選びによって私は救われました」と証し、次の日に「私は主イエスを信じる決断をし、それが私を救いました」と証しても、どちらも本当なのである。どちらも聖書的なのである。ただし、聞いている方は「それは矛盾だ」と言う。論理的でないから。しかし言わせておけば良い。聖書の真理は不完全な理性に合うはずない。天国で我々の理性が完全になった時、完全に理解するであろう。このように聖書は、神の100と人間の100を我々に語る。だからこそ、聖書の霊感も「有機的霊感説」を信じるのである。機械霊感は聖書的でない。神が100で、人間が0であるから。ところで近代カルビニストは、聖書の霊感説では有機霊感を信じるが、伝道だと、とたんに機械霊感へと堕落するのである。人の救いは人間の業ではないのだ、などと言って伝道しないことを誇るのである(ただし韓国は別)。
しかしパウロを見よ、あれほどの明確に「神の選びによる救い」を信じていた彼が、あたかも自分の努力が人を救うのだと言わんばかりに、救霊に励んだのである。「それは何とかして、幾人かでも救うためです」(Ⅰコリント九・二二)と。パウロにおいても、神の100と人間の100の両者が生きているのである。
これが聖書の言う「神の主権」と「人間の自由意志」の問題であって、もしこの両者を聖書の主張のように受け入れれば、カルビニストとアルメニアンの醜い論争は必要なかったのである。
「神が100なら、人間は○」これは人間の論理である。このようなものを中心に聖書の真理を歪曲して神学をつくり上げてはならないのである。
このようにして、本当に聖書に聞くことによってのみ、我々は類いまれなる真理を得ることができるのである。
聖書が本当に、神の啓示の書であり、誤りなき神の言であるならば、そして真理の最終的規範であるならば、科学をも基礎づけることができるのは当然のことである。
そしてこの点においてまず知るべきことは、コリント人への手紙第一、一章二一節「事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがない……」とあるように、もし科学を人間の思弁である哲学のもとに置いたなら、真理(神)にいたることはないのである。だからこそ、神(真理)の啓示である聖書のもとに科学を置くべきなのだ。
そしてローマ人への手紙一章二〇節「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきり認められる……」とあるように、人間は誰でも、神の創造の御手による被造物を観察すれば、神を認めるはずあるというのだ。つまり正しく科学すれば、誰でも創造主である神を認めるのである。つまり、創造主を認めない科学などないのである。だから無神論者の科学は本当の科学ではないのだ。
「無神論者(創造主である神を認めない者)の科学は、科学として成り立たない」ということを我々は主張しなければならないのである。聖書に従って。その時、人々は我々に言うであろう。「独断論者たち(ドクマティックス)!」と。それでいいのだ。まさに無神論者たちの科学は、人々を神(真理)へではなく、サタンへ導いて行くのである。ラウシャー女史や、ジュリアン・ハックスレーのように、今や多くの量子力学者、進化論者たちが、東洋神秘思想(オカルト)に走っていっているのである。まさに悪霊の力を求め、その霊の力を体験しているのである。何と最新物理学者たちがサタンに走って行っているのである。ある者たちはルシファー礼拝をしている。それを真の神(創造主)へと導かなければならないのである。
明治大学の不正入試事件が明るみに出た時、一人の明大教授が大学を辞任した。その名は栗本慎一郎、テレビによく出演していたおなじみの人物である。法学部教授であるが、経済人類学専攻であって、彼の「神観」は、
「断っておくが、私は宇宙の根源そのものであるような、宇宙全体の、始まりもなく終わりもないような壮大な「場」をイメージした「神」の存在を信じている者である。しかし、そこら辺の宗教がしばしば先に述べた程度のものを「神」とか「悪魔」にしたてあげていることは間違いない。
弱く、社会のさまざまな現実によって袋小路に追い込まれ、それによって溜まってくるストレスを折り折りの小さな爆発(小暴力)で発散することさえできない若者たちを取り込む宗教。
信じるが故に思考停止に陥る若者たち、そこで目をつぶらなければ、もはや逃げ場のない若者たちを組織の命令に服従させる宗教―そうした宗教がいう「神」や「悪魔」とは、間違いなく我々より数百年先の生命体にすぎない。
「宗教」を名乗る大半が、この壮麗なる宇宙をイメージした真の「神」を見てはいない。そうした宗教が崇拝してきた、いわゆる「神」とは、この私やあなたと五十歩百歩の「生命体」に過ぎない。
そんなものに頼るのはすっぱりやめてしまいなさい。そして、自分自身に問いかけ、自分と宇宙とのつながりの中に自分の運命を鋭く見つめていかなければならない。そのときはじめてヒトは真の「神」の創造の意図に触れ、そのルールを悟り、自分の生きていく道を知るはずだ。」
(『人類新世紀終局の選択』青春出版180頁)
この大学教授の壮大な神観は、リベラルより遙かにましである。「ヒトは真の「神」の創造の意図に触れ……」とあるように、一瞥しただけでは聖書の神との差をほとんど見い出すことはできない。そしてしかも、多くの若者たちを惑わす新宗教の低次な神々を批判しているのである。
唯物思想や進化主義に影響されたリベラルなど足元にも及ばない神観である。これでリベラルはノック・アウトである。手も足も出ない。そしてしかも彼は、量子力学に精通し、ノーベル賞を授賞した利根川進氏が「生命現象はすべて物質レベルで証明できるだろう」と言った発言を「本物の思想はDNAの遺伝情報にはのらない」と正面から批判している。
利根川進の従来の進化論パラダイムの思考のあり方を批判しているのである。これはもはや進化論に腰を低くしている近代カルビニストや福音派以上である。クリスチャンでない栗本慎一郎教授が、その壮大なる神観で、ノーベル賞をとるほどの進化論パラダイムの無神論学者をたち切っているのである。進化論に影響されている近代カルビニストも福音派も、リベラルと同じように、彼の足元にも及ばないのである。クリスチャンでない最新物理学者たちの「神観」はそれほどに高度なのである。従来の進化論など吹き飛ばされてしまう。勿論、唯物思想など影も形もない。
だからこれらの人々に対して、啓蒙思想や進化思想の影響を受けた不純な神学近代カルビン主義では全く太刀打ちできないのである。啓蒙思想や進化思想を徹底してきれいに洗い流した、本当に聖書的神学でしか対抗はできないのである。一八世紀、一九世紀の学問でつくり上げた神学など全く役に立たないのだ。だいたいそのような神学のあり方が間違っていたのである。だからトランス教授は古代教会に帰れ、と言うのである。
さて栗本慎一郎は、それでは我々と同じ聖書的な創造主なる唯一の神を信じているのであろうか。引用文で気づかれたと思うが、彼の壮大なる神は、「宇宙の根源そのものであるような」とあるように極めてアリストテレス的である。そしてまた次の「宇宙全体の、始まりもなく終わりもないような壮大な……」とある言葉で一層それが明らかになる。では彼の神観はアリストテレスのそれと同じようなものかと言えば、全く違うのである。
引用文の中に「……そうした宗教がいう『神』や『悪魔』とは、間違いなく我々より数百年先の生命体にすぎない」と一般人には訳のわからないことを言っているが、それは彼の言う「我々より五百~六百年進化した」生命体なのである。それを彼は低次な神と言うのである。
では彼の信じる宇宙大の高次な神とは何か、「人間よりはるかに進化した宇宙存在」と言う表現が、彼の著書の中にあるが、これはまさにオカルト宗教「ニュー・エージ・ムーブメント」の神ではないのか。つまり「ルシファー(サタン)」となる。
ニュー・エイジについては一部に書いた通りであるが、世界最大のオカルト宗教であって、恐るべき「反キリスト」なのである。実は栗本慎一郎が自ら語っているように「幽体離脱」をなし、悪霊との「チャネリング」を実践するオカルト行者なのである。ニュー・エージとの関係は相当に深いはずである。
このように栗本慎一郎の本体を見抜くためには、全く聖書的な神学でなければできることではない。そして現実社会で何が起きているかをみる科学的な目である。進化思想におかされた思弁で演繹的に、遠くの方から世の中を見ていては現実の人間を知ることはできないのである。
実はニュー・エージは、新しいタイプの進化論をもっているのである。だから、「利根川進の従来の進化論」とわざと「従来の」と書いたのであるが、ニュー・エージの会員に、世界的生物学者である進化論推進者のジュリアン・ハックスレーがいた。なぜ進化論学者がオカルト宗教の会員なのか。それは進化論的仮説は、本文に書いたように数学の確率からもすでに証明は無理なのである。
「東京の夢の島に台風が来て、ゴミをまきあげ、台風一過、偶然にゴミが集まってジャンボ・ジェット機ができました」(フレッド・ホイル)と言うような確率のことを言っているのである。それは無理だと誰にもわかる。それを進化論学者は「出来ます」と主張しているので、の笑いになるのである。これはミクロの世界があまりにも精巧なので、「偶然」は確率の面からだけでも無理で、「誰か知恵者がつくりました(創造論)」の方がはるかに納得がゆくのである。
そこで、従来の進化論をやめて、誰かものすごく高度に進化した存在が、すべてをつくったと言うのである。これで進化論を維持しながら、もの笑いにならずにすむわけである。しかし、その行きつくところは「ルシファー」(サタン)なのである。そしてこの世界的進化論学者ジュリアン・ハックスレーが、何とルシファー礼拝、つまりサタン礼拝をしていたのである。
このように創造主である真の神から離れた科学は、サタンへと走るのである。栗本慎一郎の高度に見えた神も、ルシファーとつながっていくのである。オカルト宗教だからである。悪霊と関係をもった者は、サタン礼拝へち向かうのである。二十世紀、そして二十一世紀(主の御再臨がまだなければ)の闘いはこのような闘いなのである。
「悪霊などいない」などと寝言を言ってる時は過ぎたのである。そんな非聖書的な神学は、何の問題も解決しないのである。
我々が学んだ神学校の先輩が、九州の原始福音の異端に走った。私が丁度インドネシアで宣教師として奉仕していた頃である。その先輩は、成績優秀(信仰や人格は別で)で、やがて神学校で教えることにもなっていた。ところが異端に走ったので、先輩、同輩が行って説得したが、どうにもならず、ついに恩師である神学校校長が説得したそうである。
しかしやはり説得に失敗し、その校長先生は、「駄目だったよ。聖霊を受けてしまったそうだから」と言ったそうである。つまり電気に打たれたような異常な体験をしてしまった者に、いくらそのような体験は「気のせいだ」と言っても、「神学的には起こり得ない」と契約神学や、デスペンセーショナリズムでやっても駄目である。
そのような場合は、「異常な体験はたしかにある」と彼の体験を認めなければならないのである。事実は事実として。「ただし、それは悪霊だよ」と言ってはじめて、彼は自分の否に気づくのである。そして解放を願うようになるのである。彼は現在、行方不明だそうである。このような場合、まだ望みはある。それは「祈り」である。ここにこそ解決があるのだ。
この点において我々は、大いにペンテコステ教会から学ぶ必要がある。もちろん我々福音派も、大いに祈りを強調する。しかし時間のかけ方も、信仰も、ペンテコステ派にはかなわない。それはもはや賜物の差である。
我々の宣教師訓練センターは超教派であるので、福音派からペンテコステ派まで、種々の教派から訓練生が来る。数年前に、天安門広場事件が起きた時、我々はテレビに釘付けであった。その時、ペンテコステ教会から来ていた訓練生の姉妹は「先生、断食させてください」と言って十日間、断食をして中国のために祈った。
その時、所長の私(福音派)をはじめ福音派の訓練生たちは、テレビをみていた。どちらが正しいか。祈る方か。テレビで中国をみる方か。このようにペンテコステ派の祈りは質が違うのである。もちろん、我々も中国のために祈りはする。しかし祈り方が違うのである。我々福音派は聖書信仰、聖書である。聖書なしにやって行けない。しかしペンテコステ派は、祈りなしにやって行けないのだ。だから、互いに学ぶべきなのである。
あまりにも明らかなことだが、主なる神は一人のキリスト者に、すべての賜物をお与えにならないように、一つの教派にすべてをお与えにならないのである。それは謙遜を身につけるためである。
他から学ぶという謙遜のためである。だから他教派から学ぼうとしない者は非聖書的になって行くのだ。つまり、皆で同じ誤謬をなしていて気がつかない。いや、うすうすわかっていても修正しない。ところが、他教派をよくよく見ると変なことをしている。「あんなことが許されるのか」と思って聖書を良く読んでみると、なんと聖書的なのである。そこでそこから学んで成長し、より聖書に近づくのである。
もしある「きよめ派」の教派が第二のめぐみを否定するというので「カルビンなんか読むな。あれは悪魔だ」と言ってカルビンとカルビン主義のすべてを否定するなら大変な宝を失うことになる。同じようにカルビニストが他教派を軽蔑してわが教派は最高などとうぬぼれたいなら、お笑いぐさである。また非聖書的である。だから、教派、教会の伝統は重んじるべきであるが、そこに立っては、もはや成長しない。「聖書に立つ」のである。聖書のみ(何となつかしい言葉か)である。
だからより聖書的になるためには、他教派というアンチテーゼが必要なのである。もう少しリベラルが福音派を敵視したり、軽蔑したりしないで、福音派から学ぶならば、素晴らしい宝を得ることができるのに、と心ある人は思うだろう。同じようにもし福音派がペンテコステ派を敵視したり、軽蔑しないで、もう少し謙遜になってペンテコステ派から学ぶならば、教会はもう少しましになるのである。
宗教ブームで福音派も少しは増えているが、ペンテコステ派の足元にも及ばない。特に近代カルビン主義者は、一般的に知的なことばかりを求めて、霊的なことにうとい。まことに幼稚である。この点もペンテコステ教会から学ぶことである。と言うのは、我々が、リベラルとの接点あたりで、激しい神学の闘いを「知的に」やっているように、ペンテコステ派は、聖霊と悪霊との接点で、これまた激しい闘いを「霊的に」やっているのである。聖書的なペンテコステ派も悪いカリスマと闘っているのである。福音派以上に。
これは激しい闘いである。その闘いを第一線で闘っている人々から学ぶことである。祈ったことのない人から、祈りを学ぶことは空しいように、霊的なことをよくわからない人に霊的なことを聞いても何の役にも立たない。霊的な事柄をよく知っている人から霊的な事を学ぶべきである。
これほどまでにオカルトが世界的に氾濫している時代はあるだろうか。トップレベルの最新物理学者たちでさえ、オカルトに走っている時代である。ここにも啓蒙思想家たちの限界が暴露されている。カントが「啓蒙とは何か』(一七八四年)の中で「啓蒙とは、人間が未成年な状態から脱却することである……」と主張したのは有名だが、そして啓蒙思想は、フランス、イギリス、ドイツとそれぞれの特徴はあるが、共通しているのは、人間理性の解放である。
宗教から、王政から、そして伝統的な因習から。そうすればつまらない迷信なども、消え去っていく筈であった。しかし、ハイテク産業が生み出した数々の近代的利器に囲まれて、近代科学の精神を子供の頃から学んだ現代人が、何と占いや迷信に走り、呪文を唱え、どんな新興宗教でも、始めれば必ず成功するほどに人が集まり、若者がぞくぞくとオカルトの新宗教に走り、あまつさえ量子力学者までが、東洋神秘思想に答を求めに集まっているのである。聖書を離れた啓蒙思想家の限界がここにある。人間についてよくわかっていなかったのである。
今や、量子力学が、目に見えないミクロの世界から、意識の問題、そして霊の世界へと向かって進んで行っている。だからこそ「霊を見分ける」(Ⅰヨハネ四・七)ことが重要なのである。異言でも、聖霊からか、悪霊からか、見分けることが重要なのである。この点において近代カルビン主義者は、手も足も出ない。霊のことがわからないからである。だから謙遜に学ぶことである。
ペンテコステ派の先生方から、身を低くして学ぶことである。謙遜な者は祝福される。ペンテコステ派の先生方には、東大、京大出身の最高の知性を備えた方々もおいでになるのだ。しかも立派な信仰と、人格も兼ね備えた方々である。知性の面だけでも、足元にも及ばない方々であるが、謙遜にも、私のようなものからも学ぶ姿勢をもっておられるのである。我々カルビニストや福音派も、もう少し謙遜を身につけるべきである。
伝統的教会が、福音派をよく理解していないように、我々福音派も、ペンテコステ教会をよくわかっていない。ある人はペンテコステ派は異端である、などと言ってその無知無能ぶりをさらけ出している。私はある時、東大、ICU、東神大などの教授たちと、国際協力について話し合ったことがある。
その時、その東大教授が、主な話が終わって、お茶のみ話になった時、「奥山先生、福音派というのは、聖書を文字通り信じて、つまり、ホーリネスなんでしょ」。つまり、彼の頭には、聖書を神学も学ばないで、ただ文字通り信じているクリスチャンは、昔のホーリネスのようなタイプ、と言っているのがわかった。
その無知と不勉強ぶりにあきれ果てたが「福音派には、カルビニストも、ルーテル派も、バプテストもいるのです。ホーリネスなどと軽々しく言っておられますが、皆さんより立派な神学者がたくさんおられますよ」と答えたら、ウーンとうなっていた。自分の了見の狭さ、知識のなさにショックであったようだ。恐らく、福音派のペンテコステ派理解も、その程度のものだろう。極めて貧しい資料と、一面的な情報で判断しているようである。ペンテコステ派のほとんど何もわかっていないと思う。「福音派は昔のホーリネスだ」式である。
このような訳で、今や最新物理学者たちは、東洋神秘思想に近づき、意識、霊の世界に足を踏み入れている。この時、彼らを正しく導くことができるのはペンテコステ派である。そして、創造科学研究会。何と福音派が最も軽んじていた人々である。つまり軽んじられた人々の方が、はるかに優れていたのである。
近代カルビニストも福音派も啓蒙主義や進化論の影響を受けて、機械論的十九世紀的世観で神学をやったので、大きく出遅れてしまったのである。そのような誤った神学で、「悪霊はいない」「聖書と科学は別」などと非聖書的なことを言って、正統派と思っていたのである。もし啓蒙主義や進化論の不純物を取り除いて、古代教会のように聖書的になるなら、二十世紀、二十一世紀の闘いになんとか間に合う。
しかし依然として、不純物をかかえたままの神学で、自分の地位だけ守ろうとするなら、捨てられる。そして神学者たちが一瞥も与えなかったエジンバラ大学を中心としたスコットランド神学が望みである。
これらの人々、「聖書からの科学」を主張してやまない神の器たちこそが、二十世紀、二十一世紀の闘いに最もふさわしい人々である。換言すれば、最新物理学者の宇宙観の方がリベラルや近代カルビニストの狭い機械論的宇宙観よりも、はるかに多層的であり、聖書的なのである。彼らはリベラルや近代カルビニストの底の浅い十九世紀的宇宙観をとび越えて、宗教に、霊的世界に猛接近しているのである。
だからこそ、創造科学研究会(知的)の、ペンテコステ派(霊的)の出番なのだ。物理学者が宗教と共に科学する時に、最もふさわしいのは、このことを長年やってきた創造科学研究会である。また物理学者が東洋神秘思想に走った時、それは悪霊だと見抜いて、これを正しい方向に導くことができるのはペンテコステ派である。
さてここで、聖書的科学の方法論について明らかにしなくてはならない。それは何よりも有神論が大前提である。しかも哲学の思弁が考え出した神でもなく、オカルト行者が瞑想などで描き出した神でもなく、聖書に啓示された天地万物の創造主なる唯一の真の神である。永遠なる神である。
だから現時点では、量子力学の主流派(コペンハーゲン学派)に反対したアンシュタインの立場を支持する(今のところ軍配は主流派にあがっていても)。と言うのはアインシュタインはスピノザを越えて、永遠者に思考が向かっていたからである。つまりボーアの場合、キェルケゴールの実存主義の影響で、不確定性にとどまって、それ以上に進もうとしなかったと見られるからである。
さらにこの聖書的科学の方法論は帰納的なことを重んじることは言うまでもないが、「聖書は真理の最高の最終的規範であり、究極の権威」と信じる故に、演繹的である。だから「進化論学者が、〝存在は偶然による"という仮説を立てた場合、これは純粋に科学的なことだから、キリスト教からは何も言えない」などという主張には反対である。それは啓蒙主義の影響による「聖書と科学の分断の罪」による誤った考えである。我々はこのような進化論の非聖書的仮説に明確に「ノー」と言うべきなのだ。
ところが、クリスチャンの学者たちは、「近代科学は聖書と共にはじまった」と主張しながら、「聖書からは科学に対して何も言えない」と言う矛盾したことを言うのである。まずこの種の学者は、信仰がはっきりしていないか、成長していないので、神中心になれないのであろう。何よりも啓蒙主義の影響による。科学の分野においても、自然の観測者である人間が神を認めることは人間の本分であるのだ(ローマー・二〇)。
それ故に神を認めないことは人間の本分からはずれているので、自然の観測者(科学者)としてはすでに失格である。そして神を認めない科学者は哲学しかもち得ないので、正しい演繹はできない。しかしキリスト者の科学者は(但しリベラルのような名ばかりの科学者は失格)、創造主である神から正しい演繹ができる(ケプラー)。
科学主義の台頭によって経験主義、客観主義がさかんに強調され、純粋に帰納的であることを主張するが、演繹しない人間などいないのである。それは人間の本分であるからである。実はハイゼンベルグは実証主義の流れをくんでいた。だから「ボーア軌道」を否定した(確証がないので)。そのハイゼンベルグが来日し、東大で講演したが、ちょうどその時、「クオーク発見」のニュースがあった。早速、記者たちがコメントを求めた時、「それは嘘だ!」と即座に否定したと言われている(『パラダイム・ブック』日本実業出版社92頁)。
なんと主観的か。これが人間なのである。だから重要なのは何を土台として演繹するかである。哲学か、それとも聖書か。もちろん聖書こそ最も正しい演繹の土台なのである。だから進化論学者たちが「存在は偶然による」というのは真の神の存在の否定、つまり「真理」の否定であるので、科学でさえない。真の神の否定は真理への反逆である。だからこそ「進化論は自然科学でない」のである。
読者は気づかれたと思うが、エジンバラ大学のトランス教授が、「神学と科学」と言っているのに、筆者は「聖書と科学」と言ってきたことである。これがトランス教授と筆者の違いなのである。
なぜ聖書でなければならないかと言うと、いかに古代教会の神学も、所詮神学は神学なのである。だから神学のもとに科学をおくと問題となる。もし仮に、近代カルビン主義のもとに科学がおかれたら、大変なことになる。啓蒙主義や進化論にさえふりまわされるのであるから。ましてやリベラルのもとにおいたら絶望である。このように「神学は誤り得る」のである。
だから「誤りなき」聖書のもとにこそ科学を基礎づけるべきなのである。なぜなら、もし神学のもとに科学をおくと、「教会の権威」がからんでくるからである。これでカトリックも(ガリレオ裁判)、プロテスタントも(ハックスレー論争)、ファンダメンタリストも(スコープス裁判)失敗したのである。教会の権威を、真理の闘いにもち出してはならないのである。聖書を中心に静かに論じ合うことなのだ。だからこそ、神学でなく、聖書によって科学を基礎づけるのである。
今や「二〇世紀の始まりと共に幕を開けた新しい物理学は、ニュートン力学だけでなく、近代科学がよりどころとしていたデカルトの哲学をも科学的な証明によって崩してしまった」と言われ、かつて「科学的知識だけが真の知識(真理)である」と豪語した十九世紀の栄光は去って、ハイゼンベルグまでが「そもそもの出発点から、我々は自然と人間との論争に巻き込まれており、その中では科学はごく小さな役割しか果たさない」と科学の役割の小さいことを語り、何とシュレーデンガーが
「主体と客体は、一つのものである。それらの境界が、物質科学の最近の成果でこわれたということはできない。何故なら、そんな境界など存在しないからだ」と平然と主張している中で、物理学者も科学者も途方に暮れているのである。
今までの帰納法は役に立たず、何を土台に演繹すべきかを知らないからだ。この時、現代科学者を正しく導くのは東洋思想ではなく、神の啓示である聖書なのである。
最後に量子力学の話で結論としたいが、近代科学をここまで発展せしめた量子力学の大成功については万人の認めるところである。しかし前述したように、その理論は、相補性原理と不確定性原理によって基礎づけられているので、常識では理解できない。それは「粒子が同時に波動である(相補性)」と言う非常識と、「確率的偶然性」(これは進化論の確率的偶然性とは別のもの)と「観測者効果」(観測が創造する)によって成り立っている。これらの理論は、無数の実験によって証明され、現に我々のまわりのほとんどすべての近代的機械、器具、設備に利用されている。
しかし、その主流派(コペンハーゲン学派)の理論に最後まで承服しなかったのは、かのアインシュタインであった。そして「物質波」のド・プロイ、「波動方程式」で量子力学の理論構築に多大の貢献をしたシュレーデンガーたちが、主流派に反対意見を述べた。有名な「シレーデンガーの猫」は、フォン・ノイマンの「観測者効果」を否定するために提出された思考実験である。しかし今だにそれは物理学者の間で議論されている。
アインシュタインは、量子力学の成功と近代科学への多大の貢献を認め、またミクロの世界の物質の不思議な振る舞いを説明できる正確な理論として認めたが、「偶然性」をその基本とし、それ以上に進もうとしない主流派に対して、「もっとすぐれた包括的な理論」があるに違いないと確信していた。
偶然ではなく、決定論が成り立つ、と信じていた。「神はサイコロをふりたまわず」は有名な彼の言葉である。
そして彼は、宇宙の全存在の複雑な出来事を演繹できるようなたった一つの原則(統一場理論)を求めることをライフ・ワークとした。しかしそれは果たすことができなかった。「この私の仕事を誰かが完成してくれる」と信じて世を去ったのである。
アインシュタインが有神論者であったかどうかについては明確な答えがある。ある時、彼は質問された。
「ではあなたは神の存在を信じているのですか」と。「ハイ信じています。私はスピノザの神を信じています」。このようにアインシュタインの答えははっきりしている。
ただし「スピノザの神」は奥深いので一言では表現できない。スピノザを把握するのは、或る意味でカントより難しい、と言われる。しかし私はアインシュタインの神観は、スピノザよりも単純で、透明であったと思う。
彼は世を去る前に次のように語っていた。
「わたしは神が
どういう原理に基づいて
この世界を
創造したものかが知りたい
神の考え方が知りたい
そのほかは
小さなことだ」
願わくば、すべての科学者が、創造主なる神の前にひれふして、神をほめたたえるように!願わくば、すべての神学者が、キリスト者が、聖書こそ最高の最終的規範であると、本当に信じるように!
■■■■■■ 目次一覧 ■■■■■■
【第一部:悪霊を追い出せ!】
第一章 悪霊との遭遇
宣教地での遭遇
ネパールの鳥羽宣教師
南米のホーリネス教会
日本でも起こっている
精神病と悪霊つき
占いの霊
第二章 悪霊につかれるとき
拝み屋
悪霊新宗教
偶像の儀式
呪文
占い
こっくりさん
お守り・お礼
テレパシー
第三章 どうしたら解放されるか
福音の伝道
御言葉の力
賛美を歌う
クリスチャンと悪霊
過去の悪霊からの解放
解放と伝道
第四章 偶像と悪霊
仏壇と悪霊
位牌と悪霊
共産党と偶像
仏壇を壊した奥さん
悪霊を見分ける
眠りの霊
牧師の家の偶像
カンボジアの教会
御言葉と悪霊
第五章 神学的問題
雨は二度降る
神の声を聞く
異言はある
偽物の見分け
福音派はリベラルにやられ易い
第六章 教会最大の敵
ニューエイジの計画
サタンに礼拝
教会最大の敵
進化論学者とオカルト学者
エントロピーの法則
ニューエイジによる儀式
悪霊に立ち向かうために
【第二部:神学に興味をもつ人のために】
一、古典物理学の限界
二、近代カルビン主義神学と古典物理学
三、パラダイム転換(常識破り)
四、 古くて新しい聖書と科学の深い関係
五、聖書と科学の分断の罪
六、誤った弁証
七、ドグマティックス(独断論者たち=教義学)とあだ名されよ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
