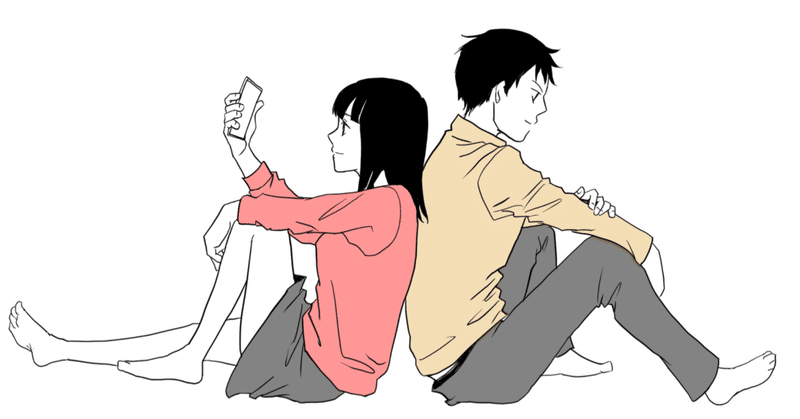
【連作短編】先輩ちゃんと後輩君 その3
第3話 先輩ちゃんは後輩君を連れ込んで晩ご飯を作らせたい
日が暮れて街中にスーツ姿の人物が多く見られるようになった。早々と居酒屋は賑わい、路上を千鳥足で歩く者も現れた。
高田 春人は飲食店に目もくれず、家路を急ぐ。右手に提げたビニール袋が乾いた音を立てる。
春人は突然、立ち止まった。逆方向に歩き出そうとした瞬間、手首を掴まれた。浮かぶ苦い笑いを引き締めて後ろを振り返る。
黒いリクルートスーツを着た青山 陽葵が上目遣いで詰め寄ってきた。
「後輩君、その態度はどうかと思うぞ」
「なんの話ですか」
「私を見て逃げようとした。違うか?」
相手の背丈に合わせるようにヒールの部分を上げる。
「自分のマンションに帰ろうとしただけです」
「逆方向だぞ」
「わかりました、正直に言います。先輩ちゃんに夕飯をせがまれるのが嫌で逃げようとしました」
春人は殊勝に頭を下げた。目にした人々はニヤニヤと笑う。気付いた陽葵は大いに焦る。
「ちょっと! 本人を前にして堂々と言うか!? 今回は偶然だぞ。待ち伏せとかでは決してないからな」
「晩ご飯を作る手間が省けたと思いましたよね。とても良い笑顔をしていましたよ」
「……それは、まあ、そうだが」
本音がぽろりと口から出た。我に返ると反撃の糸口を探す顔付きとなり、決めた、と瞬時に大きな声を放つ。
「今から私のアパートに来い。奢ってやるぞ」
「今日の料理の下準備はできています。不足した調味料を買いに出ただけで」
「いいから来るんだ! 奢らせろ!」
強引に手を握り、小さな身体でずんずんと歩く。春人はやや仰け反った姿のまま強制的に連れて行かれた。
「ここで待機だ。わかっていると思うが勝手に帰るなよ」
「わかりました」
陽葵は扉を開けて先に入る。走る音が外まで聞こえた。小さな子供が部屋の中を駆け回っている姿が目に浮かぶ。
十数分の時を経て、ようやく扉が開いた。真横から突風を受けたような髪型の陽葵が顔を出す。
「入ってもいいぞ」
「お邪魔します」
春人は玄関で靴を脱いだ。細い廊下を歩き、突き当りの引き戸を開けた。不自然な程、さっぱりした部屋だった。目はベッドと真逆の左手に向かう。クローゼットに挟まれた水色のブラジャーの一部が見えていた。
「収納が不完全ですよ」
「どこがだ?」
「あれです。指で示した方向をよく見てください」
「なにが、あああっ! 見るんじゃない! レディーに対して失礼だぞ!」
沸騰した顔で陽葵はクローゼットに駆け寄る。僅かに扉を開けて足先でブラジャーを押し込んだ。
「中身を見たことがあるので、今更、気にしませんよ」
「い、居酒屋の話はするな! 記憶にないんだから、あれだ、仕方ないじゃないか……」
それとなく腕で胸を隠し、陽葵は妙に腰をくねらせた。
春人は敢えて言及しなかった。早々と本題を口にした。
「今日はなにを奢ってくれるのでしょうか」
「覚えていたのか。もちろん食材だ」
「食事ではなくて、食材なのですか?」
「そこに調味料も付けてあげよう」
得意気に言うと陽葵はベッドの下に手を入れた。折り畳みの机を引っ張り出して四本の脚を立てる。中型の冷蔵庫に小走りで向かい、中からビールの缶を取り出した。その場で開けて飲み始める。
「この最初の一口が最高に美味いな! あとはよろしく頼んだぞ、後輩君」
「奢るのは食材だけですか」
「不満なのか?」
「できれば労力も奢って貰いたいのですが」
その一言に陽葵はふらふらと歩き出す。ベッドの縁に腰掛けてわざとらしく自身の肩を揉んだ。とどめとばかりに目頭を指で押さえ、深い溜息を吐いた。
「わかりました。善処します」
「ありがとう。楽しみにしているよ」
陽葵は満面の笑みを浮かべ、美味そうにビールを飲んだ。
冷蔵庫を開けた春人は軽い驚きで固まった。
扉の裏にある卵ケースには何もない。棚にビールはあった。強固な壁のようにずらりと並ぶ。
「卵がありません」
「下の方にあるぞ」
テーブルに移った陽葵はリモコンでテレビを点けた。適当にチャンネルを巡り、歌番組に落ち着いた。曲に合わせて軽く頭を揺らす。
春人は冷蔵庫の下部に目をやる。小さなケースに卵が入っていた。表面に貼られた紙に『温泉卵』と表記されていた。薄ら寒い笑みで別のところを探す。
牛乳がない。チーズもない。ソーセージやハムもない。パンが嫌いなのか。当然のようにバターもない。群れをなすビールの傍らに缶チューハイがあった。
冷凍室に目を移す。中はがらんとしていた。無造作に置かれた細長いトレイを手に取った。牛肉の切り落としで霜が降りた状態になっている。消費期限を二か月ほど超えていた。
溜息を堪えて野菜室を当たると一玉のキャベツを見つけた。表面を覆う葉は黄色く変色。他にニンジンの先端部分が干からびた状態で底に転がっていた。見た目が高麗人参だった。
「キャベツの黄色い葉を捨ててもいいですか」
「そんなのあったか?」
「……気にしないでください。こちらで処理します」
五枚の葉を毟ってペダル式のゴミ箱に入れた。
ほとんど料理をしていないように思えた。次に気になるのは調味料。春人はキッチン周りを片っ端から調べた。
オイル関係はごま油のみ。塩は見つかった。香辛料の類いはなかった。
「醤油はどこですか」
「醤油は二日前に使い切ったぞ」
平然と答えた。春人は堪えていた溜息を吐いた。
引き続き探索は続く。包丁を見つけた。菜切り一本。それ以外はない。
「これは」
戸棚の奥に袋麺を見つけた。都合がいいことに二つある。キャベツと牛肉は十分に具になる。手料理とは言い難いが何もないよりはいい。引っ張り出して、え、と声を漏らす。
二つ共に袋が開いていた。中に麺は入っている。肝心のスープの小袋がなかった。
「何度も質問して悪いのですが、ラーメンの袋を見つけました」
「そうか」
「ただスープの袋がありません」
「ああ、思い出した。深夜に小腹が空いた時に使った」
「ラーメンとして食べなかったのですか」
その言葉に陽葵は間を空けた。缶ビールを一気に呷る。
「夜に食べると太るから、食べた気分になりたかった」
「それでスープだけにしたのですか」
「まあ、そういうことだ」
「二つも?」
「二回、あったからな」
陽葵は立ち上がった。冷蔵庫から新たな一本を取り出し、春人と目を合わせないようにして元の位置に戻った。
春人は見つけた食材をキッチンの台に集める。そこに自身が購入した調味料を加えた。希釈用の麺つゆとオリーブオイルであった。
「……できないこともないか」
鍋を取り出して水道水を注ぎ、コンロに載せた。プラスチック製の小さなザルを用意した。沸騰する前にキャベツを菜切り包丁で切り始める。牛肉の切り落としは手で千切った。
その様子を陽葵は横目で窺う。とても嬉しそうに笑ってビールを飲んだ。テレビから新たな曲が流れる。歌詞が爽やかに伝えた。若い男女の淡い恋心。
陽葵は曲に乗ってゆらりゆらりと上体を揺らした。
陽葵はビールを飲む手を止めた。漂う匂いに反応して子犬のように鼻をくんくんさせる。
「できたのか!」
「一応は。過度な期待はしないでください」
両手に皿を持った状態で春人が言った。陽葵の前に一品を置き、箸を添える。
「見た目は悪くない。それにごま油だけではないな。良い香りがするぞ」
「家用に買ったオリーブオイルを使いました」
春人は対面の位置に座ると箸を手にした。
「真ん中のこれは温泉卵か。食べる時は混ぜ込めばいいのだな?」
「好きなように食べてください」
「そうか! それでこの料理はパスタなのだな」
「強いて言えば『塩焼きそば』になると思います」
「後学のために作り方を教えて欲しい」
くりくりした目で両手を合わせる。キッチン周りの寂しい状態を考えれば甚だ怪しい。春人は見極めるような目をした。軽く息を吐いて話し始める。
「わかりました。麺を固めに茹でてザルで湯切りをします。事前に温めておいたフライパンには、ごま油とオリーブオイルが入っていて素早く麺と絡めます。味付けは塩と麺つゆでしました。千切りしたキャベツは色味を考えて仕上げの段階で入れて完成です」
「なかなかの工夫だ! 問題は味だな」
箸で麺を摘まみ、口に含む。軽く啜って味わうように食べる。
「味が絶妙だ。淡白な塩を麺つゆが風味でカバーしている。いや、旨味も感じられるな。まさに万能調味料だ」
「偶然ですが持ち合わせた調味料に助けられました」
「これに温泉卵を混ぜると」
中央に収まる卵を箸で突き刺し、掻き回す。麺と絡み合った部分を垂らさないように一塊に丸めて口の中に押し込んだ。そこはかとない幸せを湛《たた》えた顔でもぐもぐと口を動かす。
同じように春人も麺を啜る。咀嚼しながら小動物を愛でるような目をした。
「とてもまろやかになる。奥深さを感じるぞ。袋麺でここまでの味を出せることに驚いた。少し口の中が油っこくなればビールだな。いい箸休めになる」
饒舌となり、うきうきした状態で立ちあがると冷蔵庫に駆け寄った。二本の缶を持ち出し、一本を春人に差し出した。
「いただきます」
「どんどん飲むといいぞ。全部、私の奢りだ」
「ありがとうございます。先輩ちゃんは程々にしてくださいね」
「どうしてだ? 例え酔っ払ったとしても誰にも迷惑を掛けないぞ」
新たな缶を開けて飲み始める。
「裸になられると、こちらが困ります」
その言葉に陽葵はむせた。取り出したハンカチで口を覆い、鼻が痛い! と言って春人に非難の目を向けた。
「一度、経験したことなので」
「もう、ない! 絶対にないから!」
「安心しました」
穏やかな表情で春人は麺を口に運ぶ。口直しに缶を開けてビールを静かに飲んだ。
二人は塩焼きそばを平らげた。空になった缶が何本も立ち並ぶ。大量のビールの影響で陽葵はテーブルの空いたところに突っ伏した。意味が聞き取れない寝言を垂れ流している。
春人は涼し気な顔でビールを飲んでいた。一気に傾けてテーブルの端に置いた。
「……どうするか」
陽葵を見て呟く。時間の経過で冷え込んできた。エアコンが必要になる程ではない。酒量の関係で身体が冷えている様子は微かな震えで見て取れる。
春人は立ち上がった。陽葵の背後に回ってスーツを脱がせた。
「……背、名……痒い、って……」
「寝ていても顎で使いますか」
取り敢えず、背中を適当に掻いた。何故か笑い声を漏らす。
手にしたスーツは床に広げた状態で置いた。一度、クローゼットに目がいった。頭に不安が過るのか。開けようとはしなかった。
「運びますよ」
返事がないまま後ろから抱き締める。軽々と持ち上げてベッドに運んだ。足元に丸まった掛け布団を広げて陽葵に被せた。
「帰ります」
電気を消した春人は足音を立てないようにして出ていった。
暗い部屋に小さな舌打ちが聞こえた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
