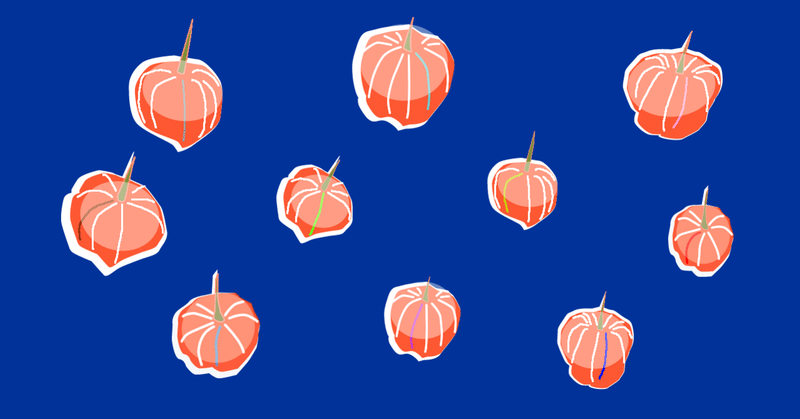
不思議な小噺 第ニ夜 「お聖伝さん」
母の故郷に、「お聖伝さん」と呼ばれた霊能者がいた。
おしょうでんさん、と呼ぶ。
由来はわからない。
昔から「お聖伝さん」と呼ばれていたので、そう呼ぶ以外ない。
今、ネットで検索しても「お聖伝さん」のことはどこにも残っていない。
風の民となった。
「お聖伝さん」との出会いはほんの数十分だったが、その密度の濃さは、自分の物事への向き合い方に大きく影響するほどだった。
母の故郷は徳島県美馬郡半田町である。
「半田そうめん」で有名なところだが、大蛇伝説のある土々呂の滝も地元では神秘的な滝として崇められている。
「あんたのこと、お聖伝さんにみてもらおう」
実家へ帰省していたある日、母から誘われた。
今から20年ほど前、わたしが24、5歳の頃だったと思う。
当時マンガ家になるために、就職もせずバイトをしながら、まったくあてもない原稿を描いていた。
担当さんもついておらず、一体これからどうなるのかわからないフラフラした状況だった。
「よう当たる人なんよ。昔から御勤めされとってなあ。遠方や県外からわざわざみてもらいにくる人もおるんよ。
ある女の子が芸能界に入りたくてお聖伝さんにみてもらったら、デビューできるっていわれて、ほんまかいなあ、って思っとったら、本当にデビューしたんやって。」
「へえ。。。。」
テンションが高めの母の熱気を帯びた言葉に、わたしは少し距離をおき白けた心持ちで答えた。
2000年代当時、世の中は空前のスピリチュアルブームであった。
「オーラの泉」が放映され、守護霊やら前世やら、のちのパワースポットやら、多くのスピリチュアルワードが一般人にも浸透し、火付け役の霊能者はメディアに引っ張りだこであった。
わたしもみえない世界にはとても興味があった。
小さい頃から宜保愛子や「あなたの知らない世界」をみて育った人間である。
けれども一方で、「霊能者」たるものはそうそういるものではない、という思いもあった。
母親の推す「お聖伝さん」も、せいぜい祈祷ができます、ぐらいであろう。
あまり気乗りせず車に乗り込み、すぐに尋ねた。
「で❓お金はどれくらいかかるん❓まさか○万とか包むの❓」
まず大きなチェックポイントである。
これで30分で3万とか5万とかいうものなら、ハンドル奪ってでもすぐに引き返した方がいい。1万でも惜しい。みえないもの、確証のなきものの話に大金を支払うことほど馬鹿げたことはない。
「霊能者」ときくと、ローソクを鉢巻にブッ刺して目を見開いて「金‼️」と心で念じつつも「南無妙法蓮華経」などと唱えている自称霊能者を彷彿してまう。
母は言った。
「何円でもいいんよ。相談者の好きな金額で構いませんって。昔からそうよ。」
「。。。。。。。」
。。。へえ。。。。
さあ、どこから化けの皮が剥がれるかな、と内心ワクワクしていたわたしは、少しだけ拍子抜けした。
霊能者という名を被った紛いものがたくさん跋扈する中で、お金を重視していないということは、確かに地域で長く親しまれているからかもしれない。
「でも、包まんわけにはいかんでしょう。どれくらい❓」
「2000円にしといた」
まあまあ妥当な金額か。
もしかしたら地域で暗黙のルールで定められている金額かもしれない。
「でも、ああいった御勤めは皆が皆、できるわけではないんよね」
山道を運転しながら母が言った。
「今やられている方も、「お聖伝さん」というお役目を引き継いだ方なんよ。
ずっと昔から地域でおったのよ。相談事をきく役割として。」
「へえ。。。」
「なかには「お聖伝さん」になりたくてなりたくて、弟子入りした人もおるって。霊感を持ってる人って憧れるんやろうねえ。。。。。そしたらなあ。。。」
「そしたら。。。❓」
「その人、気がおかしくなってしもうたって」
「。。。。。。。。。。」
「なんの修行だかをするんかわからんけど、選ばれた人しかなれへんのちゃう❓出来ん人の方が多いんやから。ああいうのは下手に飛び込んだらあかんてことやな。」
修行。。。。。
世間を恐怖に陥れた某宗教団体のテレビでみたビョンビョン飛び跳ねる異様な修行風景を思い出したわたしは、ますます行くのが気が重くなってしまった。
まあいいや、ニセモノだったら、ハイハイと受け流して終わろう。。。
車は蛇のような長いうねうねした山道をのぼってゆき、広大な田園風景の中を降りてゆき、入り組んだ住宅街に入った。
「ここじゃ」
車を止めて、石階段を登ってゆくと、平屋の日本家屋があった。
田舎にある、一見すると昔ながらの普通のお宅だ。
「こんにちは。。。」と引き戸を開けると、目の前の光景にわたしは凍りついた。
部屋の一辺、6メートルほどがお堂のようになっていた。
そのお堂一面を、大きな注連縄が這っているのだ。
出雲大社の巨大な注連縄があるが、あれの個人宅バージョンだとご想定下されば
イメージしやすいかと思う。
何十年も息継がれているような、暗く、深く、闇の方が大きいお堂と、その上を巨大ツチノコのようにずおおおお。。。んと這っている注連縄。。。。
いつスケキヨがひょっこり出てきても、双子の老婆が登場しても、お堂の奥から手毬唄が流れてきてもおかしくはない、市川崑監督が泣いて喜びそうなセットではないか、と強烈に感じたのを今でも覚えている。
その異様なる光景にビビーンと絶句してしまったわたしは、お堂の目の前に座った、白衣をきた後ろ姿のお婆さんをみた。
黒い大きなお堂に向けて、ちょこんと座っていた小さい背中であった。
この小さいお婆さんが「お聖伝さん」らしい。
受付の穏やかな顔つきの白衣を着たお爺さんが、「ようこそお越しくださいました」と挨拶をして下さり、「こちらに生年月日とお名前をどうぞ」と紙を差し出した。
お聖伝さんが知る情報はこの二つのみである。
お聖伝さんは、前の相談者の方と話をしていて、ひととおり済んだ後、休む間もなくわたしの番になった。
そこであらためてお聖伝さんの顔をみたわけだが、小さく、癖のない優しい顔つきのお婆さんだった。
注連縄やお堂の禍々しい迫力とは正反対の、穏やかで、そこら辺の畑で農作業の合間に畝に座ってお茶をしていそうなおっとりした小さなお婆さんだ。
「今日はどんなことで来られましたか?」
やはり優しい口調で尋ねられた。
マンガ家としてデビューできるかどうか、を話した。
このようなお婆さんにマンガのことを相談するのはどうなのか、一種の気恥ずかしさを感じたが、お聖伝さんはうんうん、とうなづき、
「わかりました。ほな、きいてみますね。」
とお堂の方に座り直し、数珠を持って祝詞を唱え始めた。
祝詞の内容はまったく覚えていないが、「あめつちの。。。」や「お聖伝。。。」という言葉は入っていた。
それまでの穏やかな口調から、少し低くなった声で祝詞を唱える小さなお婆さんをみて、「イタコみたいやな。。」と、本物のイタコを見たわけでもないのに、不思議な迫力に圧倒されてしまい、ただただ、どこまでも深く暗いお堂とお聖伝さんを眺めるしかなかった。
ひととおり祝詞がすむと、お聖伝さんは、こちらに向きなおりいった。
「わかりました。ほな、お伝えします。」
。。。。ゴクリ。
「夜も寝ずに、描かれている様子がみえます。
ものすごく努力されとります。
いい巡り合いを受けて、あと2、3年でデビュー出来ます。
人が人を繋いでくれます。それでデビューされるようです。」
ま。。。まじか‼️
当時なんのあてもない状態だったので、その言葉だけで一気にわたしの中でお聖伝さんの株が上がった。
「ただ、注意してほしいことがありましてねえ、
この子は神経がとても細い。身体も強うはない。
健康には重々注意されること。
ちゃんと寝た方がええですね。
あともう一つは。。。マンガを描くのが好きとのことやけど、
文字を書くのが、とても好きな子なのだと仰られております。」
この言葉に、キョトンとする。
誰が一体仰られておられるのか。。。。
当時のわたしは、「寝ないでどこまでやれるか」を試すかのように徹夜も厭わなかったし、体力を過信して不摂生が普通だった。
まだ健康面に危機感を抱くようなことがなかった無頓着な若さがあった。
しかし、体力の限界がそれほど長くないことを悟った四十路の今なら、
お聖伝さんの言ってくれたことは、なかなか的を得たものだったとわかる。
「ありがとうございました」
「頑張ってな。身体に気をつけて。」
空気と溶け込んだような、我がない、優しい柔和な顔だった。
わたしの後にも相談者が来ていたので、挨拶をしてすぐに後にした。
車に乗ってわたしは言った。
「とても、いい人やったね。」
母は、それみたことか、と言わんばかりに
「じゃろう〜‼️昔からずっとあんな感じで変わらんと見続けとるんよ。地域の人から遠方の人まで。」
と頷いた。
いいことを言われたからといって、評価したわけではなかった。
うまく言葉では言い表すことが出来ないが、あの我欲のない、全く威厳のない、邪気というものも感じられない、柔和な雰囲気とその奥に潜む多くを語らない賢さ、のようなものを感じた。
あくまで自分は見えぬ誰かからお伝えを受ける器にすぎず、それをまた相手に伝えるお役目であることに徹底している。
それを生業としているが、それ以上のお金儲けのベクトルを必要とせず、
地域の人々の相談役として自分の能力を使うことを今生の勤めだとしている。
一言でいうと、無欲の方だった。
その器の大きさと、ただ淡々と自分の役割をこなし、能力の鋳型に似合った生き方をされていることに感銘を受けた。
たしかに、みながみな、なれる器ではないだろう。
霊感があっても、人格というものが同じ分量、いや、それ以上伴わないと到底つとまらない。
もっというと、霊感は生き物の本能として多かれ少なかれ誰しもが備わっているものだが、人格というものは、痛い想いを何度もして長い年月をかけて磨かねばなかなか身につかないものだと思う。
大抵の相談事は、個人の欲望や願望、苦しみ、恐れである。
それらを突き離したところから無の境地で霊感を使って伝えてゆくことは容易ではなく、場合によっては厳しいことも伝えねばならない。
それらを研ぎ澄まされた心で操縦できる愛情が人格かと思う。
あのお婆さんに、霊能者というおどろおどろしい言葉は似合わないなと思った。
やはり、「お聖伝さん」がしっくりくる。
地域の人から親しまれて呼ばれる、「お聖伝さん」という言葉が。
それから、何人かの霊能者にみてもらったが、もっとも印象深かった方が、この「お聖伝さん」だった。
かつては、「お聖伝さん」のような役割を持つものは、どこの地域にもいたのではないだろうか。
村人からの相談や、神仏と村との橋渡しをし、見えぬものを降ろす役目をし、卜占を行い、時には薬師にもなり、名付け親になったり、おくりびととなったり、雨乞いや疫病、村の災いを退ける祈祷をする。。。
いわば、神主やお坊さんとは異なる立場の、草の根的に村の精神的支柱となった人たちである。
しかし、近代化が進み、都会へ人が流出しはじめ村機能が衰退するにつれて、その役割を持つものが衰退してゆき、消えていった。
ただでさえ村の心配事を一手に引き受けるような御勤めができるものは希少で、限られる。
そんな現代で、「お聖伝さん」がまだ生きていた土地はかなり稀有だっただろう。
あれから、お聖伝さんにまた会いたいと思っていたが、その密かな願いは叶えられなかった。
数年後にお役目を終えたと母から聞いた。
受付をされていた弟さんのお爺さんがしばらく跡を引き継いだが、その後、お二人とも寿命を終えられた。
最後の灯籠を見送るかのような、心淋しい気持ちだった。
何十年。。。もしくは何百年と続いた風の伝えきく民の存在が、誰に語り継がれることもなく、母の故郷から静かに消えていった。
お聖伝さんは、今はもういない。
