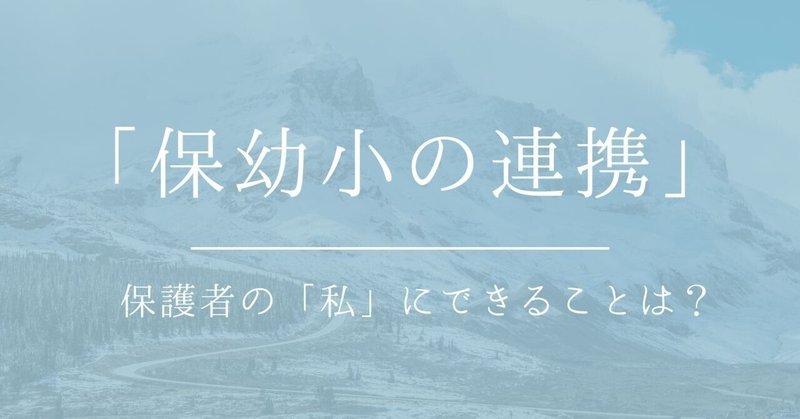
「保幼小の連携」。保護者として私にできることは?~発達173号を読んで~
先日届いた発達173号を、少しずつ読み進めています。
今回のテーマの1つは、「保幼小の連携」。
現在、息子小1、娘年少を抱える私にとって、心から関心のある内容です。
ここまで読んだ中でも、論点は実に様々です。
日本の保幼小の連携の実態は、決して明るくないこと。
諸外国と比べた時にも、日本では、幼稚園・保育園と小学校教育で、大きな隔たりがあること。
小学校だけでなく、保育園や幼稚園からも、小学校へ連携するために子どもの「学び」を見取る必要があること。
自治体も、サポートをしていくこと。
それぞれの組織が、保幼小連携について当事者意識を持ち、子供の学びを繋げていくことが重要だと感じました。
それだけではなく、今私ができることは何か?を考えてみようと思いました。
考えた結果、日々、子供を観察し、見守ることなのかな、と考えています。
小1の息子を見ていると、小学校で学んでくることはもちろんたくさんあります。ひらがなもカタカナも漢字もこんなに書けるようになって。国語力の養成は非常に重要だと思っているので、ありがたく思っています。
一方で、小学校に行きたくない時があることも、事実です。
幼稚園や保育園と全く異なる環境へ突然投じられ、自由な時間が少なくなり、教室の中で座っていることを強要され、「今」自分がやりたいことと違うことをやらされる。
慣れない時期があるのも、当然です。大人はやりたくないことはやらないのに、子供には当たり前にやらせる不思議なカルチャー、それにあえなく呑まれる私。
息子が学校に行きたくないと言った時、私はなるべく彼の気持ちに寄り添い、気持ちを受け止めるように心がけてきました。
学校に行きたくないという思いを受け止めて、「どうして行きたくないか」という思いを、彼が話せるだけでいいから、聞いていました。そしてどうしても行きたくないときは、お休みしました。
そして学校に行ってくれている時は、今日は学校でどんな楽しいことがあったのかを日々聞いて、彼の中で楽しい時間があることを認識してくれるように、話していました。
すると最近では、「●●の時間、たのしくないんだよねー」とか、「チューリップが、ぼくのは特別なんだよー」とか、学校での時間で楽しい事とそうでない事をだんだんと、話してくれるようになりました。
もし親から「何を言ってるの、学校に行こう」と言われてしまえば、彼らの心は閉ざされて、親に本音を言えなくなるきっかけになってしまうかもしれません。
子供たちを見ていればわかる通り、彼らの発達は絶えず連綿と続いていくものです。それを保育園・幼稚園と小学校でステージが変わっただけで区切ってしまうことは、大変ナンセンスに感じます。
大人たちが「幼児フィルター」「小学生フィルター」を通して子供を見すぎないように注意が必要だと思います。
これは、保護者の視点からの意見、とも言えるのかもしれません。
自分の子どもに対して絶対とも思えるくらい適切とは思えないやり方があったとしても、保育園・幼稚園や小学校、自治体のルールを、今すぐに変えることは、できない。
もどかしい思いを抱いていました。
では、私に出来ることは無いのか?いやそんなことないって、今日改めて思いました。
息子と毎日一緒に居るのは、私。
彼の変化に気づけるのも、私。
彼の話を聞いて、気持ちを受け止めてあげられるのも、きっと今は、私。
できるだけ彼が楽しいこと、好きなことに傾けられるように、見守っていくことは、きっと私たち親ができること。
子どもと一緒に居られるしあわせを、うれしさを、噛み締めて。
少しでも彼らの人生が明るくなるように、見守ろうと思います。
さて、このように「自分ができることは何か」と考えるようになったのは、7つの習慣の「主体的であること」という第一の習慣が、ものすごく私の心に影響をしています。
今までどれだけ反応的に過ごしてきたか、よーく分かりました(^^;
だから今は、自分の「外側」で起きていることに対してぼやくのではなく、私は何ができるのか?私がどうすればそれを変えていけるのか?を考えるように努めています。もちろんまだまだ、出来ないときのほうが多いですがっ。
今すぐにどうこうできることではないけれど、そういったその思考習慣・行動習慣は、きっと1年後5年後10年後の私の習慣になっていく!と信じて、少しずつ取り組んでいこうと考えています。
今日はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました!
hona
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
