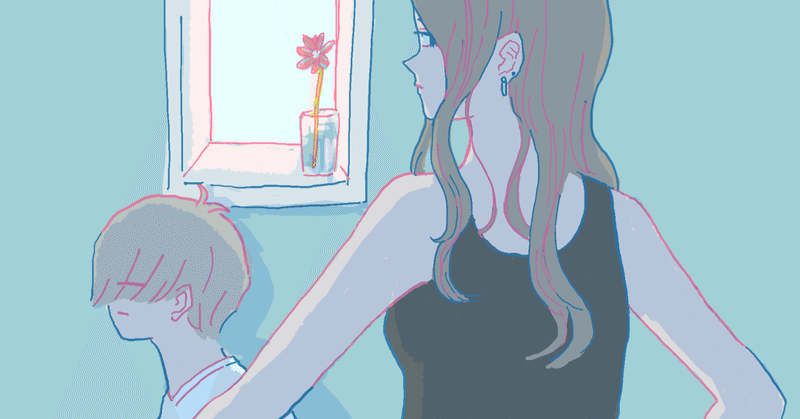
写真家の恋人が「うつ病」になり、わたしが唯一の被写体になった日のこと
「写真を撮るのがこわいです」
裂けるような、激しい痛みだった。
触れていないのに、想いが気体としてぶつかる。理解者なんてそもそも簡単には現れない。全身が膿んでいるよう。唾を二度ほど飲み込み、泣き崩れるあなたを抱える。どんな言葉をかけても響かないような気がして、ただひらすら隣にいることしかできなかった。
人は誰しも落ち込む。
その心情を隠す人がいたり、気付かず過ぎ去ってしまう人がいたり、上手に前を向ける人がいたり、零しつづけ、傷口を広げてしまう人がいたりする。
「そんなこともわからないの?」
今日、わたしは職場で上司に質問をしたら、突き刺すようにして返される。もっとわたしができる人間であればよかった。なにもかも一度で理解できて、一生それを忘れない完璧な人間になっておくべきだった。
結局わたしは仕事のやり方を教わることができず、その後、大きなミスをしてしまった。それも、わたしひとりで解決できるものではない。それこそ誰かに迷惑がかかるもの。出てきそうな水滴を、必死に押し込む。
「なにやってんの」
心臓が凍りつく。同じ人だった。
ほんの少しでも大きな声、冷めた声を聞くと涙がぽろぽろと出てきてしまう。「こんな歳になってなにをやっているのだろう」。自分がわるくて、不出来で、伝えるべきことを伝えずにいるせいで、誰かの「怒」を引き出している。小さな脳髄は音もたてずに粉々になり、誰もいないところで目から滝を流す。難しい。難しいよ——。
◇
「ただいま」
家に帰ると、ベランダでひとり、真剣にぼんやりとしている人がいた。そこで洗濯物を干したり、煙草を吸っていたりするわけではない。あなたがただ、存在していた。
「おかえりなさい」
梔子色の光を背中に浴びて、曇りなくあなたは笑う。わたしは恋人の彼と一つ屋根の下で暮らしている。彼の表情を見て、残っていた、外で出し切れなかった涙を零す。落ち込んでしまった日は、とめどなく愛を味わってしまうのだ。
泣いているわたしをやさしく抱きしめてくれる彼は先週、病院で「うつ病」と診断された。「わたしがしっかりしなきゃ」と思えば思うほど、上手くいかない日々が続いた。元から上手くいっていた日などほとんどなかったのに、目指す場所が変わったせいか、最近はよく溺れる。
彼のほうが不安なはずなのに、彼の前で噴出するような絶望的な泣き声を出してしまう。「大丈夫、大丈夫」と、無意識に口を動かすようになった。誰かに習ったわけではない。そうでもしないと、なにかか弾けてしまいそうだった。
日々、泣き続けるわたし。
日々、寝込んでいる彼。
支え合うという関係に限界がきている。わたしは彼のことが「好き」だ。けれどそれは心のどこかで"支えてもらえる前提"で愛していたのかもしれない。弱い過去のわたしを想像すると、また心のどこかに亀裂が入る。小一時間泣いても終わらない、そんな姿を見て、彼は言う。
「僕に、なにかできることはありませんか」
いままで、彼はそういう台詞を好まなかった。わたしも似たところがある。言われなくても人を愛したいと思っている。その方法や道は、相手に教わりたくない。通じ合えると、夢を見すぎていたのかもしれない。わたしは粉々になっていたものを必死にかき集める。どうにかしてわたしは、わたしと彼を救う方法を考えていた。
——なにも思い浮かばない。
数年という単位で眠ってしまいそうな体だった。愛するだけではなんの解決にもならない現実。彼の「負担」を考えると、わたしは自分のことをそもそも自分で愛することができない。本当は、ゆっくりしていていいよと言いたいのだ。でも、言えない。
ふたりでぼんやりと、狭いベランダに出た。お互い覚束ない足取り。それでも彼との愉しい生活は、いまでも思い出せる。「当たり前だ」。文章を書くのが好きなわたしと、写真を撮るのが好きな彼。たまたま出会ったわたしたち。出会うのが必然だったと思いたいわたしたち。つなぐ方法が出かかったその瞬間、彼が先に零す。
「しをりさんのことを、撮らせてくれませんか」
薄目ではあったが、彼はまだわたしのことを愛しているようだった。写真家として生きていた彼がうつ病になった、そのきっかけは「写真」への恐怖だったそう。
突然、雷が落ちたような衝撃。パニック発作が起きた彼を取り囲んでいたのは、責任や期待、プレッシャー、それ以外にも。"好き"だけでは生きていけない瞬間がある。"好き"だからこそ、息が苦しくなる瞬間がある。
だから。より「純粋」を求めて。
景色などを撮る。彼はもともと、人を撮る写真家ではなかった。そしてわたしは、写真に映るのが大の苦手だった。なぜならわたしは「女の子」として生きたいのにもかかわらず、映り、出来上がる一枚はいつだって「男」だったから。
そんな苦しみも、彼は知っている。
わたしが「女の子」になりたい想い。そしてそれが叶うまで寄り添うと、昔彼は微笑む。愛する人の前でだけ、わたしはワンピースを着たり、スカートを穿いたり、口紅を塗ったりできた。ヒールに足をはめてみたかった。彼の瞳だけは、純粋にわたしを女の子として見てくれる。
彼は言っていた。
以前、わたしが「書くことがつらい」と零した日。
「書くことがつらかったら、あなたの景色を僕に見せてください」
そんな彼の言葉を言い換える。
今度は、わたしが彼に伝える番——
「撮るのがこわかったら、あなたのレンズの前でわたしが笑います」
とんでもない、自惚れの愛である。わたし自身、第三者が見て、整った容姿ではない。そんなことはわかっている。慰めも必要ない。
愛する彼が見るわたしは、うつくしい。文章も写真も、あらゆる「創作」が人の好みだとしたら、少なくとも彼の瞳に映るわたしは艶めいている。
.
.
自分の「世界」を創りたい。
咲きたい「場所」がある。
「お前はだめな人間だ」「そんなんじゃどこへ行ってもやっていけない」「男が男を愛する、女が女を愛するなんて間違っている」「あなたの文章はつまらない」「あなたの写真は退屈だ」
全て、言わせておいてあげる。
初めて、彼が構えるカメラのレンズに目を向けた。泣いていた顔を宙へ放った。撮ってもらうのは「笑顔」がよかったから。
読んでくれているあなたに、届けたいもの。
彼の言った、わたしには好きな言葉がある。
「笑顔は、皆"平等に"うつくしい」
現実で何度失敗をしても、挫折をしても、わたしはその言葉を思い出した。人の気持ちに鈍感に生きるくらいなら、痛くてもいいから敏感に生きたい。
泣いて、泣いて、もうだめだと思う瞬間、掬う。
「そんなこともわからないの?」「辞めたらなんにも残らないよ」「大丈夫って言ったよね?」なんて、言わないから大丈夫。
無数の涙。
理由があって泣いている人。
理由はないけど泣いている人。
理由がわからなくて泣いている人。
「大丈夫」と言った人が、本当に大丈夫になる日がきますように。「救われました」と言った人が、本当に救われる日がきますように。
わたしは人一倍泣き虫だから、「泣いてもいいんだよ」と伝える文章を書きたい。
レンズが濡れていた。
恋人の、唯一の被写体になってわかったこと。
それは、"笑うことを諦めない人"の涙が、この世で一番、うつくしい。
書き続ける勇気になっています。
