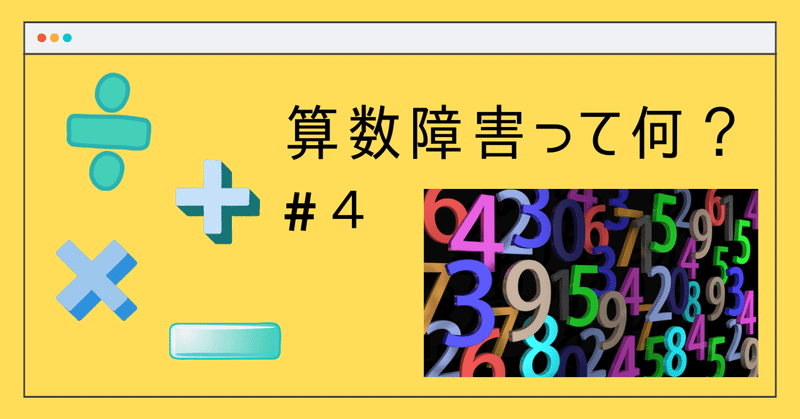
#79 手を動かして学ぶ!算数力アップの秘訣
算数障害には、次の4つの領域があると言われています。
①数処理(数字・数詞・具体物の対応)
②数概念(基数性と序数性)
③計算(暗算・筆算)
④推論(文章題)
算数障害といえば、この4つのうちのどれかの理解に著しい困難を示します。
くわしく知りたい方はこちらを↓
とてもわかりやすいです。
前回は、②数概念についてお話しました。
今回は、③計算(暗算・筆算)です。
これは手ごわい相手です。
数回に分けて考えていきます。
今回は暗算です。
暗算ができるようになるには、
①5の合成分解
※合成とは→1と4で5
※分解とは→5は1と4
②10の合成分解
③和が20までの数のたし算、ひき算
例えばこんな子がいます。
3+1のような簡単な計算でも、指を使ってしまう。
時間はかかりますが、結果的には正解します。
プリントやテストではそれほど悪い点数ではないので、気付かれにくいのです。
このような子は授業中、机の下で指を使って計算していることが多いです。ご家庭でも指を使って計算していないかチェックが必要です。
ではどうしてつまづいてしまったのか?
量として捉えずに、数え足しや数え引きをしてしまうので、数概念が定着していないことがわかります。
さらに遡って数処理でつまづいている可能性もあります。
では、どうすればよいのか?
具体物を半具体物に変換し、
さらに半具体物を、数に変換させる活動を繰り返していくのです。
例えば、りんごが5個。
🍎🍎🍎🍎🍎これは具体物。
これを、半具体物に変換
〇〇〇〇〇(算数ブロックを使用し、🍎を〇(ブロックに置き換える操作をさせる)
さらに半具体物を数に変換
〇〇〇〇〇→5
こうしたブロックでの操作活動を繰り返すことで数概念は身に付いていきます。
この操作活動をふっとばして、授業をすすめると、大変なことになります。
たまに、
「先生、算数ブロックつかわないの?」
「遊んでしまう子がいるから算数ブロックは使いません」
などと指導してしまう先生も見かけたことありますが、
これは
まずい
です。
教師自ら、数概念を育てることを放棄したことになります。
ご家庭でもその操作活動を大切にしていきたいところです。
算数ブロックは100均では売っていませんが、カラフルブロックなるものなら売ってます。家庭ならこれで十分です。
ですが、下のようなブロックがあるとご家庭で教える際、学校と同じように教えることができますよ。
あともう一つ。
手遊び歌があります。
これは5~10までの合成分解を楽しく理解させることができます。
今日はこれくらいでおしまい
たし算、ひき算についてはまた今度。
お楽しみに!
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
