
独裁者の統治する海辺の町にて(20)

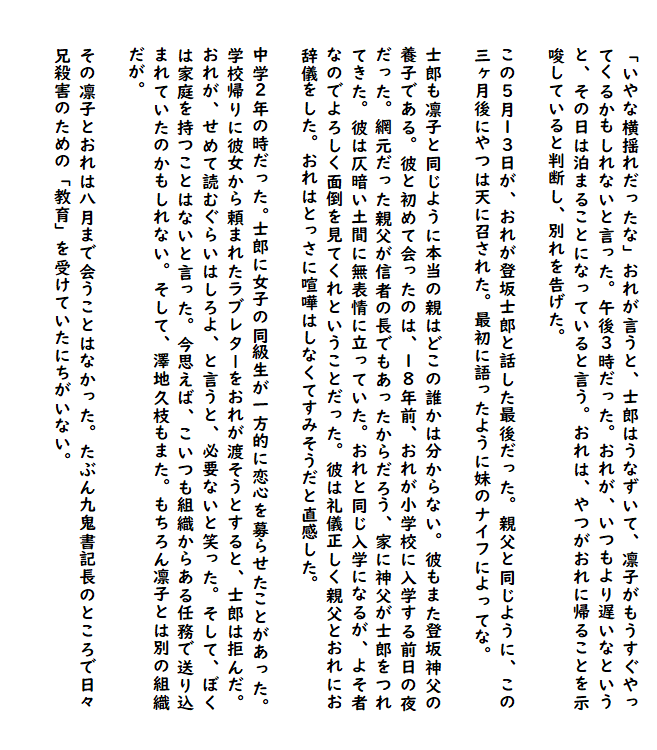
「ただ碧いだけの、何事もない海だった。あいつらがくるまでは」
おれはこの言葉を二度聞いている。一度目は、2年前の3月、おれが大学を卒業し、一時帰省していた時だ。親父は船の上でつぶやくように言った。その3ヶ月後、親父は「海難事故」で死んだ。そして、2度目が今日だ。士郎もつぶやくように言った。
「ただ碧いだけの、何事もない海だった。あいつらがくるまでは」
「おれは、その〈あいつら〉のメンバーだがな」おれは冗談めかして言った。
「それはしかたないさ。二方面から阻止にかかるのが理にかなっているからね」
「信用しているのか」
「信じるしかないだろ」
「凛子は?」
「あいつは来たときから違う世界にいる」
おれはたまらず言った。
「警戒しろよ」
「ありがとう。もしおれが殺られたら、久枝さんを・・・」
士郎は言いさしたまま口をつぐんだ。おれは焦れて、少しいらついた口調になった。
「久枝さんをどうしろって言うんだ、お前はあのとき会いにいけとは言ったが、それだけだった、会って何をどうするんだ」
「久枝さんに聞いてくれ、いや、一緒に逃げてもいい」
「どっちなんだ」
「お前に任せる」
「無責任だぜ」
「そうかもしれん」
士郎が、そう言ったとき、揺れがきた。それは足を踏ん張ればしのげる程度のものではあったが、なにか目に見えないもの引っ張られるような変な引力を感じた。
「いやな横揺れだったな」おれが言うと、士郎はうなずいて、凛子がもうすぐやってくるかもしれないと言った。午後3時だった。おれが、いつもより遅いなというと、その日は泊まることになっていると言う。おれは、やつがおれに帰ることを示唆していると判断し、別れを告げた。
この5月13日が、おれが登坂士郎と話した最後だった。親父と同じように、この三ヶ月後にやつは天に召された。最初に語ったように妹のナイフによってな。
士郎も凛子と同じように本当の親はどこの誰かは分からない。彼もまた登坂神父の養子である。彼と初めて会ったのは、18年前、おれが小学校に入学する前日の夜だった。網元だった親父が信者の長でもあったからだろう、家に神父が士郎をつれてきた。彼は仄暗い土間に無表情に立っていた。おれと同じ入学になるが、よそ者なのでよろしく面倒を見てくれということだった。彼は礼儀正しく親父とおれにお辞儀をした。おれはとっさに喧嘩はしなくてすみそうだと直感した。
中学2年の時だった。士郎に女子の同級生が一方的に恋心を募らせたことがあった。学校帰りに彼女から頼まれたラブレターをおれが渡そうとすると、士郎は拒んだ。おれが、せめて読むぐらいはしろよ、と言うと、必要ないと笑った。そして、ぼくは家庭を持つことはないと言った。今思えば、こいつも組織からある任務で送り込まれていたのかもしれない。そして、澤地久枝もまた。もちろん凛子とは別の組織だが。
その凛子とおれは八月まで会うことはなかった。たぶん九鬼書記長のところで日々兄殺害のための「教育」を受けていたにちがいない。
#小説 #創作 #短編小説 #連載小説 #鯨
#文学 #組織 #少女 #漫画原作 #連載小説漫画
#原発 #原子力発電 #地震 #教会
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
