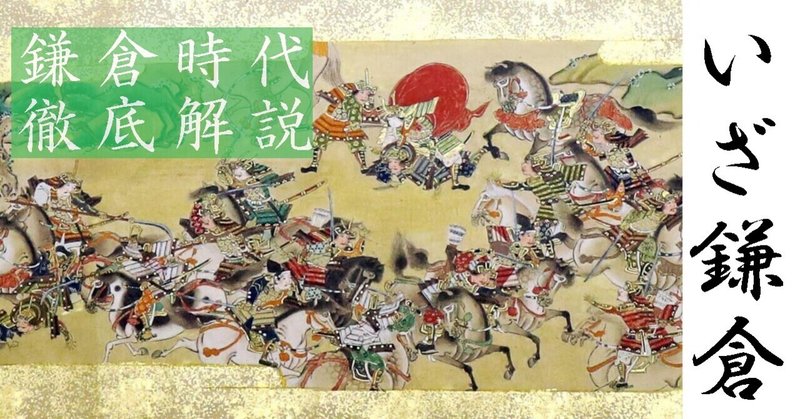
【いざ鎌倉:人物伝】北条政子
今回は北条政子について。
前回が義時でしたので、弟が先になりましたね。
今さらながら政子を先に書けば良かったと思いました。
今回の人物伝は本編で掘り下げる機会のなかった政子の逸話をまとめたいと思います。
「北条政子」
名前の話ですね。
この人は創作者泣かせでして、実は本名がよくわかりません。
「政子」は実朝の後継者問題で上洛した際、後鳥羽院から従三位に叙された際の便宜上の名前であり、この時61歳。
晩年の話であり、頼朝ともとっくに死別した後ですね。
当時は女性の本名は公に使用しないものであり、それ以前の名前は記録に残っていません。
頼朝は「政子」という名前を呼んだことは一度もなく、知りもしなかったはずなのです。
これまでの大河ドラマや創作物ではあまりこの事実を重視せず、頼朝との出会いから「政子」として登場するのが当たり前でした。
『真田丸』ではよく知られた「真田幸村」を真田信繁として描き、「幸村」の名前に特別な意味を持たせる演出をした三谷幸喜氏ですが、来年の大河では政子の名前をどう扱うのか注目すべきポイントと思います。
政子の性格
弟・義時と比べれば政子はやはり性格を窺い知るエピソードが多いように思います。
よく言われるように嫉妬深いというのは事実でしょうね。
頼朝が政子の嫉妬を恐れ、表立って側室を持てなかったことは一夫多妻が当たり前だった当時にあって極めて異例と言えます。
この嫉妬深さは、政子が長男・頼家を妊娠中に頼朝が寵愛した亀の前の屋敷を牧宗親に命じて打ち壊させた事件で爆発しています。
頼朝が堂々と側室を持てればもう少し男児を多く得ることもでき、源氏将軍家が3代で滅びることはなかったかもしれません。
鎌倉殿=尼将軍
政子の死後に定められた御成敗式目の第7条では、
「一 右大将家(源頼朝)以後、代々の将軍ならびに二位殿(政子)御時充て給はるところの所領等、本主訴訟に依つて改補せらるるや否やの事」
ととし、歴代将軍と政子によって与えられた所領は訴訟によって権利を奪われることはないと定められています。
「代々の将軍ならびに二位殿(政子)」であり、政子が将軍と同格に扱われていたことがわかります。本編でも解説した通りこれは、政子が将軍ではなくとも幕府の棟梁である「鎌倉殿」であったことを意味しています。
四代将軍九条頼経が政子死後5か月後に元服し、翌年に将軍宣下を受けた事実も政子からの代替わりを意味していることは明らかでしょう。
政子は「尼将軍」の異名に違わぬ征夷大将軍の職務代行者であったと言えます。
政子と長男・源頼家

2代将軍源頼家
政子と2代将軍頼家の関係は非常に悲しいものでした。
頼家の妻・若狭局が比企能員の娘であったことから、北条vs比企の政争の中で政子と頼家は親子でありながら対立を深めていくことになりました。
そして、最終的には父・時政、弟・義時とともに比企氏を滅ぼした政子は、頼家を死に追いやってしまいます。
政子はその後、自身の孫でもある頼家の子供たちの面倒をよく見ています。
頼家への罪滅ぼしであったのかもしれません。
頼家次男の公暁は、政子によって引き取られ3代将軍実朝の猶子となりました。僧としての修行を積み、政子の取り計らいで鶴岡八幡宮別当に就任しました。
三男の栄実も政子の後見によって僧としての道を歩むことになり、栄西の弟子となりました。
政子が頼家の子たちに武士ではなく、僧としての道を歩ませたのは将軍家の後継者争いから排除したかったという以上に、政治とは無縁の世界で長生きして欲しかったという政子の優しさであるようにも思います。
ただ、残念ながら公暁も栄実も政治とは無縁ではいられず、政子より先に命を失うことになってしまいました。これは政子の望むところではなかったでしょう。
また、頼家の長女・竹御所も政子が庇護し、実朝御台所の猶子としています。実朝御台所は実朝死後に帰京していますので、その後の面倒もやはり政子が見たと考えられます。
政子の死後、その葬儀や仏事に竹御所は積極的に関わりました。
男子のいない源氏将軍家は政子から竹御所に継承されたと言えるでしょう。
幕府の行事にも出席するようになり、御家人の尊崇を集め、4代将軍九条頼経の御台所となった竹御所は、祖母政子の後継者的立場となりましたが、残念ながら頼経の子を死産し、自身もその際に亡くなりました。
もう一人の子
頼朝と政子との間に産まれた男子は頼家と実朝の2人だけですが、頼朝には妾との間に産まれたもう一人の男児がいます。
後に貞暁と呼ばれる男児は実朝の6つ年上の寛喜3(1186)年生まれです。
その誕生は政子の怒りを買い、貞暁は政子を恐れた頼朝によって遠ざけられ、人目を憚るように育てられました。実朝が生まれる直前に鎌倉を離れ、京の仁和寺で僧としての修行を積みました。
承元2(1208)年、貞暁は仁和寺を出て高野山に移っています。
建保6(1218)年、実朝の将軍後継者問題で上洛した政子は熊野詣にも出かけ、その帰りに高野山に立ち寄り、貞暁と面会したと伝わります。
これは両者にとっての和解のきっかけとなったのでしょう。
貞暁の誕生に怒り、その人生を大きく変えさせることとなった政子ですが、この後、貞暁に帰依するようになっていきました。
実朝も頼家の子たちも命を落とし、貞暁が頼朝の血を引く唯一の男系男子となったことで貞暁を見る政子の目も変わったのかもしれません。
年を重ねて政子自身が丸くなり、自身の行いを過ちであったと反省するようになったということもあるでしょう。
本来は自身の孫である頼家の子らに任せるつもりであったであろう、源氏将軍家の慰霊を政子は貞暁に依頼するようになり、資金援助も行っています。
そして、嘉禄元(1226)年に69歳で生涯を閉じた政子の遺骨は高野山にも分骨されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
