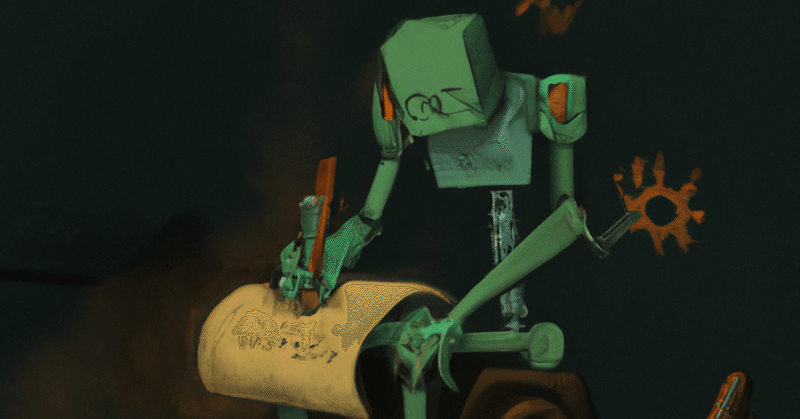
小説を書きたい
前置き
一体、何を書きたいのか決めてから書く。
何か、こう憧れとか、そういうもの。
自分に無いもの。これだ。
「心は解き放てる」という事。
もしくは、そうであって欲しいという願い。またはあって欲しい救い。今の自分と真逆のもの、憧れ。だが、もし憧れに至ったとしても、そこには代償もあるということ。それでもいい、今、心はここから解き放たれたんだ。
じゃ、書いてみよう。
「心風(neurosis)」
1.海岸

海岸まで降りて来て、海を目の前にして立ち止まった。
そうか結局もう、ここまでなのか。
その時、後ろから来た風が、男の背中をぐいっと押してから、
その心を絡めてとって、一緒に海へと飛んで行ってしまった。
男の身体がまだグズグズと立ち止まっている海岸も、眼下でまるで大きな生き物のようにうねっている海原も、解き放たれた心にとっては同じだった。
空にも海にも境など無かった。
内へ内へとこもっていった心が今、晴れやかなる日差しの中を、少しばかりの不安と共に風になって遠くへ遠くへと流れて行く。
きっとあの海岸はスタートでありゴールだ。
そう、心にとっての。
いつかいた場所であり、そしていつか行く場所。
それがあの海岸だ。
それがわかると、つい嬉しくなって振り返りそうになった。
これまでの憂鬱が嘘のように軽くなるのを感じたからだ。
でも、そうはしなかった。
行けるところまで、この解放感に浸ってみたかった。
海と空の間を滑る様に進んでいった。
やがて向こうにうっすらと白い影が見えてきた。
あれは、島だ。小さな島。
今なら、あの島を見に行くことさえ容易いだろう。
2.島

風は島中の木々をまんべんなく撫でまわして、大きなざわめきを起こした。
びっくりした鳥たちが、パッと飛び立って風の言いなりになった。右へ左へ上へ下へとさまよった。そうやって何とかやり過ごしてから、周囲を確認するように一回りして、ゆっくりと迷惑そうに降りて行った。
島には老人がいた。
流れ流されて、縁もゆかりも無いこの島にいた。
社会から逃げるかのように。
ある程度生きれば、誰かを愛したり傷つけたりもした。
だが、老人にはもはや待つ人も、帰る場所も無かった。
さらに残された時間は少なく、老人もまたそれを知っていた。
もはや起き上がる事の出来ない体を横たえたまま、一体いつになったら迎えが来るのだろう。何故いつまでも痛みと共にいなくてはならないのだろうか。そして、好き勝手に生きた代償なのかも、とぼんやり考えていた。
窓から見えるのは、変わり映えのしないいつもの景色だった。といっても、老人の白くなりかけた目には物の輪郭がぼやけて見える程度だった。おそらくあれは木だろうし、この大きなのは大きな岩だろうし、あの光って見えるのは海だろう。
どれも老人にとってはもうあまり意味の無いものになりつつあった。
そこに、びゅうっと風の音が聞こえた。
大きな風の音だ。
この音は老人の遠くなった耳にも届いた。
そして、老人の見ている景色は左から右へと傾いた。
木とはそんなに柔らかかったのか、とぼやけた視界の中で思った。岩はビクともしなかったが、岩の表面から剥離した物が風で飛んで行った。ぐにゃりとひしゃげた木々、そしてそこからちぎれて舞う枝葉。それらは四方八方へと動いてから、どこかへと運ばれていった。
老人の家は隙間風によって、一瞬にして換気されたようだった。新鮮で冷たい空気は、家の中の病や淀みみたいなものを取り除いて、肺の中にもきれいな酸素を送り込んで行った。
あばら家がガタガタと震えながら耐えている。いくつかのトタンは剥がれたり、戻ったりしてバタバタと音を立てた。その内の1枚がべりっと剥がれて飛んでいき、何かに当たってバフッと落ちてそのままズリズリと引きずられて行った。
風に飛ばされて行った鳥たちの中で、その飛ばされたトタンにぶつかって1羽の鳩が落ちて行った。他の鳥たちはしばし騒然としていたが、しばらくすると全て忘れたかのように、風の当たりにくいところにフラフラと降りていった。
風は揺らして、揺さぶって、壊して、そして奪った。だが、それも吹き終わると何事も無かったかのように、元の静けさを取り戻していた。
老人は力を振り絞って、深い呼吸をした。そして、少しだけはっきりした頭で思った。
自分はきっと、この風のように生きたのだ。
そうして、最後の瞬きをした。

風は、たどり着く行く先など決まっていないかのように通り過ぎて行った。
3.森

風はいつしか、大きな森の上を走っていた。
鬱蒼と広がる森の遥か北の彼方に、岩肌の山々が見える。
頂上付近には白い雪が積もっているようだ。
このまま進むと、あの鋭い岩山を越える事になる。
風は自分が凍ってしまう事や、すでに凍ってしまった風たちと一緒に、やたらめったらに吹きすさぶことを良しとはしていない。
だから、進路を南に変える事にした。
身をひるがえして方向を変えると、ふと森の隙間から、何かがキラキラと光っているのが見えた。そこにも、あそこにも。どうやらあれは川のようだ。太陽の光が水面に反射してるようだ。川は、大きな森を横断するように走っていた。
川の流れは南に行くにつれて、広く大きくなっていった。緩やかになる流れに、風のスピードも少し緩んだようだった。
やがて、川は突然、水煙と共に途中で途切れたように見えた。風は驚いて一瞬立ち止まったが、それが実際には、大きな滝となって下へ落ちていたとわかると、水に付き合って下までは行くつもりがないので、別の方向へと進路を変えようと大きな円を描くように旋回した。

滝になっている少し上流のほとりに少女が立っている。白いケープのようなボロを着た少女は、水が落ちて行くところをまんじりともせず見ている。
少女は、みなしごだった。気が付いた時、少女の周りには大人はいなかったし、食べる物も着る物も十分ではなく酷い有様だった。似たような境遇の子供たちが、草や虫、施しなどを受けながら何とか支え合って暮らしていた。少女はその中の一人だった。
少女と一緒暮らしていた子供たちは、皆、病を患っていて長くは生きられなかった。栄養失調と不衛生が原因だった。そしてこの日、少女だけを残して最後の仲間が逝ってしまった。亡くなった子供たちは、滝の上流から順番に流して弔った。誰がこれを始めたのか、なぜそうするのかはわからないが、少女もそれに従った。
仲間の体は少女とおなじようにやせ細っていたが、それでも少女には重すぎる程だった。なるべく引きずりたくは無かったが、そうする以外に方法がなかった。ようやく最後の仲間だった物を川に浮かべた後、だんだんと早くなる水の流れがそれを運んで行った。
少女は迷っていた。このまま見えなくなるまでここにいるべきなのか、それとも目を背けるべきなのか。答えは出なかった。ただ滝の方向を見て、仲間の身体を視界に入れてはいたがじっくり見ようともしていなかった。
少女はその場に立ち尽くしていて途方に暮れていた。この後どうしたらいいのか、この後何をしたらいいのか、何も浮かばなかった。
1つだけわかっていたのは、寂しくなるんだろう、という気持ちだった。これまでは誰かがいた。けれども、これからは孤独だった。それは恐ろしい事だ。
それがわかっているからこそ、少女は動けなかった。これから孤独と共に生きなくてならないから、それと向き合うのが怖かった。
少女はいつもお腹がすいていたし、咳だって出る。だが、それはいつも通りだった。だから、少女はこんな状況でいつも通りに、腹を減らして咳をしている自分に妙に苛立だった。
流された仲間の身体はとっくに見えなくなっていた。
もしかしたら自分もこの川の先、この滝の向こうに行けば皆に会えるんじゃないだろうか。そう思い始めたのは無理もない事だった。だがもういなくなった仲間たちから、決して滝に近づいてはいけないときつく言われていた。だから、少女はどうしたらいいのかわからないのだ。そしてその仲間たちはもういない。
一歩踏み出して、仲間のあとを追うのか、それとも振り返ってその日が来るまで生きるのか。その選択すら出来なかった。少女の生活は(それが生活と呼べるようなものだとしたら)いつも死が身近にあった。だが、それは自分でする選択だとは思ってもみなかった。
少女はこれから薄暗くなる前に寝床を探す必要があった。そして、出来れば何か食べ物も探さなくてはならない。
だから、生きるのであればここにいてはいけないのは明白だった。でも、足は歩き方を忘れてしまったかのようだったし、目は川の流れ以外の物を見ようとはしなかった。
少女の視界の中で川の流れの中から1匹の魚が飛び出た。魚は、一瞬空中に浮かぶと、瞬く間にぽちゃんという音を立て波紋を残して水中に戻っていった。
少女は、一度だけ仲間が捕まえてきた、いやたぶん拾ってきた腐りかけの魚を食べたのを思い出した。川の水と何かが混ざったような匂いがしたし、ヌルヌルとしたそれは、苦くもあり青臭くもあったが、火を起こして焼いて、皆で分け合って食べた。その味は忘れていなかった。たぶん、少女が食べた一番おいしい物だった。
あの魚をまた食べたい。
そう思った。
だが、すぐに一緒に食べた皆はもういないし、どうやって捕まえるのだという声が聞こえて来た。
少女はその自らの声に体を震わせた。必死になって見ないようにしてきた絶望が、一瞬でも生きようとした少女に重石となってまとわりついてきた。希望と共に絶望はやってきた。
もう足に力が入らなくなった。少女はヘナヘナと、その場に座り込んだ。そしてそのまま重くなった頭から、水面へと落ちるところだった。が、何とかギリギリのところで踏みとどまった。
立ち上がって、歩かなければ。
うずくまったままの姿勢で少女は思う。
でも・・・でもそれは、一体何のために?どういう理由で?
そうしなくちゃいけない理由が自分にはあるの?
もう、誰もいないのに。
少女は目を閉じた。
旋回して来た風が渦を巻くように強く強く吹いた。
そして、もう動かない痩せた背中をふわりと水の中へと押しやって、そのまま空高く舞い上がっていった。
4.砂漠
その砂漠は、立ち入った者は生きては帰れないという意味の名がついていた。いくつもの山々と、いくつもの湖を合わせてもその砂漠の広さには届かなかった。
それでいて頂上に雪と氷を蓄えるような標高の高い山脈が、ぐるりと輪を書くかのように砂漠を取り囲んでいた。山脈の盆地とも平野ともいえるような場所で、昼は熱と砂だけがあった。
また時折、山からの吹き下ろしのような強い風が吹いた。東西南北からそのような風が砂漠に吹き込んでくるので、あちこちで砂嵐や竜巻が起こった。

舞い上がった砂が全てを埋め尽くし、流れて来た水は地底へと飲み込まれるので、砂漠には砂のほかに何もない。
何も拒まない環境は、何かを残す事もない。
夜になると、凍てつくような寒さが忍び寄ってくる。わずかばかりに残っていた水を全て固め、潤いを奪っていく。日が昇る朝方のほんのわずかな時だけが、砂漠の優しい顔かもしれない。だが、それもすぐに太陽が許してはくれないだろう。
だから、人々は砂漠から得られるものは何も無いと言う。
もしどうしても何か得ようとするのならば、代わりに差し出すのはその命かもしれないのだ。
嵐とも半狂乱とも言えるこの”風のパーティー会場”に、図らずも合流する事になってしまった。高い山の尾根を雲と一緒に登っていき、何とか日の出ている隙に山の反対側へと一気に降りて来たところだった。
風たちは思うがままに吹いて、砂煙を巻き上げてはやたらめったらに砂を散らかしていった。ルールも秩序も何も無かった。いくつかの風が合流したかと思えば、またいくつかの風に分裂したりしていた。
中には正面からぶつかり合ってしまい、お互いに消滅する風までいた。だが、そんな事が起きていても、この宴とも言うべき状況を変えたり止めたりすることは出来そうになかった。風たちは完全にコントロールを失っていた。

砂漠の表面にはその乱交ぶりの跡だけが、くっきりとした風紋(ふうもん)となって残っていた。が、それもまた新たな風によって塗り替えられていく。
西から吹いてきた風が、砂丘の背を使って高く舞い上がった後、雲に触れるか触れないかのところまで上がると否や、勢いよく砂の地面にぶつかった。あまりにも勢い良くぶつかったので、大量の砂が周囲に巻き上げられ、風の形を一瞬残して地面がえぐれたかのようにへこんだ。
そのえぐれた地面の中には、2体のミイラがあった。骨と風化した服、少しばかりの装飾品。このミイラは男女で、恋人か夫婦だったようだ。2人は抱き合ったポーズのまま埋葬されたようだ。
それぞれの手を取り合って互いの胸の上に置き、向かい合って横たわる2人。愛の誓いは、死が二人を分かつまで。だが、この2人には永遠がそこにあるようだった。死して尚、いや、死してこその永遠があった。
先ほどの西の風の後ろを、お調子者の南から来た風がすぐに追っていた。西の風と同じように、砂丘を使って空高く昇り、何も見ないで下へと急降下して来た。
急降下して来た南の風は、西の風が作った窪みに同じ様にして激突した。その衝撃で、2体のミイラは粉々になった。長い間、日の光にも空気にも触れていなかったのが、急に地表に出たため、もろく崩れやすくなってしまっていたのだ。
ミイラだったものは数えきれないほどの砂の粒となり、砂煙の中へ混ざっていった。もう手を取り合った2人の形はここには無い。それはまるで永遠の終わりであるとも言えた。
窪みは別の風によって、徐々に平に慣らされていった。遠い昔に、同じように誰かだったかもしれない砂の粒が、風によってとめどなく窪みに流れ込んでいく。
やがて、何もなかったかのようなもとの砂漠に戻っていく。ここでは全てを覆い隠してもまだ、決して風が止む事は無い。
5.街
街に吹く風は、自然のそれとは違っていた。
大きなビルに阻まれて、入り組んだ街並みに邪魔されて、人の群れをかき分けて、細かく小さく散り散りになりながらも、無理やりにでも行きたい方向へと進むからだ。
街の淀みを一手に引き受けて、風は流れて行く。良い思い出も、悪い思い出も、過ぎ去ってしまえば過去になり、どんな思いも風と共に行ってしまう。
街に住む人の想い毎に、風は形を変えて行く。いびつに、そして冷たくなった風たち。苦にされども、楽にはされなかった。吹いても吹かなくても文句を言われた。
街に住む人達には、風も吹かないような安定した日こそが最良の日のようだった。平穏で変化の無い日々、だがそれこそが到底起こり得ない無理な話なのだ。

風の本分とは、望む時は吹いてこず、望まない時に風は吹いてくる。
その男に、やりたい事なんて無かった。
何となくで就職したし、小さくともやりがいとか生きがいはやっている内に見つかるだろうと思っていた。だが現実はそう甘くなく、すぐになぜ仕事をしなくてはならないのかという、答えの無い疑問を抱えながら、ただ働くという自己矛盾に苛まされていた。
何のために働くのか。という事と、何の為に生きるのか。は男にとってはとても似た問題だった。特にやりたい事が無い人間は、自分がやる事がある時、それが人生においてとても意味があると思いたいからだ。
だが時が経つにつれ、この社会というシステムにおいて、自分のやっている事が、髪の毛一本とか砂の一粒かのように小さい事が分かってきた。要するにそれが道端に落ちていても誰にも気にされないのである。
誰にも感謝されず、誰にも必要とされない自分は、一体何のために働くのだ。繰り返し問うてみるも、答えは空。空っ風が吹くばかりである。
一般論的に良く、お前の変わりはいくらでもいる。という言葉を聞くかもしれないが、実際のところは、自分の変わりなどいなくても社会は問題なく回る。という現実の方が大きかった。
そう思ってから、この状態であと何十年も同じ様に働くのか?と思うと、男は発狂しそうだった。やってもやらなくてもいい仕事。それに自分の何を捧げるのだろうか。
社会は真っ暗で、希望の種火さえ許してくれそうになかった。
ついにある日、男は全てを投げ出してしまう事にした。もう全部やめてしまっても、誰も何も困らないし、もし本当に代わりが必要ならば、それは遅延なく補充されるであろうこともわかっていた。
朝起きて、男は風の行くまま、気のままに出かける事にした。会社にはしばらく休みにします。とだけ伝えて、スマホの電源を切った。会社から電話があるかも知れないが、さして重要な事は起こらないだろうとも思えた。
そして、行った事の無い道を歩いたり、入った事の無いお店で食事をしたりした。話したことの無い人に話してみようかと思って、バーやスナックに行って見たが、そもそも話をするのが面倒だし、自分の事を聞かれるのも面倒なので、合わないと思ってすぐに出てきてしまった。
銀行で残高を確認した後、10万円くらいを引き落として、財布の中に入れた。家賃や光熱費の引き落としもあるだろうが、ま、何とかなるだろう。適当なホテルを取って、シャワーを浴びて寝よう。
一晩経てば、冷静になっていい考えが浮かぶかもしれないし、逆に何てことをしてしまったんだと、後悔するかもしれない。どっちにしても、何か今までと違う事をしたという事実の方が大事に思えた。
街の外れにあるホテルの1室からは、繁華街の灯りを内海を挟んで見る事が出来た。煌々と光るネオンやライトは、海面に反射してゆらゆらと揺れていた。同じ物でありながら、こうも違う物に見えるのかと感心してしまった。
内海を挟んで、という事は、この辺に海岸もあるのだろうか。男は明日、チェックアウトする時に、ホテルのフロントにでも聞いてみようと思った。スマホの電源を入れれば、自分が今どこにいて、近くの海岸も調べられるのだろうが、会社からの連絡があっても無くても動揺するだろうから、電源を入れる気にはならなかった。
次の日、チェックインする前に、ホテルの食堂で朝食を食べていると、ホテル周辺の物を紹介しているパンフレットを見つけた。それによると、バスに乗って5分くらい行けば、海岸近くまで行ける様だった。
昨日、丸一日ぶらついて、一晩ぐっすり寝たおかげで、少しばかり健全になってきた。
するとやはり男には後悔の念がひしひしと沸いてきていた。どうして会社に、しばらく休むなんて言い方をしてしまったのか。1日、ないし2日休んでまた復帰すれば良かったのではないか。
それに昨日はずっとスマホの電源をオフにしていたが、これから電源を入れて、誰からのどんな連絡があるか確認するのは、何とも恐ろしい話だ。たった一日であるが、されど一日である。
男は、自分が大して重要な仕事をしてはいないと考えているし、ある意味それは正しいかも知れないが、重要な人間では無いとしても、安否を確認する義務みたいなものが、雇った側にはある。だから、会社から連絡があったとしても不思議ではない。
だが、せめて海岸を見て、波の音を聞きながら深呼吸して、気持ちが落ち着いてから電源を入れよう。そして、誠心誠意謝るなりなんかして、明後日からでも、いや今日の午後からでも、菓子折りでも持って謝りに行こう。その後は、ま、何とかなるだろう。まさか、殺されやしないんだから。
そうして男はバスに乗ってお目当ての海岸へと向かった。
久しぶりに見る海岸は、思ったよりもゴミが有った。真っ白で余計な物のない砂浜を見たかったが、今日日そんなものは身近には無い。なるべくゴミを見ないようにして、男は波打ち際までやってきた。
波で濡れ無さそうなところで座って、大きく深呼吸を3回してみた。海と言っても内海だから、防波堤が視界に必ず入ってくる。防波堤の互い違いになった隙間のところから、外海が見える。タンカーらしきものがぼんやりと浮かんでいる。
男は意を決めて、スマホの電源を入れてみた。
着信20件、メッセージ1件。
すべて会社の上司からだ。きっちりと30分おきに掛かって来ていた。
とりあえずメッセージを開いてみた。昨日の夜11時に来ていたようだった。
お疲れ様。しばらくと言わず、もうずっと休んでもらって構わない。私物は荷物は宅配便で送る。ゴミとして処分されないだけ感謝しろ、ゴミが。以上。
簡潔明瞭である。
何がそんなに気に障ったのだろうか。なんとも労基法違反で、横暴のように見える。このメールだって立派な証拠になることだろう。
が、こんなに上司との関係がこじれてしまったのであれば、もうその会社に長くいる事も出来ないだろう。それにどうやら毛ほども冗談ではないみたいだ。

終わりか、というどす黒い気持ちと、ついに解放された、という晴れやかな気持ちが入り混じって、曇天が男の胸には広がっていた。
男は海を見て思う。
そうか、結局もうここまでなのか。
そこに後ろから来た突風が、男の心を絡め取って行った。
6.いつかいた場所、いつか行く場所
あの海岸以来、風の中に男の心はあった。
だが今、風は男の背中からまた、びゅうっと吹いた。
男の心は抜け殻だった体に戻った。
戻るや否や、涙が溢れ出て来た。
自分では、もう止められなかった。
泣いても泣いても足りないような気すらした。
境などのない海と空。
島の老人。
森の痩せた少女。
永遠なる砂漠のミイラ。
海岸にたたずむ自分。
解き放たれたと思った男の心が、風になって見て来たものは、あまりに悲しくて、辛いので、腹立たしい程だった。こんな事ならば風になど心を預けるじゃなかった。
そして尚悪い事に、最後に心は自分に戻ってきた。何も変わっていない、解き放たれてなどいない自分に返ってきてしまったのだ。
だが、それは当然でもある。男が風と見てきた限りでは、どこにも救いなどなかった。あったのは様々な形の絶望と、死と虚無だ。そこを風となって駆け抜けてきただけだった。
もはや涙を止めようという気すらなかった。
だが、何かをわかったような気になっていただけなのかもしれない。と、男が思い始めたのは、もう辺りが暗くなって涙が枯れるころだった。
境の無い海と空は、どこまで行っても一緒だった。海も空も一つであると良く言う。つまり、この社会は、どこに行っても同じなのかもしれない。違うのはそこで自分がどうするかであって。
島の老人の最後は、寂しさと悲しみがあったが、それだけでは無かった。自分は風の様に生きた。と気が付いて逝った。いい時の風を捕まえようと思って網を広げても、風はその網の隙間から抜け出ていってしまう。ただそれだけなのだ。あの老人も、その時その時の自分の風を生きただけで、最後は皆、似たようなものなのかもしれない。そして何より、最後に納得できたことがうらやましい程だった。あれが理想だとは言わないが。
痩せた少女の背中を押したのは、男の心ではなく、風だった。それに風はただ旋回しただけだ。それがたまたま少女の最後を、仲間と同じにしただけだった。男の心は、あの少女を救えるならばどうにかしてあげたいと思わないでも無かった。ただその時、男は風でしかなかった。強く吹く以外に、風が出来る事は無かった。少なくとも、自分勝手な解釈かも知れないが、これ以上、少女が苦しむ事も、悲しむ事も無くなったという事が、男にとってのほんの少しだけ溜飲を下げるようなただ1つの事実だった。だが、風でなかったとしても、男に何ができたのだろうか。
生きているのであれば、自分が死んだ後の事まで、気にしたくない。それが男の考え方だった。だが、死が訪れると必ず自分以外の誰かが弔う事になる。それは家族かも知れないし、全くの他人かもしれない。仮に、天涯孤独であったとして、共同墓地に埋葬されるとしても、役人や誰かの手によってそこに入れられる。その時、あの2体のミイラのように生前の形を残す必要はあるのだろうか?そもそも本当に永遠に形に残る物なんて必要なのだろうか?形が残っているからといって、それが永遠であるなど言えるのだろうか?あの2体のミイラが砂になって散っていく時、男の心は、これで良かったんじゃないだろうか。と思った。愛し合った2人を、永遠という檻(おり)から解き放つことができたんじゃないだろうか。と。
海岸にたたずんでいた抜け殻の男。心がどこかに行ってしまっても、心臓は動き、呼吸を止めないでいた。どうやら人は心が無くても生きていけるらしい。生きるというのは一体、何なんだろう。一体どういう理由があって、今ここで生きているのだろうか。あちらこちらへと飛び回っていた男の心は、解き放たれただけじゃなく、新たな鎖をしょい込んできてしまった。しかし、そもそも生きるという事はそうやって何かを背負っていくものなのかも知れない。悲しく辛い事ばかりだとしても、それが嫌になっても、それで仮に終わりを選んだとしても、それでもどうやってもこの世に吹いている風が止む事は無い。それを感じられなくなるだけだ。
だから、例えしょうがなしにでも、捕まえる事も、止める事もできないのならば、いっそ好きなように吹かせておくしかない。この吹く風がさまざまな思いや出来事を絡めとって、やがて自分という風になるのだとすれば、最後には自分もあの老人のように、納得できるのかも知れない。それが良いとか悪いとかではないのだ。少なくとも自分にはその可能性くらいはあるんじゃないだろうか、まだ、今ならば。
いつしか、波は男のつま先を濡らしていた。
波は月の引力が海を動かす事で起きるという。
その波が大気を動かす事で、風を起こすのだ。
無関係のようで、繋がっていることもある。
自分と言う風が、何かを動かす事もあるのかも知れない。
そう思いたい。
足元の砂が波にさらわれて、足跡を残した。
だがこの足跡もまた、波によってすぐに消えてしまう。
それでも男は振り返って、駅へと歩きだした。
涙の痕が残った頬に、風が少しだけ優しく触っていった。

おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
