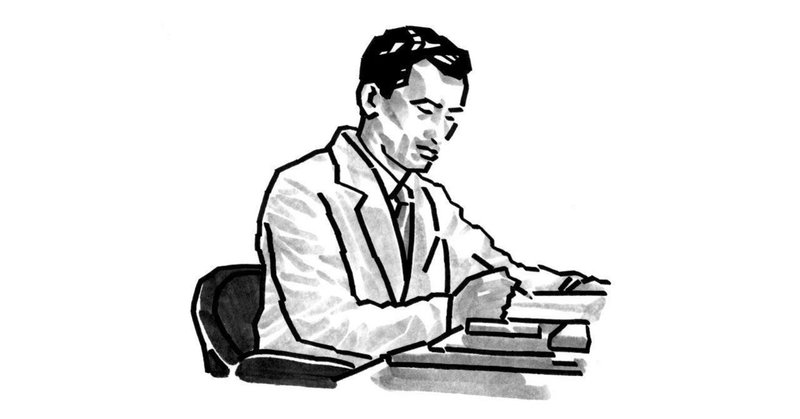
読んだ本から自分のウィークポイントを知る #56 「メンタルが強い人の習慣」
2020.08.19(水)本日、在宅勤務なので昼休みにnote更新!
ヘッダー画像なんかすごく実直な感じのお医者さんの画像をえらんじゃった。今回はこの本の感想を!
と思って、リンクを探すために「メンタルが強い人」で検索したらびっくりするぐらいまとめサイトが出てきた。
https://www.businessinsider.jp/post-204711
NIKKEI STYLEとかはこの系統の記事が結構多い。
なのでCOMEMOとかNIKKEIとかのハッシュタグよくつけてますが・・・
ちなみに私は、メンタルやストレスに関しては「圧倒的に強いタイプ」ですが、社内では「第一種生成管理者&メンタルヘルスマネジメントⅡ種」を受験したり、いろいろと対策もしてるからというのがあるかもしれませんが・・・
この本を読んでいただきたいのは、企業でメンタルヘルス系の担当になっている方だけでなく、だれでも読んでいただきたい本だったりします。
テレワークストレス
今回、この本では「在宅勤務という非日常状態がいつまで続くのか?先が見えないことによるストレス」についても書かれているので参考になる人も多いかなと思います。
①運動不足によるリスク
②生活リズムの乱れによるリスク
③人と話すことが減ることによるリスク
このnoteの続編で私が何をしてるのか?もここ最近の動きも日記的ネタとして書いてみようかなと思うので、「ストレス対処の続編」をしばらくお待ちください。この本の中にも結構出てくる内容です!
よく見る「好きなことを仕事にしている人」へ
「なぜ働くのか?」ってのは、長く仕事を続けるには大切なことです。
「好きなことを仕事にしてる」からいいんじゃないかーという人もいるんですけど、特に私のいるITの業界は、この考え方で結構失敗してる人を見てます。(特に今、就職活動で「IT希望の人」)
「プログラミングが好き」だからとか、逆に「人付き合いが苦手だから」とか。
実は私は20代はこの考え方で仕事してた時があります。
最初はすごく楽しいんですけど、30代ぐらいから壁を感じます。
今、プログラミングを知らなくても、IT業界はおそらくそこで技術をつけて食べていこうとする人間なら、おそらくこの先もたくましく生きていくと思います。
年齢によって求められるスキルが違うので、大学生の時にプログラミング、20代で人と働くこと、30代でマネジメント、40代でビジネス論とどんどん変化してます。
年齢というよりも「やれる人捕まえてやってもらう」ほうが、「みんなのためにも生産性があがること」と思ってやってるところあり。
memo-1:ストレスに悩まない人の7つの習慣
書籍に書いてあったことを少し紹介
1.好きなことをする
これ仕事以外で幸せな時間や生活の中から自ら作り出せる人
2.構える
最悪のケースを定期的に想定できる
→逆に起こったら嬉しいしなりをを日ごろから考えれる人
3.区切る
ストレスにかかっている時間や空間を断ち切れる人
4.捨てる
自分の力が及ばないものに対して無駄な努力をしない人
5.体を使う
体を使って緊張を緩和できる人
6.書く・人に話す・読む
話してすっきりできる人
note書いたり読んだりする人もこれに当てはまるかも?
7.新しい出会いを求める
一定の「ルーティン」を持つことも大事とは言われますが、ワンパターンな日常よりも変化を少しずつ体験することもいいかなと思ってます。
もし、ストレスを感じやすいという方は、この「7つの習慣」やってみるといいかもしれません!
memo-2:部下を追い込まない叱り方
私がメンタルヘルス担当になった時にもよく聞かれることなんですが、「叱る→パワハラだ」と言われることがあると管理者/監督者たちから、聞いたことがあります。
管理者/監督者であれば、叱り方は以下の事に気を付けて、叱ってみるとどうでしょうか?
①今しかるべきか?
②この場所・この場面でしかるべきか?
③私が叱るべきか?
私は、「叱らない」というやり方を取ることもあります。
「し」身体的接触は絶対禁止
「か」過去は責めずに隔離した二人で
「り」理論的に(感情的にならず)
「ぐ」具体的に
「せ」性格を責めない
私が、管理者の方々→部下へ「叱ってたり/叱られたりする」ところも見ることはありますが、これが出来てない人は、結構いると思います。
端から見ても「それはパワハラかもね」も多いんです。
memo-3:5つの「聞く」
この辺は誰でも「聞く態度」として現れてくると思うので、メモ!
①音を感じる=「聞く」
②傾聴・注意して耳に入れる=「聴く」
③尋ねて答えをもとめる=「訊く」
④機能が働く、できる=「利く」
⑤効果があらわれる=「効く」
よく「傾聴スキル」とも言われますが、「あの人聞き上手だわー」と言われるようになると、これらができるようになってる人かもしれません。
まとめ
産業医の方が書いた書籍なので、「外資系エリート」に限らず、どんな会社や組織に属しているワーカーがテーマになると思います。
読んでいるといろんなパターンがあります。パワハラ上司の下についた場合、対人ストレスに見舞われた場合、メンタル不調の同僚を見かけた場合、逆に自分が相手にストレスとならないような立ち振る舞いであったり。
この本の著者のWeb記事があったので紹介しておきます!
https://president.jp/articles/-/36966
それではみなさん、よき仕事ライフを!(* ̄▽ ̄)ノ~~ マタネー♪
ここまで読んでくれてありがとうございます! 読んでくれる方の多くの「スキ」で運営されてます!! XやInstagramのフォローは自由にどうぞ!
