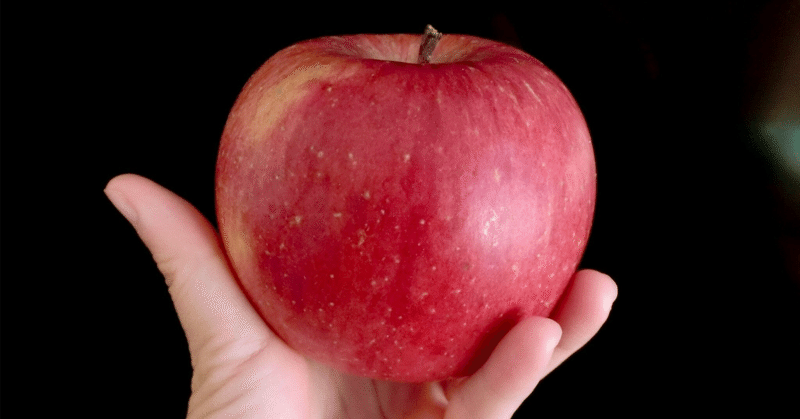
第Ⅻ章 アップルゲニウス−1
vol.1
僕は、槍さんの話を聞いて考え込んでしまっていた。復讐という名の怪物のことについて。そんな僕を見かねたのか。槍さんがつぶやいた。
「そろそろ、何か食べませんか。ここのカレーめちゃくちゃ美味しんですよ。」
「そうだな。セレン早く何か食べよう。腹が減ってはなんとやらだぞ。」
「それをいうなら腹が減っては戦はできぬだよ。」
「そういうことだ。早く食おうぜ。もう腹が減って死にそうだ。」
そう言って、剣崎は僕にメニュー表を渡してきた。メニューを見ると、鹿肉のキーマカレーと鴨肉のバターチキンカレー、猪のポークビンダルの3つが書かれていた。どうやらジビエ週間ということらしく、ジビエのスパイスカレーが今月の推しメニューらしい。僕は、ジビエカレーが気になったので、鴨肉のバターチキンカレーを頼むことにした。剣崎は鹿肉のキーマカレー、槍さんは猪のポークビンダルを注文した。みんながみんな違うカレーを頼んで、少しずつ分け合うというヤツだ。みんな全部気になっていた。メニューを注文してしばらくの間各々スマートフォンを見たりして暇を潰した。
「お待たせしましたー。」
店員さんの爽やかな声と共に、東南アジアを思わせるような香りと共に、カレーが運ばれてきた。どのカレーもとても美味しそうだった。お互いのところに皿が行き届いたところで、いざ実食。
「美味しい。」
一同が声を揃えてつぶやいた。鴨肉の油ガッジューシーでいい出汁が出ている。バーターと一緒にとても濃厚なのにくどくないカレーがそこにはあった。
「ちょっとずつみんなでシェアしようか。」
剣崎が僕らに提案した。みんな、そのつもりだったようでお互いのカレーを出して分け合った。そしてまた、美味しいと連呼した。鹿肉のキーマカレーについては、癖が強いかと思っていたが、そんなん事はなくでも野生み溢れるような香辛料が使われており、とても味わい深かった。猪のポークビンダルは、酸味のあるカレーが猪を全体的にさっぱりとさせており、圧力鍋で煮たのだろうか。お肉がほろほろで美味しかった。
「どのカレーも最高だな。」
「そうだね。やっぱりきてよかった。」
剣崎と槍さんは嬉しそうに話していた。そんな二人がどこか懐かしい風景に見えたのは何故だろうか。カレーといえば、未来に連れられて一緒に映画を見たのもカレーの物語だったっけー。カレーの香りがどこか懐かしさを記憶の奥から呼び起こし、感傷的な気分にさせていた。だが、そんな風になっていてはダメだ。僕は、今僕の物語を進めている最中だ。こんなところで終わるわけにはいかなかった。しかし、剣崎たちから教えられたSNSのアカウントはなんだったのだろうか。こんなことをできる人間は限られているー。いや、見た瞬間から僕はもうその答えに辿り着いていたんだ。だって、あの動画を作成できるのは僕の身近に一人しかいないのだからー。
「ところで、この後セレンは何かあるのか。」
「え。どうして。」
「いや、久しぶりに本物のサウナに行くのはどうかなって思って。最近行ったのは先輩が教えてきたサウナもどきだったじゃん。」
「ああ、そういえばそうだったね。うーん、とりあえず暇だから行こうかな。」
「おし。じゃあ行くか。」
そう言って、僕と剣崎それから槍さんは残りのカレーを胃袋に書き入れてサウナへと向かった。場所は、いつものプライベートサウナにした。
サウナに着くとお客さんはまばらにいた。なんだか、ホテルのようなプチ旅行に来た気分にさせてくれる気分が懐かしい。それくらい本当にサウナに行くのは久しぶりだった。個室に行って水着に着替え、サウナハットを被り、いざサウナへと入った。入ってすぐにうわっと思った。なかなかに熱い。ここのサウナは、100度を超えており、サウナの中では熱い部類に入る。あの頃は、慣れていたせいでなんとも思わなかったが、久しぶりともなると、かなり熱く感じた。濡れたタオルの上に座ると1分も立たないうちに汗が滝のように流れ出た。目は汗が滲んで開けることができなかった。剣崎の方を見ると、随分と涼しい顔をしていた。槍さんも普通に座っっていた。「コイツら、最近来てないとか言っておきながら二人で来てるな。」と腹の中で思った。
5分が経とうとしていた。僕は、もうすでに外に出たかった。がルーティーンとしては、10分くらいがベストであった。それを考えると、ここで出てしまうのは、非常に勿体無い行為であった。プライベートサウナは、学生にとって安くはない。1回1回を大切にしなくてはならない。そう思い、僕は、あと5分を頑張ることにした。時計が1秒1秒を刻んでいくのがとてもゆっくりに見えた。苦しい。300秒を一つ一つ数えていく。カズ得ることに集中することで、辛さを紛らわす。ふうふうと、呼吸が荒くなる。長い長い時間が経ってやっと10分が経った。僕は、剣崎や槍さんの方など見向きもせずにすぐに外に行き、水風呂に入り外気よくへと走った。テラスにある椅子にゴロンと寝転がるともう全身の力が抜けていた。整っている。そうやって、バタバタとしていると、剣崎と槍さんがゆっくりとやってきた。
「セレン、ちょっと鈍りすぎじゃないか。たかが10分でこんなにグロッキーになるなんて。」
「いや、そっちは、何度かきているだろ。久しぶりのサウナの人には思えないよ。」
「まあ、たまに二人でもきているからですかね。」
余裕の表情で槍さんが、僕に言ってきた。二人はもう一周するらしい。僕はっもういいと言ってオロポを一人で飲んでいた。一人でくつろいでいると、羚羊さんからメールが一通入っていた。内容を確認すると、今度時間があるときに話がしたいというものだった。僕は、土曜日なら空いているという連絡を入れると、すぐに返事が帰ってきた。そして、土曜日に羚羊さんと会うことになった。僕がスマホを眺めていると、剣崎と槍さんがやってきた。
「いやー。整ったわ。セレンもちゃんと定期的に来ないとダメだぞ。」
「はいはい。ちゃんと行くよ。」
剣崎は、満足げにオロぽを飲んでいた。幸せなやつだ。コイツは、きっと悩みなんてほとんどないのだろう。羨ましい限りだ。しばらくゆっくりとしてから、僕は剣崎と槍さんに別れを告げて家路へと急いだ。
土曜日の昼。僕は、羚羊さんに言われた通り、出版社にやってきた。やってくるると、そこには黒奈もいた。黒奈と会うのは、白弓先輩ににもかいに誘われて以来久しぶりだった。黒奈と雑談をしていると羚羊さんが、慌ててやってきた。
「二人とも急に呼び出してしまってごめんね。」
そう言って、僕らにちょっとご飯でも食べに行こうと言って外にタクシーを呼んでくれた。タクシーに揺られて10分くらいすると、そこは高級焼肉店だった。普段学生じゃ絶対に行くことはないだろうお店について僕はついつい緊張してしまった。店内に入ると、羚羊さんが名前を店員さんに伝えた。すると、個室に案内された。
「さあ、二人とも遠慮せずに食べてね。」
そう言ってメニュー表を渡された。メニューを開くと、普通のお肉の10倍はするんじゃなかろうかという勢いの値段が書かれていた。僕は、恐ろしくてなかなか注文できないでいると、黒奈は遠慮なく注文を始めた。
「ハラミ、ミノ、タン、ザブトンあとハツとナムルの3種もりに、キムチとー。」
「おい、黒奈。そんなに頼んだら流石に悪いだろ。」
「え。だって遠慮しなくてもいいって羚羊さん言ったじゃない。」
「そうだけど、限度ってやつがあるだろう。」
僕が黒奈と揉めていると、羚羊さんが笑っていた。
「相変わらず、黒奈ちゃんはこういうとき遠慮がないね。いいんだけど。あっと、セレンくん。気にしなくて大丈夫だよ。本当に。独身貴族なめんなってね。」
「本当にいいんですか。」
僕は、念押しに尋ねた。
「本当に大丈夫だよ。今回の記事で二人にはとてもお世話になったし。それの報酬ってことで。二人に給料を払うことはできないから、ここで存分に食べてもらうってことだから。」
そう言って羚羊さんは笑顔でメニューを渡してきたので、僕は流石にこれ以上遠慮しているのは悪いと思ったので、いくつかお肉を注文した。黒奈が注文したお肉が次々と到着してくる。それを、丁寧に焼く。焦がしてしまってはせっかくのお肉が勿体無いと思い、真剣だった。やっと1枚を焼き終えて、軽くタレにつけてお肉を食べる。
「○△○◇~☆」
言葉にならない声が出た。つまり、めちゃくちゃ美味しいということだ。今までに食べたことのない味わい、肉が柔らかいし、油は甘く美味しかった。こんなお肉を食べたことがない。僕はこんなお肉がこの世にあったのだろうかと思うほど感動した。黒奈を見ると、黙々とお肉を口に運んでいた。黒奈が黙って食べるときは、大抵集中して食べているときだ。黒奈もまた、僕と同じようにお肉の味wP噛み締めていた。そんな僕らの姿を見ながら羚羊さんもお肉を食べていた。しばらくすると、羚羊さんが僕らに話しかけてきた。
「ところで二人とも、本当に今回はありがとう。」
「いえいえ、こちらの方こそ感謝しきれないです。奴らに復讐を行うことができました。」
「それはよかった。あれからどうかな。何か奴らから接触があったりとかはなかった。」
「いいえ。何もないです。沈黙って感じですね。ほとぼりが冷めるまでは何も行動してこないんじゃないんですか。」
「そうか。もし何か接触してきたら言ってほしい。きっと、君に何か危害を加えてこようとするかもしれないから。」
「すみません。そんなところまで気を配っていただいて。」
「いいんだよ。大人にもっと頼りな。君は、一人で背負い込もうとしすぎているのかもしれない。」
「確かに、そういうことは多いのかもしれません。」
僕は、トングを見つめながら呟いた。思えば、何かあるとどこか一人で考え込んでばかりかもしれない。復讐については、黒奈が支えてくれたけど。
「今回だってそうよ。私が言わなかったら、ずるずるとこのこと引きずったままだったと思うわ。」
黒奈が僕に向かって言った。確かにその通りだと。僕は何も言えず、ただ苦笑いを浮かべることしかできなかった。肉が焼ける音がする。脂が弾けてテーブルに広がる。僕達が呼んだ波紋は、油汚れのように頑固なもののようだった。しばらく考え込んでいると、羚羊さんが僕に言った。
「セレンくん。何か背負い込んでいるでしょ。」
「えっ。そんなことないですよ。」
「そういうの、もういいから言っちゃいなよ。」
羚羊さんはここぞとばかりに聞いてきた。僕は、その押しに勝てず、ポツリぽつりと今の心境の変化を話した。
「たくさんのことがありました。ある人は、ブルーガーデンのせいで職を失い。ある人は、命を落としたり。そんなことを見聞きすることが、自分の犯した復讐の重さがずしりと感じました。社会に与える影響は僕が考えているよりもとても大きかった。僕は、自分の行った行為に対して本当に正しかったのかー、疑問に思っているんです。それは、復讐というなの十字架を背負っているかのような。」
僕の話を黙って羚羊さんは聞いていた。たまに相槌を打ちながら。
「そうだね。そういう気持ちになってしまうよね。わかるよ。」
「羚羊さんもそういう気持ちになるんですか。」
羚羊さんはグラスのウーロン茶の縁をなぞりながら懐かしむようにして話し始めた。
「そうね。今はないけれど、昔は会ったわ。確か、帝京電子という会社の不正を告発した記事だったかしら。」
「確か、石油式暖房機から一酸化炭素が発生していたことや火災報知センサーの中身が空っぽだったとか言ってかなり問題になった事件でしたよね。」
「よく昔の事件なのに知っているわね。」
「子供の頃、父がクレームを入れたのを覚えていて。」
「なるほどね。それならその説明については省いても良さそうね。では、話を戻すわ。」
そう言って羚羊さんはグラスの烏龍茶を一口飲んで話を続けた。
「あの頃、私は新人記者だった。そんな私が、初めて受け持った大きな山だったの。どうしても、結果が欲しかったわー。だから必死で調べ上げた。被害者宅に取材をしたり、加害者となった帝京電子の製造本部長に突撃取材をしたり。どんなに細かいことも調べたわ。長い調査の末に告発記事を投入した結果、記事はかなりの反響だったわ。私は、善人のつもりでこの記事を書いたわ。人命被害が出てはいないもののこんな命に関わるようなことを平気でしていた行為が許せなかった。正義の鉄槌を私が行わなければー。今思えば、若さゆえの感情よね。そういったものもあって、私はのめり込んでいたわ。」
羚羊さんは、一呼吸をおいてから再び話し始めた。
「そのかいもあって、一面記事で載せてもらったわ。気持ちが良かったわ。なんせ、自分の記事が週刊誌の一面に載るなんて夢にも見ていなかったもの。今と違って小さなコラム記事を載せてもらえればとても良かった時代だったから。でもね…。その記事の影響は大きすぎた。当時の社長は辞任に追い込まれ、担当となった責任者は自殺。おまけに、帝京電子の株価は下落し、ほぼ倒産状態まで追い詰められた。これによって当時勤めていた社員2千人はほとんど路頭に迷うようなこととなった。その人たちの家族から、出版社までクレームが大量にきたの。クレーム対応は、アルバイトがほとんど対応していたのだけど、人手が足りなくて私も対応することになったの。あるときは、死ねと一言だけのものや、長々とその記事についてのクレームを言う人。人生めちゃくちゃにしてくれたなって。様々な罵詈雑言を浴びせられたの。当時の私は被害者の男性からストーカーされて、何通もの殺害予告をされたりしたわ。そんなに否定されちゃうと、なんだか私のやった内容がまるで間違っていたと感じていしまうようになったわ。そう、今のセレンくんみたいに。」
「そんなことがあったんですね。でも、羚羊さんはどうやってその気持ちから脱したんですか。」
羚羊さんは、ちょっと目線を落として話を続けた。
「そうね、一番は慣れることね。」
「慣れる?」
僕は、羚羊さんの言葉を詠唱した。
「そうよ。慣れてくるの。いろんなことに。急になんてことはないわ。徐々に、私が記事を書くことで拡がる影響も何も感じなくなった。熱々のお風呂に入ったときに、最初は熱くて入れないけど、だんだん慣れると湯船の熱さが心地良くなるような感覚と一緒よ。セレンくんは、今がその熱熱のお風呂に足を踏み入れたところなの。だんだんと肩まで浸かれるようになるわ。」
「そうなりますかね。」
「不安になるのも仕方ないわ。そう気弱なくてもいいのよ。どっしりと構えておけばいいの。」
「そうですねー。」
僕は、羚羊さんの言葉をゆっくりと飲み込んだ。
「それにね。報道とは、自由でなくてはいけないわ。闇に隠れた事実を誰もに知らせることは義務であるわ。犠牲なくして大義は得ることはできないのよ。」
「なるほど。」
「ちなみにこれは私の上司の受け売りだけど。」
そう言って羚羊さんは、大きなお肉を頬張った。
「本当にここのお肉美味しいわね。」
僕は、羚羊さんの意見が正しいとか間違っているのかについてまだわからずにいた。でも、もしかしたらこの問題は、正しいとか正しくないとかそういう問題はないのではないかと思った。
「てか、いつの間にお肉あと一切れになってる。」
僕がテーブルを見ると、あれほどあったお肉はもう一切れになっていた。横を見ると黒奈がナプキンで満足そうな顔で口を拭いていた。
「あら、二人が話に夢中になっているから私が食べてあげたのよ。」
僕は、少し呆れながら最後の一枚のお肉を焼いた。羚羊さんは、追加で注文してもいいと言ってくれたが、あまり食欲もなかったので大丈夫と伝えた。
最後のお肉が焼けるまで、三人で軽い雑談をして過ごした。最近、大学生で流行っているものなどを聞かれていた。きっと、次の特集か何かにつながるものだろうか。羚羊さんは、そうやって色々な情報を集めているのだと思った。さすが凄腕の記者だ。お会計は総額いくらになったのか見るとレシートをチラ見すると、いつも見る値段よりも一桁数字が大きかった。僕は、思わず顔に驚きの表情が出たが、羚羊さんは涼しい顔をしてお会計を済ませていた。
「今日は、ありがとうございました。」
「いえいえ。また、、美味しいものご馳走するわよ。」
「そんな、悪いですよ。」
僕が申し訳なさそうに答えると、羚羊さんは嬉しそうに答えた。
「大丈夫、ちゃんとその分の取材はするから。」
抜け目がないなと僕は思いながら、羚羊さんと別れた。その後、黒奈の提案で僕と黒奈は映画を見ることにした。ニンニクの匂いを纏いながら僕たちは、映画館へと足を運んだ。
「周りのお客さんにニンニク臭いとか思われないかな。」
「そうね、こいつら焼肉食べてきたなって絶対バレちゃうわよね。」
「ところで、何の映画を見るの。」
「ああ、ホラー映画。」
「えっ。」
僕は驚いた。ホラー映画なんて初めてだった。というか、ホラーはあまり得意ではなかった。修学旅行で行った遊園地のお化け屋敷が忘れられない。あの時もビビり散らかして当時の彼女に惹かれたのを覚えている。
「セレンくん。もしかして、ホラー映画は苦手。」
黒奈が僕に聞いてきた。
「ふ、普通かな。」
僕は、少しだけ嘘をついた。
「普通って割には反応がー。」
「いや、黒奈がホラー映画なんていうのが珍しいというか。意外というか。」
「ああ、そういうことね。ホラーは意外と好きなのよ。」
「ふーん。」
僕は軽く返事をしてチケット売り場えと足をすすめた。若干、帰りたい気持ちになっていた。黒奈は先ほどあれだけ食べたのにポップコーンの特大サイズを注文していた。これからホラー映画を見る奴がこんなにポップコーンを頬張るのかという感じだった。僕がポップコーンを見ていると黒奈がそれに気づいたらしい。
「セレンくんも食べるでしょ。」
「あ、うん。」
いや、そういうことではないんだよな。そう思いながら、僕らはホラー映画が上映される劇場へと入っていた。劇場を見渡すと、人はぽつりぽつりといた。うん。これなら多少うるさく叫んでも迷惑はあまりかからないな。そう思い、僕は席についた。
席についてしばらくすると、映画は始まった。お決まりの映画泥棒がから始まり、広告が流れる。やっと、ジーッというノイズ音と共に映画が始まった。
ー教会に集められた若者たち。湿った匂いのする教会ではある儀式が行われていた。悪魔を憑依させる儀式。悪魔に取り憑かれた人間たちが集ってい、最後には自分自身も悪魔になっていく。抑えきれない復讐という衝動を抱えながら、主人公たちはそんな教会に夏休みにやってきた大学生達だった。
あらすじからして怖い。物語が始まって横を見ると、黒奈は終始ポップコーンを口に入れていた。その間も、洋館では不可解な現象が起きていた。僕は、黒奈の手を握る。ビビっていたわけではない。人肌を感じたかった。儀式を見てしまった大学生が悪魔に取り憑かれる。刹那、僕は黒奈にキスをした。恐怖を紛らわせるために。黒奈は最初は嫌がっていたが、仕方がないなと言って続けた。キスはポップコーンとニンニクが混じったカオスな味になっていた。レモンの味なんて何にもしない。もうそんな僕らは純粋でもないのだ。周りで悲鳴が上がる中、僕らは何かの儀式のように唇を重ねていた。映画が終わるまでに、僕らは何回かキスをした。ニンニクの匂いが感じられなくなるほどにー。
映画の上映が終わり、僕らはカフェで休憩することにした。
「ねえ、セレンくんのせいで内容何も入ってこなかったじゃない。」
「ごめん。」
僕が注文したコーヒーを啜りながら黒奈に謝った。自分でもどうかしていると思う。暗かったとはいえ、公の場であんなにキスをするなんて。
「そんな積極的なら、普段からやってほしいわ。それとも、セレンくんも取り憑かれちゃったのかしら。悪霊に。」
「そんな、滅多なこと言わないでくれよ。」
「わからないわよ。ムッツリさんな悪霊に取り憑かれちゃってるのかもしれないわよ。」
「はいはい。」
「それはそうと、何か私に言いたいことがあるんじゃないかしら。」
黒奈の空気が変わった。
「そうだね。」
僕は、ずっと言わなくてはいけないことがあった。剣崎からあの動画を見せられた瞬間から、あの動画を撮影できた人物について考えていた。あの場にいたのは、僕と油野と黒奈。そして、あの音声の距離感からすると、僕と油野の近くだった。油野があの動画を撮るメリットない。そして、僕ではない。残りは、そう。黒奈だけしかいないんだ。
「剣崎から、SNSに僕と油野が言い争っている動画が公開されていた。あの時、僕と油野は議論に集中していて撮影する余裕なんてなかった。だからー。」
「私が撮影して、公開したと言いたいのね。」
黒奈が、僕よりも先に答えた。
「そうだ。」
黒奈は即答した。
「撮影したのも、SNSに公開したのも、セレンくんが思っている通り。ー私よ。」
「なんでそんなことしたの。」
「「なんで」って。それは、セレンくんの復讐の手助けになると思ったからに決まっているじゃない。」
「そうだよね。でもー。」
「でもって。『そこまでは、求めていなかったと。』言いたいの。」
「うん。」
「随分と臆病なのね。あれほど、復讐に取り憑かれていたのに。」
「いや、そこまでやらなくてもいいじゃないか。」
「やるなら徹底しなくちゃダメなのよ。replay evil with evil .悪には悪で報いる。昔から言うじゃない。」
黒奈は、冷たく、深く僕に言った。僕は、困惑していた。
「動画を通して真実を伝えることで、信憑性がさらに増すわ。人は、悲劇に共感しやすいのよ。細かい話なんかよりも感情を揺り動かす、シンプルなものの方が。」
黒奈は、静かに言っていたが、その言葉には激しさが感じられた。
「ねえ、知っている。あの記事に否定的な意見も多くあったことを。」
「そうなの。」
「ええ。現実味がない話なんて言われていたの。このままじゃ、セレンくんがネット上で叩かれかねない。私は怖かったわ。そんなことは絶対にさせない。だから、あの動画を作成することで、物語を作ったの。意見を全てブルーガーデンが悪いというシナリオに向けるために。結果は、私の思った通りに、ブルーガーデンが悪という不調が広まったわ。」
僕は、黒奈がどうして復讐に囚われていたか分からずにいた。当事者でないはずの黒奈が僕以上に復讐に取り憑かれていることが。
「黒奈は、どうしてそこまで復讐にこだわるの。」
「セレンくんのためよ。そう前も言ったじゃない。私は、あなたがあんな下衆たちのせいで苦しんでいることが本当に嫌なのよ。」
「僕のため。それって本当なの。ここまで、誰かのためにできる黒奈がー。」
僕が言葉を言おうとすると、、黒奈は少し下を向いていた。僕も言いすぎたかもしれない。黒奈がここまで思ってくれたことを僕は拒絶するなんて。そう思っていると、黒奈が小さな声で話始めた。
「あなたは、私にとってヒーローだから。」
「ヒーロー?」
僕が問い返した。ヒーローとはどういうことだろろう。黒奈に出会ってから、何かそういうことはなかったはずだった。僕が疑問を浮かべていると。黒奈は思い出すように語り始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
