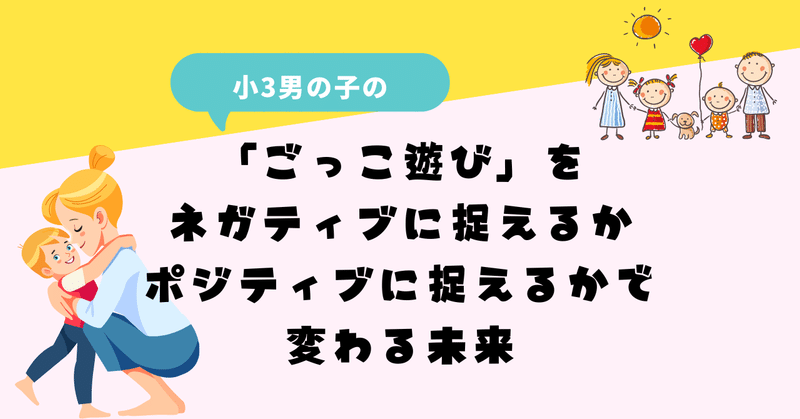
小3男子の「ごっこ遊び」をネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかで変わる未来
息子たちのお友達兄弟が泊りに来たときのことです。
子どもはうちの子と合わせて全部で4人。
小4、小3、小1、年長さんでみんな男の子。
そんな男4人お泊り会の最中のことです。
みんなゲームに夢中で他の遊びに一切興味ないくらいの状況の中、我が家の長男(小3)がごっこ遊びがやりたいようで、1人でストーリ設定し始めました。
ごっこ遊びをしたがる小3長男と周りの子の反応
子どもたちは各々武器(おもちゃ)を手にして遊びだしたときのことです。
やんわりストーリーがある戦いごっこ的なことが始まった途端、長男は急に大張り切り!
自ら武器屋さんになりきり、テーブルを配置しホワイトボードを壁に掛け値段や本日のおすすめ的なことを書いたりと大忙しで、銃の弾を入れるケースがどうのこうのと作成しだしたりと長男は夢中。
「よし!完成!武器屋来ていーよー!」と意気揚々にみんなに声をかけたときには、もう誰もその遊びしてない。
長男が必死になんか作ってたとかイメージ膨らませてなんか言ってるとかそんなことはお構いなしで、とっくにゲームに没頭中。
チーーーーン。
子どもは各々夢中になるのもすぐだし冷めるのもすぐ。
長男はしょんぼり。
温度差はんぱない。。。
長男が今回のお泊り会で一番輝いていた瞬間だった。
実際武器屋の商人になれた時間は1分たらず。
準備に10分以上かかり、実際武器屋だったのはまじで秒だった。
長男は武器屋になるまでは本当に楽しそうだったが、この遊びは終了していると気づき落胆。
もともとかなりの繊細くんなので友達に自分の主張をうまく伝えることは苦手。さらに強く言って誘うなんて超ハードルが高い。
「みんな違う事始めちゃったね」と声かけたど本人は「うん。。残念。。」の一言。
つら。
男の子のごっこ遊びは何歳まで許容できるか?
そんな子供たちのやり取りを見ててふと思った。
長男って〇〇ごっこ好きだよな。
〇〇屋さんじゃなくても、レゴとかトミカとか、トランスフォーマーやガンダム、ポケモンのフィギュアとかで延々とブツブツ言いながら遊んだりすることが多い。
小さいときはなんとも思わなかったことも年齢とともに、心配になってくることってあります。
子どもの好きなことや遊び方をどう捉えるかは大人次第。
小3のごっこ遊びは幼いと捉えますか?それとも肯定的に捉えるのますか?
はたまた遊びに年齢なんか関係ないと思えるか?
この物事の捉え方で子どもの未来は大きく変わってきます!
みなさんならどうですか?
過去の私だったら長男の行動を見たときにこう思ったと思います。
みんなで遊んでいるのに協調性がない
小3でごっこ遊びなんて幼い(ほかの子が乗り気ならそうは思わないんだと思う)
準備に時間かかりすぎたから仕方ない
没頭するのもいいけど周りのじょうきょうもちゃんと把握しようよ
そう!基本的にネガティブに捉えがちなんです。
周りと違う行動をする息子を見るたびにヒヤヒヤ。
親として正してあげなきゃ!という正義感と使命感。
今回のごっこ遊びの件はあくまで一例ですが、学校生活もまさに同じです。
みんなと同じ行動ができるようにを基本とする教育。
《 平均的になんでも卒なくこなせるように 》
具体的な教育の在り方や考え方はどんどんアップグレードされているものの、この教育のベースだけは私が子供だった頃から変わっていません。
100と0より50と50の方が良いという考え。
そんな教育を受けて育った私自身が、子ども達の個性を心の底からは認めてあげれていなかったんです。
個性を大事になんて頭では分かっています。
でも子供が困っていることを目の当たりにすると、正しい道に導かなきゃ!苦手を克服しなくちゃ!と思ってしまうのが母親です。
でも苦手克服よりもっともっと根本的にやるべきことがあります。
それは子どもの個性含め存在を認めること。
もうこれしかないです。
お母さんが子どもを認め、ネガティブになりがちな考え方を本気で変えることが大切です。
そうすれば
ごっこ遊びも何一つ悪いことはない!
むしろ考え方変えたらいいことしかないんです。
うちの子だけ
できない?足りない?苦手? ではなく
うちの子は
興味がある!なぜ?どのように?
に考え方をシフトして「無い」ことから「有る」ことにフォーカスすると、どんどん子育ては楽になり、子どもは驚くほど成長していきます。
ごっこ遊びがもたらす影響は最強で最高だった!
ごっこ遊びによって得られることは 創造性!!! これにつきます。
想像力と創造力は違くて、想像はその名の通り、イメージ!
頭の中で思い浮かべる力。
魔法が使えたら~、空が飛べたら~などのファンタジーな世界も想像性です。
その上で創造力とは想像したこと具現化すること。
頭でイメージしたアイディアや物事を実際に形にする力です。
この創造力って子どもはものすごく高いですよね。
これは伸ばそうと思えばどこまででも伸びる限界のない能力でもあります
そういった視点で振り返ると、
イメージを形にしたくて必死に武器屋の準備をしてたんだ!
いっつもストーリー作りながらレゴで基地作ったり、背景書いたりポケモン人形並べてバトルさせたりしてるのも素晴らしいことだったんだ!
と息子のことを認められるようになり、むしろ誇らしくさえ思えてきます。
誰も考えもつかないことをイメージしてさらに形にできるなんて天才じゃないですか!?
親の視点と考え方次第で子どもはみんな天才になれます♡
ごっこ遊びは言い換えれば完全なる「クリエイティブ」
ここまで掘り返して考えると、実はめっちゃクリエイティブじゃん!!って思いませんか?
日本人は特に教育の概念からも平均的なことから目を背けるのはなかなか難しいことでもありますが、よく考えてみるととてもシンプルです。
これからのAI時代。
最も必要と言われてるのは「非認知能力」
これがまさに創造力!
AIは勉強は人間以上に出来て当たり前。
算数も国語も理科も社会も学校で習うような答えが決まっていることは今後AIがすべて担当していきます。
逆にAIができないことって何?
ないところから作ることです。自分で考えて形にする力。
つまり 0➤1のチカラ。
1から2は出来る人は多いです。賢い人ならみんな努力すればできます。
でも0から創造し1にするってゆうのは本当にすごいことなんです。
誰も思いつかないようなことを形にするんですから!
この能力って各々の独創性が大事になるし、誰ともかぶらない。
AIだって真似できない能力です!
って考えたら子どものやることなすこと全部にめっちゃワクワクしませんか?
超クリエイティブ!
子ども達の能力を見つけ出してあげるのも親の役目です!
苦手ばかりに注目するのは今日でいったん休憩しましょう。
私も息子たちの伸びしろを今日も目を凝らして探したいと思います♡
一緒に頑張りましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
