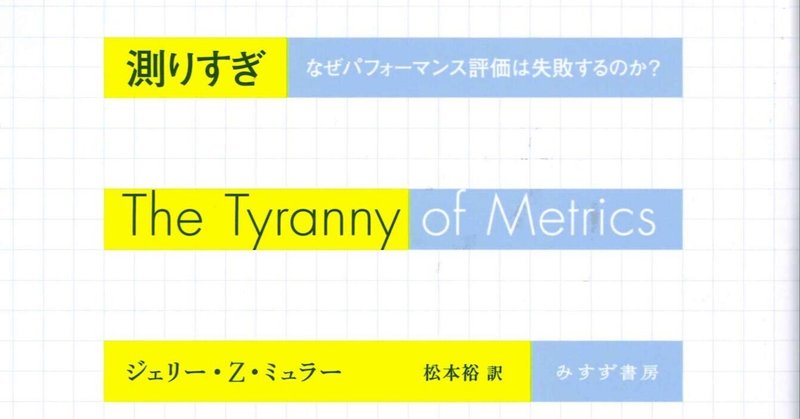
ジェリー・Z・ミュラー 『測りすぎ 一一なぜパフォーマンス評価は 失敗するのか?』 : 焦点化による 〈視野狭窄〉
書評:ジェリー・Z・ミュラー『測りすぎ 一一なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?』(みすず書房)
『なぜ現代においてこれほど多くの組織が本来果たすべき機能を果たせず、生産性を落として組織内で働く人々に不満を抱かせているのか、その大きな理由のひとつ』(P13〜14)が『数えられるものすべてが重要なわけではなく、重要なものすべてが数えられるわけではない』(P19)という事実を忘れた『測定執着』に、多くの人(特に経営者や管理者)が捕われてしまうからだ。
そのことを、具体例をしめして説得的に論じたのが、本書である。
『測定執着』の具体的な問題点や、それを避けるための留意点については、すでに他のレビュアーが本書の内容紹介をしているので、私はここで、ややもすると「数字の問題」だと思われがちな、この『測定執着』という誤謬の問題を、もうすこし一般的な文脈に移し、ちがった角度から紹介したいと思う。
どんな会社にでも「数値目標」というのはあるだろう。それ自体は、著者も繰り返しているとおり、決して悪いことではない。しかし、何でもかんでも「数値目標」にして掲げたら良いというものではない。なぜならば、各種の仕事の中には、「数値」に落とし込めない要素が、多分に含まれているからだ。
例えば、介護従事者は、介護した人(被介護者)の「人数」で、その労働実績を測るわけにはいかない。当然のことながら、介護の「質」の問題が大きいからだ。あるいは、よく話題にのぼる警察官の「交通違反取締り」なども同様で、単純に「取締り件数」が多ければ良いというものではない、というのは誰しも納得できるところだろう。やはり、ここにも「質」の問題が絡んでくるからである。
要は、「質」とか「満足度(という感情的評価)」というのは、相対的なものであり、簡単に「数字」には落とし込めないし、それでも数値表記されていたとすれば、それはいささか「信用ならないもの」であることが少なくないのである。
しかし、「数字」というのは、比較しやすく、その意味でわかりやすい。一見したところ「相対的」ではなく「客観的」「絶対的」に見えるから、人は「数字」をありがたがりがちなのだが、それはまさに「信仰」と同様、ありがたいけれど、いささかうさんくさいものである場合が少なくないのである。
「人間の意志や行為」というものは、基本的に「相対的」なものであって、「客観的」ではあり得ない。「客観的」に見えるのは、ある種の「限定的な物差し」を当てているからに過ぎない。
つまり、「物差し」の種類は、無限に存在するのだが、人は自分の「主観的」な基準で「物差し」を選び、それで測った「数値」を、それが「数値」であるがゆえに「客観的」だと「主観的に誤認してしまう」のである。
したがって、「数値化」というのは、すべて「焦点化」だと考えるべきなのだ。何が大切な要素で、何が(比較的)そうではない要素かを、測定者は主観的に決めた上で、その基準に合った「物差し」を持ってきて、対象を測定する。自分にとって大切だと思える(恣意的)要素を、測定対象の「本質」だと思い定めて、その「本質」だけを測れるように、その他の要素を「ノイズ」として排除するのである。これを私は「焦点化」と呼んでみた。
しかし、こうしたやり方が、所詮は「主観的」で「恣意的」なものでしかないというのは、誰にでもわかることであろう。
結果が「数値化」されているから、なんとなく、文句の付けどころのない「客観性という権威」を帯びて見えるけれども、その「数字」は、主観的選択でしかない「焦点化」によって、捏造されたものに過ぎないのだ。
しかしまた、それでも「数字」の魔力は、絶大だ。
よく言われるように「数字が、すべてを物語っているじゃないか」という上からの言葉に対し、「数字は、ごく一部のことしか物語ってはいない」と反論できる人は少ないだろうし、そう反論したところで、しばしば経営者や上司は、その言葉の意味を理解できるほどの知性を持ってはいないだろう。
したがって「数値化」という「暴力」に抗するのは、容易なことではない。
しかし、だからと言って「数値化の暴力」に黙って従うだけでは、私たちの人間としての大切な部分、数値化できない部分が、どんどんと切り捨てられていくことになるだろう。
だから私たちは「数値化」とは、本質的に「焦点化」に過ぎず、さらに言えば「切り捨て的単純化」にすぎないのだということをしっかり理解した上で、この「暴力」に抵抗していかなければならない。
「数値化」とは、「複雑な多様な現実」に向き合えない人間の「(能力的な)弱さ」が生んだ、一種の「方便」なのである。
私たちは、聖徳太子ではないので、あれもこれもいっぺんに聞いて、すべてに配慮することはできない。そのような「弱い存在」だからこそ、「数値化」という「焦点化」「単純化」に頼らざるを得ないという、残念な事実を深く銘記すべきなのだ。
そして、その「人間の弱さ故の、数値化という方便」という事実を忘れたとき、人は「視野狭窄」におちいって、非情な「単細胞」人間になってしまうのである。
書評:2020年3月2日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
・
・
