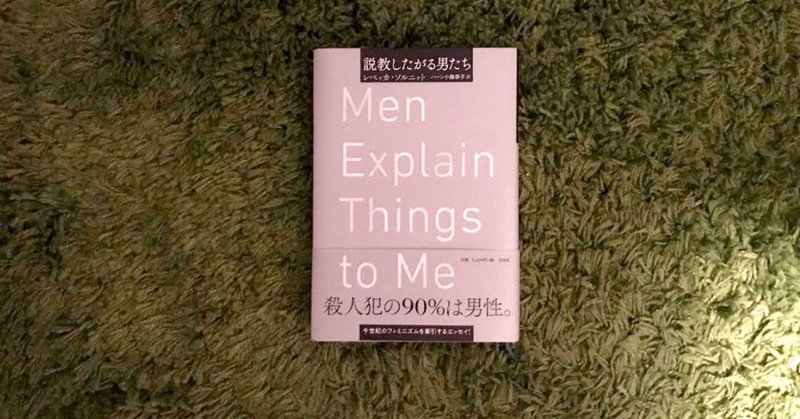
001 ブックレビュー 『説教したがる男たち』
体罰の問題、新潮45の問題、ちょっと前なら東京医科大の問題、、、。個人的には確固たる考えや思想を持てていない。そこはしっかりすべきだと思うんだけど、まずは、マイノリティやフェミニズムのことに対して無知なのが原因だと思っている。
そんな心の奥に引っかかった思いもあって、この本を読んでみた。リコメンドはせいこうさん。
恥ずかしながら今更「マンスプレイニング」という言葉を知った。2010年NYタイムズの「今年の言葉」に選出されている。
暴力を振るうメカニズムは、他者を自分がコントロールする。すなわち、あなたをコントロールする権利がある。といったような内容が、あちこちに散らばっている。マウンティング的な仕組みかな。
たくさんの事例が用いられているんだけど、決してファクトの分析だけでなく、なぜそうなるのか?なったのか?まで書かれているので読み応えはすごい。
IMFの専務理事ストロスカーンのメイドに対しての暴行事件が書かれている部分がある。彼の事件が本書のテーマにとって最もアイコン的なところでもあるんだけど、IMF自体への分析もしていて、とても勉強になった。
結論的には自由貿易のイデオロギーを反映しすぎた組織に変貌し弊害が起きているという内容なんだけど、ここでの補足としてクリントン元大統領の謝罪コメントが引用されていて、これは何かすごい納得できた。
と同時に世界の流れがもう「富める国が貧しい国に何かを与える政策」の限界を認め。そういった構造の経済は持続性がないということがスタンダードになってきているんだな〜とも感じた。昨今のサステイナブルな経済の概念でもある「サーキュラーエコノミー」との合点もいった。
そのほかにも、アナ・フェルナンデスの絵画やカサンドラの物語、ヴァージニア・ウルフという作家の話など、美術や文学からも女性軽視、レイプ、暴力などなどを紐解いていて重厚な内容だった。もちろん、僕は教養に乏しいので、ここに名前を挙げた人は今まで知らなかった。
緻密なリサーチがされているので、暴行、レイプ、DVなどの事件の判例から事件の詳細まで、しっかり書かれている。犯罪率や暴力の原因といった統計も網羅されている。そこへきて、彼女の体験といったドキュメンタリー、美術や文学からのアカデミックな見地、政治・経済の時事ネタも盛り込んでいてすごい執筆力だと思った。
メディアとして目を向けると、この本の内容がWEB記事やSNSいったところでまずは発信されているところが面白い。書籍になるには時間もかかるし、超保守派からの意見などもキャッチアップしにくいだろうし、、、なんか新しい書き手の傾向だとも思った。
最後に引用を、、、
「私たちはまだまだ解放されていない。競争と無慈悲さと短絡的な思想と社会・経済的個人主義を賛美するシステムから。」
「自信過剰と無知」が、どれだけ愚かなことを気づかされた1冊でした。ってか、タイトルがいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
