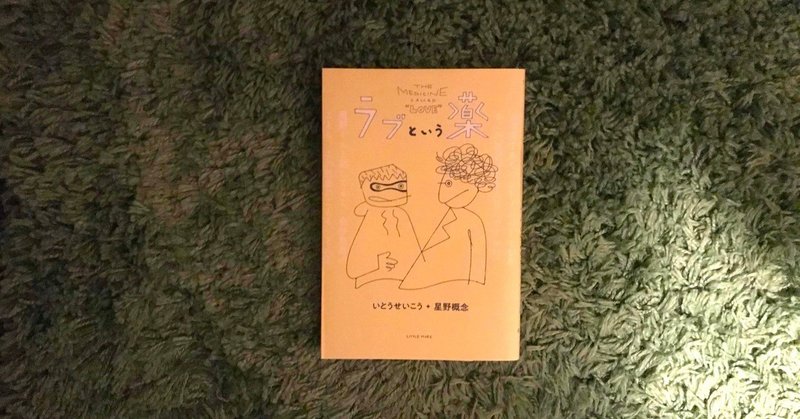
002 ブックレビュー 『ラブという薬』
タイトル通りの影響を受けた本だった。さすがいとうせいこうさん。この本を作るとき、タイトルが先に浮かんだそうだ。
実際にカウセリングへ行った人から教えてもらった本なんだけど。この星野さんがロロロのライブサポートメンバーだったとは知らなかった。
星野さんは、非薬物療法を重視した心理療法の精神科医。ブルータスとかYahoo!でも連載しているから知ってる人も多いかと。いとうせいこうさんがカウセリングしてもらっている先生で、2人の対談形式でサクッと読めた。仕事しながらでも2日あれば読める感じ。対談は口語調だから読みやすい。
フロイトの「錯誤行為」「超自我」「死の欲動」などといった心理学の話は出てくるんだけど、基本的にはせいこうさんの話を星野さんが約分していく流れなので敷居は高くない。
精神科医とか臨床心理士の違いや総合病院と個人経営クリニックの特徴、外因性や内因性や心因性の違いなどなど、大枠の知識は得られた。精神科のある病院って「12モンキーズ」とか「カッコウの巣の上で」とか最近だと「アンセイン」みたいな映画の印象しかなかったので、なんかグーっと身近に感じることもできた。
この本のテーマは「対話」。本当にその人の立場になって考えられるか?みたいなところを軸に話が展開されている。こういうことって学校でも学ぶチャンスあるはずだけどちゃんと教わったことがないよね〜みたいなやりとりは印象的だった。
他にも「傾聴」や「共感」というワードもよく出てくる。僕は人間が成長していくには「傾聴」がとても大事だと考えている。この2人はコミニケーションという文脈で傾聴を語っていただけど角度は違うけど着眼点で同じで嬉しかった。傾聴のポイントとして、都合の良い思考、すなわち自動思考になりがちな人には、「ソクラテス式質問」を意図的に行って、その人の考えや心に寄っていくという話はかなり勉強になった。
出てきた回答に対して質問をどんどん重ねて質問していく「ソクラテス式質問」を面接なので使っていた気もするけど、無意識でやっていたので、今後は意識してみたいなと。
あと、僕の解釈とアレンジは入りますが、義務感に翻弄されている人や具体化できないと何もできない人って「物事の背景を考えてみる」というプロセスが抜けている!というような内容もあって、これは激しく同意でした。まさにその通りだと、、、。
2人の話は、後半部分の社会や文化について話すところも面白い。トランプとオバマ。いずれの時も虐げられるまではいかないが、日陰になる人がいるという話。多様性だといっても、それは起こりうる話。とても腹落ちした。あとは、ホリエモンが出てきて日本の社会の潮目が変わった。お金が最強の価値、儲かるならいいけどお金にならないなら人助けなんてしなくていい!と平気で言う人が増えた!と言うせいこうさんの考察はごもっともだし共感した。
これはモンスタークレーマーと同じ発想。「自分は損をしたくない」
「相手が悪ければ何を言ってもいい」みたいな感じ、、、損をやたらと嫌う社会。もっと無駄なことや損をしておこうと思った。
ちょうど、この本を読む前に、お酒の席で「マズローの五段階説を軸にインフルエンサーの話」をしてたので、今回の本はハマった〜。SNSと承認欲求の関係。依存から抜けることが悟りで釈迦になる。でも困難だから依存Aから抜けて依存Bに行くの繰り返し。
結局、僕らはこれの繰り返しなんですね。
認知行動療法で大事なのは人間の「感情と考え」は別ということらしい。これは初耳だったんだけど、「考え」という部分を可視化できないと感情も行動もともわないFacebookの反応でいうといいね!は感情、うまいね!は考え。うまいね!ボタンを作って欲しい!
という星野さんの話はインパクトあった。確かに感情でしかレスができない。
あ〜もっと、面白い話があってアンダーラインめっちゃしてるんですがまとまりきらないんで、この辺で終わります。リトリモアっぽいおしゃれな感じで、今回も良い本に出会えた〜。全く、うまくまとまらない乱文でした!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
