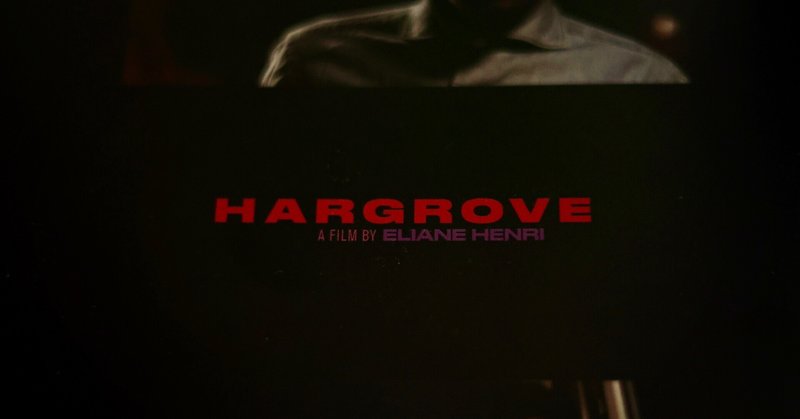
ジャズをつなぐ理由|Roy Hargroveのドキュメンタリー映画『人生最期の音楽の旅』
2010年代のジャズヒーローといえば、ロイ・ハーグローヴ。2018年に急逝した氏はマイルス・デイヴィスがもたらした革新をロバート・グラスパーにつないでいます。日本でも上演が始まったドキュメンタリー映画を観てみれば、ジャズをつなぎ続けなければいけない理由が見えてくると思うのです。
2018年に49歳の若さでこの世を去ったトランペット奏者、ロイ・ハーグローヴ(Roy Hargrove)。長年の友人でもあったエリアン・アンリ(Eliane Henri)が撮影したドキュメンタリー映画が、いよいよ日本でも公開された。結果的に最後となってしまったツアー中のハーグローヴを追った作品は、氏の才能と苦悩を、美しくも儚く描き出している。イタリアの町を歩くシーン。足を引きずる様子からは、晩年の病状の悪化が見て取れる。それでもステージに立てば、笑ってしまうほどの軽快なグルーヴを聴かせてくれるから恐ろしいものだ。巨匠ソニー・ロリンズ(Sonny Rollins)がインタビューで語るように、アーティストにとってのこの世界は、本来のものではないのかも知れない。複雑なハーモニーの構成音一つひとつを聴き取ることができたというハーグローヴは、誰よりも高い解像度で音楽の世界を観ていたに違いない。ジャズに特有な言葉を演奏に置き換えて、オーディエンスの心に届けることに優れていたと称賛したのは、トロンボーン奏者のフランク・レイシー(Frank Lacy)だっただろうか。他にも、クエストラヴ(Questlove)やハービー・ハンコック(Herbie Hancock)など、生前に親交の深かったアーティストへのインタビューを中心にストーリーは展開していく。
しかし登場するアーティストは皆、カラード(colored)だ。ジャズをヒップホップと混ぜ合わせ、広くブラックミュージックに昇華させたハーグローヴの周りには同志が集う。唯一の白人がマネージャーのラリー・クロジアー(Larry Clothier)であって、ここでは氏の才能を搾取する典型的な支配者として描かれている。映画を盛り立てるために、自らヒールを買って出たのではと思わせるほどの戦略家は実際のところ、ハーグローヴを誰よりも売れっ子に育て上げた。2010年以降、私たちが毎年のように日本でハーグローヴのステージを観ることができたのも、クロジアーのおかげだろう。白人が作り上げた今の社会システムの中で、ジャズミュージシャンが成功を収めるためには、これが正しい選択だったと信じるしかない。自分たちの文化と尊厳をどう守っていくべきなのか。アンリ監督の悩みは、ハーグローヴがキューバに渡ってまでラテン音楽に打ち込み、ラテン・グラミー賞の受賞が噂されるもヒスパニックではない(スペイン語すら話せない)ことから、批判の声が上がったというエピソードを挟み込んだことにも表れている。

世界中の音楽はつながっている。先日、ビルボードライブ東京ではUKジャズの牽引者シャバカ・ハッチングス(Shabaka Hutchings)が自身のバンドを引き連れて、公演を行なった。USから遠く離れて独自の展開を見せるイギリスのジャズだけれど、ブラックミュージックとしての本質は変わらない。自らの音楽を、自らの手に取り戻そうとする。キューバと同じくカリブ海に面する中南米・バルバドスにルーツを持つハッチングスは、レゲエやラテンのリズムを巧みに操って、私たちをスピリチュアルな世界へ誘おうとする。それは始まりの地であるアフリカまでをも振り返らせるもので、実際、このバンドは南アフリカのミュージシャンたちで構成されている。かつての植民地同士のつながりが、新たな居場所を探ろうとしているのだ。そこが音楽だけの世界であってはならない。精神世界や、宇宙という哲学的な場であってもならない。これを認めてしまっては、アフロフューチャリズムの始祖サン・ラ(Sun Ra)の頃から何も変わらないではないか。それはすなわちビバップまで遡っても変わっていないことを意味する。その熱量の高さからジョン・コルトレーン(John Coltrane)に例えられることも多いシャバカ・ハッチングスは、まさかの今年いっぱいでテナーサックスを置くという。
ロイ・ハーグローヴはジャズミュージシャンとして、スタンダードナンバーを好んで演奏した。その理由の一つに詩の美しさがあったのだと、映画を観て気付かされる。窓辺に座ってインタビューを受けるハーグローヴはいくつかのスタンダードを口づさみながら、歌詞を覚えることの大切さを語った。そうすることによって、正しいメロディが分かるという。Qティップ(Q-Tip)やエリカ・バドゥ(Erykah Badu)との共作で「Poetry」という名曲も残している氏がヒップホップを引き合いに出したのは、攻撃的で汚い言葉ばかりが蔓延する社会への批判なのだろう。決して雄弁とは言えない語り口で、若手ミュージシャンたちを諭している。ライブの後も毎晩のようにギグに参加し、朝まで後進育成にあたったというハーグローヴは、そうやって自分たちの音楽を次につないでいきたいと思っていたに違いない。そして、いち早くこの現実世界が安住の地になることを願っていたに違いない。目を閉じたまま話すハーグローヴの姿が印象に残る。氏の人生最期の音楽の旅は、私たちに受け継がれたように思うのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
