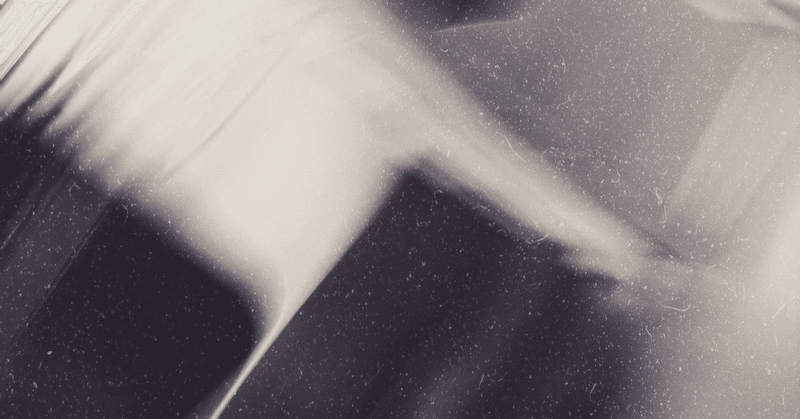
『進化』(掌編小説/ホラー)
まさか遭遇するとは思わなかった。
東京には独自の進化をした人類が一定数いるという噂が、先月SNSで話題になっていた。ネットにありがちな誰かがでっちあげた都市伝説の類かと思って真剣に取り合わなかったのだが、いま目の前に「彼ら」がいる。
たまたま私は東京に来ていた。本社での会議が長引いて、ぎりぎりで駆け込んだ終電の地下鉄で遭遇したのだ。
彼らの首は前方に90度曲がっている。胴体から首が直角に生えているような感じで常に下を向いているため、顔は見えない。彼らは一様にスマートフォンの画面をタップしたりフリックしたりと指先の動きが忙しい。睡眠以外のほぼ全ての時間をスマートフォンに充てる彼らは、その日常生活に適した進化を遂げたという。
都市伝説は本当だったのかと驚きつつ、冷静になろうと、鞄からお茶のペットボトルを取り出して喉を潤す。その時、背中にドンと何かが当たった。
誰かが自分と同じように出発寸前の終電に駆け込んできたようだった。その衝撃で、飲んでいたお茶が飛び出して、ジャケットとシャツが濡れてしまった。振り返ると、黒髪の後頭部が目の前にあった。若い女性のようだった。
「すみません! ぎりぎりだったので・・・はあ、はあ、はあ」
軽く会釈してから女性の姿をよく見ると、彼女も「彼ら」の一人だった。私に謝って頭を下げているのだが、長い髪が紐暖簾みたいに地面に向かって釣り下がっていて、顔は全く見えない。見えているのは後頭部だけだった。私はあのホラー映画を思い出した。
「あの・・・、お茶こぼしてしまったみたいで」
彼女は申し訳なさそうにハンカチを差し出した。その声質と話し方にはどこか品があって、私好みだった。
「いえいえ。僕もギリギリで駆け込んだ立場なので、気にしないでください」
そのまま、私たちは帰りの方面が同じだったこともあって、電車内でずっと身の上話をしていた。
「私、電車内でスマホを見ずに過ごしたの初めてかもしれません」
「ほんとですか」
「はい。移動中はもちろん、いつでもどこでもスマホやタブレットなどのデバイスを見ています。ものごころついた時から枕の横には子育てタブレットがあって。家族との会話はスマホやタブレットがほとんどでした」
「え、家族の顔を直接見てないってこと?」
「はい。画面越しでしか見たことがありません。成長とともに、私の首は少しずつ前のめりになって、中学生の時点で40度、高校生の時点で70度、成人した時には90度にまでなりました」
「へえ・・・そうだったんですね」
「そんなふうに育ったこともあって、デバイスは体の器官の一部のようなものです。いわゆるスーパーデジタルネイティブなので、スマホやPCなどのノウハウやスキルを活かせる仕事に就きました。たぶん、この車両に乗っている“下向きの人たち”は同じ企業に勤めている人だと思います。彼らも私と似たような境遇で育ったんだと思います」
「・・・正直言うと、あの、失礼かもしれないですが、ネットの都市伝説だと思っていました」
「あの噂を流したのも、うちの会社の人間です。意図的なものなんです」
「意図的なもの? 」
「少しずつ世の中に私たちの存在を浸透させていくプロジェクトです。今はまだフェーズ1です」
「へえ・・・」
「今日は画面の中ではない人とこうして話せて幸せです。みんなこの姿が怖いのか近づいてこないんです」
「あの、一つ気になることがあるんですが、聞いてもいいですか? 」
「はい、何でしょう」
「なぜ電車で通勤されているんですか? 全てのことをオンラインでやってそうなイメージなのですが」
「会社に行っても誰とも会話しません。先ほども言いましたが、私たちがわざわざ通勤するのは、少しずつ世の中に私たちの存在を浸透させていくプロジェクトの一環です」
想像以上に彼女はよく喋った。いや喋りたかったのかもしれない。
「あの、これも何かの縁というか、せっかくこうやって話もできたし、お顔をちらっと見せてもらえないですか?」
「・・・」
彼女はしばらく黙っていた。声質から想像するに彼女はきっと美しい顔立ちをしているに違いないと思った私は、勢いで言ってしまった。初対面で踏み込みすぎた自分に少し反省した。
「あ、初対面で失ですよね。やっぱりいいです。ごめんなさい」
「いえ、大丈夫です。見せるほどのものではありませんが。ふふふ」
「いいんですか」
「下から」
「えっ」
「下から覗き込んでもらっていいですか?」
「あ、僕が屈んで下から見上げるってことですね」
「はい・・・」
彼女はこちら側に体を向けた。
「では失礼します」
「どうぞ」
僕はゆっくりと頭を下げて筒状になった髪の毛の中をのぞきこんだ。薄暗くてはっきり見えない中、目をこらすと、鼻も口もない顔の真ん中に、血ばしった巨大な目があって私をじっと見下ろしていた。
(了)
読んでもらえるだけで幸せ。スキしてくれたらもっと幸せ。
