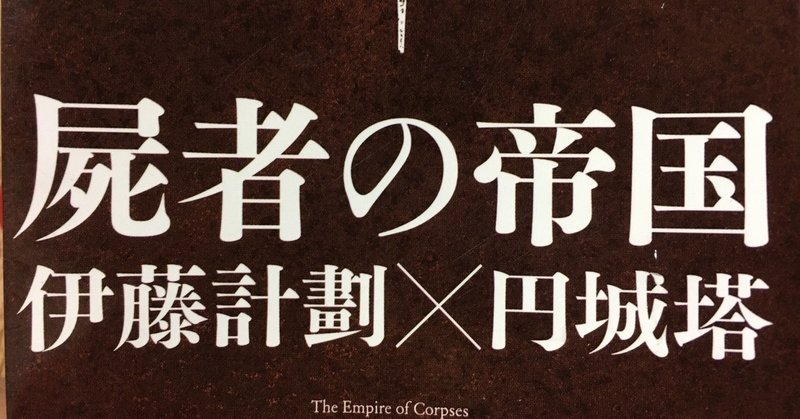
屍者の帝国/伊藤計劃×円城塔
死んだ人間の身体を再利用しそれなりの仕事はできるよう、疑似霊素をインストールする。
100年前、18世紀の終わりまで、人間の肉体は死んだら黙示録の日まで甦る事はないとされていた。しかしいまは、そうではない。死後も死者は色々と忙しい。
と、ジョン・H・ワトソンが語る19世期末のロンドンで、物語ははじまる。
ロンドン大学で医学を学ぶワトソンは、卒業を間近にしたある日、屍体に疑似霊素がインストールされ、動く死者になる瞬間をはじめて目にすることになる。
その施術を行なったのは、ワトソンの指導教官であるジャック・セワードと、その恩師であるエイブラハム・ヴァン・ヘルシング。
死者が甦る瞬間に立ち会った後、ワトソンは、ヘルシング教授とセワード教授の2人に連れられて、多くの屍体たちが乗合馬車の御者として働くロンドンの街を生者が御者の馬車に乗って移動し、モンタギュー街で探偵をしている弟のいるMという男に会い、アフガニスタンでの仕事を請け負うことになる。
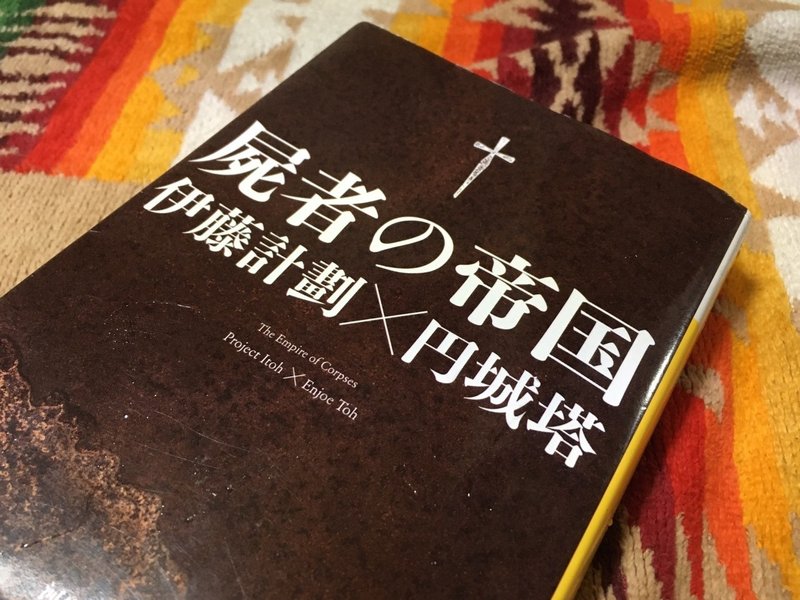
これがこの小説を企画した伊藤計劃が記した「プロローグ」の概略だ。
しかし『虐殺器官』『ハーモニー』に続く3作目として、この『屍者の帝国』を企図した伊藤計劃はそのプロローグ部と企画用のプロットだけを残して、2009年3月に亡くなった。
その後、この500ページを超える大作を完成させたのは、疑似霊素をインストールされた死者ではなく、円城塔である。
昨年『エピローグ』を読んで以来、僕は円城さんの小説のファンだ。
そして、『虐殺器官』も『ハーモニー』も面白く読んだので、いつかこの作品も読もうと思っていた。
そして、読みはじめると面白く一気に読んだ。
19世期末世界の著名人たち
冒頭紹介したプロローグの一部を読んで、すでに気づいた人も多いだろう。
この小説の主人公は、あのワトソンだ。兄にMという人物をもち、モンタギュー街で探偵をする、あの有名な探偵の友人であり、相棒であるワトソンだ。
2人がベイカー街221Bで共同生活をはじめるのは1881年の1月のことだが、この小説は1878年からの1年半ほどを描いている。
そして、そのワトソンに屍体への疑似霊素のインストールの瞬間を見せ、ワトソンを長い旅となる物語の入り口に案内するのは、この物語の20年前、トランシルヴァニアであの有名な吸血鬼退治をしたとされるヴァン・ヘルシングとセワードの師弟だ。
それだけではない、このワトソンの物語には、19世期末の小説世界の登場人物がほかにも登場する。
アフガニスタンでは、ロシアから来たあの兄弟の3男のアレクセイ・フョードロヴィチ・カラマーゾフと、彼の知人でもあるニコライ・クラソートキン、そして、アレクセイの兄でもあるドミートリイ・フョードロヴィチ・カラマーゾフも会話の中で登場する。
それとアメリカ人で南北戦争(1861年-1865年)で南軍についた富豪のレット・バトラーと、ハダリーというどこか機械的な美女。
そして、フランケンシュタイン博士とその創造物。
こうした小説の登場人物たちだけでなく、本当に19世期を生きた著名人も登場して、小説の主人公たちと共に、物語の時間を過ごす。
インド総督でアフガン戦争を通じてアフガニスタンをイギリスの保護国としたロバート・ブルワー=リットン、全人類の物理的不死及び復活などの思想をもつロシア宇宙主義の草分けである思想家のニコライ・フョードロフ、日本の電気通信の父ともいわれる政治家の寺島宗則、加算器の発明家でコンピュータ企業バロースの創始者で、小説家のウィリアム・バロウズの祖父でもある同名のウィリアム・シュワード・バロウズ、南北戦争時の北軍の将軍で、第18代アメリカ大統領ユリシーズ・グラントなどがそうだ。
この顔ぶれ。あとで詳しく書くが、断片化した世界をもたらした技術を軸に、政治や経済をハンドリングした人々が並ぶ。
現実の歴史上の人物と複数の異なる小説内のそれぞれ本来重なることのない複数の創作世界の人物たちが入り混じった、パラレルワールドの交差点のような作品だ。
そうした虚実入り混じった19世期の著名人たちが、さらに労働力として、兵器として、自動筆記具兼情報記録および検査ツールとして、動く死者たちが活用される世界で繰り広げられる物語が、それが、この『屍者の帝国』という小説だ。
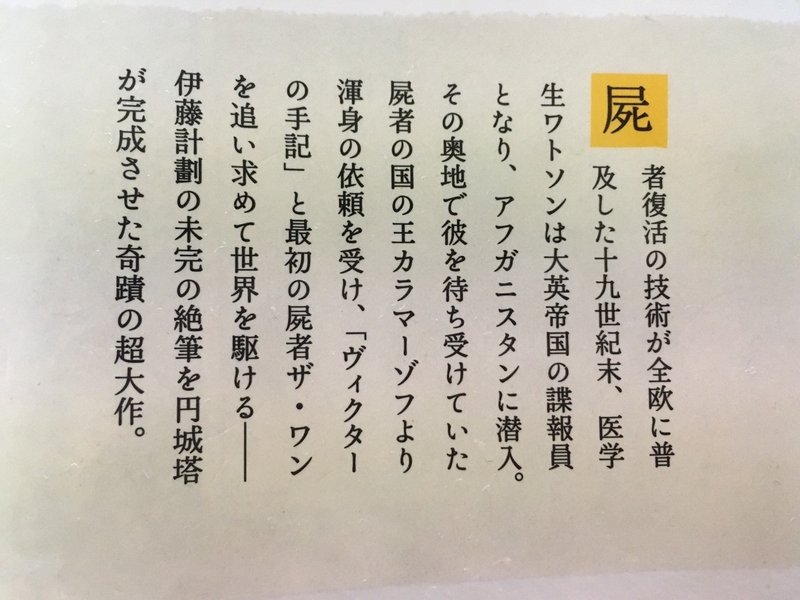
断片化の時代としての19世紀末
19世紀末という設定自体も、僕の萌えポイントだった。
高山宏は、その時代に誕生した推理小説を扱った『殺す・集める・読む』のなかで、19世紀末という時代をこう論じている。
その作者たちが生を享けた19世紀末は猛烈な断片化の時代だった、と言っておけばひとまずは答になるだろう。まさに炯眼のジョージ・ニューンズの言った「断片(ティット・ビッツ)」の時代。その断片を「データ」として引き受け、それに「意味」を与え、もってふにゃふにゃと不定形の世界に〈解決〉と〈形〉とを与えようとした動き、それがたとえばジャンルとしての「推理小説」の〈発明〉をうんだのである。
先にもすこし頭出ししたが、「断片化」はとうぜん、この小説内でも1つの鍵だ。
通信技術でネットワーク化が進み始めた世界で、ワトソンが旅するインド、アフガニスタン、日本、アメリカは、通信技術でつながっていつつも、物理的には断片化している。
つながると同時に断片化した世界で、争いはより断片化した2点間以上のあいだの指令のやりとりがスムーズに行えるものと、断片化していて他の断片との通信速度が遅すぎるがゆえにほとんどスタンドアロン化したものとでは、圧倒的な優劣が決まる。
残念ながら、この小説においてワトソンはかなり分がわるい。
鉄道網も海上の交通も、駅間や港間のあいだの場所をなきものにしたという点では、断片化を促進したものといえる。
情報も、ストーリーも、連続的には進まなくなっている。とぎれとぎれでそのままでは意味がわからない情報をひとびとは自分自身でつなぐあわせることで隠れた意味を読み解く。
それが推理小説につながるのは当然だ。
疑似霊素をインストールされ、動きを取り戻す死者たちの動きにしても、スムーズさを欠いたぎくしゃくなものとして、断片化している。生者と死者を分け隔てるのは、その連続性と断片性だ。
前者の意味は一見明白だが、後者の意味は断片化しているがゆえに謎めいている。果たして本当にそうか?という疑問はこの小説における1つのテーマでもある。
そんな死者たちが世界中の都市で仕事を得て、蠢いているのは、通信技術や萌芽のみられる情報処理技術&計算・解析技術により増大した情報の断片が世界中にあふれかえっているのと同じなのだろう。
同じように死がそこにある都市を描いても、この小説が描く世界の様相は、1つ前で紹介したジュネの世界とはあまりに違いすぎる。それは屍体があまりに情報と重ね合わせられているからだろう。その意味では、この小説のほうがよほど二元論的な見方に囚われているのだろう。
情報や病原菌を載せるメディア
もうひとり、19世紀の推理小説を「室内空間」という観点から論じた柏木博も紹介しておこう。
まるで「質屋」のようにものを集めた過剰なブルジョワジーの室内。それは、19世紀、あるいはヴィクトリア朝時代の室内にみられる傾向であった。それは自らの痕跡や記憶を室内につなぎ止めておくためである。
『推理小説の室内』という本からの抜粋だが、19世紀のイギリス、ヴィクトリア朝の時代に室内崇拝が高まった理由として、柏木さんはコレラなどの大流行も手伝って、外が嫌われたことをあげている。
産業革命により都市部の人口が急激に増加したことで衛生面が極度に悪化したことと、交通網の発達で人の移動が容易に、活発になったことで、病原菌もまた感染経路が拡大したことによる。
実際、この小説内でワトソンもまたコレラに罹患する。日本において、屍体を媒介にして。
自分自身は死んでいるがゆえに罹患することなく、生者に病原菌を媒介するメディアとしての屍体。
その役割は、ワトソンの旅に連れそって、彼が行なったことを記録し続けたり、さまざまな情報をアーカイブしてくれる、フライデーと呼ばれる動く死者の役割と実は変わらない。
情報を載せるメディア、病原菌を載せるメディア。屍体はそのメディアとしての役割を鮮明にみせるが、果たして、それは生者との違いと言えるか? いや、情報を載せ、病原菌をはじめとする微生物たちを大量に身体にたくわえ、それらと共存し、それらなしでは生きられない点では生者も何も変わらない。
意識とは何か? それは人間特有のものなのか?
では、情報を載せ、微生物を載せるメディアとしての生物として、人間は他の生物と違うのか?
そこに、チャールズ・ダーウィンが登場する理由がある。
進化論自体は、チャールズの祖父のエラズマスが科学の世界に持ち込んだものと言われている。エラズマスはこの小説の舞台である19世期の後半よりも前、18世紀の末から19世期の初頭にかけて生きた人物で、医師であり、自然哲学者であり、詩人であった。
エラズマス・ダーウィンも、花や植物を人間の男女に変えるという、オウィディウス風の擬人法を用いた。この意味では、近代植物学の父たちはより古い伝統の至近にいて、新時代の先駆者であると同時に旧時代の人でもあった。
と、書くのは、『女性を弄ぶ博物学』のロンダ・シービンガーだが、こうした詩的想像力がエラズマスのなかでは生物進化という科学的な探求と容易に結びついた。
そんな人物だったからこそだろう。エラズマスは、蒸気機関の発明家であるジェームス・ワットや、あの有名な陶芸品メーカーの創始者であるジョサイア・ウェッジウッド、酸素の発見者として知られる化学者のジョゼフ・プリーストリーらなど、錚々たる自然哲学者、起業家や経営者、発明家、化学者、作家などか集うルナ・ソサエティというコミュティをつくり、18世紀後半から19世期初頭にかけてのイギリスの産業革命の推進のひとつの原動力となった。
そうした社会的な流れのなかで進化論という仮説は構造されたのだ。
科学的な思考においても、現実の社会においても、断片化された情報が膨大に生み出され、それを載せる乗り物が必要とされるなかで、人間はその最有力の手段として活用されたが、それはすでにずーっと昔から微生物たちが自分たちの乗り物として人間、いや、その他もろもろの生物を利用し、共生してきたことの拡張だと言える。
さらに言えば、人間に情報が載ったのも、言葉という、意識という微生物と変わらぬ断片が載ったのも、産業革命などがはじまる、はるか前、人間が言葉というもの、道具というものを使いはじめたときからだ。
そういう観点から、この小説では、人間の屍体だけが、動く死者として活用可能なのは何故か?と問われる。
疑似霊素が人間の屍体だけにインストール可能なのは、人間だけがもともと生前に霊をもっているからで、もとより生きていてなお霊をもたない人間以外の動物には疑似霊素はインストールしようがないと語られたりもするが、果たして人間だけがそんなに特別なのか、そうだとして、それは何故なのか?を問うものが、この小説には登場する。
500ページという決して短くはない作品だが、それほど時間をかけずに読めたのは、そうした歴史的にも、科学的にも面白い仕掛けが無数に散りばめられているからだろう。
おすすめの一冊だ。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
