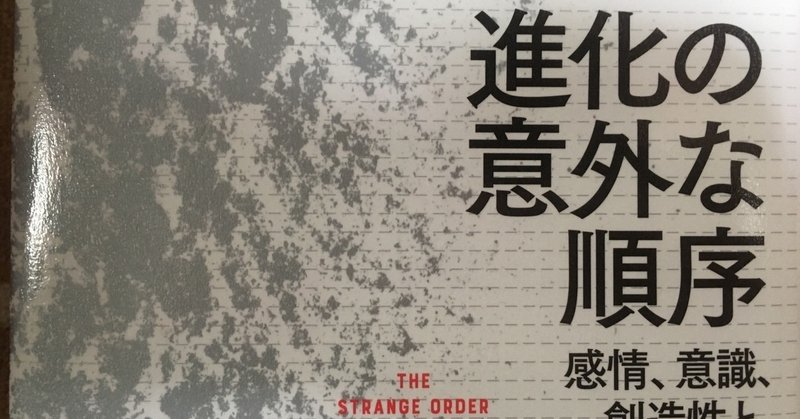
進化の意外な順序/アントニオ・ダマシオ
今年は僕の読書的には当たり年だ。
このアントニオ・ダマシオの『進化の意外な順序』も当たりだった。
人間の意識というものを、冷たい電気のパルスのようなものに還元してしまわずに、生物が蠢きながら行う化学的なやりとりとも切ってはきれないものであることを暴くことで、哲学的な二元論の伝統を破壊するという、きわめて僕好みな内容だったからだ。

その意味で、内容は、タイトルである「進化の意外な順序」よりも副題である「感情、意識、創造性と文化の起源」のほうがそれを表している。
感情や意識や創造性に文化と並んでしまうと人間にフォーカスが当たっているように思えるが、そうではない。「起源」とあるように、感情や意識がどこから来たかという問いに対する回答が、細菌や社会性昆虫などの地点から語られる。
「意外な順序」といわれるのは、文化的な社会につながりそうな利他的な活動の選択が、心を持たないはずの単純な動物にも「協調」「共生」的な行動がしくみとしてプログラムされている様子が見られるからだ。
そのカギとなるものとしてダマシオが想定するのが、生体の調子を良好な状態に保とうとする機能としてのホメオスタシス。
まずは、このあたりからすこし本の概要と僕がそれをなぜ面白いと感じたのかを紹介していきたい。
心なき細菌たちの行う協調
ホメオスタシスが生物が感情や意識、果ては文化を生みだす創造性を獲得していくカギとして、この本では位置づけられる。
たとえば、ダマシオは、そのことを以下のような形で表現したりもしている。
ホメオスタシスの規則は、協力のプロセスの背後に存在し、「総合的なシステム」の出現にも大きな役割を果たすなど、多細胞生物の進化の歴史を通じて至るところで作用していた。そのような「全身体システム」なくしては、多細胞生物の複雑な構造や機能は出現しえなかっただろう。
複数の個体同士の協力のプロセスが背後にあって、ホメオスタシスは機能する。
ダマシオが着目するのはその点である。
細菌のような、単細胞で、とうぜん心や神経系ももたない原初的な生物でさえ、敵から身を守って生きながらえるために仲間と協調して動く機能があるという。
その際、「仲間」かどうかを判断するのに、彼らはたとえ遺伝的なつながりがある近親者であっても、「集団のなかに「裏切り者」が見つかると、つまり防御を手伝おうとしない個体がいると」、「その個体を遠ざける」のだという。「細菌は、近縁であっても集団的な営為に協力せず自分の役割を果たさない個体とは協力し合おうとしない。つまり、非協力的な変節者を冷たく扱うのだ」と。
もちろん、細菌は心をもたない。知性もないし、感情もない。
それでも、彼らは集団の利益になる行動を選択しようとしない「裏切り者」を集団から遠ざけ、集団全体の利益を優先しようという選択を行う。
「細菌は、たとえその知性が感情や意図や主観を備えた心に導かれているわけではないとしても、非常に知的な生物だと見なせる」とダマシオが言うのは、こうしたある種自動的ともいえるホメオスタシスの機能が備わっているからだ。
協調のカギとしてのホメオスタシス
「「ホメオスタシス」という用語は一般に、主観や熟慮なしに自動的に作用する非意識的な形態での生理コントロールを意味する」とダマシオはいう。
非意識的であるから、心の有無はホメオスタシスが働くかどうかには関係ない。だから、心をもたない細菌の集団も役に立たない裏切り者を切り捨てることで、集団の状態を良好なものに保つことができる。
もちろん、ホメオスタシスの機能は、細菌の集団に見られるものではない。
むしろ、多細胞生物においては、より複雑な形でホメオスタシスが機能しえる。
ほとんどの生物は、エネルギー源が枯渇したとき、意思の介入なしに食物や水を探すことができる。また周囲に食物や水が存在しなくても、たいていの生物はその事態に自動的に対処することができる。蓄えられていた糖分がホルモンによって自動的に分解され、当面のエネルギー源の欠乏を埋め合わせるために血流を通じて分配される。
ホメオスタシス、それはほとんどの生物に備わっている「何があっても生存し未来に向かおうとする」ために生物が自動的に行う「連携しながら作用するもろもろのプロセスの集合」なのだ、とダマシオはいう。
その心を介さない自動的な複数プロセスの集合の起源に、細菌の集団内で行われる化学物質のやりとりによる集団の生命維持行動を、彼はみている。
ホメオスタシスの規則は、協力のプロセスの背後に存在し、「総合的なシステム」の出現にも大きな役割を果たすなど、多細胞生物の進化の歴史を通じて至るところで作用していた。そのような「全身体システム」なくしては、多細胞生物の複雑な構造や機能は出現しえなかっただろう。
そう、それは多細胞の生物の体内における膨大な量の細胞同士が協調して、生物そのものを動かすことを可能にするための基本的な機能なのだ。
多細胞生物の体内の機能が動くためにも、生物そのものが体外的な意味で移動するという意味でも、細胞同士の協調が前提としてなければ、多細胞生物などはそもそも成り立たない。
ダマシオはその起源にホメオスタシスを可能にするための協調をみているのだ。
異種間の細胞同士の化学的なやりとり
生物同士の協調ということで思い当たるのは、進化生物学者のリン・マーギュリスが40年以上前に提案したホロビオントという異なる生物同士の共生関係だ。
たとえば、人間も、牛も腸内にたくさんの細菌を生息させているが、その細胞の数はいずれも本体である人間や牛自体の細胞の数よりはるかに多いとされる。
人間の場合であれば体内に居候する細菌の細胞は人間自身の細胞の10倍だと言われている(ただし腸内だけでなく身体全体に居候している細胞の数)。
それらの細菌はただ腸内に居候しているだけでなく、腸内での消化や栄養吸収を助けている。
牛の場合であれば、彼らは草食動物であるにもかかわらず、彼ら自身の腸には植物繊維を分解する機能はなく、その機能を担うのは居候である腸内細菌なのだ。
つまり、細菌なしでは牛は生きていけない。
それは人間も同様だ。
マーギュリスのいうホロビオントという共生の単位は、そうした牛と細菌、人間と細菌のハイブリッドな状態を指す。
化学的なやりとりと神経活動の連携
とうぜん、牛と細菌、人間と細菌のあいだに、いわゆる神経系を介したやりとりなどはない。哺乳類と細菌は神経でつなかってなどいないからだ。
そのやりとりはもっぱら、化学的な物質を介した「心なきコミュニーケーション」である。
それは細菌同士のコミュニケーションと同じ種類の方法である。
共生しているとはいえ、人間と細菌のあいだの関係が言葉やイメージを介さない自動的なものであるのは、まさにその神経系を介さない点に由来する。
逆に言えば、人間本体の細胞の細胞同士はもちろん化学的な物質を介したやりとりも行なっているが、それと同時に神経系のネットワークを介したコミュニケーションも行なっている。
そして、そうであるがゆえに、哺乳類は心的な面でも統合されているのであり、みずからの意思により好きな方向に身体を移動させたりという複雑な行動をとることができるのだ。
それが哺乳類に限らず、神経系を手に入れた多細胞生物が、化学的な物質のやりとりでしかホメオスタシスの機能を実行できない生物との違いである。
そして、それらの生物は神経系による情報のやりとりを手に入れることで、感情を手に入れ、イメージを手に入れ、意識や記憶を手にし、そして、それらを用いた創造的な思考力を手にする。
想像力をはばたかせて、単に形状や空間内の位置だけでなく、音(穏やかなもの、耳障りなもの、騒々しいもの、かすかなもの、近くから聞こえてくるもの、遠くから聞こえてくるものなど)のマップや、触覚、嗅覚、味覚に由来するマップを考えてみよう。さらに、生体内の「事象」、すなわち内臓やその作用を下に構築されたマップを想像してみよう。こうした複雑に絡み合った神経活動の記述、すなわちマップは、私たちが心のなかでイメージとして経験するものに他ならない。各感覚モードのマップは、イメージ形成の基盤であり、時間の経過に沿って流れるそれらのイメージが、心の構成要素をなしている。それは複雑な生物に生じた革新的な一歩であり、ここまで述べてきた身体と神経系の連携の結果なのだ。
ただし、それら人間に特有とも思える、意識や心といった機能は、一般的に考えられているように神経の機能のみによって得られるのではなく、それよりもはるか以前の生物も用いていた身体的で物理的な化学物質のやりとりと一体となってこそ、働きうるものであることをダマシオは指摘する。
そのことこそが本書の一番興味深い点だといえるだろう。
進化の意外な順序
「進化の意外な順序」。
そのタイトルは、このきわめて人間的ともいえる、感情や意識、さらには、異なる個体同士の協調による社会性などの起源が、細菌のような単細胞生物ですらもっていたホメオスタシスにあるというダマシオの考えから来ている。
ホモ・サピエンスの知性に欠くことのできない支えであり、文化の形成に重要な役割を果たしてきた強力な社会性は、衝動、動機、情動の装置にその起源を持ち、より単純な生物の素朴な神経プロセスから進化してきた可能性が高い。さらに時をさかのぼると、それは一群の化学物質から進化してきた。しかもその一部は、単細胞生物の内部にも見られる。私がここで言いたいのは、文化的反応の形成に不可欠な一連の行動戦略から構成される社会性は、ホメオスタシスが備える道具の1つだということである。社会性は、アフェクトに導かれて人間の文化的な心に入ってくるのだ。
たとえば、同じ神経系でも中枢神経にくらべると、脇に追いやられて忘れ去られていることの多い、腸管神経系などはダマシオ的な観点からすれば、「身体と神経系の連携」が行われていることが確認できる代表的な場所となる。
腸管神経系は、最近になって「第2の脳」と呼ばれるようになった。この栄誉は、腸管神経系の規模と自律性に基づく。進化の歴史の現時点において、構造面でも機能面でも、腸管神経系が主役の座を譲るのは高次の脳のみである点に疑いはない。しかし、進化の歴史から見て、腸管神経系の発達が中枢神経系の発達に先立つ可能性を示唆する証拠が得られている。それには相応の根拠があり、根拠はすべてホメオスタシスに関係する。多細胞生物では、消化機能がエネルギー源の処理のカギになる。食物の摂取、消化、必須栄養素の抽出、排泄は、生命の維持には欠くことのできない複雑な処理である。
食物の摂取、消化などのエネルギー源の処理が多細胞生物とって根源的なものであればこそ、その神経系は、中枢神経系が整備される以前に、優先されて整備され、それはまさにエネルギー源の処理が化学的に行われることを維持するホメオスタシス機能を強化し、機能不全によってエネルギーが途絶えることを避けるためのものだった。
「何があっても生存し未来に向かおうとする」ために、神経系はさらに古くからあるホメオスタシス機能である化学的なやりとりとの協力を図ったということだ。
ラディカルに常識的な思考
こうした「身体と神経系の連携」の先に、感情や意識が生じたのであれば、意識と物質的身体をわざわざ分け隔てようとする従来の哲学の二元論的思考はあらためてどうかしていると思う。
少し前に、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』という、これまたここ数年来のあたり本ともいえる本を紹介したが、そこでのベルクソンの思考もダマシオをはるか200年近く出し抜くかのように精神と物質のあいだに垣根を設けることの間違いを指摘していた。
物質の知覚と物質そのもののあいだにあるのは、単に程度の差異であって、本性の差異ではない。純粋知覚と物質は、部分と全体の関係にあるからだ。これはつまり、物質はわれわれが現にそこに見て取っているのとは別の種類の力を及ぼしたりはしない、ということである。物質は何らかの謎めいた力などもっていないし、そんなものを隠しもてるはずもない。
もちろん、まだベルクソンの時代に、現代の神経科学のような知識は存在しないし、細菌同士が化学物質をやりとりしていることなども彼は知らなかった。
それでも、二元論を否定する物質と精神のつながりを見いだしたところに、ベルクソンのおそろしいまでの常識的な思考の素晴らしさがある。
ここで「常識的」という言葉を用いるのは、保守的だという意味ではまったくない。むしろ、デカルト以来、当時はまだ主流であり、ともすれば現代において、まかり通る二元論の伝統を打ち破るほどのラディカルな常識さがベルクソンにはある。
真に常識的な思考をすれば、物質と精神が切り離されているはずがないことを見出したわけだ。
トランスヒューマニストの誤り
その常識的な思考の素晴らしさをダマシオも引き継いでいるように感じた。それがこの本を僕が面白いと思った理由でもある。
たとえば、ダマシオは、不死を望んで、精神をコンピュータにアップロードできると考えるトランスヒューマニストの考えを真っ向から否定する。
トランスヒューマニズムの背後にある主たる考えは、人間の心をコンピューターに「アップロード」することで、永遠の命を確保できるというものだ。現時点では、このシナリオの実現はあり得ない。この考えは、「生命とは何か」に関する理解の限界と、いかなる条件のもとで生身の人間が心的経験を構築しているのかをめぐる理解の欠如を露呈している。いったいトランスヒューマニストは、何をアップロードしようとしているのか? 心的経験でないことは確かだ。少なくとも、たいていの人々が自分の意識ある心に関して抱いている考えに合致し、ここまで私が述べてきた装置やメカニズムを必要とするものとして心的経験を見なすのならば。本書の主たる考えの1つは、「心は脳だけではなく、脳と身体の相互作用から生じる」というものだ。トランスヒューマニストは、身体までアップロードしようとしているのだろうか?
トランスヒューマニストは、精神と物質がそもそも切り離されているという二元論をいまだに(非常識に)信じているからこそ、みずからの意識ある心、果ては自分自身の精神なるものをコンピュータにアップロードできると考えているのだろう。
しかし、ダマシオが言うように「生物は種々の組織、器官、システムの集合であり、それを構成するあらゆる細胞が、タンパク質、脂肪、糖分から構成される脆弱な生体をなしている」のであって、
コンピュータにアップロードできるような「一連の命令からなるコードなどではない」。それは「手で触れることのできる物体なのだ」。
そういう常識的に考えることが、デカルトの直系であるトランスヒューマニストはできないのだ。
「身体と脳の関係」が新たな光のもとで眺められるようになると、哲学や心理学における無数の問題に生産的にアプローチすることができるようになった。古代ギリシャのアテネに始まり、デカルトによって擁護され、スピノザの痛烈な批判を跳ね返し、コンピューターサイエンスに貪欲に利用されてきた二元論は、過去のものにならんとしている。たった今必要とされているのは、生物学的に統合された視点である。
このような常識的な宣言をごくごく普通にできるダマシオのこの1冊はとても興味深いものだった。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
