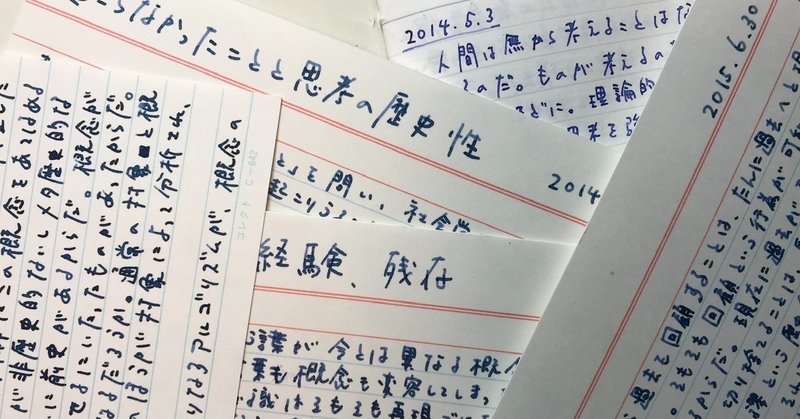
理論研究と歴史研究をめぐる方法論的覚書
1 芸術作品に対して(あるいは他のどの文化事象や社会事象でも同様だが)理論的にアプローチする際の最大の危険は、自分があらかじめ抱いている図式に当て嵌まるもののみを選んでしまうことだ。そこには何の発見も洞察もない。既知のものの複写であり、さらに悪いことには、芸術の(あるいは事象の)消去だ。自分の思考の枠組みのなかに一切の対象を整理していくだけで、対象との出会いによって揺さぶられることのない論述方法に代えて、むしろ論じる対象にあわせて視点と視野も動くような論述方法が必要だ。しかもその視点と視野の動きの構造をも、論述自体の歴史性さえも、あらわにする論述方法だ。
この意味でこそ、歴史をたどる必要がある。伸びていく枝葉をひとつひとつたどり、広がっていく根をひとつひとつたどる労苦を惜しまないことだ。花束は美しいかもしれないが、生長を待つよろこびはない。ただ萎れて別の花に取り替えられるだけである。
2 もし概念によってモデルを組み立て、その論じる対象の複写を作り上げようとするなら、組立(概念同士の整合性をつける作業)と調整(概念と事象を一致させる作業)の二度手間になってしまう。さらに悪ければ、自分の空想を現実と取り違えてしまう。
だから、はじめから歴史の細部──芸術の作品──をたどろう。しかも、自分の視点と視野の歴史性を示すような細部=作品を。そうすれば、理論ははじめから歴史に一致して描き出され、思考ははじめから現実のなかで動くだろう。これだけが、理論の名に値する理論研究にちがいない。歴史の重荷をいっそう多く引き受けるほど、理論はより速く、ますます遠くにまで行けるようになる。理論それ自体の歴史性が、普遍性への最短経路だ。
3 理論がもたらすのは、問題に応じて文脈を跨ぎ越える視点であって、いかなる問題にも解答を与える方法ではない。感覚印象や観念連合は、どれほど状況とは無関係な、恣意的なものに思えたとしても、それ自体の文脈に根差して生じている。感覚も概念もそれ自体の歴史をもつ。理論研究とはそれらの歴史性を示すことであり、そうしてある文脈に別の文脈を交差させて、視点を移動させていく。移動はまた翻訳でもある。かくして理論は歴史のなかを移動し、歴史そのものになる。
4 人間は無から考えることはない。事物が、事象が、対象が、考えさせるのだ。対象が考えるのだと言ってもよいかもしれないほどに。理論的対象とは、そうして雲のように人間に思考を強いて、考え込ませ、文化・社会・歴史を形成してしまうもののことである。もし思考が知覚の拡張だと言えるのであれば、理論的対象は経験を開くものにほかならない。
研究し分析しようとする対象は、当然のこと、それぞれに歴史をもっている。けれどもまた、その対象を分析し研究しようとしているわれわれの概念も、歴史をそれぞれにもっている。ある概念が発明される以前に成立した対象に対して、なぜその概念を当て嵌めることができるのか。それは、概念が非歴史的ないし超歴史的な普遍性を有するからではなく、概念に前史があるからだ(そして後史もあるからだろう)。ある概念が発明される以前に、その概念を発明させるにいたったものがあったからだ(そして発明以後にそれを翻訳させるにいたるものがあるだろう)。もしその概念自体を研究対象にするならばどうなるか。概念と対象のあいだの通常の関係は逆転し、むしろ概念のほうが対象によって分析され、構成されることになろう。
たとえば「芸術」という言葉が現在のそれとは異なる概念を指していたときの芸術経験は、もはや言葉も概念も変容してしまった今、取り戻しようがない。けれども、認識はそもそも再現ではなく、再構築でもなく、むしろ翻訳であると捉えるなら、嘆くにはあたらない。「芸術」が「art」の訳語として使われるようになったとき、それまで芸術と呼ばれていたものがそう呼ばれなくなり、芸術とは考えられていなかったものがそう考えられるようになった。これは西洋の概念が日本の文物を再編したことであると同時に、西洋の概念のなかに日本の文物という異物が侵入したことでもある。この交差的な運動を捉えることで、現在の概念のなかに過去の経験が残存しているのが見えてくるだろう。
5 言語に歴史があり変遷があり経緯があるように、概念にも歴史がある。哲学が哲学史からしか始まらず、人文学が古典からしか始まらないのは、そのためだ。人間は概念という、先人の残した思考の跡をたどってしか考えることができない。だが問題は、言語における歴史性と規則性とが奇妙に交差するのと同様、概念の歴史がけっして時系列に並ばず、その構造をそれ自体で捉えるのが困難であることだ。加えて、概念は言語と一致するとはかぎらない。それゆえ概念の歴史を理論的対象から描き出す作業が必要になる。経験から概念へと接近することになる。
6 おそらく概念史は、語句の定義のカタログとしてではなく、潜在する経験のアルゴリズムとして構想しなおされるべきだ。
7 概念史は、概念の歴史をまさに感覚として、身体的に感得でき、感得させるにまでいたらねばならない。逆に身体性は、そこに歴史的な概念性が体現されるにいたるまで鍛錬されていないのなら、無知の隠れ蓑でしかない。
8 概念に必要十分な定義を与えてその本質以外のさまざまな差異を捨象するのではなく、その逆に概念の前史と後史を見渡してありとあらゆる差異を包摂することが、普遍性へといたる経路だ。その道筋を示すのが理論的対象としての芸術作品であろう。美学はまさに内包的真理に対する外延的真理の探究として始まり、ゆえに芸術をパラダイムにしてきた。概念の前史と後史は、比喩と翻訳において、イメージとして、さらには美的経験として、広がっている。
差異を包摂し、多様性を通してこそ普遍性にいたろうとするとき、そこに統一的な共通尺度を想定するわけにはいかない。共通尺度なしに、意味の相補関係、観点の翻訳関係をいかに分節化するか。文献学と修辞学はその分節の技法の最たるものだ。かくして真理はそのつど文脈において把握され、実効的真理になることだろう。
9 現在の状況と関心から過去を回顧することは、たんに過去へと現在を投影しているわけではない。そもそも回顧や投影という行為が可能なのは、現在が過去に影響されているからだ。過去が現在に残存しているからだ。投影をたんなる誤謬の類として切り捨てることは、歴史に対する誠実な態度ではない。その誤謬を誤謬という歴史的事実として、その内実に踏み込まねば、歴史は理解できない。それは、現在の思考に閉じ籠ることも、過去の事実に飛躍することも、許さない。投影もまた残存であると捉えて、時間の逆転を再逆転することで、「時代」なる抽象的な枠組みから解放された歴史のなかではたらく理論があらわになる。
10 もし歴史学が「起こったこと」を問い、社会学が「起こっていること」を、文学と自然科学が「起こりうること」を問うのだとすれば、哲学は「起こらなかったこと」を問うのかもしれない。思想の研究からは意図・意向・志向といった次元を排除できない。思想を生存の技法と見なし、思考を行為の水準で捉えて、哲学者が書いたものを読解することは、たしかに多くの発見や洞察をもたらしうる。しかしながら、書かれたものに加えて書かれなかったものにまで考察を広げるのでなければ、事実を超え出ていく思考を把握することはかなわない。書かれなかったものへの注意が、書かれたという事実と書いたという行為への着目を補うとき、思考はその歴史性でもって歴史を形成する理論として姿をあらわす。伝記主義的な作者の意図が問題なのではない。理論と歴史の区別がもはや不分明となる次元ではたらいている思考の構造の問題である。
(2014年5月3日─2020年7月1日)
