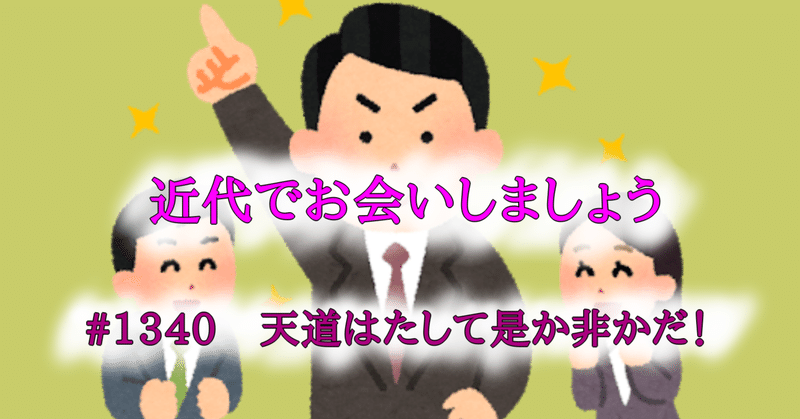
#1340 天道はたして是か非かだ!
それでは今日も幸田露伴の『露団々[ツユダンダン]』を読んでいきたいと思います。
中国の大都・南京に田亢龍[デンコウリョウ]という男がいます。眉があがり、鼻がたかく、唇の両端ははねあがり、観相見の実例に引き出されそうな顔立ち。独身者で、甕を叩きながら楚辞を呻り、香港から100ドルで買い寄せた弦が調整されてないヴァイオリンを弾いています。ぶんせいむの求婚の事件は、世界の新聞に掲載され、亢龍は独り言をいいます。「このぶんせいむという奴はかなり話せる奴だ。世界中からるびなを娶ろうと俗物どもが集まるだろう。しかし中華の人物と肩を並べることができるものか。るびなを侍妾として掃除をさせてやろうか。それにしてもこの広告の終わりのところが少し変だな……」
「嗚呼、大聲[タイセイ]里耳[リジ]にいらず、其[ソノ]調[チョウ]愈々高くして和する者愈々[イヨイヨ]少[スクナ]しとは韓娥[カンガ]が雍門[ヨウモン]に嘆じた所以だ、……噫[アア]見識の高すぎるにも弱るで、……吾[ワ]が道[ミチ]大にして吾が調[チョウ]高しだから、容れられないかもしれない。天道[テンドウ]果して是歟非歟[ゼカヒカ]だ、……然し林間に桂[ケイ]あれば野客[ヤカク]も其[ソノ]香[コウ]を知り、礫中[レキチュウ]に玉[タマ]あれば村童[ソンドウ]も其[ソノ]美を見ざらむやだ。
『列子』湯問篇に、こんな話があります。
昔、斉の国を訪れた名高い歌姫・韓娥が食べ物の持ち合わせがなくなり、斉国の城門である雍門で歌を歌い始めると、村人は感動し、食べ物を恵みます。彼女が去ったあともその声は三日間も消えることなく、村人は城門から離れなかったといいます。また、宿泊を断られた韓娥は、哀切の歌を歌いました。すると村の老人と子供が悲しみと憂いに沈んでしまい、三日間何も食べようとしなくなりました。村人は韓娥に懇願して村に戻ってもらい、歌を歌ってもらうと、みなが楽しんで歌って手を叩いて躍り我を忘れました。その遺風で雍門の人は、今でも歌がうまいといいます。
「天道是か非か」は、司馬遷の『史記』伯夷伝に出て来る言葉です。天は善人に味方して悪人を滅ぼすなんてことは、本当にあるのだろうか、それともないのだろうか、と人間が経験する不幸や不運に対する激しい悲しみや憤りを表すことばです。
それにしても、亢龍、とんでもない自信家ですねw
「彼[カ]の俗物中[チュウ]吾[ワレ]あるに、吾を知らずむば是れ盲[モウ]のみ、盲のみ矣[イ]、……盲乎[カ]盲か、天下皆な盲だ。已むなん乎[カ]と、喟然[キゼン]として天を仰ぎ、嗒焉[トウエン]として気を吹く時、不圖[フト]窓の下を見れば、往来何となくざわ付き、老幼[ロウヨウ]頻[シキ]りに馳せありくに眼をとむれば、群[ムラガ]りたる人の中に、一人[イチニン]の老翁[ロウオウ]あり。
ということで、この続きは……
また明日、近代でお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
