
映画感想 シン・仮面ライダー
庵野秀明、道楽映画第2弾!
今年3月に公開された『シン・仮面ライダー』が早くもAmazon Prime Videoに登場! 公開から4ヶ月で配信だからものすごく早い。庵野秀明監督『シン・エヴァンゲリオン』『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』に続く「シン」シリーズ4作目。今まであまり振り返られることのなかった石ノ森章太郎の原作版『仮面ライダー』をベースに、現代的な解釈を加えた作品となっている。
本作の企画は、東映の子会社ティ・ジョイのプロデューサーが映画『ヱヴァンゲリオン新劇場版:Q』の配給の時に出向していたことで庵野監督と関係を構築。2016年、庵野秀明が『仮面ライダー』の新しい劇場版のアイデアをメモにまとめ、プロデューサーに提示、ちょうど2021年が「仮面ライダー生誕50周年」ということもあって、そこを目指して制作のGOサインが出た。
しかしコロナウイルス蔓延のために制作が遅れ、2023年にようやく公開された。
庵野秀明はテレビシリーズで制作されてきた『仮面ライダー』シリーズを踏まえつつ、石ノ森章太郎の原点に立ち返り、「仮面ライダーとはなにか?」を改めて再検証し、分析し、変換し、再構築を試みた。つまり長年特撮ものを見てきた人間の視点で、「仮面ライダーってこういうことじゃないの」という想いが直球で込められている。
デザインには前田真宏、山下いくと、出渕裕、コヤマシゲトが参加。アクションシーン絵コンテには劇場版『エヴァンゲリオン』の監督を務めた鶴巻和哉(苦労人)、『ハツカドール』や『イロドリミドリ』の監督であるげそいくおが参加している。
スタッフリストを見ていて気付くのは「庵野秀明」の登場回数の多さ。脚本、コンセプトデザイン、モーションアクター、タイトルロゴデザイン、工学作画、総宣伝監修、ポスターデザイン……獅子奮迅の働きぶりである。よほど『仮面ライダー』がやりたかったようである(というか、“今回も”モーションアクターやったのか)。
キャストを見てみよう。

仮面ライダーこと本郷猛を演じる池松壮亮。本郷猛といえば藤岡弘という「見るからに強そう」なイメージがあったが、今作での本郷猛はかなり意思が弱い。どことなく碇シンジを思わせるところがある。

緑川ルリ子を演じる浜辺美波。か、かわいい……。本郷猛の相棒役を務めるが……どことなく綾波レイを思わせるところがある。
あれ? 『エヴァンゲリオン』の残像が見えてきた……。
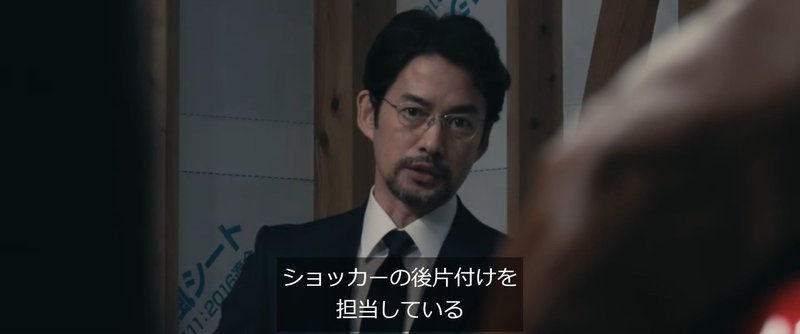
もう一人紹介したいのは「政府の男」という役で登場した竹野内豊。『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』と本作の3作に登場。しかも『シン・ウルトラマン』と同じ役名。実写「シン」シリーズすべてに登場し、もしかしたら同一人物かも知れない……という含みを持たせている。
それでは前半のストーリーを見ていこう。イー!
(シン・仮面ライダーの戦闘員は「イー!」とか言わない)
爆走するトラックに、バイクが衝突した。バイクに乗っていた男と女が奈落へと投げ出されていく。女の側に異形の男が迫ってきた。
「裏切り者に死を。それが私の仕事です。ですが、組織の命令は生け捕りでした。なので今は、二度と逃げ出さないために、お仕置きに留めておきます」
異形の男――クモオーグは女を拘束し、その目を潰そうとする。
そこに――何者か! 一同が見上げた。
「バッタオーグ! 完成していたのですか!」
そこにいたのは、バッタの仮面を付けた男――本郷猛だった。本郷猛は数十メートル奈落の底へと飛び降りた。鮮やかに着地を決める。異形の力を獲得した本郷猛にとって、その高さは致命的ではなかった。有象無象の戦闘員が本郷猛を襲いかかる。本郷猛は圧倒的な力で戦闘員を蹴散らしていく。砕ける頭部。はじけ飛ぶ身体。血しぶきが飛ぶ。阿鼻叫喚の光景だった。
な、なんだこれは……なんなんだこの身体は……! いったい僕はどうしてしまったんだ。
動揺する本郷猛の前に、緑川弘がやってくる。
「君は組織が開発した昆虫合成型オーグメンテーションプロジェクトの最高傑作だ。体内とエナジーコンバーターに残存しているプラーナを、強制排除すればヒトの姿に戻れる」
本郷猛は悪の組織・ショッカーに人体改造されていた。その本郷猛を脱走させたのが、本郷猛を改造した緑川弘自身だった。
「組織のオーグメント達は君と同等の力を持って、その力を個人のエゴに使っている。本郷くんは他人のために、多くの力なき人々のために使って欲しい。君に、組織を倒す我々の計画を手伝って欲しい」
緑川弘は悪の組織ショッカーのために働いていた。しかしショッカーの活動に疑問を持つようになり、本郷猛を改造した後に脱走させたのだった。ショッカーと戦う力を与えて……。
そこにクモオーグが襲来し、緑川弘が死ぬ。
その娘である緑川ルリ子が誘拐され、本郷猛は後を追う。バイクに乗り、“仮面ライダー”に変身し追いつくと、クモオーグと戦いになる。激闘の末、クモオーグを撃退するのだった。
本郷猛と緑川ルリ子はただちにその場を離れる。ショッカーと戦うために、拠点となる緑川ルリ子のセーフハウスへと向かう。しかしそこに男が2人いた。”政府の男”と“情報機関の男”だった。
2人の男の目的はショッカーの壊滅。そのためにショッカーの内情を知る緑川ルリ子と、ショッカーに改造され超人となった本郷猛に協力を求めてきたのだった。仲間は多い方がいい。本郷猛と緑川ルリ子は政府の男と協力するのだった。
ここまでのエピソードでだいたい24分。仮面ライダーに変身し、最初のボスであるクモオーグ撃退後、政府の男と協力関係となる。起承転結の「起」だけど、結構詰め込まれている。
テレビ放送されている『仮面ライダー』は日曜日の朝にやっていて、主な視聴者層は子供(しかもある年代から『仮面ライダー』のあとに『プリキュア』がやっている)。そういうこともあって、テレビ版『仮面ライダー』の表現はいつも抑え気味になっていた。
でももしも表現上の制約を取っ払ったら『仮面ライダー』はどうなるのか。石ノ森章太郎の原典に立ち返って、あらためて『仮面ライダー』とはどういうものなのか……というところからこの作品は始まっている。

まず、仮面ライダーに変身しているとき、本郷猛自身はどうなっているのか。この描写からわかるように、すでに“人間ではないもの”に変化している。どこか「フランケンシュタイン」的な異形となっている。
だからこそ、「仮面」をかぶる。異形となってしまった身体は、どちらかといえば「内蔵」みたいなもの。それを覆うための「殻」が必要となってくる。だから『仮面ライダー』の怪人たちはみんなヘンテコな仮面をかぶる。怪人たちは仮面をかぶって完成形となるのだ。
(最初のシーン、本郷猛はバッタの仮面を外そうとするが外せない……というシーンがある。あれでこの力、姿がある種の「呪い」であることを表現している。本当は普通に脱げるのだけど、「呪い」っぽさを表現するために最初のシーンは脱げないようになっている)
人間はそもそも「体毛」がないから「服」を着る。文化発達の段階で、ただ「服を着る」というところから、その服でいかに自身の文化圏を表現するか……とアイデンティティと結びついたものに変わっていった。怪人が自分の身体的な性質がわかるような仮面をかぶっているのは、それが「私です」という彼らなりのアイデンティティの表現であるからだった。こういうところで、『仮面ライダー』の怪人がどうしてあんなヘンテコな格好をしているのか……という理由を与えている。

「風の音が聞こえる。なぜ体の中から風の音がする? 僕が殺した? いや、体が勝手に動いてた。わからない。人を殺して、なんで僕は平気なんだ」
変身すると姿だけではなく、精神性も変わってしまう。仮面ライダーに変身すると人間性は喪われ、暴力衝動のままに行動してしまう。行動のリミッターが効かなくなってしまう。これが超人になることの代償。姿だけではなく、精神性も「人間」ではなくなってしまうのだ。

「見てください、この圧倒的な殺傷能力。ヒトではない喜び! あなたも同じオーグメント。なのに、この幸せがなぜわからんのです。さあ、あなたも死んで私の幸福の一部となってください」
クモオーグはすでに怪人としての自分を受け入れている。ごく普通の人間として社会生活を送っていたときには抑制されていた暴力性……それが解き放たれている喜び。自由に人を殺していい……という“タブーを犯すこと”が怪人たちにとって喜びになっている。

そんなクモオーグと向かい合っているときの仮面ライダーの姿。ぼんやり立っていて、すこし首を傾けている。映画ではよくある表現で、この状態は理性が働いていない状態。クモオーグ以上に理性が壊れかけていて、相手の言葉が耳の中を通り過ぎているような状態だ。
本郷猛の演技を見ると、ほとんど無表情、棒読み……感情が抜け落ちている。仮面ライダーとなることで、人間性がどんどん抜け落ちていく。
現代人はもはや自然と相対することがなくなってしまったから、うっかり忘れがちだが、人類というのはそもそも「自然界最弱の存在」だった。7万年前、野生動物に怯えながら、肉食動物が狩り、食い荒らした後にコソコソとやってきて、その残りを漁る生き物……それが我らホモ・サピエンスだった。
実は人類は自然界最弱の存在。世の中的には「人類最強の男!」みたいな称号があるが、それで野生のクマやライオンと素手で殴り合って戦えるか……というとまったく歯が立たない。スポーツの世界で最強の存在であっても、自然界にいけば相変わらず最弱の存在が我々だ(よくもこんな弱い生き物が生き残れたな……というくらい)。
私たちは自然界最弱だった……という過去とはもう向き合っていないが、意識の端っこでどことなく「自然界最弱である」ということを気にしている。だからこそ「超人」に憧れる。しかし、実際に超人となってしまうとどうなるのか。超人とはなんなのか。そこで「仮面ライダーになってしまうことは、どういうことか?」ということがテーマに盛り込まれている。
私達は「社会」というものを作り、その世界をルールだらけにして、それを守ることでお互いを権利を守るようにしている。それは自分の身を守るためでもあった。それが超人になると、いろんなものが壊れてしまう。人を殴っちゃいけない……なんで? 物を盗んではいけない……なんで? 理性的なリミッターが外れて、野生のままに行動してしまう。人間としての形が崩壊していく。本郷猛はそういう「壊れていく自分」とも葛藤していく……仮面ライダーこと超人になるということは、そういうことではないか――とこの作品は語っている。
後のシーンで食欲も湧かなくなっている……と語られている。あの調子だと性欲もないのだろう(だってルリ子ちゃんみたいな可愛い子の側にいてもなんとも思わないんだよ)。これも人間性を喪おうとしている過程の一つなのだろう。

「大丈夫だ。僕は人を守りたいと思う。自分の心を信じる」
「……ことにしたのね」
この台詞を、本郷猛は妙にプルプル震えながら言う(他のシーンでもやたらと震えているんだけど)。
本郷猛は理性の崩壊を前にして、自分の力に溺れそうになる。そこでコウモリオーグとの戦いの後、「僕は人を守りたい」とその力の扱い方を決める。“目的を持つこと”で「人間性の崩壊」を食い止めようと決める。
場面は線路の上。『シン・エヴァンゲリオン』でも線路の上は登場人物達のターニングポイントが描かれる場面だった。このシーンで、本郷猛は自分の生き方を定めるのだった。

「謝ることなんてない。私を助けただけで充分。それに緑川は、あなたを勝手にバッタもどきにした男なのよ。気にしないで。私も気にしない」
では緑川ルリ子ちゃんはどういう人物なのか。わかりやすいのはこの場面。「謝ることはない」……と言いながら、本郷猛と目を合わせないし、視線も泳いでいる。ルリ子も人との接し方がよくわからない。どこか綾波レイ的な存在。
こんなルリ子が本郷猛とどんな関係を結んでくか……が映画のドラマ的なポイント。

もう一つのルリ子の役割は、ポスタービジュアルを見たほうがわかりやすい。ルリ子が本郷猛と“2号”こと一文字隼人に赤いマフラーを巻いている。ポスタービジュアルがその様子を「儀式」的な一場面としてピックアップされている。
要するにルリ子は、異形の怪人・仮面ライダーにヒーローとしての役割を与える存在。本郷猛は理性が壊れそうになるも、「ルリ子を守る」という命題を持つことで理性を保とうとする。
ショッカーに洗脳され、暴力性のままに行動していた一文字隼人の洗脳を解き、「仮面ライダー2号」としてのアイデンティティを与えたのもルリ子。ルリ子という存在が、すべての軸になっている。ルリ子は魔を払い、迷える者に道筋を与える……ある種の「巫女」のような存在といえる。

ハチオーグことヒロミが倒された後、綾波レイ的だったルリ子は急に感情を発露するようになる。友人らしき存在の死に直面し、心情的に寄りかかる相手を失い、そのフラストレーションをわかりやすく表に出そうとする。
ただし、そのやり方が極端で下手。”わざとらしく”なっている。急に情緒に目覚めるからコントロールが効いてない。
この変化が、本郷猛とルリ子の関係性を変える切っ掛けを作る。本郷猛とルリ子の関係は、あくまでも互いに利用価値があるから一緒にいるだけ……。しかし次第にルリ子は、本郷猛を「心情を預ける相手」へと見なすようになっていく。関係性は急速に“恋愛”へと向かって行く。
しかし『仮面ライダー』の本質は悲劇。意に沿わないのに怪物の力を背負わされるような男の話。この恋愛が成就するわけがなく……。

次に悪の秘密結社・ショッカーとはなんなのか? この作品ではどう描かれたのか?
「ショッカー」とは、「Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling(計算機知識を組み込んだ再造形による持続可能な幸福組織)」という文章の頭を取って「SHOCKER」。
作中では次のように描かれる。
ショッカーを設立させたのは日本にいたとある大富豪。この大富豪は自分の資産を用いて【人工知能アイ】を生み出す。アイの目的は世の中を観測する目的で生み出された。やがて2体目の【人工知能ジェイ】が生み出され、アイはクローズドネットワークに引きこもるようになる。そのジェイもやがてバージョンアップされたケイが生み出されて廃棄。現在、アイとジェイが活動している。
「アイ」の名前は「愛」であり「I」である。「愛」と「私」という意味を含んでいる。人工知能ジェイとケイはアルファベット順のI・J・K。JとKにも何かしらの暗喩がありそうだけど……よくわからない。とにかくも、Kが生み出されたことによってJが引退することになる。IとKの間にできた欠落……「欠落」のモチーフがここにも出てくる。人工知能も何かしらの欠落を抱え、無意識の葛藤を抱える。

やがて創設者は自殺してしまう。人工知能アイとジェイに「人類を幸福に導く」という究極の命題を与えて。
アイは考えに考えた末、最大多数の幸福に人類の幸福はない……と判断した。深い絶望を抱えた人を救済することこそが幸福である。この考えに沿って、ショッカーはある特定の個人を一方的に拉致し【救済】することを目的としていく。
というわけで仮面ライダーもクモオーグもコウモリオーグもみんな何かしらの絶望を抱えていた。それを救済する目的で、超人的な力を与えていく。
弱い人間であるから悩むんだ。超人にさえなればもう悩む必要はなくなる。――しかし、実際に超人になってしまうと理性の崩壊に直面することになる。要するに悩んでいる人を拉致してロボトミー手術を施すみたいな話。
クモオーグはこう仮面ライダーに語りかける。
「私の戦闘員への殺害行為、実に見事でした。あなたも人間を殺す幸せを知りましたね」
社会ルールにがんじがらめになるから苦悩する。理不尽に遭う。理不尽に遭って泣き寝入りすることになる。だったら、むしろ社会道徳なんてものは崩壊させてしまったほうが、「解放」される。絶望はなかったことになる。その瞬間に救済がやってくる。
しかし仮面ライダーはそれに抗ったせいで、「苦悩」を背負い込むことになる。

ショッカーにはもう一つの目論見がある。この場面はショッカーに殺害された工作員たちの姿が描かれるが、工作員達に外傷はなく、みんな笑顔で死んでいる。これはなんなのか?
「チョウオーグによるプラーナの強奪。その人を形成するプラーナの配列を壊さずに別に空間に転送する。いわば、魂を別の場所に連れて行かれた感じ。そこを私たちは、ハビタット世界と呼んでいる」
プラーナとはサンスクリット語で「呼吸」「息吹」を意味する。同時に「風の元素」や「生命力」も意味に含んでいる。なぜなら呼吸は生きていくために必要だから。そこで昔の哲学者は、呼吸していること、生命、それを引き込む「風」を連想で結びつけていた。

仮面ライダー変身シーン。特撮ヒーローお約束の「変身シークエンス」ではなく、バイクで走りながら、ベルトに風を入れる……という描き方になっている。それでタービン(?)を回転させ、力に変換し、変身させる……という仕組みになっている。大気中のプラーナを身体に充填させ、それが超人:仮面ライダーの力の源……となっている。

チョウオーグに殺された人々……というのは暴力を振るわれたのではなく、プラーナを抜き取られたことによって死んだ。身体的には死んだとは(医学的に)いえないけれども、魂を抜き取られたから、もう蘇生することはない……という状態だ。
ルリ子の兄、チョウオーグことイチローは人々の魂をハビタットに送り込むことを「天国への道」と考えていた。魂を一つの世界、一つの価値観の中に封じ込める。そこはきっと差別も暴力もない。全員がささやかな幸福で満たされる平等な世界。それがイチローの考えるユートピアだった。
しかしルリ子は「ハビタットは煉獄」と考える。そこには悲しみも理不尽もないが、喜びもない。不平等も暴力もないが、自己もなく、特定の誰かを愛することもない。それは「ディストピアだ」とルリ子は言い放つ。それが本郷猛という愛する人を獲得したルリ子が思い至った結論だった。
ある意味『エヴァンゲリオン』で描かれた「人類保管計画」の延長上のテーマ。「シン」シリーズとしての地続きを考えさせるテーマ設計だ。
超人になってしまった人間の内面、そんな人間がいかにして人間性を保ち続けるのか。不平等が蔓延するこの時代において幸福とは、平等とは? 子供向け特撮劇『仮面ライダー』では曖昧だったショッカーの目論見を明確にさせ、「大人向け」の作品として、骨のある作品となった『シン・仮面ライダー』。
ところが、ぎっちょん。
『シン・仮面ライダー』は映画として見ると、いまいち緊張感に欠ける平凡な作品になってしまっている。どこが不味いか……というと「映像」。映像が「映画の画」になってない。
(ところが、ぎっちょん …それまでの文脈と異なる結果を述べるときに使う。『ドリフターズ』の持ちネタとされるが、由来はもっと古いらしい)
まずアクションシーン。何が描かれているのかよくわからない。流れを見るとわかるけれども、あまりにも細かくカット割りされていて、せっかくの立ち回りが寸断されてしまっている。カットの流れを見ていると、記号的なシーンの羅列にしか見えない。
それに、どうやら撮影にiPhoneやらGoProを使ったらしく、そういった画面はとにかく安っぽい。素人っぽく見えて、画面に「格」がない。iPhoneやGoProは取り回しがよく、通常のカメラではできないような構図ができる。例えば地面すれすれのカットは、地面を掘ってカメラを設置しなければいけないが、iPhoneだったら可能になる。バイクにもお手軽に取り付けられる。そうやって撮られた画面は、確かに奇抜な構図になっているが、しかし映画の画になっていない。ただ奇をてらっただけのようにしか見えず、むしろシリアスなドラマ感を減退させてしまっている。

こちらはジャンプ宙返りの瞬間の画像。このカットが入ると場面転換になる……というのは特撮ドラマのお約束的な描写だけど、これをリアルな世界背景を持った映画の世界で描くと、浮いて見えてしまう。急に安っぽいテレビ特撮に気分が引き戻されてしまう。
アクションシーンはそういうシーンの連続で、見ていてもぜんぜん超人らしいバトルシーンに見えない。「カット割りでごまかしてるな」という感じ。その一方で、やたらと血しぶきが飛ぶ……というわかりやすすぎる描写。それがバイオレンスを安っぽくさせていて、さらに作品の品格を落とす結果になっている。

後半に入り、突然アクションのほとんどがCGになり、明らかに動きの悪い生身のアクションよりかは楽しくなるけれども、構図も動き方も「アニメ」。人間の動きじゃない。アニメだったら違和感はないけれども、実写でアニメ的なものをやりすぎると違和感しかない。この上に、アニメ的なエフェクトまで加わり、画面の「格」はどんどん落ちていく。
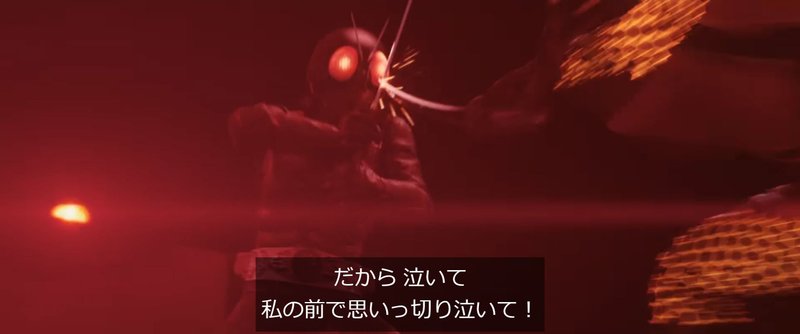
物語の展開を映像ではなく、ほとんど台詞で説明してしまっているのも良くない。本郷猛の心情、ルリ子の心情……どちらもみんな台詞で語ってしまっている。台詞だけの作品になってしまっていて、映像に重点を置いてない。映像に自信がないかのように見えてしまう。
クライマックスのチョウオーグとの戦いは、圧倒的な力で仮面ライダー1号、2号が追い込まれるのだが、後半に入り、急にチョウオーグが弱体化する。あれはプラーナの補給ができないから……という理由だけど、展開だけを見ると、仮面ライダーを勝たせるためのご都合主義にしか見えない。映像でそういう展開に至るまでの説得力が作り出せていない。
クライマックスシーンに限らず、『シン・仮面ライダー』はそういう場面だらけ。映像に力がない。映像に力がないから、どのシーンも作り物っぽく感じられる。映画を観ている……という実感が薄い。
『エヴァンゲリオン』の時の圧倒的な絵力はどこへ行った? 『シン・ゴジラ』でも構図がキレッキレだった。庵野秀明作品は構図が強かったはず。ところが『シン・仮面ライダー』はただ奇抜なだけで、全体から力が抜け落ちてしまっている。抜け殻のような映像が漫然と流れているだけ……になってしまっている。
『エヴァンゲリオン』の呪いから解放された後で、気が抜けてしまったのだろうか。どこか庵野秀明らしさがない。作品から緊張が感じられない。庵野秀明のニセモノ作品を見たかのような気分だった。
『シン』シリーズは、昔懐かしの特撮ヒーローをもう一度再検証する……ということがテーマだ。『ウルトラマン』が描かれた頃は、そこまで「そもそもウルトラマンは何者なのか?」「何が目的なのか?」「社会はどのように反応したのか」……という奥行きまで描かれていなかった。もしも現代的な解像度であの特撮ヒーローを描くとどういうことになるのか?
『シン・ウルトラマン』にしても『シン・仮面ライダー』にしても脚本上はそのテーマは達成されている。狙い通りのシナリオは描けている。『シン・ウルトラマン』も『シン・仮面ライダー』も現代に問うシナリオになっている。ところが、どちらの作品も映像が弱い。中途半端で安っぽい。もちろん関わっているスタッフは業界一流の人々なのだけど、目標としている地点が低い。映像の目標設定をどこか間違えている……そう言うしかない。それが『エヴァンゲリオン』であれだけ映像の力強さを生み出した庵野秀明作品となると「おい、どうした」と言いたくなる。あんたの実力はこんなもんじゃないはずだ、と。これはあんたの本気じゃないだろ、と。庵野秀明の途方もない実力を知っているからこそ、「どうしたんだよ」と言いたくなる。庵野秀明はシナリオライターではなく、映像作家でしょうが!
そういえば庵野秀明は「三振かホームランしか打たないバッター」と言われていた。ホームランの時はもちろん場外ホームラン。過去には『キューティーハニー』(「シン」ではない)という迷作もあった。三振するときは勢いよく空振り三振する。そういう作家だ。
次回作ではホームランを打ってくれることを期待しよう。当たれば場外ホームランなんだ。そういう奇跡的なホームランを打ってくれる作家だから、ここに留まらず、次の作品に期待しよう。
『シン・ウルトラマン』にしても『シン・仮面ライダー』にしても決してダメな作品ではない。テーマは明確だし、語るべきものはある。シナリオは良い。ただ映像作りに素人目にもわかるくらいに「迷い」がある。いったいなにに迷っているかわからないが……。おそらくその迷いを乗り越えたとき、次なる傑作が生まれる――そう期待していよう。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
