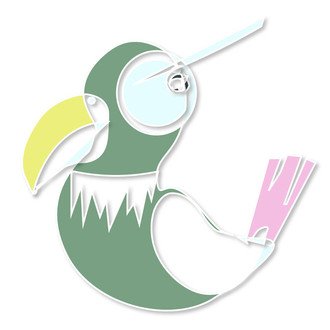記事一覧
上京して二ヶ月、祖母から手紙が届いた。
「そちらにはたくさんの光があるのでしょうね。私が教えた中で、貴方はいちばん踊りが上手だった。覚えている?湖のほとりで踊った夜のことを——」
忘れるものですか。赤信号の明滅が、ネオンの光が、敵うわけない。
月の光に、影は一番よく踊るのだから。
ドライヴに行こうと君が誘う。
ホットサンドを二人でつくった。珈琲を淹れるにも手分けをする。
これまでもたくさん二人で分かち合ってきたし、これからだってたくさんの事を共にすごす。
安堵、歓喜、葛藤、苦悩、不安——。
だけど、君を横に乗せて走らせる車の喜びだけは、僕のひとりじめだ。
「パンナコッタには苺のソースがいいんだ。君も知っているだろう」
キウイだってとっても合うのよ。食べてごらんなさいよ。
どれ、そう言って生クリームをたっぷり使ったパンナコッタを口に運んだ。
あまい香りに、キウイの程よい酸味。
「うん、悪くないな」
それが聞きたくてわざとやったのだ。
「本を読むとね。こう、ぱっと目の前が開けてくんだな。読んだ本はね下に積んでどんどん視界が高くなるんだよ」
そう六年前に話していた彼は、昨日高いビルの屋上から飛び降りた。
きっと彼は一気に積みすぎたんだ。塔みたいに積んで、そうしてはたと気づいたんだよ。ここからどうして降りようかと。
しかし、漁師の家を出て山なんかにきて、親不孝だとは思ったりしないのかい?と僕は訊ねた。
「私はいま美味しい野菜と、健康な土を育てています。その土は川を綺麗にしていずれ海もきれいにします。そういうのもありかなと思ったんです」
そう言って彼女は、とびきり綺麗に秋刀魚を平らげた。
マーマレードの香りがして、僕は急いでベッドを出た。
流感にやられたじいさんの部屋を通ってダイニングに駆け込むと、母が朝食をならべている。
僕は居てもたってもいられずに声をあげた。
「母さん、今日はピクニックなんだ。バスに大勢乗っていくんだよ」
「坊や、それよりもまずは挨拶でしょ」
黒を叩いて手のひら打ったら遥かな概念うまれて出てさ。
そこにあるものくるりと集めて寄せて丸めて大地にしてね。
そしたら君たちぴょこんと出て来て僕はにっこり微笑むわけさ。
水と大地を足して割ってその間。僕がみるのは青い海。青い空。
青い青いというけれどそんなに青くはないはずさ。瞳。
バーでスーツを着込んだ男が話しかけてきた。
「結局さ、彼は書店のベストセラーと名作の棚から思い出したように手に取って切り貼りする、いわば付け焼き刃仕事なんだよね。はは」
ああ、彼っていうのはね、と僕の名前を付け足したので、僕はアルコールをどれだけ呑めば君は消えるのかと訊ねた。
さいきん母さんのつくるおにぎりの味が変わった。
父さんは何も気づかないみたいだけど、僕だけは知っている。
ごはんを丸めるところで、最近はこっそり見慣れない白いのを混ぜ込んでいるのだ。
すこしずつそれは毎日続けられている。
僕だけが知っている。
「アジノ○○」
「うまいね、母さん」
遥か頭上高く飛行機が走っていった。
あんなに速く飛ぶエンジンを積んだつもりはなかった。
無茶なことをしやがる。
そう思いながら、僕はあいつが下ろしていったパラシュートを畳んだ。
その向こう、脇に押しやるようにして、ここにあるはずのない機銃すら置いてあるのを見つけて、愕然とした。
絵描きは盗んだ絵の具でみごとな絵を描いた。
しかし、やがて罪悪感に急き立てられて、跡形もないように火を点した。
そうして姉は焼け死に、未完成の絵だけが遺された。
未完成のくせに、この世のものとは思えないほど美しかった。
筆は借りた。あとは絵の具、と僕は小銭をつよく握りしめた。
アツアツのご飯に合うのは、やはり二日目のカレーだ。火が入ると、くつくつと一度眠った香りが還ってくる。口に香りを感じながら、鮮やかなキャベツを細かく刻んでおく。どろっとよく煮込まれたルーをご飯にかけ、そしてふわりとキャベツをのせる。すこしソースを垂らすのもいい。さあ、どういこうか。
三つ角を曲がったところに寂びれたうどん屋があって、きつねが美味い。
掛け布団みたいな厚いお揚げを一口やって、熱い出汁がどっと流れ出るもんだから、それに多少口のなかを傷めてでもまた一口齧りたくなる。
思い出したようにずるずるっとうどんを啜って、胃が火照ってくるのがたまらない幸福だ。
川から老婆が流れてきて、村ができて以来の騒ぎになった。
風車とおにぎりと、それから若い男の記憶を携えていた。
意識ははっきりとしているが、川にいる間の記憶だけがぽっかりと抜け落ちている。
男の名前をつぶやくのを見て、上流ではまだ少女であったのではないかと、そんな馬鹿な空想をした。