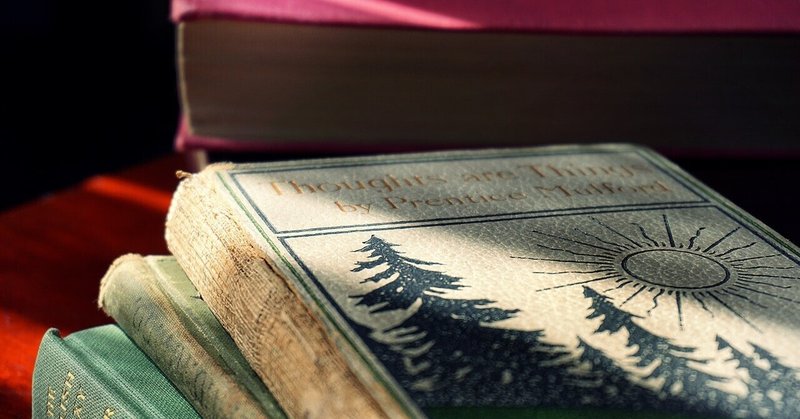
2020年のベスト洋書と翻訳書(植田かもめ)
植田かもめの「いま世界にいる本たち」第32回
2020年って、一体何だったんだろう。いつもオススメの洋書を紹介しているこの連載であるが、今回は番外編で、年間を通じたベスト洋書と翻訳書を紹介したい。ノンフィクションとフィクションから各3冊ずつ、ラインナップは以下の通り。今年発売された本が中心であるが昨年のものも混ざっている。筆者の個人的なセレクトであることをお断りしておく。
Yancey Strickler "This Could Be Our Future"
Mariana Mazzucato "The Value of Everything"
デヴィッド・グレーバー 『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』
エイモア・トールズ『モスクワの伯爵』
ミン・ジン・リー『パチンコ』
ハイケ・フォーラ『100年の旅』
「価値観を変える」ノンフィクション編
言うまでもなく、今年は世界中が新型コロナウイルスに振り回された年で、その影響は現在進行形の世界史として続いている。
コロナが社会をどう変えるかについて論じる本も既に数多く発表されているけれど、ぶっちゃけそういう本は賞味期限が早いものが多いのではないかと思う。
よって、ここではコロナが発生する前から「社会の価値観を変えなければならない」と説いていた本を3冊オススメしたい。今まで当たり前にできていた事が制限されると、人は「当たり前」だった価値観も見直すものだ。
まずは、この連載でも紹介した、ヤンシー・ストリックラーによる"This Could Be Our Future"である。本書は、現代の資本主義の特徴を「金融の最大化」(financial maximization)と名付けて、それに代わる価値観のあり方を提唱する。今年一番、読んでいてワクワクして、勇気をもらった。Kickstarter社の共同創業者である著者のストリックラー自身が、本書が重視する持続可能性などの価値を体現している人物でもある。
また、同じく以前紹介した、経済学者マリアナ・マッツカートによる"The Value of Everything"は、「価値とは何か」について17世紀から振り返る傑作だ。価値観がいかに変遷してきたかを知ることで、いまは「当たり前」に思える価値観が、実はいくらでも変わり得るものだと学べる。
そして、よりラディカルに「仕事」や「労働」の価値を見直すのが、デヴィッド・グレーバーの 『ブルシット・ジョブ』である。「クソどうでもいい仕事の理論」というサブタイトルがついたこの論考はクソ面白い作品で、読みながら何度も声を出して笑った。なぜ、完全に無意味だと本人でさえ気付いているような仕事が世の中にあふれているのか。なぜ、介護や福祉など世の中に必要不可欠な職業の収入が低いのか。そんな、ぼんやりと誰もが気付いているけれど誰もうまく説明できない疑問を入り口にして、本書は仕事や労働の価値を再定義する。なお、残念ながら著者のグレーバーは2020年の9月に逝去した。
これら3冊は、同じ問題を別の角度から探究しているようにも思える。目先の金銭的な価値を追うだけの社会ってなんとなくヤバそうだ、と多くの人が感じている。では、それに代わって何が価値ある事なのかを、どう定義して、どう測定すればいいのだろう。これは、「SDGs」とか「ESG」とか「ステークホルダー資本主義」とか、世界中がいろんな看板を取っ替え引っ換えして考えようとしている問題だ。"This Could Be Our Future"は、企業は金銭的な利益目標とは別に「自らのミッションに基づく価値創造(Mission-driven Value Creation)」を目指すべきと説く。"The Value of Everything"では、単なる価値の「抜き取り」(Value Extraction)が、価値の創造(Value Creation)と混同されることを問題視する。そして『ブルシット・ジョブ』では「価値(Value)」と「諸価値(Values)」を区別して、後者は必ずしも金銭的な利益に還元できないと論じている。
「人生を考える」フィクション編
さて、続いてフィクションを3冊オススメしたい。まずはエイモア・トールズの『モスクワの伯爵』である。ロシア革命によって政治犯とされた伯爵が、モスクワに実在するメトロポール・ホテルに一生軟禁という「自粛」を余儀なくされる物語だ。不運な境遇に置かれる伯爵だが、はっきり言って悲壮感は無い。あてがわれた部屋でモンテーニュやロシア文学に浸って人生を考えるーーーだけでは飽きてしまって、ホテル内の理髪店やレストランで、人と語り合い、人生の味わいを再発見する。激動のロシア史を背景に、「自らの境遇の主人とならなければ、その人間は一生境遇の奴隷となる」と伯爵は言う。
次に、ミン・ジン・リーの『パチンコ』。1910年から1989年まで、朝鮮半島と日本を舞台に四世代にわたる家族を描いた長編である。在日コリアンというアイデンティティについての小説であるが、同時に「自分でコントロールできない運命とどう向き合うか」がテーマでもある。戦争や社会の激変にパチンコ玉のように翻弄されながら、ある登場人物は「なあ、人生ってやつには振り回されるばっかりやけど、それでもゲームからは降りられへんのや」と語る。
最後に、簡単に読めて、心に沁みる本を一冊。ハイケ・フォーラの『100年の旅』は、0歳から99歳までの年齢で人生に何を感じるかを、それぞれ見開き2ページのイラストと一行のコメントで表現する。人生という「不可思議な旅」で出会う感動や挑戦、喜びや哀しみが切り取られていて、読んでいると、いつかの自分や、自分が知っている誰かを思い出さずにはいられない。手元にずっと置いておきたいと思わせるような一冊である。
以上、どれも長い時間軸で人間について考える本なので、今までの人生を振り返ったり、この先の人生について考えたりすることが多かったであろう2020年にオススメしたい。
参考:2019年のベスト洋書と翻訳書
執筆者プロフィール:植田かもめ
ブログ「未翻訳ブックレビュー」管理人。ジャンル問わず原書の書評を展開。他に、雑誌サイゾー取材協力など。ツイッターはこちら。
よろしければサポートをお願いいたします!世界の良書をひきつづき、みなさまにご紹介できるよう、執筆や編集、権利料などに大切に使わせていただきます。
