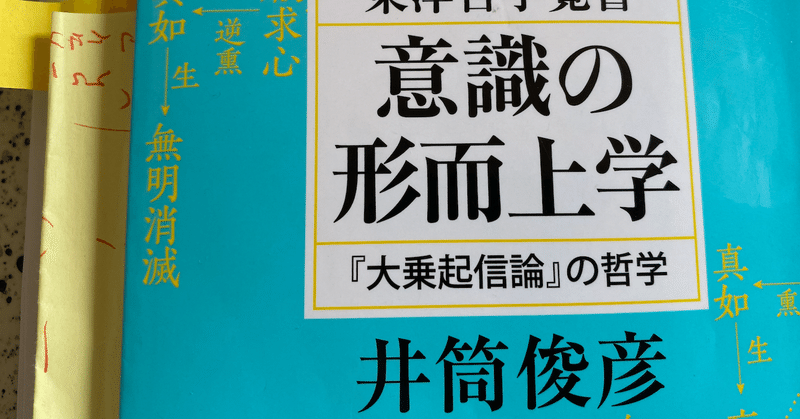
創造とは分かり方(分け方)を進化させることである -井筒俊彦著『意識の形而上学 『大乗起信論』の哲学』より
(このnoteは有料に設定していますが、最後まで無料でお読み頂けます)
井筒俊彦氏の著書『意識の形而上学 『大乗起信論』の哲学』を読む。
この本で井筒氏は「意識」という言葉を、大乗起信論の言葉である「心」に「ホンヤク」するということを試みる。「意識」という言葉と「心」という言葉が異なりながらも一つに結ばれる所から、井筒氏の思考が一挙に展開する。
「ホンヤク」がなぜカタカナになっているかというと、井筒氏が『意識の形而上学』の中で、カタカナでホンヤクと書かれているからである。
意識と心の「ホンヤク」についてはこちらのnoteにも書いているのでぜひご参考にどうぞ。
「ホンヤク」をするということは、「読む」ということでもある。
読むということには、二種類ある。
第一は原典を復唱するような読み方である。「原典によればAはBだと書いてありました」と報告する読みである。私自身を含めて勉強中の凡夫にできる読みといえば、ほぼこればかりである。
何より哲学書や思想書ではなく、日常に溢れる文書や言葉については、こちらの復唱するような読み方の方が強く推奨される。「この道路の制限速度は30km/hです」と書いてあるところで、「私にとっては制限速度とは超えるべきものという意味である」などとやっていては即逮捕である。
言葉には、特に書かれた文書には、誰が読んでも同じになる正しい意味というものがあって、その正しい意味を正しく再生できるようにすることが子供が大人になるための勉強なのだ、と、そういうことで日常世界は再生産され続けている。
◇
ところが、ここで一つ大きな問題がある。
この「言葉には誰が読んでも同じ正しい意味というものがある」ということは、仮にそういうことにしておきましょうという約束事のようなもので、実際に現実に実在の実体として誰が読んでも同じ正しい意味というものがあるわけではない。そういうものは端的に「ない」のだけれども、「あるということにして」日常世界の表層の一貫性を安定させているのである。
おそらく大概、人類はそれでなんとかなってきたのであるけれども、それまでの日常世界の安定性が崩れようとしている時、常識では「理解できない」こと「あり得ない」ことがあり得てしまうようになった時に、あり得ないと唱えてもどうにもならないことになる。
こうしたところで必要になるのは、理解できない事柄を理解できるように「理解の仕方」自体を組み替えること、「あり得ない」ことを「でも、あるよね」ということで、その「ある」と他の「ある」との間にどういう折り合いをつけるかを考えることである。
ここに登場するのが、第二の「読み」としての創造的な「ホンヤク」である。
大乗起信論の「心」を「意識」にホンヤクするという井筒俊彦氏のレベルになると、哲学することあるいは思考することは、まさに"読み"の可能性を創造する営みへと高まる。
創造的な読みのためのホンヤク
ある言葉の意味が「わかる」/「わからない」というのは、この言葉通り「分ける」ということである。
わかるとは「分ける」ことであり、分けられたものを並べたり重ねたりすることができるということである。
一方「わからない」とは「分ける」ことができないということである。
分けられたり分けられなかったりするということは、ある言語を共有する集団の中で脈々と受け継がれてきた「分け方」のパターンに当てはまるかどうかという問題である。
◇
私たちは分ける。言葉によって分ける。
この言葉によって分ける働きをするのが、井筒俊彦氏が『意識の形而上学』で論じるところの「意識」である。「意識」は意味分節にして存在分節でもある「分節する」動きである。
この分節の動き方は個々人の意識や身体を超えた、人類史的な時空のスケールの中で進化してきたモノであり、ある個人において特定の形態をとって顕現したモノである。このモノを「超個人的」な「純粋叡智的覚体」と呼ぶ。
純粋叡智的覚体とは、ユングの集団的無意識であり「集団的アラヤ織の深層における無数の言語的分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個人的聯合体系である」(井筒俊彦『意識の形而上学』p.60)。
◇
ホンヤクというのは、この集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系を、いわば強制的に変身・進化させる技(ワザ)なのである。それはつまり、分かり方を変えるということである。
ある言語の体系(集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系)Aの中のあるひとつの語を、他の言語体系(集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系)Bの中のあるひとつの語に置き換える(ホンヤクする)。
そうすることで、次のような影響が生じる。
翻訳する=される語と語の結合は、それぞれの語がその内部に位置を占めるAの意味カルマの堆積の超個人的聯合体系(意味分節構造)とBの意味カルマの堆積の超個人的聯合体系(意味分節構造)との間に接触点、遭遇点を作り出す。
この接点の発生が引き金になり、AとBそれぞれの意味分節体系の中で、それまで相容れないものとして区別されていた二つのものが一つに圧縮されたり、それまで区別ができなかったところに新たな区別の線がひかれたりする。こうしてAとBそれぞれの体系が組み直され、変容し、進化する。
このホンヤクが発生させた接触点から意味分節体系の変容・進化が始まるように触発すること、これを井筒氏は「我々の言語意識を、間文化的、あるいは汎文化的、アラヤ織の育成に向かって深め」ることであると論じる。これこそが井筒氏の目指すところである。
心真如・心消滅
意味分節=存在分節のやり方は動くものであり、進化するものだということ。
それは日常という分節体系を固めることに特化した営みに邁進している私たち凡夫にはなかなか理解しにくいことであるけれども、なんとか頑張ってこのことを理解する鍵は、意識(心)を双面的なものとして捉えることにある。
即ち、意識(心)は、一面では絶対無分節の非顕現(未現象)態であるとともに、他の一面では有分節の現象態でもある、と考えるのである。
『意識の形而上学』で井筒氏は、前者の無分節態を「心真如」と呼び、後者の有分節態を「心消滅」と呼ぶ。
前者、心真如は、存在分節=意識分節以前(「無」意識)である。それは「存在がない=空っぽ」、「意識がない=空っぽ」ということではなく、分節化へと向かう傾向に充満した未分節である。
他方、後者の心消滅は存在分節=意識分節の世界である。これこそが「無数の存在単位の重々無尽に錯綜する有存在分節的存在世界」、つまり私たちの素朴な日常の「変異流転する現象的意識」とそれが経験する存在者たちからなる世界である。
※
この二つの面は、互いに無関係ではなく、無分節態が即、有分節態であり、非顕現態が即、現象態であるという関係にある。
無分節と(有)分節、非顕現と顕現は、あくまでも「ひとつ」のことの「ふたつ」の姿なのである。あるいは絶対的無分節の非顕現態は「現象的「有」への限りなき可能態としての「無」意識」であり、「「有」分節に向かう内的衝迫の緊張に満ちた「無」分節態」である。
「普通の平凡な人間の、日常的経験の世界に起滅妄動する煩悩多重の「有」意識が形而上学的永遠不動の「無」意識と「一にあらず異にあらず」という自己矛盾的関係で本質的に結ばれている」(井筒俊彦『意識の形而上学』p.73)
分節の有・無は、「一にあらず異にあらず」、一つのことでありながら二つのこと、二つのことでありながら一つのこと、一即二、二即一ということになる。
集団的言語阿頼耶識を育成する
絶対的無分節と有分節とが「矛盾的に合一」していると考えることで、おもしろいことになる。
即ち、私たちの日常の意識、堅固に他と区別されそれ自身の本質によって確固として現存していると感じられ信じられる事物たちに対する妄執に満ちた日常の意識が、他でもない「絶対的無分節の意識(心)が分節態の意識に転換」したものだということになるのである。
「「衆生心」は、現象面においては、「妄心」の乱動であって、その鏡面上に顕現する一切の存在者は、『起信論』的見処からすれば、悉く妄象だが、「衆生心」の本体そのものは、あくまでも洞然として清浄無垢である、という」(p.76)
私たちが生きている中で「分からない」よりは「分かる」ほうが良いことだと思われている。それは間違いない。いろいろ分かっている方が、分別がついているほうが、うまく生き延びることができるわけである。
ところがその「分かる」の先がある。分かった分かったと言ってある特定の分かり方に固まってしまうのは妄執ということになる。分かり方、分け方にはいろいろな可能性がある。わたしたち人類は、絶えず分け方を動かし、新たな分け方を試す余地に開かれているのである。
※
分け方を動かし、新たな分け方を試すこと。それは井筒氏の言葉を借りるなら「超個」の「集団的言語阿頼耶識を育成する」ということになる。これこそが人類の思考と知性の創造性、イノベーションということの鍵だったりするわけである。
そして何より、人類の歴史を顧みると、この分け方を動かし、新たな分け方を広め普及させたのは、孤独に孤立した個々人の頭のなかで生じる出来事であるというよりも、人と人の間で実際に言葉を物質化して移動するコミュニケーション・メディアの巨大な技術的システムだったのである。文字の発明しかり、印刷技術しかり、新聞、ラジオ、テレビもしかり、そしてインターネットもしかり。
そういう意味でいうと、昨今のAIによって接続がパーソナライズされるSNSというのは、「集団的言語阿頼耶識を育成する」という観点からして、はたしていかがなものなのだろうか? という話になるが、これは別のnoteに前に書いているのでぜひともご参考にどうぞ。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。
m(_ _)m
関連note
※
ここから先は
¥ 150
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
