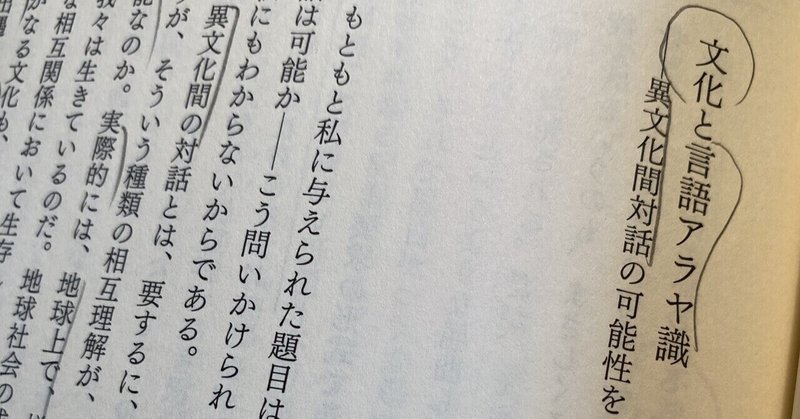
深層意味論入門-分別のつけ方を遊動させる - 井筒俊彦 著「文化と言語アラヤ織」を読む
(このnoteは有料に設定していますが、最後まで無料でお読み頂けます)
◇
井筒俊彦氏に「文化と言語アラヤ織ー異文化間対話の可能性をめぐって」という論考がある。『意味の深みへ』という一冊に収められている。
「異文化間の対話なるものが、そもそも可能であるのか否か」
と言う問いかけから始まるこの論考には、「言語」を、「コミュニケーション」をどうやって理解しうるかと言うことについてのエッセンスが詰まっている。
言語が現実を非現実ではない現実として述べ出す
言語はコミュニケーションの道具だと思われている。
実際にコミュニケーションの道具になる。
例えば「傘を持ってきて」と誰かに言えば、傘を持ってきてもらえたりする。「傘」という言葉は、拡がって雨水が身体に降り注ぐのを防いでくれる”あれ”のことを表すのだ、「みんな」が同じようにそう知っているのだ、と、私たちはしばしば思っている。
ところで言語を異にする外国の人などとの交流経験が豊富な人であれば「みんな」が”あれ”を「傘」と呼ぶわけではないと言うことも知っているはずである。日本語を解さない人に対して「傘を持ってきて」とお願いしても、何も持ってきてもらえない可能性が高くなる。さまざまな言語が”あれ”をさまざまな音声で呼び、文字で書く。
それでも雨を遮りる"あれ"は”あれ”であり、"あれ"を「カサ」と呼ぼうが、「アンブレラ」と呼ぼうが、"あれ"が”あれ”であることは絶対に揺るがない、そう考える向きもある。さまざまな言語は"あれ"に対してぞれぞれ違った音の「ラベル」を貼り付けているだけで、ラベルさえうまく張り替えれば「翻訳」ができて、コミュニケーションも成功するはずだ、と。
※
ところが、である。
井筒俊彦氏が論じているように、20世紀の言語論(学)的転回と呼ばれる思想の潮流に大きな影響を与えたソシュールの言語論や、それを1000年以上も遡る例えば華厳哲学などの言語論などでは、言葉を"あれ"に貼り付けられるなんでも良いラベルのようなものだとは考えない。
そこで言葉は、意味分節作用として考えられる。
意味分節作用。つまり言葉とは、区別をすること、分節をすること、である。
「地球上に存在する諸言語の一つ一つが、それぞれ独自の「現実」分節の機構を内蔵していて、それが原初的不分節(未分節)の存在をさまざまの単位に分節し、それらを人間的経験の色々な次元において整合し、そこに一つの多層的意味構造を作り出すのである。」(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.156)
言葉がいくつもの区別を繰り出す。
その区別する作用と、その作用の結果として残されたものともの同士の区別と対立を材料にして、私たちは私たちにとっての「現実」を意味ある対立関係から成り立つ世界として経験するようになる。
「現実」は一つのテクストだ。「現実」は初めからそこにあるものとして、客観的に与えられたものではなく、人間が言葉を通じて有意味的に織り出していく一つの記号空間である。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.178)
「現実」の手前に言葉がある。
「現実」と「非現実」とを区別しているのが言葉である。
現実が言語と関わりなくまずそれ自体としてあって、それにラベルのような言葉が貼り付けられていくとは考えない。「現実が先にあって、言語が後から付随する」という順番では考えないのである。
最初の一撃を加えるのは言語である。というか、言語として現象すると捉えられることになる、分別、分節化、区別すること、などと呼ばれる出来事である。
分別、分節化、区別すること。その後に、分節された項目たちの関係の網の目として、「言語」と「現実」の両方が、それぞれ影のような姿を現すわけである。
分節すること。そのシステムの表面構造と深層構造
現実もまた分節作用の産物である。
それは、私たちが、言葉のかたまりとしての「言語」の中に閉じ込められているということを意味するのだろうか?
「言語」によって作り出されたイリュージョンのあれこれを、現実だ非現実だと言いながら、喜んだり汲々としたりしているのだろうか?
言語の檻を抜け出して、その外に広がる「本当の現実」に辿り着くことはできないのだろうか?
この問いに対する答えは、全て「イエス」でもあるし、「ノー」でもある。
「イエス」であれ「ノー」であれ、「問い」を構成する言葉の塊を是非の対立関係のどちらかに置き換えることができるというのは、この問いも、またその是非も、ある言葉の分節体系を前提にしているからである。
「イエス」でも「ノー」でも、そう言うことを言えるのは、ある一連の言葉として顕現する分節作用の組み合わせの中で、論理として矛盾なく成立すかどうかという話である。
「本当の」などと言って、それをイエスとノーの対立のどちらに置き換えるかを考えようとすること自体が、「本当」と「本当ではない」を区別し、「イエス」と「ノー」を区別し、その二つの区別をどちらの方向で重ねようかと思案していると言う、あまりに言語的な仕業である。
※
華厳哲学を含む仏教の考え方では、この区別すること、分節すること、分別することこそが、生死を隔絶させ、自他を隔絶させ、人と恐怖と欲望の渦に苛まれるよう追い込むのだと考えたのである。
「東洋哲学の諸伝統を通じて、根深い言語不信が働いていることは注目に値する。…コトバの意味表象喚起作用に謀られた人間意識の「妄念」すなわちコトバの生み出した現象的多者を、客観的にそのまま実在する世界と思い込む人間意識の根本的な誤り、を打破して、その基礎の上に、絶対無分節者の立場から見た分節的世界の真相を、改めて捉えなおそうとする試みなのだけれど、…この「妄念」を打ち破るには手間がかかる。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.167)
先ほど言語を「その中」に、私たちを「閉じ込める」「檻」などと表現したけれど、果たして私たちが言語を通じてはじめて「現実」を作り出していると言うことは、そういう箱の中に閉じ込められている的な状況としてイメージして良いのだろうか。
このイメージは、一面では確かにそれらしいが、実はそれは一つの見かけ上のことである。
なぜなら、言語は二つの様態を持つのだから。
言語の二つの様態。井筒俊彦氏はそれを表面構造と深層構造と表現する。「面」と「層」の使い分けが鍵である。
だが、コトバには、いま述べたようなアラヤ識的基底がある。コトバを社会制度としての言語(ラング)の側面だけに限定してみる人は、言葉の表面構造だけしか見ていない。そこには慣習的な意味を担う慣習的な記号のシステムがあるだけだ。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」p.178-179)
言語の表面は「使い古されて色褪せた記号のコード」の体系として見え、「ほとんど化石化した意味の構成する、固くかたまった動きのとれないシステム」に見える(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.179)。確かにそれは、私たちを閉じ込める檻のようだと言っても言い過ぎではなさそうだ。
しかし、私たちが「傘」「傘」と言って、簡単にコミュニケーションをすることができるのは、まさしく言語のこの表層構造が安定し、固まっているからに他ならない。言葉の表層構造の見かけ上の安定性が、予測可能で効率的なコミュニケーションを可能にしている。
言葉が分節作用としてのその正体ではなく、効率的でスマートなコミュニケーションの手段・道具としての仮の姿を表すのは、この見かけ上の安定性においてである。
言語の深層構造
しかし、言葉には深層もまたある。
この深層は「アラヤ識的基層」とも呼び変えられる。
言語の深層は「創造的エネルギーにみちた意味マンダラの溌剌たる動き」に満ち溢れている(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.179)。
創造的で、溌剌たる動き。これは人を閉じ込め縛り付け身動きできないよう固めてしまう何かとは、ずいぶん様子が違う。
井筒氏は次のように書く。
そしてこの全体的意味マンダラの一領域として眺められる時、一見、制度化され、因習化し、枯渇し切ってしまったかのように思われていた「外部言語」すら、意外な生命力を示しはじめるだろう。なぜなら、コトバの表層構造も、本当は、アラヤ織それ自体の外化形態に他ならないのだから。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.179)
表面構造も深層構造も、どちらも同じひとつの言語の生き生きとした躍動が示す二つの影である。表面構造と深層構造は、別々の二つのものではない。あくまでもひとつの事柄であり、一つの事柄が見せる二つの顔なのである。
表面と深層、固まっていることと動いていること。
この区別は、「良い」と「悪い」の区別とは関係がないことである。
表面のコミュニケーションと、深層のコミュニケーション
言葉を表面構造と深層構造の二つの姿で捉えることは、特に「コミュニケーションが成立しない」と言われるような状況にあって、強力な思考の力を授けてくれる。
何をどう言っても話が噛み合わない。
懇切丁寧に説明し、説得しているのに、わかってもらえない。
私たちの日常は、リアルでもバーチャルでも、そんな場面で溢れている。
特にSNSなどでは、双方とも良かれと思って自分の信じることを言葉に出している人たちの間で、言葉のやりとりが「コミュニケーション」どころか殺傷力を持つほどの罵詈雑言の応酬にもつれこんでしまうこともある。
こうしたコミュニケーションが不可能なのではないかと思われるところで、言葉をその表面構造ではなく、深層構造を動的に生成し続ける分節作用として思考することが力を与えてくれるのである。
[…]しかし、もし我々がコトバの深層領域に気づき、それに注意を向けるなら、文化の本源的言語性に関する我々の見方は根本的に変わってしまうだろう。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.179)
コミュニケーションには、表層のコミュニケーションと、深層のコミュニケーションの二層がある、と考えると良い。
私たちがしばしば直面する「話が通じない」型のコミュニケーション不全は、表層のコミュニケーションで生じる。互いに言葉を交わし合い(時に投げつけ合う)二人の間で、それぞれが寄って立つ言葉の分節体系が異なっているのである。
しかも厄介なことに、「愛」でも「自由」でも、なんでも良いのだけれど、ある一つの言葉だけにフォーカスしてみると、それは音声の上でも字面の上でも、二人の間で「同じ」なのである。
しかし、字面の上では「同じ」「一つ」の語でも、二人の人の間では、その「語」がどういう対立関係の重ね合わせ(対立関係のネットワーク)の中で、どのポジションを占めるかが異なる。
この二人は、ある一つの同じ言葉を用いて「同じこと」を論じているようで、全く異なった対立関係のネットワークを動かしているのである。それでは話が通じないのは当然である。
そこでは語は、表層のシンボルとしては「同じ」であるけれど、意味が全く異なるのである。
※
ちなみに「意味(意味する)」とはどういうことかについては、こちらのnoteに詳しく書いたつもりである。
※
一方、深層のコミュニケーションとは、二人の人の、二つの異なる分節体系が衝突すると同時に接続され、双方ともに一度ガラガラと崩れ落ち、そして元とは別の体系に組み立て直されることである。
「異文化の接触とは、…異なる意味マンダラの接触である。…意味マンダラは、特にそのアラヤ織的深部において、著しく敏感なものだ。刻々に生滅し、不断に遊動する「意味可能体」は、それ自体において既に、本性的に、限りない柔軟性と可塑性とを持っている。まして、異文化の示す異なる意味マンダラに直面すれば、鋭敏にそれに反応して、自らの姿を変える。(井筒俊彦「文化と言語アラヤ識」全集第八巻P.181)
分節すること、区別すること。
それはあくまでも「すること」であって、何か固まった出来合いの「もの」ではない。分節すること、区別することは、動きである。常に動き続けている。
動きであるが故に、それは「本性的に」「柔軟性と可塑性」を持つのである。
水面の波紋を思い浮かべていただくと良い。
ある同心円を描く一つの波紋に、別の波紋がぶつかると、二つの波が新たな構造を描き出す。区別することは、そのようにして、ちょうど波の高いところと低いところの区別が動き続けるように動き続ける。
表面のコミュニケーションを、出来合いの固まった分節体系を棍棒のように使って「殴り合う」ことだと比喩的に言うならば、対する深層のコミュニケーションは、常に動き続けている二つの分節作用のさざ波を共鳴させることである、と言えるかもしれない。
まとめ
今や言葉は「ビッグデータ」の一つとして、人間による読み書き解釈を介さずにアルゴリズムによって変換されたり配列されたりするものになっている。
今や言葉は、「同じ人間同士」のコミュニケーションから、多数の「異文化」の人間の間のコミュニケーションへ、そして従来は「人間」からはっきりと分け隔てられていた「機械」のような他者とのコミュニケーションに巻き込まれている。
あるいは地球環境の壊滅的な変容は、人間を、これまた従来は「人間」からはっきりと分け隔てられていた「動植物」や「自然」とのコミュニケーションへと誘っている。
そうなるとますます、分節すること、区別すること、分別をつけること、その「やり方」を柔軟に動かし続ける余地を、私たちは保ち続けなければならないということになる。それも「忙」しい日常のさなかでそうしなければならないのである。
いかがでしたでしょうか。
最後まで到達していただき、ありがとうございます。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。
m(_ _)m
関連note
◇
ここから先は
¥ 100
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
