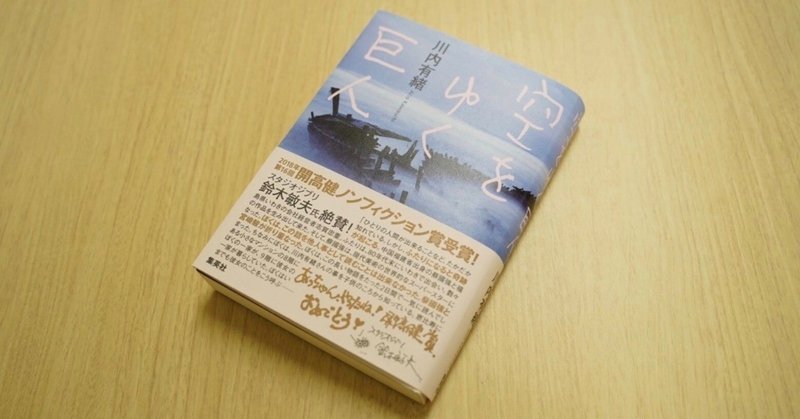
全文公開『空をゆく巨人』 第六章 時代の物語が始まった
第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第六章です。
第六章 時代の物語が始まった(いわき・一九九三年)
海に火を走らせる
「志賀さん、藤田さん、せっかくだから、しばらくいわきに住んで作品をつくりたいと思います」
「それ、いいですね。では、家を探しましょう。どんな家に住みたいんですか?」
「山の上にあって、海が見える家がいいです。庭では菊の花を育てたいです」
日本に来て七年、蔡は三六歳になろうとしていた。
志賀は、その希望に沿って家を探したが、海が一望できる庭つきの貸家なんてそう簡単に見つからない。方々に聞いてまわると、いわき市の北部、四倉(よつくら)に、普段は使われていない家があると耳にした。訪ねてみると、崖の上に建ち、海に向かってひらけた眺望がすばらしい。家主に頼むと、快く借りられることになった。
「いやあ、ここは、いいですねー! 希望通りです」
喜んだ蔡は、個展の四ヶ月前となる一九九三年の一一月に、単身でいわきに引っ越してきた。
一九八四年に開館したいわき市立美術館は、現代美術に力を入れ、イヴ・クライン、アンディ・ウォーホルなどのコレクションが充実した美術館である。そんな特別な場所に向けて気合いが入った蔡は、溢れんばかりのアイデアを携えていわきに来ていた。
「海の沖合に、火を走らせたいのです」
引っ越しの直後、丘の上の家に志賀、ギャラリーいわきの藤田など数人の仲間が集まっていた。蔡はすぐに作品の構想を説明し始めた。
志賀の記憶によると、説明はこんな感じだったそうだ。
「万里の長城でやったことを、今度は海でやりたいんです。沖合で火薬を爆発させて、炎によって地球の輪郭を描きます。水平線に炎が上がると、火が地平線を形づくるのが見えますね。暗いほうがいいので、新月の晩にやりましょう」
たぶん実際の説明は、こんなに洗練されていなかったはずだ。のちに放映された『ズームアップ福島 地球の輪郭を描く』(NHK)というテレビ番組のなかで、蔡はこんなふうに説明している。
「夜、真っ暗になった闇のなか、向こう側から点火して、一瞬のうちに、一本の微妙な光、スーっと。地球の輪郭をきれいに見えるように出す、というプロジェクトです」
もはや美術館のなかですらない〝作品〟に、人々は、へえ、面白そうですね、と答えるしかなかった。たぶん、誰もそれがどんなものかは想像できていなかったのではないかと志賀は振り返る。
何はともあれ、その構想は「地平線プロジェクト」と名付けられた。普通ならば「水平線」と呼びそうなものだが、描くのは地球の輪郭なので、「地平線」である。
内容はさておき、問題は予算だった。
計画のスケールは桁違いで、少なくとも数千万円の予算が必要だろう。しかし、いわき市立美術館が用意した予算は二〇〇万円。
予算が少ないなら、それに見合った作品をつくる、という発想は蔡にはなかった。どんなに予算からはみ出しても自分がやりたいことをやる、それしか考えていなかった。しかし、小さな子どもを抱えた蔡の生活も非常に苦しかった。年を追うごとに作品の規模が大きくなるわりに、収入は少ないままだった。
さらに、いわき市立美術館に「地平線プロジェクト」のアイデアを話すと、美術館の外で行われる野外プロジェクトにまでは予算がまわせないという。しかし、志賀も蔡もそこで「はい、そうですか」と引き下がる人間ではない。かわりに、志賀たちは、「地平線プロジェクト実行会」を立ち上げた。「必ず実行する」という決意を込めて、あえて「実行会」と名付けた。中心メンバーは、藤田や志賀の他、数名。そして、美術館内に設置される作品に関しては美術館が、地平線プロジェクトは「実行会」が責任を持つという線引きを行った(だんだんとこの線引きも曖昧になっていくのだが)。
それでもさすがに心配だったと志賀は振り返る。いまのところ、地平線プロジェクトの予算はゼロ。この状況で、無謀ともいえるプロジェクトを実現するには、一般市民から多大な協力を得なければならない。要するにタダで手に入れなければいけないものが山ほどあるのだ。しかし、いわきの市民は「芸術なんて、わがんね」「ボランティアって何だ?」という人がほとんどである。いや、何もいわきだけではなく、まだ日本に地域芸術祭がほとんど存在しないこの当時、美術制作ボランティアという概念もまだないに等しかった。
そこで、志賀はこう説いた。
「蔡さん、やっぱり『芸術は難しい』と思われてしまってはダメだあ。何かわかりやすい言葉で説明でぎねえかな」
蔡はすぐにその意図を汲み、翌日には短い言葉を紙に書きつけてきた。
この土地で作品を育てる
ここから宇宙と対話する
ここの人々と一緒に時代の物語をつくる
たった三行に、作品への想いがシンプルに力強く表現されている。とりわけ、「ここの人々と一緒に」という言葉が良いと志賀は思った。
「いいですね、蔡さん。これでいきましょう」
その言葉を頼りに、実行会メンバーは周囲に協力を呼びかけはじめた。
ジュピター
当の蔡は、あくまでも自分のペースで物事を進めた。アイデアのスケールは大きいものの、カリスマティックに周囲を駆り立てるタイプではない。朝起きると、まずはコンビニで買ったおにぎりとコーンスープを食べる。中国では冷めたご飯を食べる習慣がない。おにぎりを食べるためには、温かいコーンスープが欠かせなかった。
「お金の余裕はなかったはずだけど、蔡さんからは、悲愴感のようなものはまるで感じなかった」
と、いわき市立美術館の平野は言う。
しかし、「地平線プロジェクト」はすぐに暗礁に乗り上げた。何しろ、「水と火」という科学的矛盾に満ちたアイデアである。
「蔡さんが、海で何かやりましょうっていうくらいだから、色々やり方を知ってるのかと思ったら、何も知らないんだもんなあ!」と志賀は、懐かしそうに苦笑する。
当の蔡は、何ら根拠のない持論を展開した。
——プラスチックの容れ物に火薬を入れて、次々と爆発させたら、もちろんプラスチックは割れて水は入ってくるんだけど、火は水よりも速く進むでしょう。だからきっとうまくいくでしょう。
——うーん、蔡さん、さすがにそれは無理があるんじゃないか。
こんなトンチンカンなやりとりを前に、先行きを不安に思ったふたりの実行会メンバーが早くも去っていった。
志賀は、いまや大好きな仕事すらも手につかなかった。この当時の志賀は、あるカー用品の卸売販売に力を入れていた。アメリカで開発された特殊な車体の保護剤で、一度塗布すればその後五年間ワックスをかける必要がないというのが売り文句の商品だ。
志賀がこの商品に出合った経緯も、なかなか面白い。商品輸入元のC社の営業マンが、東北機工が携帯電話をたくさん販売していると聞きつけて、会社を訪ねてきたのだ。
「八年前にこの外装保護剤の輸入を始めて、色々なカーショップで売っているけれど、あまり販売が進まない。特に東北での営業が伸び悩んでいます。よかったら商品を売ってくれませんか」
話を聞いた志賀は、ワックスを塗ったり、洗車したりせずにすむならば環境にいいだろうと考え、「いいですよ」と答えた。それまで培ったノウハウを体系化し、営業してみると、すぐに手応えを感じたので、本腰を入れていた。
しかし、その営業活動すらも、ここのところ一時停止ボタンが押されていた。志賀は、いつでも自分の心の羅針盤が指す方角に忠実だ。いまの羅針盤が指す先にあるのは、地平線プロジェクトだった。
「おーい、蔡さーん! おはようございます!」
朝起きるなり、崖の上の家に向かい、玄関に大きな声をかけた。
蔡が玄関口に顔を見せると、「さあ、今日は何をする?」と尋ねた。蔡は、よく凍りついた階段に足を滑らせながら、車に乗り込んだ(「何度あそこで転びそうになったかわからない」とのちに懐かしがった)。
「よし、いくべ!」
志賀がエンジンをスタートさせると、車中にはいつもホルストの「木星(ジュピター)」が流れていた。「木星」は、当時から現在に至るまで、志賀が好きでやまない管弦楽曲だ。のちに歌手・平原綾香が歌詞を乗せて歌い(『Jupiter』)、大ヒット。広い宇宙で星と星が奇跡的に出会い、夢を追いかけることのすばらしさを歌うこの曲は、できすぎなほどふたりにぴったりな一曲であった。
船の墓場を見つけて
個展の準備が始まると、蔡は「作品のために廃船が欲しい」と話した。それも大昔に使われていた木造の船がいいという。
「そう、船け? じゃあ、探してみっか」
志賀は、四倉港に車を向けた。
船は、蔡の作品にたびたび登場する代表的なモチーフのひとつである。海のシルクロードの玄関口で生まれた蔡は、夥(おびただ)しい数の木造船が港に出入りするのを見ながら育った。いわきも同じく港町だが、すでに木造船は姿を消し、金属製の船にとって代わっていた。その過去のものとなった木造船を、いわきの象徴として復活させたいという。
志賀たちが四倉港に着くと、ちょうどよく木造の漁船が打ち捨ててあった。造船所の職員に、「あの船が欲しいのですが」と頼むと、「持ってってええど」と答えた。船首部分はすでに切り取られていたものの、保存はされていたので、復元することはできそうだ。「しばらくとっておいてください」と頼み、港をあとにした。
後日、船を引き取りに行って、あっと驚いた。船首部分がなくなっているではないか。
「邪魔だから燃やした」と造船所の職員はあっさりと言う。これでは、もう作品には使えない。
蔡は端から見ていても気の毒なほどにしょんぼりと気を落とした。
「大丈夫ですよ。なくなってしまったのは、もっと良い素材を見つけるためだったんですよ」
志賀はそう声をかけ、一緒に漁港をまわった。この一帯には、全長六〇キロにも及ぶ海岸線に多数の港が連なっている。木造船のひとつやふたつくらいまだどこかにあるはずだと車を走らせた。しかし、いくら聞いてまわっても、もはや木造船はどこにもなかった。
あれは、奇跡的な一艘だったのかもしれない……。
志賀も港をひとつあとにするたびに、焦りを募らせた。残るは、小名浜(おなはま)港だけだった。福島県最大の港で、漁船から国際コンテナ船まで多くの船が出入りする。
そうだ、小名浜といえば、あいつがいるじゃないか。
志賀は、ある人物の顔を思い浮かべた。成人学校時代の友人で、潜水作業専門の会社「ナポレオンエンタープライズ」を経営している佐藤進である。志賀は、佐藤の会社に立ち寄ることにした。急な訪問にもかかわらず佐藤はふたりを歓迎し、お茶を出してくれた。
「木造の廃船を探してるんだ、どっか知らねえが?」
そう話すと、佐藤は「そんな廃船なんか、何ぼでもあるど」とあっさり答えた。
場所は、すぐ近くの神白(かじろ)海岸だという。蔡は「すぐに行ってみましょう!」と声をあげ、佐藤を案内役にして車を飛ばした。
すでに日が暮れ、辺りは暗かった。
打ち寄せる波の音だけが、ザザーン、ザザーンと鳴り響いていた。
懐中電灯で足元を照らしながら歩いていると、砂のなかに巨大な物体が埋もれている。
「おおお! 船だぞ、あったど!」
志賀は喜びの声をあげた。
それは、かつて漁師たちと一緒にカムチャツカ半島まで旅した北洋サケマス船だった。
まだ木造の船が主流だった昭和初期、漁師は不要になった船からエンジンや油を抜き取り、重りとともに沖に沈めた。その後、時間が経つうちに、潮流の関係で多くがこの浜に流れついたのだ。数えれば、一〇艘以上あるようだ。
それはまるで、船の墓場だったと志賀は言う。
夜の浜辺に、珍しく興奮した蔡の声が響いた。
「これですよ、私が欲しかったのは、これです!」
長い一日だった。
ふたりは、ああ、良かった、と志賀の自宅に寄って休憩した。窓の外では雨が降り始め、まもなく嵐の様相を呈してきた。すると、蔡はそわそわし始めた。
「波で船が流されてしまいませんか。心配です」
「いやあ、大丈夫だろう」と志賀は言ったが、蔡は「うーん」と黙り込み、心配そうに窓の外を眺め続ける。
落ち着いて考えれば、何十年も砂浜に埋まっていた船が簡単に流されるわけがない。そう論理的に説明して蔡を納得させることは、難しくはなかったはずだ。しかし、やっとのことで見つけた船を心配する気持ちに、志賀は寄り添ってあげたかった。
「じゃあ、ロープで固定しに行こうか」
「そうしましょう!」
ふたりは雨のなか車を飛ばし、神白海岸に戻った。風雨はますます激しさを増し、全身ずぶ濡れになりながらロープを船にかけ、消波ブロックに繋いだ。蔡は「これで安心ですね」とようやくほっとした表情を見せた。これじゃあ象を糸で繋ぐようなもんだなと志賀は思ったが、口には出さなかった。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします
導火線、重機、ビニール袋など、入手すべきものはまだまだあった。蔡が新たな作品の構想を出すたびに、志賀はそれを持っていそうな人を探し出し、無償で提供してくれないかと頼みにいった。深々と頭を下げながら、「お手数をおかけしますが、よろしくお願いします」と繰り返す。それを見た蔡は、「志賀さん、あの言葉を教えてください」と頼み、それからはふたり一緒に「お手数をおかけしますが……」と言うようになった。蔡の日本語のボキャブラリーはそう多くはなかったが、できる限り自分の言葉でも語りかけた。
「そこの人々と一緒に対話して、作品、たくさんつくる。おそらく、それは、いいなと思います」
そのあまりの熱心さに多くの人が「よおし、わがった」と快く応じてくれた。
志賀は、どうやったら人々に快く楽しく協力してもらえるかを考え続けた。何ごとも楽しくなければボランティアでやる意味がないというのが、志賀の信念である。
そこで思いついたのは「記録」だった。ここで、二〇年以上にわたり志賀や蔡の活動を映像に収めることになる、名和良(なわまこと)が登場する。名和が経営する「映像記録社」は、東北機工の真向かいにあった。ある日突然、顔見知りの志賀が訪ねてきた。
「おーい、名和くん、プロジェクトの記録を撮ってほしいんだけど」
そのときの志賀は、髭をぼうぼうに生やし、「まるでガオー、ガオーと吠えるライオンみたいだった」と名和は言う。ライオンは、熱心にプロジェクトの説明をし、「無理をしなくていいんだ、名和くんが来れるときだけでいいんだ」と言った。
「いやあ、もしお金を出せって言われたらたぶん断ったけど、ビデオ屋はビデオを撮ることはできるよなって思いました」(名和)
こうして、展覧会の準備の合間には、それまでに撮影、編集されたビデオを囲んで「上映会」が開かれた。おいしい料理や酒が振る舞われ、志賀は協力者の労をねぎらった。ビデオを見て「あ、○○さんが映ってるよ」「ああ、こんなことがあったねえ」と盛り上がると、それまでの苦労は楽しみに変わった。こうして、誰かがきちんと見ていると感じると、人はより頑張れるものだ、と志賀は言う。
同じように志賀は、写真家の小野一夫にも記録写真の撮影を頼んだ。スタジオでの広告写真の撮影を中心にしていた小野は、「スナップ写真は得意分野ではないし、仕事も忙しいし、ちょっと大変だなあ」と思いつつも引き受けた。「おいしいご飯」と「活動の記録」。それらは、このあとも志賀が大切にし続けるものである。
砂浜に埋まった船を引き揚げるのは、とりわけ大変な苦労だった。潜水会社を営む佐藤進は、地元の建設会社「大木土建」の社長を連れてきた。志賀たちが、「すみませんが、ボランティアでお願いします」と言うと、大木は「よし、わがった」と快く引き受けた。
建設会社の社員たちは、ショベルカーなどの大型重機を砂浜に持ち込んだ。佐藤もウェットスーツを着込み、冷たい海に胸まで浸かりながら、引き揚げの陣頭指揮をとった。
「蔡さんも、シャベルで掘ったり、できることを手伝ってくれたよ」と志賀は言うが、手伝うという言い方も妙なものだ。
関係者が見守るなかで、大木は何時間もショベルカーを操作したが、船はビクともしない。大量の砂や水を含んだ船は、予想よりもずっと重たかった。
「どうやっても掘り出せなくて、どうすっかと思ったら、翌日、大木さんは、もっと大きな重機を持ってきてくれたよね。人間ってさあ、お金じゃなくて、その人の能力が発揮できれば一生懸命やるんだなって思ったね」(志賀)
冷たい海風で体が冷えるので、傍らで火を焚き、豚汁で温まりながら作業を続けた。紅虹も、手製の水餃子やスッポン料理を手にして、四歳になった娘の文悠を連れて浜辺までやってきた。
「それは、それは、おいしかったよねえ。あれで、すっかり胃袋をつかまれちゃった」と一日中ビデオ撮影をしていた名和は笑う。
翌日は、船の舳先(へさき)に穴を開けてロープをかけ、巨大なショベルカー二台で船を引っ張った。
「よーしいけ! よーしいけ!」
佐藤が大きな声をあげる。ショベルカーはじりじりと動き続ける。
ついに、ようやく十数メートルもある船が、打ち上げられた鯨のように姿を現した。重さは、約九トン。
しかし、ここからがまた大変だった。船を運ぶには、いくつかの塊に解体しなければならないが、船のなかには砂がぎっしりと詰まっていて、チェーンソーでは簡単には切れない。砂を水で洗い流し、何度もチェーンソーの刃を研ぎ、船を切断していく。しかし、ただ無闇に切り刻むわけにはいかなかった。木造船というのは複雑な構造をしていて、木材の強度と柔軟性を巧みに利用することで絶妙なバランスを保っている。不用意に切断すると二度と復元できなくなる恐れがあった。そこで木の特性を知り尽くした地元の宮大工と年老いた船大工が作業に加わった。
冬の海風で震えながら、一同は夜を徹して作業を続けた。もはや蔡はただ見守ることしかできなかった。結局、引き揚げと切断作業には一週間を要した。すべての作業が終わったあとに、蔡が建設会社の大木にお礼を言うと、笑いながらこう答えたそうだ。
「何だ、〝ボランティア〟っていうのは、カネもらわないことだったのか、はっはっは」
芸術は寒いんだなあ
蔡は、家の庭で栽培した菊を煎じてお茶にして出したい、さらに、その茶器を地元の土からつくりたいという計画も温めていた。
「中国では菊の花をお茶にして飲むんですよ。菊は目にいいんです。飲んだら(地平線も)よく見えるようになりますね。だから、お茶をつくって展示で出しましょう」
そこで協力を頼まれたのが、茨城県在住の陶芸家、真木孝成(まきたかしげ)だった。真木は初め、ボランティアに参加する気はなかったが、蔡と志賀の話には耳を傾けた。
「昔の雰囲気で、荒っぽい感じの茶器をつくりたいです」という蔡のイメージを聞くと、「それだったら、こんなふうにしたらどうか」とアドバイスをした。すると、満面に笑みを浮かべ、「いいですね、真木さん! それでは、その感じでつくってみてください」と言うではないか。
アーティストなのに、自分でつくらないと作品にならないのに、と思いながら、真木は茶器の制作に同意した。気がつけば真木自身も、蔡が持つ不思議な魅力に吸い寄せられていた。(『蔡國強通信』Vol.6)
後日、真木は二〇ほどの茶器や土瓶、火鉢を仕上げた。それは、蔡のイメージ通りだった。
こうして、多くの人の好意を借りて、展覧会の準備は進んでいった。蔡は、色々な人に支援を頼みにまわる日々は、「人生の修行だった」と振り返っている。
それにしても、のちにアーティストとして大成功する蔡にとっては「修行」でもいいが、志賀にとってはどうだったのだろう。いい年をした男が自分の仕事を投げ出して、さして興味もないアート作品の制作に勤(いそ)しむなど、なかなか理解に苦しむ。そんな疑問をぶつけると、志賀はこう答えた。
「絵の才能っつうのは、俺にはわがんねかった。でも、面白いんだよ、蔡さんが。いろんな壁にぶつかるよね。でも全然めげない。それも条件のひとつとして、さらに発想を広げてくんだ。諦めたり縮小するってことはなくって、アイデアが無尽蔵って感じだよね。俺は、どうやって金をかけないで実現すんのかをずっと考えてんだ。それを考えんのが楽しいんだ!」
どうやら、志賀にとっては、修行というよりも、楽しい時間だったようだ。見返りを求めず、人のために方々で頭を下げ、苦行すらも楽しみに変化させる、それは稀有(けう)な才能だろう。もしかしたら、長く訪問販売をしていたこととも、関係しているのかもしれない。「苦越」と横尾が書いたように、苦しみの先にこそ、何かかけがえのないものがあると志賀は信じていたのかもしれない。
同時に、志賀は人の才能にとことん惚れ込む。以前の志賀は、横尾のモノを売る才能に惹かれた。同じく今度はアーティスト・蔡の発想力に惹かれた。そういうずば抜けた個性と能力を持つ人々と一緒に何かをすることは、志賀にとっては喜びなのだ。
しかし、「楽しかった」という感覚は、大勢のいわき市民も同じだったのかもしれない。壁にぶつかるたびにみんなで頭を突き合わせて相談した。蔡は、人々の意見を聞くなり、すぐにアイデアを柔軟に練り直し、筆ペンで描かれた図面を持って嬉々として現れた。
やがて五〇〇〇メートルにも及ぶ気が遠くなるような導火線づくりも始まった。まだプロジェクト資金が不足していたので、市民に「導火線を一メートルあたり一〇〇〇円で買ってください」と呼びかけ、何とか制作にこぎつけた。
作業場は、山のなかの工場跡地。「短時間の参加でも大歓迎」という自由参加にしたので、多くの人が仕事の合間にやってきた。
「とにかく寒がったなあ」と現在六〇代となった米屋の女性はしみじみと思い出す。大量の火薬を使うので火気は厳禁。かじかむ手で、導火線をビニールにくるむという単調な作業が続く。それでも、現場の雰囲気はわいわいと明るかったそうだ。
「何だ、芸術ってのは、寒いんだなー!」
「んだなあー!」
そんな冗談でわはははーと笑いあい、夜になると温かいカレーを食べた。しまいには、美術館の館長や取材に来たテレビ番組のスタッフまで作業に参加した。結局、入れ代わり立ち代わり、のべ数百人が作業に関わり、終わるまでに二週間を要した。
そんな市民の輪の外には、環境破壊などを理由に地平線プロジェクトに反対する住民もいた。ある日、新聞社や美術館、そして蔡宛てに「プロジェクトを中止しろ」という怪文書が送られてきた。今回、方々に取材をするなかで、その怪文書をまだ保管しているという人がいた。見せてもらうと、便箋にして何枚にもわたる脅迫ともとれる文章である。対応に苦慮する関係者を前に、当の蔡は「反対者も参加者ですね。大事にしたほうがいいです」と話した。
学芸員の平野は、そんな蔡の仕事の進め方をこう評している。
蔡のプロジェクトは様々な矛盾と混乱を内部に保留したまま進行していく。それは一つ一つ整然と筋道に従い物事を積み上げていくスタイルとはまるで程遠いもので、様々な異分子さえもプロジェクトを成立させるに必要な要素として扱われる。蔡において矛盾は矛盾として肯定され、混乱が生み出す無秩序でさえそれは世界にとっての必然となりえる。
(『蔡國強—環太平洋より—』)
これは、実に興味深い考察である。普通ならば、何か目標がある場合、それを達成するために必要なスキルや人を集めよう、そして逆に達成を阻害する要因は排除しようと考えがちである。しかし、蔡にとっては、出会った人、居合わせた人のすべてが、作品を成立させる要素となるのだ。この世界は混沌としており、コントロールなどできないことを蔡は受け入れ、むしろ喜んで混沌に身を委ねていた。
海の沖合を走った仄かな火
そして蔡がいわきに移り住んで四ヶ月後となる一九九四年の三月六日、個展『蔡國強—環太平洋より—』はめでたく初日を迎えた。蔡があまりにもたくさんの作品をつくったので、階段の隙間やエレベーターのなかすら展示場所として利用された。
エレベーターのなかにあったのは、《平静的地球》というインスタレーション。ユニークなコンセプトで、「いま考えると、相当に時代を先取りした作品ですね」(平野)。
エレベーターの壁はすっぽりと紙で覆われ、壁には宇宙から撮影された地球の写真を映し出す不思議な装置が据えつけられていた。写真は宇宙から見た夜の地球の姿で、人間の営みがある都市部だけが電気の光で実際に輝いて見えるように細工されている。
誰かがエレベーターに乗り、ドアが閉まると同時に写真のなかの地球の電気がフッと消え、地球は闇に包まれる。そして、二秒が経過すると、いつもの光溢れる地球に戻るという作品である。蔡がこの作品にあてたメッセージは以下の通りだ。
人間が作り出す明かりのためにこの1000年間に、地球の膨大な資源が使われてきた。2秒間だけ、地球を休ませ人間が地球に夜を返す。人間が地球に宇宙を返す。地球は宇宙のほとんどの惑星と同じように静になる。この国際的な共同作業により地球はひとつになり、そして地球は時空を越え千年前、万年前、原初の時と同じように過去と連結する。1999年12月30日PM24時59秒〜2000年1月1日0時1秒の間に、地球の光を2秒間消す。宇宙からみると地球は真っ暗になる(筆者注:本来二秒間であれば「31日23時59分59秒」が正しいと思われる)。
(「蔡國強「平静的地球」へのメッセージ」『蔡國強—環太平洋より—』)
地球は疲弊しきっている。そこでほんの一瞬だけでも人類がすべての明かりを消し、地球を休ませてあげようと呼びかけているのだ。
さらに展示室をまわれば、あの苦労した廃船も凛(りん)とした姿で立っていた。外側の板を取り去られた船は、いまや「龍骨(りゅうこつ)」と呼ばれる骨格を露(あらわ)にしている。何十年もの間ずっと波に洗われてきたにもかかわらず、骨組みはしっかりとしていた。その「龍骨」こそが、昔の船大工の知恵の結晶。その龍骨に再び光が廻ってくるという意味をこめ、作品は《廻光(かいこう)—龍骨》と名付けられた。
展示室には、船の解体と組み立てを指揮した年老いた船大工もぶかぶかのスーツを着て現れた。蔡はとても喜んで、一緒に記念写真を撮った。
美術館の屋外には、《東方より 三丈の塔》という巨大な立体作品が三つ設置された。こちらは、廃船の外側の板を利用してつくられたもの。荒々しい外観の塔だが、見ようによっては両手を広げた巨人のようでユーモラスだ。塔の高さは、それぞれ約三・三メートル。三・三メートルは「一丈」に相当し、それが三つなので《三丈の塔》。
つまり、浜辺の古いサケマス船は、船と塔というふたつの作品に生まれ変わった。それらは蔡が故郷・泉州で毎日眺めていたものだ。蔡は大切な友人、いわきの人々にもはや帰ることができない自分の故郷を見せたのである。
その夜は、いよいよ「地平線プロジェクト」の本番。海を見守る実行会メンバーは心配そうな表情を浮かべていた。
「最終的には、ごぼうやネギを入れる農業用の長いビニール袋を二重にして導火線を包んだんだけど、うまくいくのかどうかは誰にも確信はなかったよね」(志賀)
確かに、ごぼうの袋と聞くと何とも心もとない。しかも、つなぎ目の部分はビニールテープで止まっているだけだった。少しでも水が浸入してきたら、そこでジ・エンド。いままでの実験では、一度も成功したことがなかった。
当の蔡は、耳まですっぽりと覆う帽子をかぶりながら、「失敗してもいいんです、プロセスが大事なんです」とおっとりとした口調で繰り返す。この「失敗してもいい」という蔡のスタンスは、ポーズやなぐさめではない。そのあとのアーティスト人生でも一貫したものだ。空や海を舞台にした蔡の作品の成否は、しばしば天候に左右される。実際に、このあとの蔡のプロジェクトは、何度も強風や嵐で中止になったり、失敗したりする。そういった抗(あらが)えない自然の力こそ、蔡が作品に取り込みたいものだった。
しかし、実行会のほうには、失敗できない切実な事情があった。実は、いわき市長がこのプロジェクトのために、二〇〇万円の補助金を新たにつけてくれていた。税金を使い、多くの人に期待してもらっている以上、絶対に成功させなければ、とプレッシャーを感じていた。
夕方になると、地元の人だけではなく、東京の美術関係者なども浜辺に集まり始めた。いったい何が起きるのだろうと海風に震えながら、誰もが胸を膨らませていた。しかし、今日に限って海は荒れ、波が高く、関係者は心配していた。これでは失敗するのは確実に思えた。
海上保安庁と相談の結果、翌日までプロジェクトを延期することに決定。スピーカー放送で延期が知らされると、人々はガッカリしながら帰っていった。
さて、翌日。海はうって変わって凪(な)いでいた。海を知り尽くした佐藤進は、「今日はいいぞー、今夜ならやれる」と高らかに宣言した。
午後三時、蔡や志賀、平野、佐藤たちは四隻の船に分かれて、沖合二・五キロの場所に導火線を浮かべる作業を開始した。
夕方になると、再び見物客が浜辺に集まってきた。その数はざっと五〇〇〇人。沖合には何艘もの監視船が出ていた。導火線が浮かぶ五キロの間には、いくつもの小さな港があった。漁船が通ると導火線を切ってしまう恐れがあったので、漁船にも操業を一時停止してもらうよう頼んでいた。
夕焼けが美しい日だった。
六時、ようやく長い導火線を海に浮かべる作業が終了。いよいよ点火である。夕日が沈むと、浜辺は深い漆黒に包まれた。写真家の小野も、海岸でカメラを構え、いまかいまかと待っていた。
ある瞬間、海の向こうでパーンと小さな光が破裂し、バリバリという音が聞こえ、炎が波間を走り始めた。
それは、想像していたよりもずっとか細い火だった。人々は思わず目を凝らした。あ、消えた、と何度も思った。しかし、気がつくとまだ水面を走り続けている。いいぞ、消えるな、と浜辺の人々は応援した。知らず知らずのうちに、人々は「がんばれ、がんばれ」と呟(つぶや)いていた。小野が浜辺にセットしたカメラは、闇のなかの細い光をしっかりと捉え続けた。
がんばれ、がんばれ。
「龍みたい、脈打ってるみたいだ」
船の上にいる蔡は、落ち着いた口調で呟いた。
波に呑まれたかのように見えた炎は、バリバリという爆発音とともに走り続けた。
がんばれ、がんばれ。
がんばれ、がんばれ。
その無数の祈りが届いたのだろうか。点火から二分後、火は無事に終点に到着した。船上の実行会メンバーからは「おー!」「やったー」と安堵の声があがった。「地平線プロジェクト」は、成功したのだ。それにしても、「イベント」と呼ぶには、あまりにも弱々しい光で、あっという間のできごとだった。
それでも、暗い浜辺は歓喜の声に溢れ、人々は甘酒で乾杯した。蔡が浜辺に戻ると、「蔡さん、おめでとう」「おめでとう」と次々に声をかけられた。おめでとうと言われるべきは、いわきの人々のほうだと感じ、蔡は何だか照れくさかった。
この土地で作品を育てる
ここから宇宙と対話する
ここの人々と一緒に時代の物語をつくる
この言葉で始まった、蔡といわきの人々の四ヶ月の挑戦。
個展は二八三九人の来館者を迎え、幕を閉じた。これは、いわき市立美術館における現代美術系の企画展としては、ごく平均的な来館者数だった。
蔡は、感謝の気持ちを込めて、協力してくれた人々に対してそれぞれ自作の絵をプレゼントした。潜水会社の佐藤の絵には、船の上から導火線を流す姿を描いた。そこには、「作業船が引いているのは、少年の夢と男のロマン」という言葉が添えられた。
蔡が茨城に帰ると、いわきは「何もない場所、本当の日本」に戻った。丘の上の家を引き上げるとき、蔡は「一〇年たったらまた一緒に何かやりたいですね」と言い残した。そして海の沖合を走った仄かな火の残像は、人々の心に焼き付けられた——。
そんな話を聞いたあと、「いま、あのときを振り返ってどう感じますか」と、学芸員の平野に尋ねた。取材時には副館長となっていた平野は、昨日のことのように顔をほころばせた。
「よく(炎が)行きついたなあと感じましたねえ。〝感動〟という言葉では言い表せないです」
「そうですよね……。ただ一般の人にとっては、その意味を理解しにくい作品だったと思うのですが、どう受け止められたでしょうか」
その思い込みに満ちた質問に対し、平野は「いや」と驚いたように首を振った。
「そんなことはありません。〝地平線に一本の光〟は、とてもわかりやすかったと思います。作品としては現代美術の難解さではなかった。光ですので、感覚的に捉えられるんですよね」
その言葉にハッとした。光は美しい。その美しさは、誰もが本能で感じるものだ。蔡の意図がどうであれ、それは間違いない。彼が〝光〟を生み出す人だからこそ、人は彼の周りに集まるのかもしれない。——闇のなかに浮かぶ光が見たくて。
平野は、ふっと笑みをもらした。
「あのとき、作品づくりを通じて人の輪ができた。それが彼の最大の作品なのかもしれないですね。もし美術館の資金が潤沢にあったら、たぶんまったく別の作品になったでしょう。資金がなかったから、むしろよかったのかもしれないですね」
展覧会の翌年の一九九五年、蔡は慣れ親しんだ日本を離れ、アメリカ、ニューヨークに移住した。それは、アーティストとしての新たな出発を意味していた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
続きはこちらからどうぞ。
書籍でお読みになりたい方はこちら↓からどうぞ。
空をゆく巨人 目次
プロローグ
はじめに
第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年
第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年
第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年
第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年
第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年
第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年
第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年
第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年
第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年
第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年
第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年
第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年
第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年
第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年
第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年
エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
