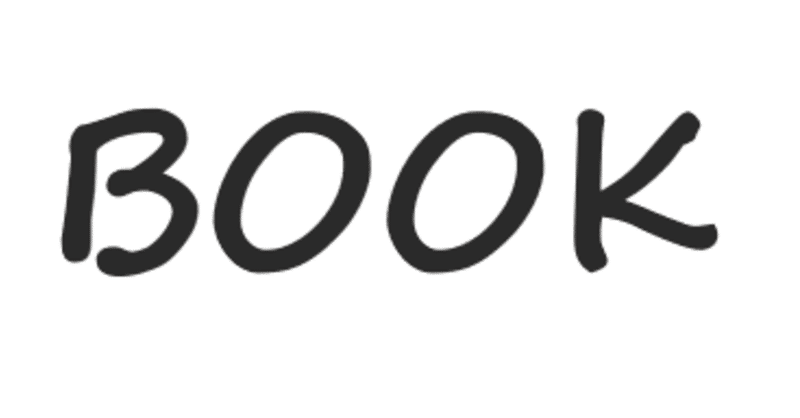
【今週の1冊】2020年10月①『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』末永幸歩(ダイアモンド社)
美術の授業というと、なんとなく自分で作品をつくったり美術史や作品と作者の名前を覚えさせられたりという印象が強いのではないだろうか?本書では、現役の美術教師がアートの見方や考え方について解説している。知識の暗記やクラスメイトと比べてうまく作品を作ることは本質的には重要ではない。近年ビジネスマンの間でアートが流行っているが、仕事も含めこれからの人生で役立つアート思考を本書で学ぶことができる。
本書では全体を通して、アートとは何か?アーティストとは何か?を考えていくことになる。アート思考とはどういうものかを植物にたとえて説明した後、20世紀のアーティストたちがアートの常識を打ち破ってきた過程からアートとは何か、アートとどう向き合うかを考えていく。
全体を通して、読者がアート鑑賞などのワークに取り組みながら進んでいく。ワークといっても大変なものや単純作業のような退屈なものはなく、気軽に楽しく取り組めるものになっている。
中でも、”アートという植物”と「鑑賞者と作品のやり取り」の部分は必読だ。
”アートという植物”は、アート思考をわかりやすく解説している部分である。簡単に言うと、自分の興味を種、それを探求していくことを根、探求の結果生まれたものを花にたとえており、自分は興味をもったことをさまざまな方向に探求していった結果、それらがどこかでつながって何らかの成果(有形無形に関わらず)が生まれるという過程を表している。重要なのは花ではなく根を伸ばしていく過程であるというのは、作品の良し悪しで成績をつけられてきた私たちからすれば新鮮に感じるところだろう。
次に「鑑賞者‐作品のやり取り」の部分だが、ここで大切なのは、あくまで「作者‐作品のやり取り」とは別であるということだ。私たちは美術館でアート鑑賞をしようとすると、ついつい作者の意図などの「正解」を探しがちである。ご存じの通り、現代は正解がコモディティ化して価値を失ってきている時代である。主に学校教育を通して染みついた正解を探すくせから脱却し、自分だけの答えを出せるようになりたいところだ。少し話がそれたが、アート鑑賞は正解探しではなく自分がどう感じたかが重要ということであり、これは現代の生き方にも通じる大切な考え方と言えるだろう。
私は本書を読んだことで、上に書いたような正解探しのくせを少なくとも自覚できたと思う。このくせはあまりにも私たちに浸透しすぎて、実際多くの人が自覚すらできていないのではないだろうか?気をつけていてもついやってしまうのだ。まずはこのくせを自覚し、見聞きしたことや経験したことについて自分なりに感じたり考えたことを、それがどんなに拙いものだったとしても認めることが大切だと私は思う。本書を読めば、アートを通してその様な考え方の土台を身につけることができるだろう。
美術館に行ってもいまいち楽しみ方がわからない、昨今のビジネス界隈でのアートブームは気になるけどなんで今アートなのかがぶっちゃけよくわからないといった人には特におすすめの1冊である。
よかったらサポートお願いします!本代にします。
