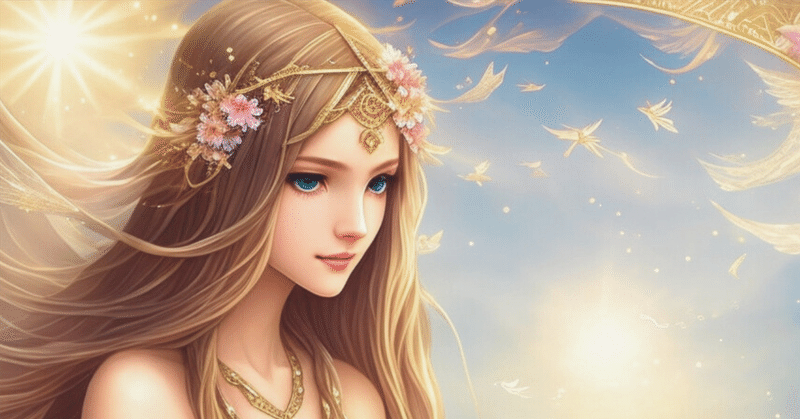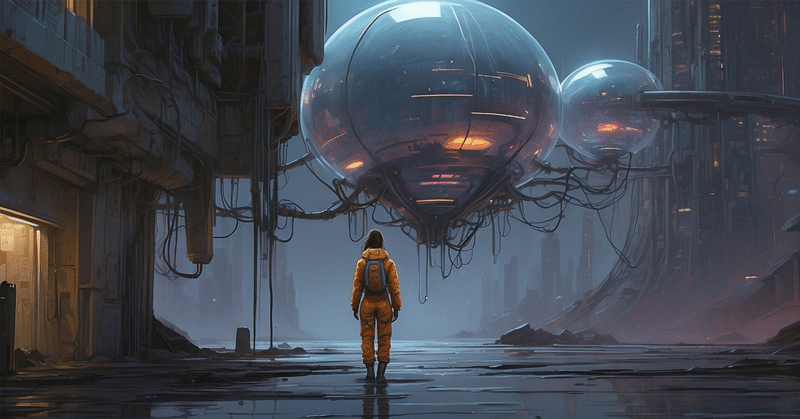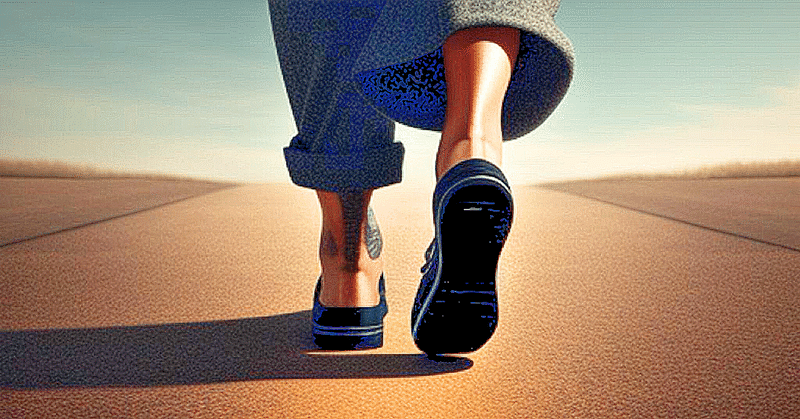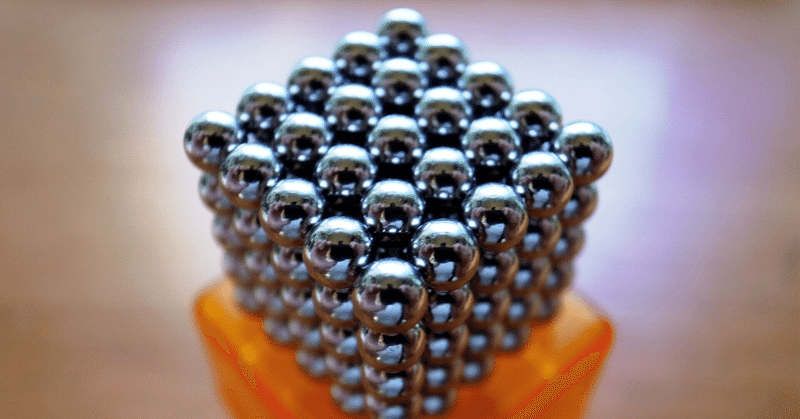#中世哲学
八木雄二『神を哲学した中世』読んだ
中世哲学入門シリーズ。
読みやすくてよかった。
形而上学や論理学的なこと、というか悪い意味でのスコラ学的なところに深入りしないで、どうしてあのような煩瑣な理屈を必要としたのかに力点が置かれている。
したがって、中世の人々の思考に入り込むことになる。大衆がふつうに神の実在を信じていたこと、修道院や大学の学者たちの理屈の組み立て方など。
なぜ中世の人々の思考を学ぶ必要があるかというと、あの時代
山内志朗『中世哲学入門』読んだ
ぜんぜん入門書じゃない入門書。むりやり2回読んだ。
今年の初夏にラテン語の勉強を再開したとき、ちょうどよいタイミングで山内志朗先生のシラスのチャンネル『ラテン語が一瞬で身につく夢の哲学チャンネル』略して夢ラテが始まったのである。
私は山内先生はお名前しか存じ上げなかったのだが、朴訥とした語り口に一瞬で魅せられてしまい、そのときちょうど発売された『中世哲学入門』を購入したのである。
しかし日本
富松保文『アリストテレス はじめての形而上学』読んだ
中世哲学をヨタヨタと学び始めたが、そうすると避けて通れないのがアリストテレスである。
かといっていきなり原書を読むわけにはいかないので入門書を探したところ、これがよさそうだった。
Ciniiで検索すると著者はベルクソンとかメルロ・ポンティとかを専門としているようだが、まあいいだろう。NHK出版ならクオリティは担保されているだろう。
タイトルのとおり主に形而上学の一部を解説しているが、デ・アニ