
【枝豆】採りたての味はスーパーでは永遠に味わえない(プランター菜園 完全マニュアル)
「お湯を沸かしてから採りに行け」
それが、枝豆の本当の味を知るための食べ方です。
実は、枝豆は枝から切り離すと急激に鮮度が落ちるのです。
ですから、スーパーでは永遠に枝豆の本当の味を知ることはできません。
さらに不思議なことに、枝豆を育てると、その土に栄養がつきます。なので野菜と育成にも役立ます。
そんな食べてヨシ!育ててヨシ!の枝豆って、プランター菜園を始めるのには最適な野菜なんです。
この記事では、素人の自分の実体験を元に、枝豆の栽培方法をマニュアル化しました。
サルでもできるプランター菜園、略して「サルプラン」です。以下の記事が自分の栽培結果です。
そもそも、枝豆っていう豆はない?
そもそも枝豆とはなんでしょう?
実は、大豆なんです。
大豆が未成熟なまま採られた物を、枝豆と言います。
意外と知らない人多いんじゃないでしょうか?
未成年で徴兵された若者のような感じですね。
そして、なぜか枝豆の分類は「豆類」ではなく「野菜類」なんです。
枝豆は、食べてヨシ!

大豆との違いは分類上だけはなく、栄養素も異なります。なんと、枝豆は「豆」と「野菜」のW栄養素があるんです。
大豆の栄養素(カロテンやビタミンBなど)が大増量されていたり、さらに大豆にはない栄養素(ビタミンC)も含まれています。
枝豆って、大豆にトッピング追加、栄養マシマシされた期間限定メニューみたいなものですね!

酒飲みにも優しい枝豆
枝豆の栄養素の組み合わせは、実はお酒好な人にうってつけ。
アルコール分解する肝臓を、全力バックアップしてくれる栄養素がたっぷり含まれているんです。
枝豆と酒飲みについては、下記記事に詳しく書いてありますので、よければ見てください。
そんな枝豆を最高に美味しく頂く方法は?
逆に、1番不味く食べる方法を言いましょう。
それは、スーパーで買って食べることです。

先に書いたように、枝豆は時間経っても外見上はあまり変化しませんが、収穫すると猛烈なスピードで劣化が始まります。
常温だと収穫後も成長するので、枝豆の糖分がどんどん分解され、旨味や風味が損なれ続けるのです。
たしか、スーパーって、枝豆を常温で置きっぱしですよね…。つまり、スーパーで売っている枝豆は、すでに死んでいる!

なので収穫してからすぐ食べる。「お湯を沸かしてから、収穫しろ」と言われる所以です。
プランター栽培で直採りしたものを、さっと茹でて食べるのが、最高の食べ方ってもんです!
⚫︎もし、スーパーで買うなら。
枝豆は、収穫後すぐに冷凍保存すれば、劣化スピードは抑えられます。
なので、冷凍保存のものがおススメです。
もしくは、枝付いていると劣化が遅いので、枝付きの枝豆を買いましょう。
採った後もヨシ!

普通、野菜を育てると土は痩せます。
野菜は、土の栄養分を吸って大きくなるので当然ですね。
でも、枝豆を育てた土は、栄養分が増えているんです。
不思議ですよね。何故でしょうか?
その理由は、栄養をつくる菌と共生しているからです。
枝豆の根っこには、根粒菌(こんりゅうきん)という菌が住み着きます。
植物が育つには、窒素、リン酸、カリウムの3大栄養素が必要ですが、根粒菌は、その中の1つである窒素を空気中から抽出(窒素固定)して大豆に供給してくれるんです。
枝豆の根っこには、こんなふうにコブのような膨らみ(根粒)があり、この中に根粒菌が住んでいます。

なので、栄養素の一部(窒素)を自分で調達できるので、枝豆に肥料はあまり必要ありません。(窒素以外の2大要素「リン酸」「カリウムは」は別ですが)
そして枝豆が育った後の土は、根粒菌のおかげで窒素が増えいるので、次の作物もよく育ちます。素晴らしくないですか?
話題閑休。<世界では、肥料が不足している!?>

ここで、ちょっと話題閑休。
枝豆と根粒菌の共生のように、植物が栄養を自前で調達できば良いのですが、実際はそう上手くはいきません。
そこで畑に肥料を撒くのですが、近代では有機肥料が化学肥料になって大きく変わりましました。
栄養素的には、有機肥料と化学肥料も基本は同じで、窒素、リン酸、カリウムの3大栄養素です。
違うのは効果の速さで、化学肥料はすぐに効果がでますが、有機肥料は土の中の微生物が分解してくれないと効果がでません。
コンビニ弁当を買ってきてすぐ食べるか、食材を買ってきて料理するか、というような違いですね。
しかも、化学肥料は土を選びません。土の状態が多少悪く、微生物が少なかったり栄養がなくても、化学肥料を大量にぶち込めば植物が育つのです。
これは楽ですね。化学肥料を一択じゃないですか?
しかし、大きな問題がでてきました。
ニュースで言われているような肥料の価格高騰です。

3年前から比べると、倍倍倍の4倍くらい上がってますね。ハンバーガーが130円→150円に値上げされました、なんてレベルじゃないですね。
このグラフを見てもらうとわかりますが、あの戦争が原因だけではありません。
本当の原因は、人口増加による食料需要の増加、肉中心とした食生活への変化、バイオ燃料等々による時代的な傾向から、化学肥料の需要が年々増加しているからなんです。
「じゃあ、化学肥料も増産すれば良いじゃん。」と思われるかもしれませんが、化学肥料はどうやって作られているのかというと。
窒素・・・・・化学反応により空気から抽出
リン酸・・・・リン鉱山から採掘
カリウム・・・カリウム鉱山から採掘
2大栄養素が鉱山からの採掘。さらに鉱山がある地域が限定されています。
ということで、大きな二つの問題があります。
①特定の国による化学肥料の独占が始まったら大変じゃない?
②鉱山を掘り尽くしたらどうなるの?
今はまさしく、①により化学肥料の高騰しています。
さらに②になったら今の農業ってどうなるのでしょうかね...?
枝豆の育て方
お待たせしました。枝豆の栽培のしかたについて書いていきます。
前置きが長くなってしまい、どっちが本文だかわかりませんが、こちらが本文です。
ではいきましょう!
1:準備(土づくり)
枝豆は、保水性と排水性の良い土壌を好みます。
野菜用の土で良いと思います。
自分で配合するなら、
赤玉土7:腐葉土2:バーミキュライト(天然のケイ酸塩鉱物)1。
(百均で売っています。)
さらに、アルカリ性を増やすため、石灰を土1リットル当たり1g混ぜ合わせましょう。
肥料(元肥)を入れる場合は、有機質肥料を中心で、窒素分少な目にしてください。
上記入れたら、種を植える前に1週間程度、放置しておきましょう。
2:種まき
大豆のたねとは。
枝豆の種はでかくて、どこかで見た気がします。
それもそのはず、枝豆の種って大豆だからね。
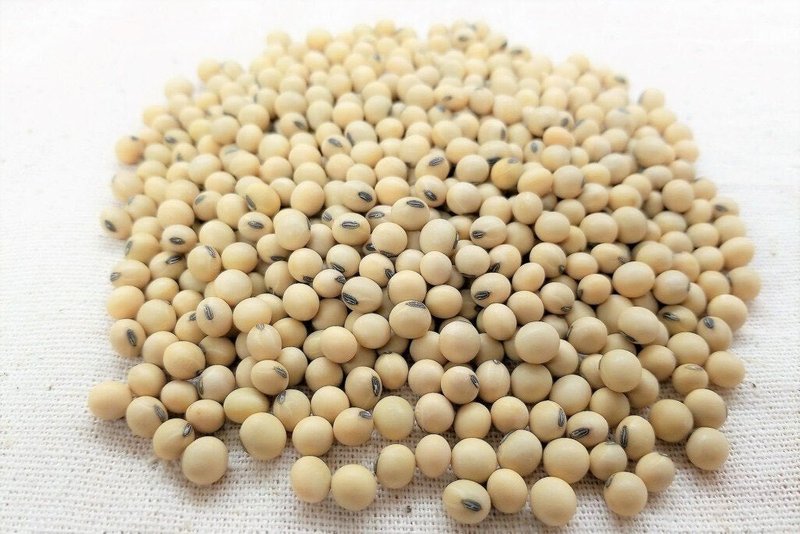
種の「へそ」と言われるくぼみの部分を下向きにして埋めるとよいです。
時期
だいたい、3月下旬以降、4月中旬(品種:極早生)、6月中旬(品種:中晩生)頃です。(気温が15℃以下の場合は、被覆資材による保温が必要)
枝豆は「極早生」や「早生」「中晩生」など品種が多く、特徴に差が出ます。種を撒く時期などは、よく確認してから品種の選択しましょう。
「ビニールポット」に種まきする
枝豆は、ビニールポットに種まきするのがベストです。
実は、枝豆の種(だって大豆だし)は鳥の大好物なので、まいた種が食べられてしまう可能性が高いからです。
そこで、発芽ふるまでは、ビニールポットを不織布やネットなどで覆って、しっかりと鳥害対策がしましょう。

埋める種の量と深さ
1ヶ所に3粒ずつ、深さ2cmくらいに種をまきます。
土を被せて軽く指で押さえてください。水やり
水はたっぷりやりましょう。
3:発芽後(間引き➝植え替え)
初生葉が開いたら、間引きを行います。
1カ所に1〜2本とします。
苗を2本くらい残して競合させたほうが、強く育つと言われています。
根がからまって隣の株まで抜けてしまうときは、はさみで切ってください。根がちょっと切れても、大丈夫です。世の中にはこんな方法もあるみたいですから。
超スパルタな苗の作り方「断根」
苗の根と若芽をすべて切るという、ちょっと驚きの苗の作り方。収穫が倍になる強い苗ができるらしいです。
(人間で想像すると、ちょっと怖い。。。)
鳥対策で不織布を掛けている場合は、取り払ってください。
もう鳥は食べませんし、不織布が枝豆の生育の妨げになります。
本葉が2~3枚出るくらいまで育ったら、プランターに植え替えましょう。
枝豆の株間は、20~30cm空くようにしてください。

4:育成中
やることが一番多く重要な工程です。順番に説明していきます。
場所
湿気に弱いので、風通しの良い場所にプランターを置きます。
また枝豆は、光を浴びる時間が短くなると花が増える「短日植物」なので、照明などで夜も明るい場所は避けましょう。水やり
枝豆の収穫量を左右するくらい重要な要素です。
①開花するまでは、頻繁にする必要はありません。
②花が咲いたらたっぷり水をあげましょう。
水が少ないと、咲いてもすぐに落下する花が多くなります。
③さらに、さやができたらに、たっぷり水をあげましょう。
水が少ないと、さやは膨らみません。
水をやればやるほど、さやの中身が大きくなると思ってください。
ただし、枝豆は湿気に弱いので、水を大量にかけるのではなく、回数を多く豆に水やりをしてください。豆だけに。土寄せ
土を根元にかぶせることにより、茎からも根が出て倒伏防止になり、除草もできます。以下のように、数回に分けてやります。

また、枝豆が伸びすぎる場合は、簡単な支柱で固定してください。
肥料
花が咲くまでは、不要です。
花が咲いたあと、花が咲いても落ちてしまったり、さやがの数がすくないときなどは追肥すると良いです。
その場合も、窒素少な目の肥料で行います。
摘心をやってみよう!
野菜の茎の先をカットすることです。先へ先へと伸びようとする枝豆を一旦ストップさせ、実に集中させます。
やり方は簡単、本葉5〜6枚の頃に、頂上の芽を手で摘みとるだけです。
葉が茂り過ぎたときや、品種が「晩生品種」のときは、是非やりましょう。(ただ早生品種はあまり効果ないとも言われます。)
【ちょっとトリビア】植物だって動く
植物は動かいないものと思っていませんか?
実は、植物は活発に葉を動かし、朝露などを溜めるなど水分を吸収したり、日に当たる角度を変えたりすることができるんです。
それは、葉枕(ようちん)という、枝の膨らんでいる部分で行います。
例えば、夜や曇りのときは、日差しが当たるように茎を下向きにし、日中は。茎を上向きにして適度に葉を立たせます。

5: 害虫、病気、見回り期間
戦いはまず相手を知るところから。
枝豆の収穫を邪魔する憎き奴ら。害虫、病気をささっとご紹介します。
カメムシ
枝豆大好きなのが、カメムシ。
さやを刺して、ちゅうちゅうと豆から栄養を吸い取ってしまうんです。
カメムシに刺されてしまった実は、小さいままで味も不味いです。
それ以外にも、こんな奴らがいます。
・シロイチモジマダラメイガ、シロイチモジマダラメイガ
エダマメの大敵。幼虫が枝豆の中に入って食害します。枝豆のさやに穴が空いているのが、虫がいる証拠。
・ダイズアブラムシ
葉っぱや茎やさやに群がって汁を吸います。
間接的にウイルス病を移されると、苗ごと病気になってしまいます。
・コガネムシ、ハスモンヨトウ
幼虫が葉を食べます。特にヨトウムシに注意。
葉がボロボロで黒い糞があるのに、姿が見えないときはヨトウムシです。
ヨトウムシについては、以下の記事をみてください。
病気
病気は、基本ウィルス(または害虫が介在)が運んできます。
・萎凋病(いちょうびょう)
下葉から黄色くなってしおれ、生育不良で枯れます。
・白絹病(しらきぬびょう)
地の茎に白い菌糸ができます。酸性土壌で発生しやすいので、土壌の酸度調整します。株ごと抜き取って処分し、土も日照消毒します。
・立枯れ病
茎の地が縦長に褐変し、やがて茎全体が褐色になります。
・斑点細菌病
葉に小斑点が生じ、黒褐色の拡大します。株ごと抜き取って処分し、土も消毒します。
・べと病
葉に淡黄色の病斑ができ、裏面に灰白色のカビが発生します。
・モザイク病
葉に緑色濃淡のモザイク症状が現れます。アブラムシが原因です。
害虫対策
防虫ネットをかぶせることです。
ただ防虫ネットで1点注意することがあります。
それは、害虫に取りつかれたら防虫ネットは外す!
これにつきます。
害虫に取りつかれたのに、防虫ネットをかぶせたままにしていると、そこはもう、害虫の飼育場になり果ててしまうからです。
防虫ネットをはずして、害虫の天敵さんにも、駆除を協力してもらいましょう。
あとは、毎日の見回り。以下がないか確認してください。
✅葉にかじられた後はないか?
✅葉の裏に虫の卵がないか?
✅葉に黒い点(害虫の糞)はないか?
病気対策
葉の色をみることです。とても分かりやすいです。
健康的な植物の葉は、みずみずしい緑色をしています。
それが、白かったり黒かったり黄色だったりすると、病気かな?と疑ってください。
6 : 枝豆いつ採る?
お疲れさまでした。収穫です!
枝豆は、枝豆=早熟な豆ですので、大きくなる前に採ります。
全体の約8割の枝豆のさやが、ふっくらしてくれば収穫タイミングです。
実が大きくなり過ぎると、食べ応えはあるものの、本来の甘みが薄れてしまいます。そして、さやが黄色くなるとそれはもう枝豆ではありません。
エダマメの収穫適期は3日~5日ともいわれています。
枝豆は1回収穫したらおしまいです。
枝豆は、ひとつの株に1回しか実がなりません。
トマトやナスのように、ひとつの苗から何回も実はならないので、実を採ると、その株はお終いです。
実の採り方は、2種類あります。
苗ごと抜き取る方法と、実ごと採る方法です。
苗ごと抜き取るときは、すべてのさやがパンパンになるのを待たずに、全体の8割のさやが膨らんだら採りましょう。
7 : 湯を沸かしてから、採れ

これは議論の余地なしですね。枝豆は収穫してからの劣化が早いので「お湯を沸かしてから採る」くらいのことをしたいものです。
それが、プランタ菜園の良いところでしょう?最高の味を味わいましょう。
採る時間としては、栄養タップリが朝(枝豆は夜に栄養を溜めるから)、甘さを味わいたいなら夕方(午後から光合成によって糖度が増すから)となります。
もし、採ってから食べるまで時間空いてしまう場合は、以下のいずれかで鮮度の劣化を抑えることができます。
・枝付で採る。枝からは葉っぱは取る。
・速攻、冷凍保存する
8 :枝豆を大豆として収穫?!
枝豆の収穫タイミングを失っしてしまった。。。。
色が黄色くなっちゃって、なんだか乾燥してきてカサカサしてる。
でも大丈夫です!
腐っているわけではなく、別の物になっているのです。
それは大豆です。
大豆が種の枝豆は、また大豆に戻るんです。
いうなれば、大豆こそが枝豆の本来の姿ともいえます。
大豆の収穫方法
枝豆の状態では収穫せず、葉も茎も枯れてカラカラに乾燥させるまで育てましょう。そうすれば、大豆として収穫することができます。

さやのまま十分に乾燥させてから、豆を取り出すのがポイントです。
でも放置し過ぎると、自然に豆がはじけて外に出てしまうので、その前に収穫してください。
9 : まだ終わりじゃない。枝豆はすべて再利用できる。

通常、野菜を収穫した後は、その土地の土に肥料を入れます。
それは、野菜が育った土には栄養素が少なくなっているからです。
でも、枝豆の場合は違います。
実は、枝豆を育てた土は、フカフカで栄養が満ちています。
先に枝豆の根には、植物の栄養素の窒素を作り出してくれる根粒菌が住みつくと書きました。
その枝豆の根が、一定期間で根から離れて分解され土に豊富な養分を供給するので、枝豆を育てた土はフカフカになるんです。
なので、枝豆を育てた土は、次の野菜を育てる準備OK!という状態になっているわけです。
というわけで、もうひと手間をかけて、次の野菜を育てるための準備をしましょう。
1. 枝豆を根元から切ります。
土の上の茎や、根はそのまま残します。
2. 根や茎がある状態で、土をかき混ぜます。
枝豆の根は次第に分解されていきます。
茎や葉も10cmくらいにカットしてすき込みます。
3. 3週間くらいかけて放置します。
根や茎や葉は2週間程度で分解され、次の野菜を植え付け準備が整った土壌になります。もし、気温が低い場合は、ビニールなどで覆うと良いかしれません。
10:<連作障害>があるか?
野菜の収穫が終わり、次の野菜を植えるときに注意することがあります。
育てた野菜に連作障害があるかどうか?をチェックしてください。
連作障害とは?
毎年同じ場所に同じ作物を栽培することを 連作といいます。
連作すると、その野菜を侵す土の中の病菌や有害センチュウの密度が高くなったり、土の中の栄養分が不足したりして野菜の育ちが悪くなります。
これを 連作障害といいます。
枝豆は、連作障害があります。
エダマメは、連作障害があるため、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにしてください。
その代わり、枝豆が肥沃にした土には、他の野菜を植えましょう。
例えば白菜は、栄養素を必要とする白菜は、枝豆を育てた後の肥沃な土に向いているそう。
また、「人参&大根」のセットも良いそうです。
さらに、人参&大根のセットはコンパニオンプランツになるので、お互いの害虫を防ぐとのこと。
枝豆と相性のよい植物(コンパニオンプランツ)は?
異なる植物を近くで育てると、相乗効果が出る場合があります。
その植物をコンパニオンプランツと言います。
枝豆のコンパニオンプランツは、トウモロコシ、レタス、ナス科、ウリ科などです。
枝豆の共生菌がつくる栄養を供給でき、枝豆につく害虫を退避させたり、益虫を呼びあいます。
基本的に、枝豆の株から約30cmほど離して植えます。
また、ミントの鉢植え(直植えすると広がるので)を隣に置くと、枝豆の天敵カメムシを退避させる効果を望むことができます。
番外編:もやしから枝豆ができる?
突然ですが、もやしって大豆なんです。
もやしとは植物名ではなく、芽し、萌しという意味で、主に穀類や豆類の種子を水に浸し、暗所で発芽、成長させたものです。
もやしは、大豆を暗所で育てたものならば、お日様の下で育てれば、枝豆になるのでは?
お手軽に枝豆や、大豆を作ることができますね。
実際に成功した人もいるみたいです。
大豆の種が入手できなくなったら、もやしを活用できれば楽ですね。
枝豆って、お酒の一品の「すぐ出てくるやつ」という認識しかありませんでしたが、日本人には欠かせない大豆の一種であったり、植物の栄養素と細菌の共生関係など、どんどん内容が広がってしまいました。
こんな奥深い枝豆、ぜひ採りたてを味わってみませんか?
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
東のテツ
#エッセイ #健康 #40代 #体験記 #習慣にしていること #野菜 #日記 #植物 #家庭菜園 #食料危機 #物価上昇 #戦争
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
