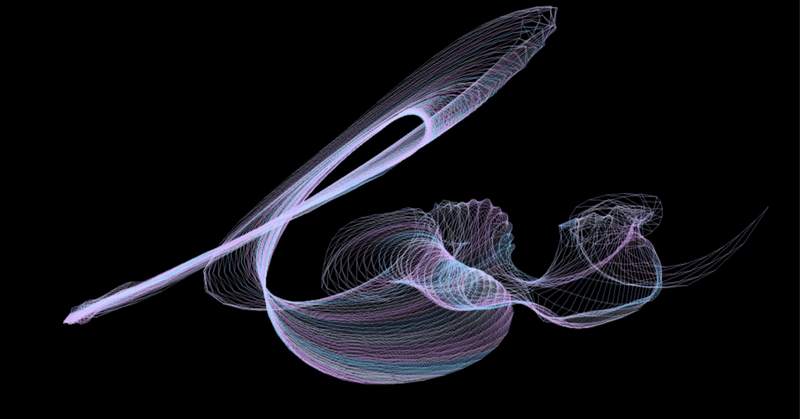
あいいれぬ月
愛していたから。
理由は、ただそれだけでした。
鬼は毎朝、毎晩、毎日、白い頬へ口付けを落とすのです。目を閉じたままの女は応えてはくれないけれど、鬼は気にしません。
何故って、女は死んでしまったのですから。鬼が、殺してしまったのですから。
"愛していたから"。ごく簡単な理由で、女は鬼に命を閉じられてしまいました。けれども、女は美しい寝顔で眠り続けています。鬼は、死してなおも気高い顔立ちの女を、深く愛しました。
愛が何かなど、鬼にはわからないのに。
「綺麗だね、綺麗だね」
鬼は何度も何度も、そう言って女の髪を撫で、頬を撫で、口付けをし、話をします。喋るのは嫌いだけれど、女は返事をしないので、鬼は喋ることができました。喋りたくなければ、黙って隣に座ればいいのです。
女との生活は、満ち足りていました。
しかしけれども、死体というのは、いずれは朽ちてしまうものです。ですから、美しい女は、少しづつその形を変えていきました。
艶やかな髪は縮れた黒糸のようになり、ふっくらとした頬は肉が落ちて骨が透けるようになり、柔らかな赤い唇は紫色に乾いて固くなり、暖かな肢体は冷たい骨と皮のみになりました。それは、この世のものとは思えない、おぞましい姿でした。
鬼は、美しかった頃の女を知っていますから、心底から恐怖しました。これが、あの美しい女と同じものだとは、到底思えません。鬼は恐れ、哀しみました。
死、というのはまったく、かくも無惨なものでした。
惨たらしいその姿を、鬼は隠すことにしました。忘れてしまうことにしました。黒ずんだ細い棒のようになった指の間に、薔薇の花を挟んで、触り心地のいい布で女を包み込んでやりました。そうして、裏庭の深い場所へ埋めました。
「どうか安らかに。美しいヒト。あんなに恐ろしい顔になったことは、忘れてしまうからね」
鬼は最後に、布の上から、頬だった部分に触れました。そして、土を被せて、女との日々にも蓋をしました。
***
それから随分と経った日のことです。
「貴方の妻にしてくださいな」
ある女が、鬼に向かってそう言いました。
鬼は驚きましたが、女は本気です。そうかそうかと、鬼は頷きました。
女は、美しい人でした。
長い髪は烏の濡れ羽色で、黒曜石のような瞳をして、雪のように白い肌、林檎のような赤い唇をしていました。鬼は、この美しい女を妻にしました。
はたして、妻、とは扱いづらいものです。鬼は難儀することもあり、その度に頭を捻りました。妻の考えることは鬼には不可解で、しかし、だから面白いものでした。
鬼は、次第に妻との生活に慣れてゆきました。
「お前、俺に愛されて幸せか」
「えぇ、勿論ですとも」
「俺といるのは、退屈しないか」
「たまにはね。でも、人といるというのは、そういうものよ」
そんなやりとりも、何十ぺんと繰り返しました。決まって、丸い月の登る静かな夜に、鬼は妻に尋ねるのでした。
鬼にとって、丸い月は美しく恐ろしいものですから、不安に駆られるのです。何故かはわかりません。ただ、鬼はそう学んでいたのでした。
妻は、そんな鬼をいつも優しく抱きしめるのです。
「貴方はとても怖がりね。優しい目をしているから、きっと、人よりも怖いものが見えてしまうのね」
「怖いのとは違うんだ。不安なんだ」
「そうでしょうとも。とっても貴方らしいわ」
「馬鹿らしいよ。月なんて、俺には手出しできるはずもないのに」
「そうね。貴方は月を恐れているんじゃないわ。もっと別のもの。丸い月のために残酷なものが見えて、それを恐れているのよ」
鬼には、妻の言うことが理解できませんでした。月でなければ、何を見ていると言うのでしょう。鬼の目には、暗闇に浮かぶ月が映るだけだというのに。
妻は、優しく微笑むばかりでした。
鬼は心底から、そんな妻を愛していましたから、当然いつかは殺してしまうと思っていました。しかし、妻を前にすると、そんな気が全然湧き起こらないのです。
もしかすると、俺は妻を愛していないのではないか。鬼は焦燥に駆られました。
そうして三日三晩悩んだ末、妻に一切を語ることにしました。
「俺は、お前を愛していないのかもしれない」
「あら、どうしてそんなこと思うのよ」
「俺はおかしくなったんだ。愛おしいお前を、どうしてか殺せないんだよ」
「私を殺してしまいたいの?」
「愛していれば、殺さなくてはいけないんだよ」
鬼の必死な様子に、妻はきょとんとして、それから嫋やかに笑いました。それはやはり美しく、愛らしい姿でした。
それなのに、鬼は困惑してしまうのです。
「どうしたらいいんだろう。お前を愛していないのなら、俺はどうなるんだろう」
いっそ慌てたように言い募る鬼に、妻は笑いをやめて小首を傾げてみせました。
「安心していいわ。貴方は私をきちんと愛しているわよ。今までとは、愛し方が変わっただけのことだわ」
「そんなことがあるかな」
「あるわよ。いいじゃない、素敵だわ。私は、本当の意味で、貴方に愛された初めての女かもしれないわね」
そう言って、妻は鬼の胸に身を預けて目を閉じたのです。
その無垢な顔つきに、鬼は亡き顔を見てしまい、胸の内が冷たくなるような孤独を感じました。けれど、見て見ぬふりをしました。
鬼は、孤独というものを見たことがありませんでしたから、胸の内に広がった冷たさが何によるものか、理解しようもありません。
ですから、
「今が幸せなら、それでいいのよ」
妻の呟いたその言葉に溺れることにしたのです。
***
二人きりの生活は、何不自由ありませんでした。朝が来れば起き、仕事をし、話したければ話し、黙りたければ黙り、そして食べて風呂に入って、夜になれば眠りました。
来る日も来る日も、飽きることなく、キリがないほどに。
そんなある日のこと、妻が突然倒れました。鬼はたいそう慌てて、妻を抱え医者へ走りました。あちこち走り回って、鬼はやっとの思いでひとりの医者を探しあてました。
そうして、妻をどうにか元気にしてくれと懇願しました。
そんな鬼に、医者は言いにくそうに、
「肺の病です。随分と酷いもので、もう治療の施しようが……」
と告げましたが、鬼には理解ができません。言葉ではなく、妻の身に起こること、自分の身に起こることが、わからないのです。
「妻が……妻が、死ぬと……? 医者のくせをして、匙を投げると……?」
殺気立ち、ゆっくりと言葉を紡ぐ鬼に、医者は怯えて口を噤んでしまいました。鬼は、舌を打って医者の元を去りました。
意識の無い妻を連れて他に行くべき場所も思い付くことができず、結局鬼は妻をしっかりと抱いて家へ帰りました。妻は相変わらず、苦しげに息をして、燃えるように熱い体で汗をかいていました。
鬼には、分からないのです。妻の病の正体も、治し方も、その苦しみも。そして、妻が死んでしまうことに何故こうも恐れがあるのかも。
「……死なないでおくれ、頼むから、何でもしてやるから」
鬼は、眠り続ける妻に向けて、譫言のように囁き続けました。それ以外に、鬼に出来ることもないのです。
何度も何度も、鬼は同じ願いを囁きました。
***
「お前だけは死んでほしくないよ」
それは、鬼の願いでした。おかしいのです。
何故って、鬼は今まで愛した女を数々殺めてきたのですから。愛していればこそ、殺さなくてはならなかったのですから。殺すことが、鬼に行える素晴らしい愛の表現だったのですから。
けれども、この妻にだけは、生きて傍にいて欲しいと思いました。
「私も、貴方をこんな世界にひとり残してしまうのは苦しいのよ。もしかすると、死ぬことよりもずっと苦しいの。でも、病なんかで死んでしまうなら、その前に貴方に殺されたいのよ。そうして、貴方の血肉になるの」
妻は鬼の頬を撫でて優しく笑いました。
鬼は、やっと震えが止まったのを自覚しました。そして、妻の手をとって、恭しく口付けを落としました。
迷いはありません。
「さようなら、愛する妻」
「さようなら、私の良い人」
妻が目を閉じたので、鬼は妻の手首に包丁をあてがい、すっと引きました。刹那、血の匂いが部屋に満ち、妻の白い手首が赤く染まりました。ぽたり、ぽたり。容器の中に妻の血が落ちていきます。
それは、命の砂時計でした。
「ねぇ貴方、憶えてるかしら?」
ふいに、妻がそっと問いかけました。
「何をだい」
鬼は身を乗り出して、妻に寄り添うように返事をしました。妻は、まるで幼子に本を読み聞かせるようにして鬼へ語りかけます。
「貴方が月を恐れるものだから、私は言ったわよね。貴方には、月を通して別のものが見えているのよって」
「あぁ、そうだったね」
「私が死んでしまったら、何を恐れていたのか、ちゃんと考えないと駄目よ。でないと、ずっと恐ろしいままだわ」
「でも、お前がいなくなってしまったら、俺には答えなんて見つけられないよ。俺は馬鹿だから、わかりっこないさ」
「そんなことないわ。それにね、貴方はひとりで答えを見つけなくてはいけないのよ」
そう言うと、妻は血の滴らない方の手を持ち上げて、鬼の胸へ掌を当てました。そうすると、鬼の耳にも、とくりとくり、と鼓動が伝わります。
「きっと、貴方にはわかるわ」
妻は、優しく言い聞かせました。
「お前が言うなら、そうなんだろうな」
「お利口さんね」
ぽたり、ぽたり。話す間にも、妻の命は流れ落ちていきました。
***
妻が亡くなってからというもの、鬼は妻の血を少しづつ飲みました。時間をかけて、ゆっくりと、無くなってしまわないよう、ほんの少しづつ。
血があるうちは、まだ妻が生きていると思えるのです。けれど、人の血なんてものは、すぐに尽きてしまうものでした。
それも、丸い月の登る、静かな夜に。
「あぁ……」
妻の亡骸の頬を撫で、窓の外を見れば、大きな月が鬼を見下ろしていました。鬼は途端に恐ろしくなり、妻に縋り付いて震えました。
考えなくてはなりません。
月を恐れる理由、月が見せるもの。いったい、なんだと言うのでしょう。
「妻よ……俺にはやはり無理なんだ……一人では……一人では考えられない……お前がいなくては、何も……愛するお前……」
告白して、鬼ははっとしました。
鬼が導き出した答えは、あまりにも冷たく、空虚で、恐ろしいものでした。鬼が恐れていたもの、月が恐れさせたもの。
……鬼が、愛する人を手にかけた、その理由。
「愛、だ……」
鬼は、愛を恐れていたのでした。
誰かを愛し、その愛を失うこと。それが、鬼にとっての恐怖だったのです。だから、愛が失われる前に、愛を殺してしまわねばならなかったのでした。
愛し愛された夫婦として、妻との日々を、美しいまま、終わらせないこと。それは、鬼が恐怖に打ち勝つ唯一つの手段だったのです。
なんと愚かで、おぞましく、情けないことでしょう。
「わかった、わかったよ……もう、必要もなくなってしまった……愛するお前……お前たち……俺も……」
鬼は、台所から包丁を取り出すと、妻の亡骸の隣へ横たわりました。そうして、乾いた唇に唇で触れ、固くなったその手を握りしめました。
この日、鬼は初めて己に刃を突き立てました。痛み、血が流れ、意識に靄がかかっていきます。
月に照らされ、鬼は目を閉じました。
恐怖も、不安も、焦燥もありません。死ぬ間際の、安らかな虚があるだけでした。
「今、行くからな……」
命尽きる前。
鬼は、ただ人間でありました。
