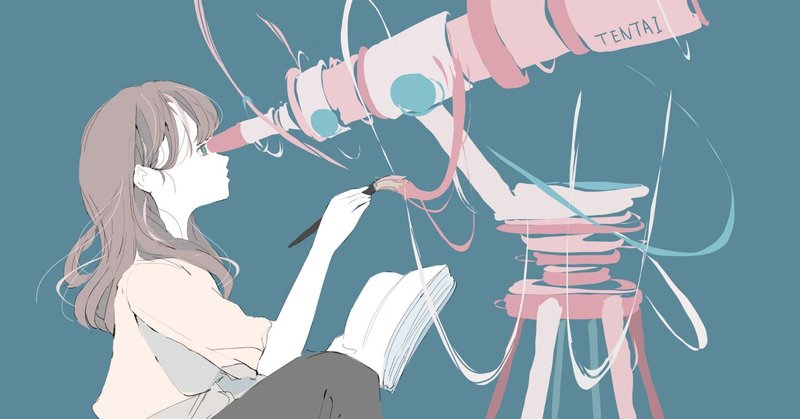
短編小説『彼の宇宙船、彼女の惑星』
「note創作大賞」の中間選考通過作品
*
田中コボルの本当の名前は、ナヤ・サガラ・ハラヤカタサァハナルという。誰も、そのことを知らない。なぜならば、彼は、ほかの渦巻き銀河からこっそりと訪れた調査員だから。
この惑星に赴任して、はや三年。人類のフリをして、中央区荒獅子町に3LDKの高級マンションを借り、何不自由なく、ひとり気ままに優雅に暮らしている。その生活の様子はすべて、母星に四次元トランスミットされる。それ自体が、重要な任務なのだ。
毎朝、必ず、七時に起きる。目覚ましは必要ない。パジャマのままでキッチンに入り、ラジオのワールド・ニュースを聴きながら、全粒粉のふわふわのパンケーキを焼き、豆の産地にこだわった珈琲をいれ、自然解凍したストロベリーをヨーグルトに散らす。慣れた手つきで、少しも無駄な動きがない。ゆったりと一時間、意識的にきちんと咀嚼して、豊かな地球のブレイクファストを楽しむ。
たとえ、雨の日でも、田中コボルにはやらなければならないことがある。さすがに、台風のときは休ませてもらったけれど。それは、午前中、寺や神社の多い近所を出歩き、ノラ猫たちを探して、専用のポラロイドカメラで写真を撮ることだった。
ビー玉のように美しい猫の眼は、時に丸くなったり、細くなったり、暗がりで光ったり。その微妙な変化から、生物学上のさまざまな、あらゆることを分析、学ぶことが出来る。
なによりも、その遠い星からの来訪者は、ノラ猫たちの自由な生き方に尊敬の念を抱いていた。
昼食は、駅前の商店街にある寿司屋のカウンターで握りを摘むか、洋食屋でオムライスかポークソテーをオーダーすることがほとんどだった。
そのあとは決まって、公園通りの喫茶店『ヌーン・ムーン』に立ち寄る。サイフォンで淹れてもらった珈琲を飲みながら、真空管アンプで初期のジャズを聴くことが出来るのだ。
田中コボルは、そこでかかるシドニー・ベシェのソプラノ・サックスやクラリネットの音色を特に好んだ。
そして、その若い女主人の可憐な笑みも。
だが、その日は、いつもと様子がちがった。
ほかの客が誰もいない喫茶店で、彼はカウンターの一番奥にひっそりと座って、すぐに気が付いた。
カップに珈琲を注ぐ女店主の背後には銀色のCDプレイヤーが置かれてあり、軽やかなジャズ・ピアノが流れていたのだ。
それは、『ヒッコリーハウスのユタ・ヒップ』、1956年の録音だった。なかなか悪くないアルバムなのだが、初期のジャズではなかった。しかも、自慢の真空管アンプはどうしたのだろう?
頭の中で大きな疑問符が浮かび、彼は思いきって、彼女に初めて話しかけてみようと決心した。
「故障ですか?」
壁際の木製スピーカーをチラッと見やり、彼が訊ねた。
「はい、そうなのです。今朝、修理の方を呼んだら、三週間以上もかかるって。しかも、あんまり見積もりが高くて驚きました。仕方がないから、これを買ってきて、やっぱり、全然違いますね」
彼女はほほ笑み、CDプレイヤーを指差した。
「もちろん、違います」
と、彼もほほ笑んで同意した。
「亡くなった夫の道楽だったので、機械はまるで分かりません。本当に悩ましいわ。クリームはお使いになりますか?」
そう言いながら、彼女はスマトラの珈琲を彼の目の前に静かに置いた。
彼は首を横にふり、
「ブラックで」
と答えた。
スマトラを飲みつつ、ふと彼は考えた。
規則には反してしまうが、ここで少し、我が星のテクノロジーを使ったからといって、決して怪しまれることはないだろう。
「ちょっと、ぼくに見せてもらえますか?」
と彼は立ち上がり、食器棚の下に設置された古めかしい音響機器まで歩いていった。一瞬、彼女はこの申し出に躊躇っていたが、微かな希望を感じているようでもあった。次に、彼は一風変わったデザインの腕時計のダイヤル・リングを左へ四十五度回した。十年くらい、局所的に時間を巻き戻せばいい。それから、彼は音響の電源を入れてみた。
問題なく、いつものように、真空管アンプから初期のジャズが流れはじめた。ルイ・アームストロングの名演奏『アリゲーター・クロウル』だった。
「壊れていませんよ。接触が悪かっただけです」
と彼は言った。
「嘘っ」
と彼女が声をあげ、満面の笑みを浮かべた。
田中コボルは思う。この女店主の美しさは、極めて自然だ。例えるなら、雪の結晶か。それとも、薄紫のシオンの花を想像させる。いや、小プレリュードハ長調。バッハのピアノ曲に似ているのかもしれない。なんて、人間は素晴らしい生き物なのだろう。
翌朝、青い空の下、田中コボルがいつものように専用のポラロイドを持って、誰もいない小さな市民公園の前を通りかかると、とても奇妙な光景を目にした。
一匹の大きな白い猫が古びたブランコに乗って、優雅に揺られていたのだ。それは、シベリア由来の名前を持つサイベリアン・フォレスト・キャットだった。
飼い主の姿は見当たらない。
彼は早足で近づいていき、カメラを構える。
シュールリアリスティックな眺めだな。
「ナヤ・サガラ・ハラヤカタサァハナル、写真なんかやめて、きみもブランコを漕ぎなさい。くたびれた脳が癒されるわよ」
そのサイベリアンは、太くて、かすれた女性の声で話しかけてきた。
一瞬、彼は驚いたが、すべてを理解して、あぁ、つまらないと気持ちが冷めてしまった。
この猫は猫の姿をしているが、本当は猫なのでは無く、母星からやって来たメッセンジャーなのだ。
彼は言われた通り、サイベリアンの隣のブランコに腰かけて、ゆっくりと自分も漕ぎ始めた。すぐに目を閉じたくなる。そよぐ風、揺られる心地よさ。確かに、悪くない。
「さて、評議会からの連絡を伝えるわ。第三惑星でのきみの滞在は、あと十日間と決まりました。速やかに退去の準備を始めるように」
とサイベリアンが単刀直入に言った。ブランコに揺られながら。
「急ですね。まだ、三年任期が残っているはずですが」
と彼は聞き、ブランコを漕ぐのをやめた。
動揺していた。この星を離れたくない。
サイベリアンは、すぐには返事をしてくれなかった。
「ぼくの調査に不備でもあったのでしょうか?」
待ちきれず、彼は膨らむ不安をぶつけた。
「いいえ、むしろ、評議会はきみの堅実な働きを高く評価しているわ」
とサイベリアンは言った。
「それでは、何故?」
「…」
「後任との引き継ぎ期間は?」
と彼は訊ねた。
「後任は来ません」
とサイベリアンが答えた。
「後任は来ない?」
と彼は言葉を繰り返した。嫌な予感がする。
「この惑星は破壊されます。評議会が、最終的に存在価値を認めなかった。残念だけど、これは決定事項なの」
サイベリアンはそう言うと、ブランコから飛び降りて、見事に地面に着地した。
地球が破壊されてしまう。そういうことか。
彼もブランコから降りる。
めまいを感じるし、言葉は出てこない。
「ナヤ・サガラ・ハラヤカタサァハナル、ひとつ、個人的に聞いてもいいかしら?」
とサイベリアンが彼を見上げた。
彼は頷いた。
「どうして、わざわざ、きみは調査対象に人類を選んだの?この惑星には、クジラやイルカのように明らかに優れた生命が存在するのに」
サイベリアンの青い目が光った。
「確かに、人間は自滅的で愚かな生き物です。けれども、夢を実現できる特別な能力がある。ぼくは、その可能性を信じてみたかった」
と彼は素直に答えた。
夢を実現できる能力。
だが、それもあと十日限りなのだ。
昨晩は、ほとんど食事が喉を通らなかった。
せっかく、嵯峨町の人気のトラットリアを二週間前から予約して、レモンのハチミツをたっぷりとかけたクアトロフォルマッジ…石窯で焼いたナポリ風のピザをオーダーしたのに…そのかわり、カンパーニャの赤ワインを二本も空けてしまった。
結局、夜明けまで一睡も出来なかった。ウオッカ、ウィスキー、テキーラ。アルコールの大海に浮かびながら、田中コボルはただひとつのことを考え続けていた。
それは、この蒼い惑星の四十六億年目の悲劇に関してでは無く、公園通りの喫茶店『ヌーン・ムーン』の名前も知らない女店主に訪れるであろう、無慈悲な死についてだった。つまり、彼は、彼女をこのまま失うことに耐えられそうになかった。
それから、朝食も食べず、野良猫の撮影任務も放棄して、十一時のオープンに合わせて女店主に会いに行った。
うわの空でメニューを眺め、ハワイアンコナ珈琲を注文すると、うまく話を切出せるだろうか、と徹夜で考えてきたシナリオに不安を感じた。
「これ、修理の御礼です」
女店主は、ハワイアンコナと共にガトーショコラを出してくれた。
「小麦粉を使わないで焼きました。タマゴとチョコレートを丁寧に混ぜると、しっとりとするの。クルミがたくさん入っています。召し上がっていただけますか?」
「チョコレートは何より好きです。だけど、ぼくは何もしていませんよ。電源スイッチを入れただけだ」
と彼は答えた。
「いいえ、あなたのおかげよ。笠井かすみ、です。おととい、お名前を聞きそびれたから」
彼女が、ほほ笑んだ。
「かすみさん、ですね。ぼくは、田中コボル」
彼も、ほほ笑んだ。
「こぼる?」
「カタカナで、コボル……と書きます」
「外国の名前みたい」
「遠い、遠い国の血が混ざっています」
「どう見ても、日本人ですよ」
「人は見かけによらない」
店内には、ジョージ・ルイスのクラリネット曲が流れていた。都合良く、他の客が誰も来なかった。今しかない、と彼は判断した。
「ガトーショコラ、美味しかった。ご馳走さまでした」
「もっと召し上がりませんか?」
「はい、お言葉に甘えて。しかし、あのぅ、ねぇ、かすみさん、今から、ぼくは突拍子もない話をしますが、真面目に最後まで聞いてもらえますか?」
と彼は言い、言葉の力を信じなければと思った。
真っ直ぐ、彼女が彼の目を見つめた。
「コボルさん、この店の常連になっていただいて、二年以上になります。ほとんど言葉を交わさなかったけれども、あなたが紳士的で誠実だと分かりましたわ。そんな方がそうおっしゃるのだから、もちろん、わたしはきちんとお聞きしますよ」
「ありがとう、ありがとう」
と彼は二度繰り返した。
田中コボルは、少しのあいだ、笠井かすみの背後の壁に飾られた絵画ポスターを眺めた。それは、帝政オーストリアの画家グスタフ・クリムトの油絵『接吻』だった。
彼女は店の黒っぽいフローリングを見つめ、彼の言葉を待っていた。
「ぼくの存在にはあなたが必要だ。どうしても必要だ。ぼくはそれをあなたに承知してもらいたいのです。承知してください」
と彼は唐突に言った。
彼女の目には、驚きと涙が浮かんだ。
「ずるいわ。それ、夏目漱石の『それから』のセリフじゃないですか」
と彼女が言った。
「ご存知でしたか。ぼくの気持ちを最も的確に表していると思ったのです。ねぇ、かすみさん、承知してくださるでしょう?」
と彼は言った。
彼女は戸惑った。すぐに返事をすることが出来なかった。白いブラウスの袖で涙を拭いた。
「あなたが好意を持ってくださっていることは、初めから気付いていました。とても感じのいい方だと思ったから、わたしは嬉しかった。でも、正直、告白されるのがずっと怖かったのです」
まぶたの赤くなった目で、彼女はそう言った。
「怖かった?」
「五年前の夏、夫を癌で亡くしました。それから心が空っぽになって、安定剤を飲みながらひとりで頑張ってきました。何故生きなきゃいけないんだろう。将来、どうなるんだろう。死んだらどこに行くのかしら。そんなことを考えたら、怖くて怖くて、夜眠れなくなりました。そんな生活が何年も続いて、何もかも自信がなくなって、他人と関わるのが恐ろしくなってしまったのです」
彼はたまらなく愛おしくなり、この地球の女性を抱きしめたいと思った。なんとしても、守りたい。
「どうか怖がらないで」
そう言って、彼は一風変わったデザインの腕時計のダイヤル・リングを左へ四十五度回した。
「あっ」
彼女は、急に貧血でも起こしたかのように、その場にしゃがみこんだ。
いつの間にか、ふたりは広大な宇宙空間に浮かんでいた。眼下には、蒼い地球が怪しく光っていた。そこは、公園通りの喫茶店『ヌー・ムーン』ではなかった。
「ここは、透明な宇宙船の中です」
そう言って、彼は怯える彼女の手をとり、ゆっくりと立ちあがるのを手伝った。
「コボルさん、これは一体」
と彼女の声が震えていた。
「ぼくは、他の惑星からきました。かすみさんには、すべてを知ってほしい」
と彼は言った。
「他の惑星?」
そう言って、彼女は息を呑んだ。
彼は腕を組んで、にっこりと頷いた。
「本当は、人間に絶対に知られてはいけないのです。厳しい規定がたくさんあって。でも、そんなことを言っていられなくなりました」
と田中コボルは言った。
「とても現実だと思えないわ」
と笠井かすみが言った。
星々の輝きが、明らかに違った。空気のある地上からでは、こんなに無限に…ダイヤモンドのように輝かない。
「何千年ものあいだ、ぼくたちは地球を観察してきました。あなたたちの存在価値を認めるべきか、認めないべきか。そして、ある結論に達したのです」
彼が足下の地球を指さした。
目を見開いて、彼女は固まった。
無数の流星が落ちていく。
紫色の美しい火の玉。
空と海の真っ青な惑星が、
赤茶けた色に染まっていく。
焼き尽くされてしまう。
「十日後の未来です。こうやって、世界は終わる」
と彼は言った。
真実は、彼女の理解を超えていた。伝わったのは、恐怖だけだった。
「どうして、こんな恐ろしいことを」
彼女は、自分が正気を失ったのだろうと思った。
「残酷だが、もはや、世界滅亡を止めることは不可能だ。でも、あなただけなら、なんとか救うことが出来る。かすみさん、ぼくと一緒に逃げてください」
と彼は言った。
「一緒に逃げる?」
「何処へだっていい。この宇宙船なら、ブラックホールの果てまでだって行けます」
「これは、何かのトリックです。きっと、催眠術なのでしょう?」
と彼女は言った。すっかり、青冷めてしまっていた。
彼は、悲しげに首を横にふった。
すると、突然、彼女は笑った。狂ったように。可笑しいことなど、何もありはしないのに。限界だったのである。
彼が黙って見つめると、彼女は泣きだした。
「コボルさん、もうたくさんです、お願い、わたしを目覚めさせてちょうだい」
やはり、無理だったのだ。
彼は諦めるしかなかった。
「かすみさん、分かりました。ぼくが、これから三つ数えます。そうしたら、目を覚ましてください。そして、あなたは今日起こったことを憶えていない」
救われたような表情になって、彼女が頷いた。
「三、二、一、」
そう言って、彼は一風変わったデザインの腕時計のダイヤル・リングを左へ四十五度回した。
五年前。その朝も、笠井かすみは入院している作家の夫のために特製の飲みものを作って、見舞いに出かけた。ヨーグルトに黒胡麻、バナナ、小松菜、生姜、マヌカハニーをジューサーにかけた。神聖な儀式のように。
「半年はもたないと言われたのに…二年以上も、俺は生きている。お前のジュースのおかげだね」
とパジャマ姿の夫が言った。
二度の抗がん剤治療で抜け落ちてしまった体毛。頭髪だけではなく、眉毛まで完全になくなっていた。肥大した腫瘍によって栄養をすっかり吸収され、やせ細っていた。当時の体重は、三十キロを切っていたはずだった。
彼女は、夫と共に生きたいと願った。彼女は、夫と共に死にたいと願った。生と死。このふたつの言葉が頭の中で区別がつかなくなった。毎日、ひとつ、夫は詩を書いた。どんなに体調が悪くても、必ず書いた。短いものも、長いものもあったが、得意の嘘は書かなかった。
「こんなことになるくらいなら、金儲けなんか考えないで、もっと普遍性のある文学を書いておくべきだったな。俺の小説は大衆に迎合したものばかりだから、十年後には誰も読まないだろうよ」
死の影を感じながら、夫が言った。
「十年後のことなんか、誰にも分かりません。あなたは一生懸命にやってきたのだから、それだけで価値がありますよ」
深い尊敬を込めて、彼女は答えた。
あれから、九日間が過ぎた。
結局、彼女を救えないのだ。そう考え、田中コボルはマンションから一歩も外出しなかった。というよりも、赤いソファに横たわり、微動だにしなかった。食事はおろか、水分の補給すらしなかった。普通の人間であれば、間違いなく死んでいただろう。幸か不幸か、彼は人間ではなかった。
その日の午後、玄関のインターホンが鳴らされた。黒いスーツを着たその訪問者は、年齢不詳の坊主頭で、奇怪な程に印象に残らない表情の男だった。
住人から返答がないと分かると、その男は厳重に鍵のかかったドアを魔法のように簡単に開け、部屋に土足で入っていった。
それから、赤いソファに近づいていき、田中コボルの頭部を両手で抱えると、器用に三百六十度回転させた。すると、胴体から簡単に外れた。血は一滴も流れなかった。
「ナヤ・サガラ・ハラヤカタサァハナル、評議会の連絡を伝える」
と男は言った。
「放っておいてください。もうすぐ、ぼくは地球と一緒に滅びるのだから」
首だけになっても、彼は話すことが出来た。
「直ちに修理を開始する。きみは我々の多次元的な管理下にあるのだ」
「修理しても、ぼくはもう働きませんよ」
「きみの任務は終わっていない。評議会は、さらなる二年間の調査延長を決定した」
「調査延長?」
彼は自分の耳を疑った。
「過去九日間の四次元トランスミットは、非常に興味深いものだ。特にあの現地人の女性に対するきみの感情パターンは完全なる想定外だった。なぜ、きみがこの未開の惑星と運命を共にしようと覚悟を決めたのか…評議会はその原因を二年間かけて分析を試みる。そのような自己破壊的な行動は、きみの人工知能にプログラムされていないからだ」
と男は言った。
彼は喜びの興奮を抑えきれなかった。
地球の寿命が延びたのだ。
「さぁ、ぼくを修理してください。一刻も早く、調査対象の元に出かけたいのです」
その夜、必要最小限の修理を終えた田中コボルは、公園通りの喫茶店『ヌーン・ムーン』へ駆けこんだ。閉店まで、あと三十分だった。
右耳の不具合を感じながら、うわの空でメニューを眺め、ハワイアンコナ珈琲を注文すると、女店主にうまく想いを告げられるだろうか、と改めて書き直したシナリオに不安を感じた。
「これ、修理の御礼です」
彼女は、ハワイアンコナと共にガトーショコラを出してくれた。
「小麦粉を使わないで焼きました。タマゴとチョコレートを丁寧に混ぜると、しっとりとするの。クルミがたくさん入っています。召し上がっていただけますか?」
「チョコレートは何より好きです。だけど、ぼくは何もしていませんよ。電源スイッチを入れただけだ」
と彼は答えた。
「いいえ、あなたのおかげよ。笠井かすみ、です。このあいだ、お名前を聞きそびれたから」
彼女が、ほほ笑んだ。
「かすみさん、ですね。ぼくは、田中コボル」
彼も、ほほ笑んだ。
「こぼる?」
「カタカナで、コボル、と書きます」
「外国の名前みたい」
「遠い、遠い国の血が混ざっています」
「どう見ても、日本人ですよ」
「人は見かけによらない」
店内には、ジョージ・ルイスのクラリネット曲が流れていた。
都合良く、他の客が誰も来なかった。 今しかない、と彼は判断した。
「ガトーショコラ、美味しかった。ご馳走さまでした」
「もっと召し上がりませんか?」
「はい、お言葉に甘えて。しかし、あのぅ、ねぇ、かすみさん。いいえ、なんでもありません。また、明日も来ますから、その時に食べてもいいですか?」
頭が真っ白になってしまい、彼は愛の告白をするタイミングを見失ってしまった。
すると、真っ直ぐに、彼女が彼の目を見つめて言った。
「コボルさん、わたし、勝手ながら、すごく心配していたのです。九日間もいらっしゃらなかったから、ひょっとして嫌われたのかと思いました。でも、安心したわ。明日も来てくださるのね。約束ですよ」
田中コボルは思う。この女店主の美しさは、極めて自然だ。例えるなら、雪の結晶か。それとも、薄紫のシオンの花を想像させる。いや、小プレリュードハ長調。バッハのピアノ曲に似ているのかもしれない。なんて、人間は素晴らしい生き物なのだろう。
*
喫茶店『ヌーン・ムーン』を後にして、田中コボル、ナヤ・サガラ・ハラヤカタサァハナルは、誰もいない公園へひとりで入って行き、錆びたブランコに腰かけた。
そよぐ風、揺られる心地よさ。頭上には、満天の星たちが見えた。
いつか、聞いたことがある。人間は夜空に願いごとをするらしい。呆れるくらい原始的ではあるが、それも案外悪くないかもしれない、と彼は思った。そして、こう願った。
どうか、世界が滅びませんように。
この幸せな瞬間がずっと続きますように。
THE END
『彼の宇宙船、彼女の惑星』
イラスト/ノーコピーライトガール
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
