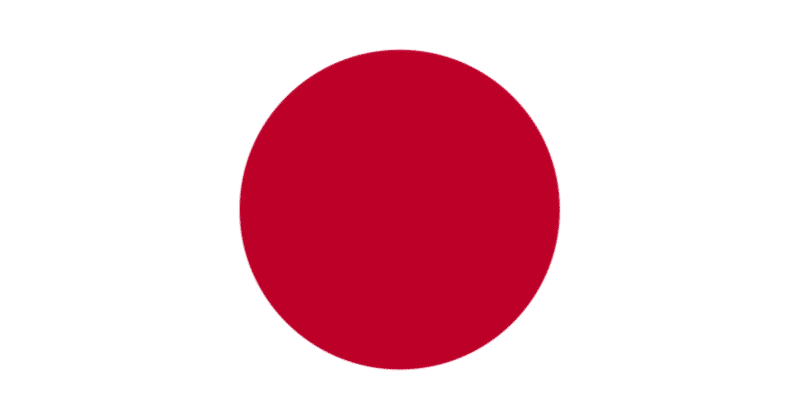
1945年、終戦の日の「朝鮮人」と「支那人」
「戦争に負ける」ということ
今日は建国記念日だが、最近の若者は、
「日本は戦争に負けても構わない」
「少し領土を取られても平気」
とか言うそうだ。
もしかしたら、日本がかつて戦争に負けたことも知らないかもしれない。
それは明らかに、アメリカの占領政策が史上まれなほど寛容だったからだろう。(その前の大空襲と2度にわたる原爆投下による市民の大量殺傷を忘れるわけにはいかないにせよ。)
1945年8月15日、戦争に負けたことを日本国民は知ったわけだが、天皇の玉音放送は言葉が難しく、また聞こえも悪くて、何を言っているか庶民にはわからなかった。
「戦争に負けた」という意味を日本国民が実感したのは、その日を境に、朝鮮人と支那人の日本人に対する態度が、一変したときだった。
火野葦平の『革命前後』(1960)は、九州で終戦を迎えた火野が8月15日前後の様子を細かく書き記した小説だ。そこから、朝鮮人、支那人が登場する部分を抜粋する。
『革命前後』は1959年に「中央公論」で連載され、1960年に刊行後、日本芸術院賞を受賞した。芥川賞作家・火野葦平の代表作の一つだが、現在は読みやすい形で流通していないので、知らない人も多いと思う。
もちろん「朝鮮人」「支那人」は歴史的呼称として使われている(現在は国が変わっており、この名で呼ぶのは差別以前に失礼である)。
また、文中の「ヨボ」は、朝鮮語の二人称で、当時日本人は朝鮮人のことをそう呼んでいた。蔑称と認識されるので現在は使ってはならない。
「あんた、ポツダム宣言を知らんのか」
日本酒もビールもないので、物資集めの名人谷木順が、朝鮮部落に出かけて行って、マッカリを一斗ほど買いこんで来た。しかし、谷木の報告によると、朝鮮人の態度が八月十五日を境にして、まるで変わったという。
「あいつ等、まるきり戦勝国民のような面(つら)をしやがってな、お辞儀もしやがらんのじゃ。一昨日(おととい)まではマッカリを買いに行くと、よろこんでペコペコしとったのに、今日は、まるきり、お前等に売ってやる、いいや、恵んでやるという態度さ。いつも買いに行く御堂川(みどうがわ)の金山がーーおい、金山、また頼むぞといったら、返事もしやがらん。金山、頼むぞ、と同じことを二度いったら、やおら、こっちを向いてーー戦争に負けた国の者が、独立国の国民を呼びすてするとはなんか、とぬかしやがる。お前らがいつ独立したんじゃ、とおれが訊いたらーーあんた、ポツダム宣言のこと知らんのか、とこそ。もう日本の属国じゃないというんじゃ。普段ならぶんなぐってやるところじゃが、怒らせたら酒を売ってくれんけ、我慢して、金山さんと呼んで、やっと一斗分けてもろて来たんじゃ。値段も前の倍取りやがった。糞面白うもない。ヨボに威張られるなんて・・」
(社会批評社版「革命前後」上巻、p236)
「負けた国が、生意気な」
江川の鉄橋を渡り、二島(ふたじま)駅に着いた。ここでは降りる者よりも乗る者の方が多かった。しかし、満員のため、大半が積み残された。
ところが、フォームに四、五人いた朝鮮人が、
「こらァ、日本人、降りれ。降りんか」
「負けた日本人、退(と)け」
などといいながら、デッキにいる客を片はしから引きずりおろし、みんな乗りこんでしまった。そして、一人の菜っ葉服を着た、菊石(あばた)の深い大男が、外に向かって、
「駅長、汽車を出(た)してもようし」
と、どなった。
ベルが鳴り、列車が動きだした。
さらに、朝鮮人たちは乱暴に入口の客を押しのけて、箱の中に入りこんで来た。
「こらア、立て」
「負けた国が腰かけとるなんて、そんな生意気があるか」
などと喚きながら、坐っている乗客を五、六人、腕や襟首をにぎって無理矢理立たせ、自分たちが腰かけてしまった。
「ひどいことをしやがる」
と、見ている者はみんな呟いていたが、誰一人、朝鮮人たちの横暴を止める者はなかった。立たせられる人たちも不服そうに、腹立たしそうにしていたが、抵抗した者はいなかった。女子供だけではなく、三十人くらいの青年や、五十がらみの親父もいたのに、朝鮮人のなすがままだった。勝ち誇ったように、朝鮮人たちは横柄な格好で、煙草をふかしたり、センベイをかじったりしはじめた。ニンニクのにおいが車内にただよって来た。
「まるで、あいつ等、戦勝国みたいな顔してやがるな」
「これまで、ヨボ、ヨボといわれて馬鹿にされた仇討をしよるつもりなんじゃ」
そんなことを囁きあっている客もあった。
(上巻、p278)
「戦争に負けるのは、情けないもんじゃのう」
裏に朝鮮人の長屋があった。(中略)いわば長く世話をしてやった子飼いの連中である。その長屋の大山という男の女房が、終戦の日の午後、松江の顔を見ると、
「日本、負けて可哀そなね」
と、いった。
同情したいいかたではなく、憎々しげな、ざまみろといった口吻と態度だった。
中には、日本の敗戦を悲しむ朝鮮人もあって、母のところへ来て、いっしょに泣いたという。
「一番困ったのは、支那人じゃよ。わたし等、そのときまで知らんだが、九州造船で支那人の捕虜を何百人も使うとったらしいね。いずれも上海か南京の方から、労働力不足のためにつれて来たのじゃろう。それが終戦になってから、毎日出て来てのう。全部じゃないが、二、三十人がゾロゾロ街を歩きまわって、時計屋に入りこんでは時計や指輪をとったり、洋服屋や呉服屋に入りこんでは着る物をとったり、あばれ放題でなあ。道通る日本人の頭をぶんなぐったり、飲食店に入ってタダ食いしたり、そりゃあひどいもんじゃったばい。警察はまるであってないとひとつこと、相手が戦勝国じゃもんじゃけ、どんな悪いことしても手出しをしきらん。このために、街の店は閉めきってしまうし、女子は逃げてしまうし、一時はどうなることかと思うた。そしたら、支那の蒋介石が、日本人をいじめてはいけんとかなんとかいう訓旨を出したとかで、捕虜の中にシッカリした者が居って、昨日からは街に出て来んようになった。実際、戦争に負けるちゅうもんは情けないもんじゃのう」
(下巻p6)
「仕方のないこと」
朝鮮人や支那人の態度の変化を見た日本人は、占領軍としてやってくるアメリカ人には何をされるだろう、と恐れた。その上陸前に街から逃げ出す者もいた。
著者火野葦平の投影である、主人公の辻昌介は、朝鮮人や支那人の横暴と日本人の卑屈に怒りながらも、一方で仕方のないことと感じる。自分も米軍に処刑されるかもしれないと覚悟し、それは、日本軍のやったことの「弾ね返り」だと理解する。
こんなにも占領軍を恐れているのは、嘗て、日本の占領軍が占領地でなにをしたかということが弾ね返って来ているにちがいないからである。残念ながら、日華事変以来、太平洋戦争の戦勝時代、敵地を奪取した日本の占領部隊は、勢あまって現住民を苦しめたことがなかったとはいえない。殺人、暴行、掠奪、放火、強盗、強姦ーー人間の正常心を失った戦場の鬼となって、それらの行為をした。むろん、軍としては兵隊をいましめ、現地人への不法行為をしないように注意はしたが、殺気だった兵隊の心を静めることが出来なかった。それが今、自分の方の問題になって来たのである。占領軍はそうする者だと国民までが考えていた。特に婦人は強姦を恐れた。昌介も多分に漏れないのである。中国から南方にかけての八年間、どこの戦線でも、日本軍が抗日文化人を逮捕し処刑するのを見て来た。
(上巻、p224)
『革命前後』は、アメリカ占領軍人の乱暴も描いているが、結局は日本軍が中国でしたようなことは行われず、やがて日本人は占領軍を熱狂的に歓迎するようになる。「マッカーサー神社」を作って感謝の意を表そう、という運動が起こったのは有名だ。
「戦勝国」である蒋介石の国民党政府に日本を占領する余裕はなかっただろうが、社会主義国のソ連が日本を(部分的にでも)占領する可能性はあっただろう。その場合、どうなっていたか。
いずれにせよ、歴史の事実としては「寛容」なアメリカに占領支配された。
その結果、日本人は「戦争に負ける」とはどういうことか、忘れた。
しかし、戦争中の日本人の行いに対する思いは、中国人、韓国人、北朝鮮人の中に、庶民感情として引き継がれていて、いまも「歴史問題」として残っている。それは、政府どうしの交渉で何とかなるものでもないと思う。
日本はかつて確かに「戦争に負けた」ということ、近隣の国民に「負けた国が、生意気な」という感情が存在したこと、そして、もしかしたら今も存在することを、日本人は忘れてはならないと思う。
<参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
