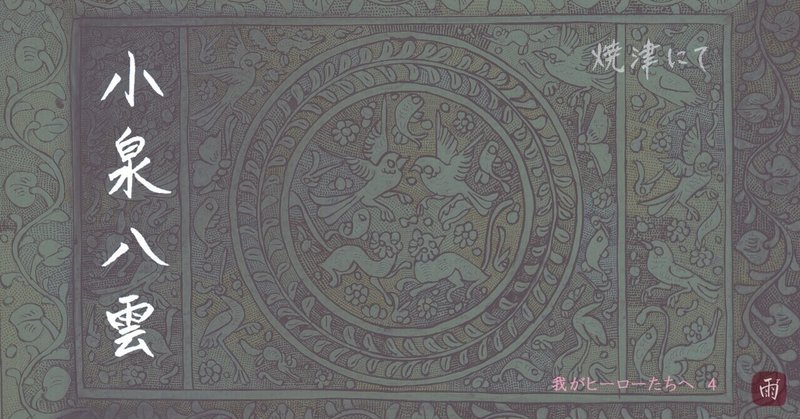
麗しのナイフ 『小泉八雲』(2020年 文庫/MUJI BOOKS 人と物13) 無印良品
先日、出先でふらりと入った無印良品でこの文庫を見つけた。
日本の各方面の作家陣から独自に選んだ人物を一冊ごとにまとめたシリーズらしく、その中から3名の人物をフルカラー版で製本しセットにした商品が数量限定で売り出されているのがまず目に留まったのだが、その脇に並べられていたのがこれら従来の単品である。
少し考えた末、単品の『芹沢銈介』と『小泉八雲』を購入することにした。
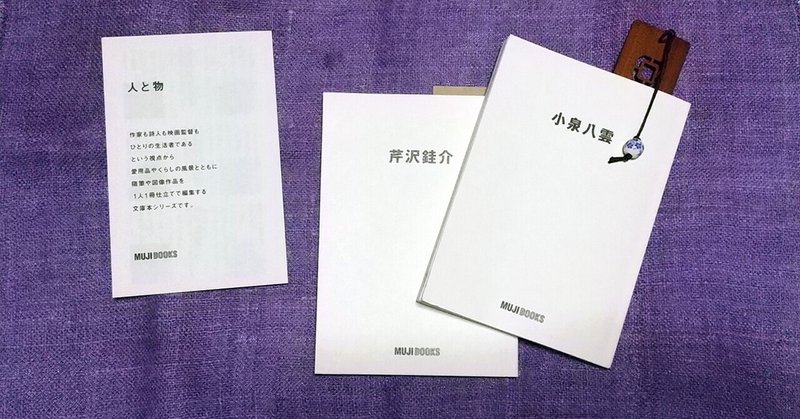
装丁が手に取りやすく、要所が押さえられていて、気軽に読むことができるのがメリット。(『芹沢銈介』はご本人が染色家のため図録も多く、カラー版を購入する価値を感じたが、バラ売りされていなかったので仕方ない!)¥500[税別]という価格をどう判断するかは人によりそうだ。少なくともこれから取り上げる『小泉八雲』には、筆者にとって不朽の愛読作『耳無し芳一』も収録されており、個人的に損した感はない。
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)好きであることは以前にも書いている。片方の視力を失っているにも関わらず、ほとんど霊感とも言える感受性をもって、“日出る国”の異国情緒の奥にあるささやかな風物や習俗を、ところどころに錦が織り込まれた反物を愛でるが如くこまやかに捉えた人であった。おそろしくよく見えたであろう白濁した左目はどことつながっていたのか。是非いつかお目にかかり伺ってみたいものだ。
さらに驚かされるのは、それを細部まで表現する力であろう。怪談も随筆も読めばまるで自分がそこにいるかのように映像が浮かび、音が響いてくる。
『小泉八雲(1850-1904)』に収録されているのは、ハーン氏が大切にしていた物やゆかりの雑貨、また多数の著述からピックアップした象徴的な短い言葉たち、写真や直筆の手紙や絵(絵もうまい…!)、そして著作の中から怪談と随想が数篇と、豊富な内容。今回は主に、随想『焼津にて』を読んだ感想を書き置いておこう。
***
『焼津にて』は1899年に初版が発行された〔霊の日本〕の中の短編である。晩年、ハーン氏は静岡の焼津の地を気に入って、夏場によく家族で訪れてはしばらく滞在していたといい、その際に見聞し感じたことなどが描写されている。ちなみに原文は英文だ。
この文庫に収められているのは〔虫の音楽家〕からの抄録であり、元の全文ではないことを補足しておく(全文はもう少し長い)。訳者は池田雅之氏。情感のある対訳が優美ですばらしい。
筆者が本作中ひときわ印象的だったのは、お盆に行われる精霊流しにまつわる部分だった。遠い異国出身の彼にとって、それは興味深かったであろう!ぜひ見物したいと思っていたのにうたた寝をしてしまい、あわてて行ったら終わっていた時のショックは察するに余りある。……しかしだ。
夏とはいえ、誰もいなくなった盆の宵の海に飛び込み、遥か彼方にぼんやりひしめく灯籠を追って泳ぐのはガチすぎる。『そうだ あれを、追おう。』じゃない。ハーン氏が焼津を初めて訪れたのが1897年で、1904年に54歳で亡くなっているわけだから、どう少なく見積もっても、アラフィフである。しかも当時の。これを読む限り、彼は至って純朴に、どうしても精霊流しを見たくて行動したまでであった。追いついた灯籠に(追いついてるし)自分が害をなすことがないよう注意しながらも、つぶさに眺め回しているのだ。奇跡のアラフィフとはこのことか。←
ただ、潮水に浸かり揺らめく灯明を見ているうちにだんだんこわくなってきて、『あたりには誰もいないが誰もいないわけでもないんじゃないか…?』という物々しいあるあるに耽っていくわけだが、まあ無理もない。(結局、世話になっている宿の夫妻に「お盆の海になんか入っちゃダメ」と咎められるはめに笑) 命知らずで得たものもあるのだろうから、差し引きゼロか。いや、人の生とはそうしたものかもしれない。(納得すんなよ)
*
ついでに同文庫内に収録されている『東洋の第一日目』で印象深かった点を添えて、感想を締めることにしよう。日本の風情を愛し後に日本人となった八雲氏は、この時点でいわゆる西洋文明社会に警鐘を鳴らしまくっている。それは、自身が見慣れてきたものと対比して、異文化がよりよく映ったという面もあるのではないか。
ただ、自然とともに育まれてきた芸術的風土に感銘を受け、そこが次第に侵されていく可能性をやるせなく思う気持ちが反映されているように感じる。それが表現される時でさえ、丁寧に磨かれた精緻な装飾が施されているナイフが、スッ…と風をたなびかせるようなのだ。今、何が起こったのかと瞬きするほどに笑 とはいえ、これほど日本の文化を魅惑的なものとして捉えていただいていたとなれば…その麗しのナイフには苦笑するしかない。
***
筆者は元々、世人にどことなくあやしまれるもの、日陰になっていることなどに、なぜかずっと興味をひかれてきた。ほとんど無意識とはいえ、そこに散らばっている砂金は、価値を見出す者にとって貴重である。バカにされるものには純粋さが宿っていたりする。
この世には、確かに見苦しいことも多い。それは古今東西においてである。ただ、びっくりするほど煌めいているものもちゃんとあるのが救いなのだ。
筆者は、何らかの美しさ(及びおもしろさ)を覚えるもの以外に、この世にさほどの関心はない。きっと死ぬまでそれだけを灯火に生きていく。それを自ら体得し決められるというのが自分の幸せだ。あとは流れに任せるまで。輪っかはつながって巡っていると思っている者は、灯籠のように流れた先でいずれ藻屑になるとしても、意外と孤独ではない。花も嵐も魂も、太古から今日まで、いつもどこかで漂っている。
妙なもん見たけどなんか元気になったわ…というスポットを目指しています
