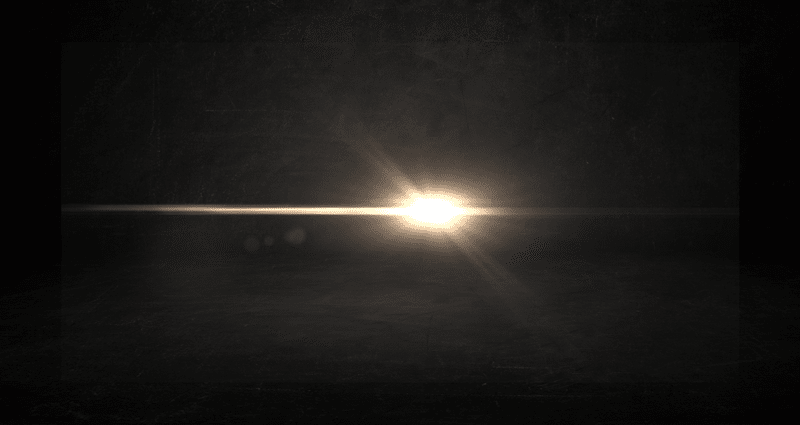
- 運営しているクリエイター
記事一覧
出生(僕が失明するまでの記憶 1)
第1章 少年時代
1977年5月23日、それが出生の日付だった。体重3000gを超える、病気も障害もない、ごく平凡な男児の誕生だった。そう聞いているので、僕としてはそれを信じるしかない。
当初、僕は「友博と名付けられるはずだった。父方の家で男児が生まれると「博」という文字が入れられるのが通例で、父にも祖父にも叔父にもその子供達にもその慣習が暗黙のうちに適用されていた。しかし、いざ名前を決める
幼い日の風景(僕が失明するまでの記憶 )2
幼い頃、就寝時に灯される天井のオレンジ色の豆電球を見るのが無性に怖かった。生まれて間もない赤ん坊に記憶などないはずなのに、ベビーベッドに仰向けに寝かされたときの心もとなさが、暗闇に浮かぶ亡霊のような明かりとともに蘇るような気がした。でも、それは確かな記憶というよりは漠然としたイメージだ。はっきりとした輪郭を持った記憶を辿ると、3歳か4歳頃の自宅周辺の風景が心に浮かぶ。
生まれ育ったのは大阪府
家族について(僕が失明するまでの記憶 3)
家は4人家族で、両親と兄がいた。当時としては典型的な家族構成と言える。しかし、控えめにも「典型的」とは言えない事情を、我が家は抱えていた。
学年で三つ年上の兄には障害があった。重度の自閉症とそれによる知的障害(当時は精神薄弱とか知恵遅れと言っていた)との診断で、それを証明する手帳の交付も受けていた。
兄は頑張っても2語文でしか話せなかった。「バス、来る」「テレビ、診た」「みかん、ない」といっ
続・家族について(僕が失明するまでの記憶 4)
兄の障害のことだけでも典型的な家族から逸脱するには十分だったが、さらに重大な要因がもう一つあった。
僕の家はK会という新興宗教に入信していた。熱心な信者というわけではなかったが、父方の親族が会員だったため、半ば成り行きでその一員に加わっていた。不自然に巨大な仏壇がただでさえ狭い家のスペースを占有していて、父が仕事に行く際にその前でおざなりの呪文らしきものをぶつぶつ唱える以外は無用の長物だった。
想像の翼(僕が失明するまでの記憶 5)
競争社会華やかかりし時代とはいえ、そこは昭和の小さな田舎町だった。両親とも実生活で忙しすぎたこともあってか、就学前の幼少期は教育とは無縁の生活を送っていた。塾や習い事はおろか、家で親に何かを教えてもらったことも、物語を読み聞かせしてもらったこともない。あるいは兄の世話に掛かりきりになって、僕については放任せざるを得なかったのかも知れない。そう書くとさぞ寂しい幼少時代を過ごしたものと思われそうであ
もっとみるはじめての友達(僕が失明するまでの記憶 6)
両親はお世辞にも社交的とは言えなかったので、近隣との関係は(K会の人たちを除いて)希薄だった。それでも僕には幼馴染がいた。同じ路地の並び、角の家に住むRちゃんだ。路地を一人で歩いているとき、家の庭で遊んでいる女の子と目が合い、気付けば敷地内に引き入れられ、友達になった。まだ幼稚園にも行っていない、4歳ぐらいの頃だったが、生まれてはじめての友達だった。
Rちゃんは髪がとても長く腰ぐらいまであっ
象徴的な一葉(僕が失明するまでの記憶 7)
Rちゃん以外の友達ができるのは、小学校に入学してからのことだ。性別や家柄が違っても同じ場所にいればすぐに仲良くなれるのは子供の愛すべき特権である。その例に違わず、僕にも友達と呼べる人が何人かできた。学校が終わって家に帰ってから、ランドセルを置いてすぐに友達宅へ遊びに行くこともあった。Rちゃんと同様大きな家の子ばかりで、たいていの家には発売されてまだ間もない任天堂のゲーム機があった。場違いな仏壇を
もっとみる欠落した記憶(僕が失明するまでの記憶 8)
異質なものに対して攻撃性が働くのは世の常である。いじめや嫌がらせが始まったのは2年生に挙がった頃からだった。靴を隠されたり、不愉快な落書きをされたり、後ろからボールを投げつけられたり、言い出せばきりがない。おなかが痛いと言って学校を休むこともあったし、原因不明の吐き気を催して病院へ行くこともあった。その度に「自家中毒」なる病名をもらい、甘いシロップの薬をもらって帰ってきたが、もちろん大した効き目
もっとみる我慢の限界(僕が失明するまでの記憶 9)
3年生になってクラス替えが行われたとたん、女の子たちにかかっていた魔法は跡形もなく消え、僕は不器用で口下手な、風采の上がらない男子に成り下がった。その一方、いじめは過激さを増した。粘り強く耐えはしたが、給食のシチューを頭からかけられたときの屈辱とやるせなさは今なお忘れることが出来ない。周囲の子供達はおろか、担任はいったい何をしていたのだろう。
転入してきたばかりの新米教師は、若い女の先生とあ
はじめての入院、そして手術(僕が失明するまでの記憶 10)
夏休みになってまだ間もない1986年7月23日、生まれて初めての入院生活が始まった。病院へ行く途中、バス停の近くにあった電気屋で母が小さなラジオを買ってくれた。退屈しないようにとの気遣いだったが、ラジオを聴く習慣がなかったので、ほとんど使わなかった。
申し訳ないとは思うけれど、親元を離れての生活には全く寂しさを感じなかった。眼科の一般病棟に入院している子供は珍しかったので、周囲の大人たちが親
転院(僕が失明するまでの記憶 11)
阪急神戸線の駅を降りて北上し、並木道を進み、瀟洒な家々が立ち並ぶ路地を抜けたところにその病院はあった。敷地に入っても建物にたどり着くまでにはかなり急な坂を登る必要があって、車でも明らかに傾斜を感じられるほどだった。
無機質で、ややもすれば威圧的でもあった大学病院の門構えとは異なり、簡素でこじんまりしていて、病院というよりは海外の寄宿舎か研究施設みたいに見えた。六甲の山間の斜面に沿っていくつか
変化(僕が失明するまでの記憶 12)
2学期の途中、眼帯をして学校に戻ると、担任の先生が変わっていた。頼りなげな若手教員が辞め、F先生という五十代ぐらいと思しきベテランの女性教諭が赴任し、後を引き継いでいた。背はそれほど高くないが、年齢相応な太り方をしていて威厳と貫録があった。その一方、眼鏡の奥にある細く優しい目には子供への愛情が感じられた。この先生なら信頼していいと思った。
変わったのは担任だけではなかった。クラスメイトの態度
マジックアワー(僕が失明するまでの記憶 13)
4年生から6年生までの3年間は最も平和でエネルギーに満ち、夢と希望に溢れた機関だった。おりしも昭和から平成へと時代が移ろう80年代後半はバブル景気の全盛期で、日本中がナイーヴな高揚感で浮きたっていた。
学年が上がり、他のクラスメイトより勉強ができることを自覚するようになって以後は、それを隠すでもひけらかすでもなく、アイデンティティとして受け入れるようになった。そうしたら多少嫌なことがあっても
夢(僕が失明するまでの記憶 14)
僕には夢があった。夢というよりは明確な目標であり、必ず果たされるべきミッションだった。それは、医者になることだった。
幼いころから「人の体」の図鑑を愛読していた影響そのままに、小学校に上がってからも医学や医療に関する興味は尽きなかった。その手の本を見つければ好んで読み(というよりそれ以外、特に小説や物語には全く興味がなかった)、「緊急病棟24時」みたいなドキュメンタリがあればテレビにかじりつ

