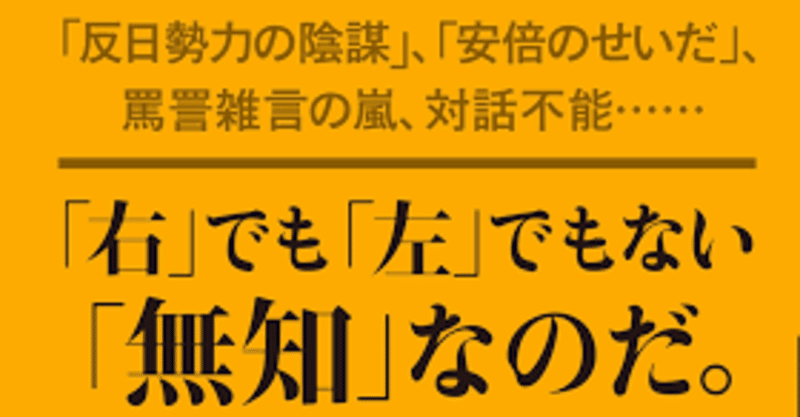
物江潤『ネトウヨとパヨク』 : 〈傍観〉批評家こそが最強
書評:物江潤『ネトウヨとパヨク』(新潮新書)
「自身の思い込みを一方的にわめき立てるのではなく、冷静な議論(対話)が出来なければならない」、ネトウヨやパヨクのような『まったく議論の出来ない人たち』になってはいけない。一一という「小学校の学級会」みたいなことしか書かれていないのが、本書である。
にもかかわらず、本書が過大に評価されることがあるとするなら、その「魅力」は奈辺にあるのだろうか。
それは、読者が著者とともに「私たちは、あいつらとは違うよね」という特権的な立場を共有し「あんなやつらとは、議論できないのも当然だよね」といった、「議論しないのは当然」という自己正当化の印籠となる点にあろう。
つまり、本書は「終章」で『それでも、対話をする心構えを持たなければならない』としているけれども、じっさいには終始一貫して『まったく議論の出来ない人たち(=ネトウヨとパヨク)』という規定を採用しているのだから、自分の主観で「こいつは議論できない相手(ネトウヨまたはパヨク)だ」と決めつけてしまえば、課題「当事者」としての議論に関わる義務を免除される、という構造になっている。
要は、「傍観者」であることを正当化してもらえ、「傍観者」として、その内心において「無責任」に「こいつら、どっともどっちだなあ。ネトウヨとパヨクの絡み合いだよ。こんなところに関わっても無駄なだけ」と、評論家気どりで、他人を見下していれば済むという、きわめて楽ちんな立場を保証してくれるのである。
これは、能力も気力も責任感もない、ごく一般的な人々には、とてもありがたい「自己免責・正当化」のための理論書ではないだろうか。
本書に書かれているのは、
(1)自身の思い込みを一方的にわめき立てるだけではなく、冷静な議論(対話)が出来なければならない。
(2)しかし(1)の出来ない人は、現にいる。それが「ネトウヨとパヨク」だ。
(3)しかし、ネットでは「ネトウヨとパヨク」が力を持ち、子供たちに悪影響を与えかねないので、対策が必要だ。
といったことなのだが、では(3)についての著者の具体案が何なのかというと「子供たちに悪影響が出る前に、最低限の知識を与えられるよう、教育制度を改革しなければならない」というものなのだが、著者自身「しかし、それは実現が極めて困難だ」と、すぐに取り下げてしまう。
では、どうするのかというと、要は「対話が出来るよう、訴えていくしかない」という、間違いないけれど今さら言うまでもない、無内容な結論に達してしまう。
しかも、これを訴える相手とは、もちろん「ネトウヨやパヨク」ではない。当然、そこは話にならないのだから、それ以外の「比較的まともな人たち」に対し「自身の思い込みを一方的に喚き立てるだけではなく、冷静な議論(対話)が出来なければならない」という「小学校の学級会」みたいなこと訴えていくしかない、という何とも「竜頭蛇尾」な結論に至るのである。
しかも、その際に心がけることは『魅力的なユーモアやレトリックを駆使した言葉を発する』(P217)ことだと言うのだから、もはや「何をか言わんや」である。
なぜ、こんな無内容な本を高く評価してしまう人がいるのか。
それは最初にも書いたとおり、〈傍観〉批評家的立場を、本書が実質的に保証してくれるからである。
「子供たちのために何かしなければ」と言いながら、実質的には何も提言できず、最後は「ユーモアやレトリック」でなどと、本気を疑わせるような提言で満足できるのは、ひとえに本書の主旋律が「バカは相手に出来ないよ。だから、賢い貴方はそんなことする必要がない」と保証する点にあり、さらには「あなたは、そういう(当事者責任を免除された)立場から、左右の知識人や言論人たちを、あいつらも所詮はネトウヨやパヨクに過ぎないと評価して満足していれば、それで良いのです」とまで言ってくれるからである。
その実例として、著者は、岸政彦が小川榮太郎の志操低劣な文章を評して書いた『恥知らずなほどあからさまで露骨な、文章とも言えないようなドロドロしたどす黒い何か』という表現が、感情的であり、相手を怒らせるだけで、対話を阻害するものでしかない、と否定して見せる。
もちろん、著者は、このように書いた岸の「気持ち」には一定の理解を示すものの、要はそれが「対話のためにならない」からダメだ、もっと相手の感情を気遣って、対話の継続が可能な表現(レトリック)にすべきである、ということなのである。
しかし、そこまで「ホンネ」を隠した「対話」を続けて、いったい何が得られると言うのであろう?
じっさい、岸の表現は、感情的かも知れないし、対話を阻害する部分もあるかも知れないが、それにしても、著者による『まったく議論の出来ない人たち(=ネトウヨとパヨク)』という「切り捨て」表現よりは、よっぽど「対話」の余地を残したものであることは言うまでもない。
著者自身は、あらかじめ『まったく議論の出来ない人たち(=ネトウヨとパヨク)』という「両極端」を切り捨てた上で、残り部分の「対話の可能性」を語っているだけであり、そんなご都合主義的な大義名分を振りかざし、他者への「表現狩り」を行うことで「我賢し」の立場を誇示しているだけなのだ。
現に、岸の小川に対する表現は「こいつ(小川)は話にならないやつだ」という感情を強く滲ませながらも、しかし「そのドロドロとしたどす黒い感情に気づけば、彼も変われるかも知れない」という「一抹の希望」を滲ませてもいる。だからこそ、岸の物言いは、このように強い表現になっているのだ。
だが、そんな岸とは違い、著者の場合は、初めから『まったく議論の出来ない人たち(=ネトウヨとパヨク)』という具合に、自身の意に添わない人間は「レッテルを貼って排除すれば良い」と思っているので、そうした恣意的排除に至るまでは「レトリックによって、相手をコントロールしよう」とするだけのものなのである。だから冷めているのだ。
では、著者が結論的に提案する「ユーモアやレトリック」とは、どのようなものなのか?
まず「ユーモア」であるが、私は本書に「ユーモア」と呼べるものを見いだすことが出来ない。
しかし、これは当然なのだ。意見の対立する相手に対し、下手に「ユーモア」を使えば、それはこちらでは「ユーモア」のつもりでも、相手には「アイロニー(皮肉)」に映ってしまう蓋然性が高いからだ。
つまり「ユーモア」というのは、ある程度の信頼関係があってこそ成立するものであって、本書が設定しているような「困難な対話の場」では、ほとんど役に立たないのである。
一一ということは、著者がここで「ユーモア」を持ち出すのは「もっともらしさの演出」でしかなく、つまり「読者に対するレトリック」でしかないのである(お気楽な読者は、単純に「ユーモアって大切だよね」と思ってくれる)。
著者の「読者に対するレトリック」は一目瞭然だろう。だが、「読めない読者」は、それにすら気づかずに、著者に煽て上げられ「いい気分」にさせられるだけなのであろう。
著者の、とてもわかりやすい「読者に対するレトリック」とは、まず「ですます調」の文体だ。
要は、「である調」「だ調」で書くと、同じ内容でも、著者が上から読者に教えを垂れているという印象を与えがちなのだが、「ですます調」だと、著者が下から読者に提案している「かのような印象」を与えるのである。
「レトリック」の重要性を強調する著者が、本書で「ですます調」を採用したのは、無論、意識的なことであり、読者をコントロールしようとしてのことである。
言い変えれば、本書は、「である調」「だ調」では素直には受け取られにくい「ご都合主義的な態度」を、「ですます調」を採用し、それに「私も人のことが言えた義理ではないですが」とか「私自身、つねに反省し自戒してます」といった趣旨の、これ見よがしな「謙虚ぶり」の装飾(レトリック)をふり撒くことで、読者をコントロールしているだけなのである。
で、これは著者が、前職で「クレーム対応係」として身につけた、演技的態度なのであろう。
腹の中では「このクソボケが」と思いながらでも、「神妙な顔」「真摯そうな態度」で相手の「ご意見」を傾聴し拝聴して「おっしゃるとおりです」「お怒りはごもっともです」「お客様のような方こそが、幣社の真の味方であると思っております」「貴重なご意見をありがとうございました」などと言って、(真の「対話」ではなく)ひたすら相手を「コントロール」することが「クレーム対応係」の仕事なのだから、「ですます調」を採用し、それに「私も人のことが言えた義理ではないですが」とか「私自身、つねに反省し自戒してます」といった趣旨の、これ見よがしな「謙虚ぶり」の装飾(レトリック)をふり撒くことなど、著者には「他者コントロール」の基本中の基本でしかない。
むしろ、著者のこのような「見せかけの態度」を鵜呑みに出来る人こそ、著者に内心で見下されるであろう、きわめて「ナイーブな読者」なのだと言えるだろう。
結局のところ、本書で、何が為されているのかと言えば、それは「対話の必要性の強調」ではない。
それは「タテマエ」に過ぎず、本当の目的は、自身を「傍観的批評家」という「特権的立場」に据えて、「我賢し」というその鼻持ちならない態度を、傍目に気づかせないようにすることでしかない。
本書で為されているのは、「対話が大切ですよ」という「第三者的」正論でしかなく、「当事者」としての対話・言論そのもの、ではない。
自身は「対話当事者」にはならず、「対話当事者」を批評する「第三者」というお気楽な立場に立って、第三者ゆえのご高説をたれるに過ぎないのである。
例えば、本書で紹介される印象的なエピソードとして「東日本大震災の支援に入った、国民的有名歌手」の話。
それは「ある国民的有名歌手が、被災者支援のために被災地での活動に入った。だが、当時すでに、被災者の中でも、そして被災者と被災者以外の住民との間でも、格差と軋轢が生じていたので、著者は、そのあたりを調整する係員として、その歌手に、歌手が支援の対象と目していた一部被災者だけではなく、そのほかにも目を向けて、バランスの良い支援を行ってほしいと依頼したのだが、歌手はその提案を聞き入れず、自分の目的はそこにはないと激高した」というものである。
ここでの著者の書き方は「この国民的有名歌手もまた、自分の正義に凝り固まった、対話の出来ない、ネトウヨやパヨクの類いである」というものだ。
しかし、これは著者の勝手な決めつけであり「印象操作」であって、公平な評価とは言えない。
というのも、この歌手が誰に救いの手を差し延べようと、それは彼の勝手であって、基本的には、他人が利口ぶって、とやかく「指図」することではないからである。
もちろん、提案するのはかまわないが、著者自身が「金を出す」わけでも「直接手を差し伸べる」わけでもなく、あくまでも行為主体(当事者)は歌手その人なのだから、彼の意向を尊重して、彼に出来ることをさせてあげれば良いのである。
それを、著者の(第三者=直接当事者ではない立場からの)提案に聞き従わない、つまり「コントロール」に従わないからといって、「独善家」呼ばわりするのは、それこそ「独善家」の態度でしかない。
著者は、いつでも「下手から他人をコントロールしようとする」人なのだろう。
だからこそ、それに従わない人間は「独善的なバカ」と映るのだろうが、しかし、著者のそうした「心根や下心」が透けて見えたからこそ、その歌手は「俺は俺のやれることをやる。おまえがそう思うのなら、そっちはお前に任せるから、お前がやればいいだろう」となっても、何の不思議もないし、これは「正論」ですらある。
誰も彼もが、全体に公平に手を貸さなくてもいい。出来ることを出来る部分で担当すればいいのである。
自分では金は出さず手も汚さず、口八丁で他人をコントロールして、それを自分の成果にしようとするような人間には、そうした歌手のような存在は「使えない道具」であり「役立たず」なのだろう。
だが、多くの人が、実際には何もしない中で、正義感にかられて支援に乗り出したその歌手は、それだけで立派な人でなのあり、それを「物わかりが悪いバカ」扱いにする者の方が、よほど「傲慢」なのである。
誠に、そこまで言うのなら「全体観のあるバランスの良い行動が大切ですよ」とか「冷静な対話が大切ですよ」といった「メタレベルの提言」に終始するのではなく、「支援当事者として直接被災者を救う」とか「対話当事者として、具体的な意見を出して議論する」とかして見せろ、ということにならざるを得ない。
しかし、それを実行したならば、著者がやれるのは「相手が議論にならない人だから、しかたなく撤退しました」という自己正当化に終るのが関の山だろう。
しかし、こんな「傍観批評家」的な人ばかりでは、残念ながら、世の中は回らないのである。
さて、このように見ていけば、著者の本質が見えてこよう。
著者が「ですます調」を採用し、それに「私も人のことが言えた義理ではないですが」とか「私自身、つねに反省し自戒してます」といった趣旨の、これ見よがしな「謙虚ぶり」を自己喧伝したところで、それは、著者自身認めている「レトリック」でしかないのだ。
人の「主張とホンネ」がいつも一緒なら、読者に読解力は要らないし、詐欺被害に遭う人もいないだろう。だが、現実はそんなものではない。
「文章」を読むとは、「著者の主張を理解する」に止まらず「著者のホンネと人柄を読み解く」ものでなければならない。そうでなければ、そんなものは「読書」の名に値しないのである。
(以上「である調」表記で)
初出:2019年6月2日「Amazonレビュー」(同6月6日、管理者により永久削除)
再録:2019年6月6日「アレクセイの花園」
