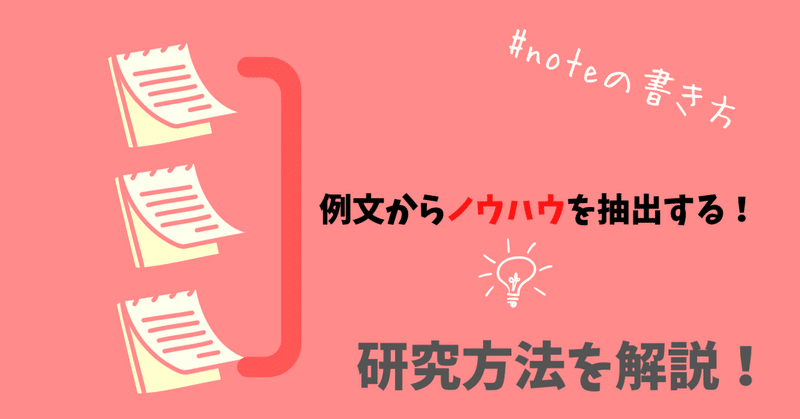
文章の分析2:あらゆる表現はnoteの勉強材料になる!表現の研究法を解説。
あらゆる表現を研究する
文章も表現の一種である以上、伝統芸能~最新のアニメまで
あらゆる表現
は文章術(noteの書き方)の勉強材料になります。
先日、Kindleの読み放題サービスで、下手をすると校長先生の話よりもつまらない文章術の本を読みました。
あまりにもくだらなすぎて、20ページくらいしか読めませんでした。
でも「こういう書き方をするとつまらなくなってしまうんだなぁ」と反面教師的に、良い勉強になりました。
表現の研究方法-心が動いた瞬間を抽象化する
実例に学ぶには、心が動いた瞬間を抽象化するのが一番です。
エッセイや小説、ビジネス書などの文章はもちろん、アニメ、ラジオ、YouTube動画も表現には変わりません。
こうした表現を見聞きして心が動いたら、抽象化によって学びを得ます。
ただ見聞きしただけでは、その表現をノウハウ化できないからです。
「抽象化する」と言っても、慣れないと難しいと思います。
まずは簡単な文章を抽象化するところからはじめてみましょう。
リンゴ。
バナナ。
みかん。
この文章(?)を抽象化すると
くだもの
になりますよね。
もちろん「食べ物」でも正解ですし、「甘いもの」でも正解です。
短い文章を実際に研究してみる
これを踏まえて、次の文章を研究してみましょう。
突然ですが、皆様って、何かをはじめたときのきっかけって聞かれたらすぐに話せますか?今の仕事をはじめたきっかけ、今の趣味をはじめたきっかけ、好きな本がある方はその本が好きになったきっかけ。
この文章は高山ゆかり先生の「話し方のハナシ」というラジオを文字起こししたものです。
僕はこの表現(ラジオ)を見聞きしたときに「すごく分かりやすい!」と心が動いたんです。
「なんで心が動いたんだろう?」を調べるために抽象化してみます。
「突然ですが、皆様って、何かをはじめたときのきっかけって聞かれたらすぐに話せますか?」
抽象化すると?→【問題提起】
「今の仕事をはじめたきっかけ」
抽象化すると?→【具体例①】
「今の趣味をはじめたきっかけ」
抽象化すると?→【具体例②】
「好きな本がある方はその本が好きになったきっかけ」
抽象化すると?→【具体例③】
問題提起として主題についての質問を投げかけた次の瞬間、「きっかけ」についての具体例を3つも挙げているんですね。
ただ「きっかけ」と言われても、いまいちイメージしにくい。
けれども「①仕事、②趣味、③本」と3つの具体例を素早く挙げることで、すぐにイメージできるので「分かりやすい!」と心が動いたんだと思います。
僕はこの方法を
トリプル具体例法
と名付けてノウハウ化しました。
トリプル具体例法は、抽象的なことを述べたら、即座に3つの具体例を示し、読者の理解を助ける表現のテクニックと言えます。
たとえば、
【抽象的なことを述べる】
noteの書き方のコツ
【すぐに具体例を3つ挙げる】
①結論から書く。
②具体的に書く。
③体験談をフル活用する。
こんなイメージですね。
ただなんとなく、高山ゆかり先生のラジオを聴いて「分かりやすいなぁ」と思っても、それだけではノウハウのエッセンスを取り出すことができません。
しかし、抽象化してノウハウ化すると、このように、自分の書く文章にラジオの表現を応用(転用)することができるわけです。
自分で発見したノウハウは強い!
実例の研究から、自力で発見したノウハウは、研究の過程で分析に苦労する分、理解度が深い。
ただノウハウを学ぶよりも、実例の中に見出したパターンの方が応用が効くのです。
たとえば、昔話は良い研究材料です。
2つの童話を実際に研究してみましょう。
【桃太郎の書き出し】
桃が流れてきた。
桃の中に人間がいた。
【うらしまたろうの書き出し】
亀を助けた。
龍宮城に招待された。
有名な童話の書き出しに共通する点はなんでしょうか?
それは、
続きに期待感が持てること
と言えます。
実際、noteでも書き出しは、続きに期待感が持てるように書くことが大事です。
あるいは、俳句に学ぶこともできます。
古池や蛙飛びこむ水の音
この名句を抽象化すると、
目に浮かぶような情景的な表現
と言えます。
実際、noteでも
「リンゴ」
と書くよりも、
「99円で買ってきた真っ赤なリンゴ」
のように、目に浮かぶような情景的な表現を使った方が読まれやすいことが分かっています。
こうした研究から分かることは、
あらゆる表現は勉強材料になる!
自分で発見したノウハウは強い!
の2点です。
まとめ
伝統芸能~ビジネス書まで、あらゆる表現は文章術の勉強材料になります。
ただ感動するだけではノウハウとして自分の作品づくりに転用できないので「リンゴ→くだもの」のような抽象化によって例文を分析します。
「文章の分析シリーズ」では、様々な文章を分析した結果をお届けしますので、今後ともよろしくお願いいたします。
以上、みず(@mizuxyz99)@Twitterフォローお気軽に◎でした!

あわせて読みたい
いただいたサポートは、よりよい教育情報の発信に使わせて頂きます!
