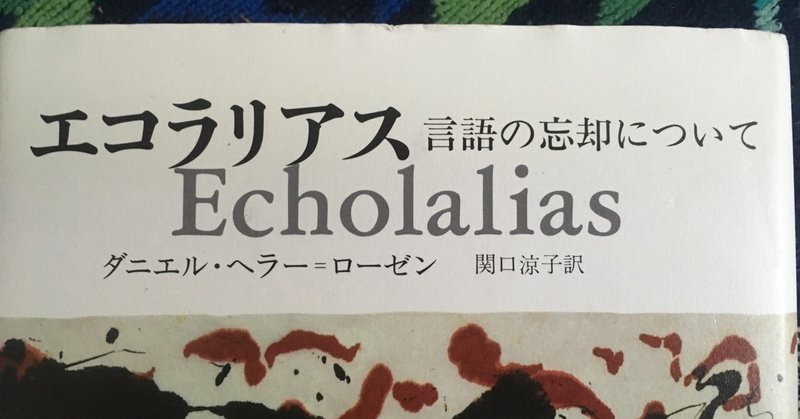
エコラリアス 言語の忘却について/ダニエル・ヘラー=ローゼン
言葉について考えることは、僕ら人間について考えることになる。
だから、言葉について書かれた本を読むのは面白いのだけど、このダニエル・ヘラー=ローゼンの『エコラリアス 言語の忘却について』はその中でも特に印象の強い一冊だった。
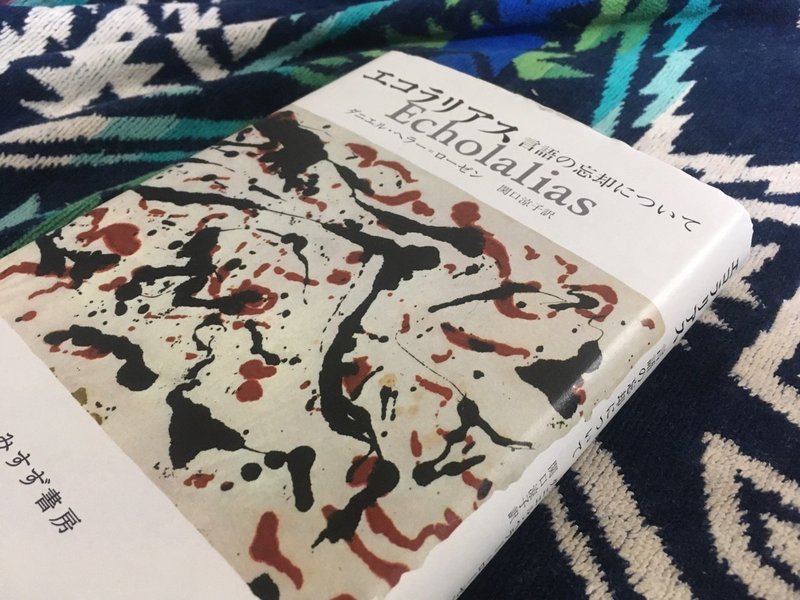
著者のヘラー=ローゼンは、母語の英語に加え、イタリア語とフランス語を母語並みにあやつり、西洋の古典語(ヘブライ語、古代ギリシャ語、ラテン語)を習得し、さらにはドイツ語、スペイン語、ロシア語、アラビア語にいたる10の言葉に通じているポリグロットだと紹介されている。専門とする学問分野もまた学際的で、哲学、文学、歴史学、認知科学、言語学に及ぶ。
だから、この「エコー(反響)」+「ラリア(話)」の複数形で「反響言語」という意味の『エコラリアス』と題された2005年に書かれた彼の2冊目の著書も、いわゆる言語学の本ではなく、哲学や文学、歴史学、さらには宗教学や医学までも取り込みながら「言語は変化するからこそ残っている」という、人間の忘却と言語の持続性について、歴史的なものだったり人類学的だったり医学的だったりさまざまな事例を豊富に紹介しながら紐とく内容となっていて、とても興味深く読了にいたった。
言語の生死
失われた言語がたくさんあることは、それほどそうした知識を豊富にもたない僕らにしてもなんとなくはわかっている。
それはひとつの国や民族の言葉がまるごと失われることもあれば、かつては使われていた単語や言い回しがいつの間にか使われなくなり忘れられていたりといったこともある。
反対に、新しい単語が作られたり、用語法が生まれることもある。
国家や民族の言葉が新たに作られるといったことはなかなかないが、紀元70年にユダヤ人の世界離散(ディアスポラ)が起こって以降、話し言葉として使われることのなかったヘブライ語が、20世紀に入って復活し、イスラエルが建国されていこう公用語として使われるようになった例もなくはない(ヘラー=ローゼンはそれをかつてのヘブライ語とはまったく別の「奇妙な語彙を持つ一種のイディッシュ語」だとしているが、だとすれば余計に新たな語の誕生だと言えるのかもしれない)。
死語という言い方があるように、僕らはひとつの言語だったり、その一部をなす単語が死んだり、生まれたりといった、生物と同じようなものとして連想しがちだ。単語単位は個体としての生物の生死、ひとつの言語の単位は生物種の形成や消滅に対応しているかのように。

しかし、ヘラー=ローゼンはそうした言語と生物の対応に疑問を投げかける。言語がいつ生まれ、いつ死んだかの特定は生物の場合のようには行えないだろうと指摘する。
例えば、ある言語を話す民族の最後の生き残りのひとりが死んだ時点が、その言語の死かというと、そう単純ではない。その人がひとり残された時点で、その人はその語を使える話し相手を失っていることになるので、その語を使う機会がない(独り言を除けば)。
しかし、それは残りひとりになるのを待つまでもなく、残された人たちが互いに離れて暮らしていて会話の機会がなくなれば同じことだ。
どの時点でその語が「死んだ」と言えるかは決定しづらい。
しかも、ヘラー=ローゼンは、一度死んだかと思われた言語が人々の努力で蘇った例も紹介している。
言語の市の特定もむずかしいが、誕生の時を特定するのはさらにむずかしい。
例えば、ヘブライ語はいつアラム語になり、古代ローマの路上で話されていた口語ラテン語は、いったいいつ、わたしたちが「イタリア語」と呼ぶ言語になったのだろうか。
ラテン語からフランス語だって同様だ。その誕生を「国家による公的な書類が初めて記された842年に生まれた」と「ストラスブールの誓約」を誕生の時としようとする説もあるようだが、それは無理があるだろう。
言語の変化と忘却
「言語の死の年代を正確に推定しようとしている言語学者でさえも、言語の誕生について意見の表明を躊躇する」とヘラー=ローゼンは書いている。
ようするに、言語というものは、個体としての生物のように死んだり生まれたりが明確なものではないのだろう。生まれて死ぬより変化し続けて、いつの間にか、かつてとはまるで別ものになるため、かつての言語の存在が忘れられたりするのだろう。
すこし話が逸れるが、この忘却と死の関係は、『ポストヒューマン』でロージ・ブライドッティが次のように書いていることとも関連しているように思う。
個別に起こることとしては、死は身体の物理的な消滅というかたちで到来することになる。だが、出来事としては――有限性への自覚、わたしの現存在の流れが中断されることへの自覚という意味での出来事としては――死はすでに生じてしまっている。わたしたちは皆、死とシンクロしている。わたしたち皆が借りられた時間を生きている以上、死はわたしたちが生きている時間と同じものなのである。
出来事としての死は、流れの中断ということの自覚として常に起こっているのだとしたら、言語の場合の変化においてはまさにこの中断が忘却されるために、言語は出来事としての死から縁のないものとなっているとでも言えるのではないか。忘却だけが人を死から遠ざけてくれるのかもしれない。

モンテーニュはこの言語の変化について自覚的だった。その有名な著『エセー』において、彼は「この言語は毎日わたしたちの手からこぼれ落ちていくのであり、わたしが生きている間にもすでにその半分は変わってしまった」と書いている。モンテーニュは、言語の出来事としての死が見えていたのだろう。それがいつどのように起きているかの特定はできなかったとしても。
これについて、ヘラー=ローゼンはこう記している。
言語の始まりと終わりは、モンテーニュの表現によって最も適切に把握されていると言える。実際、言語の「始まり」と「終わり」とは「絶え間ない変化」によってその話者から「逃れ」、自ら「形を変える」過程にある2つの瞬間に他ならず、この飛びさっていく2つの地点では、様々な理由によって、言語を話す存在であるわたしたち自身があまりに忘れがちなある事実に気づく。それは、「ある」言語がすでにその言語であるのを止めた、ということである。
どこである言語が「言語であることを止めた」かを特定することはできなくても、モンテーニュが書いているように、ある時振り返って過去のいずれかの地点と現在との2点間の差分としてみれば、「言語であることを止めた」ことを知ることはできる。モンテーニュはそれを「毎日わたしたちの手からこぼれ落ちていく」という風に感じとっていたようだ。
それは明確な「ここ」という境界を持たないまでも、特定の2点間において、ある言語が「言語であることを止めた」という閾をその間に有することがあり得ることを示しているのだと言える。
これらの閾においては、ある共同体は、自分たちが確かに新しい言語を採用したことを認識し、それが新しい言語として初めて明示されるが、そればかりではなく、その閾において、話者は、かつて自分たちのものであった言語を失ってしまったと知るのだ。
いつ口語ラテン語がイタリア語やフランス語に変化したかはわからなくても、どこかの瞬間に「新しい言語を採用した」とか「かつて自分たちのものであった言語を失ってしまった」ことに後から気づくような閾が言語の変化の流れのうちには存在しているということだ。
「言語は自らの要素の移動にしか存在しない」とヘラー=ローゼンはいう。
そして、それでも言語が僕らにとってそれが自分たちの使用に耐えるものである限り、一貫して、自分たちの言語だと認識されるのだろう。それが常に変化し、また、外来語のような形での移動が起こるのだとしても、それは僕らが普通に使えている限り、僕らの言語であることに変わりはないと感じられる。
言語の一貫性は、その前に存在した様々な言語と関係を結んだり離したりする忘却と記憶の形成の中にある。
変化とその忘却、さらには作られた記憶の錯視的な連続性によって、言語は一貫したものとして残り続けるのだろうし、僕ら自身、その言語の一貫性のおかげもあり、自己のアイデンティティを保てているのだと思う。それは個々人のアイデンティティだけではなく、国や民族としてのアイデンティティの場合でも同じだ。
変化と忘却の効能
そういう観点があるがゆえだろう。
ジョゼフ・ヴァンドリエスという人が、フランス語を守るため、「我々の言語を、決定的に自分たちの手に入った、不変のものと考えてははらない。それは意志によって獲得されたのであり、我々は、毎日、我々の祖先がしてきたように、たゆまぬ戦いによってこの言語を守らなければならない」という意見に対して、ヘラー=ローゼンはこう書いている。
このような結論は、言語に内在する変わりやすさを認識することに関しては一歩後退してしまっている。つまり、言語は変化するからこそ残っているので、「この美しい言語の遺産を完全な形で残しておく」ことなどできないのだから。
それは僕らだって同じだ。
僕らは「変化するからこそ残っている」のであって、変わらないことを目指して動き始めようとした瞬間から機能不全ははじまり、かえって自分を見失うことになる。

それは、こんなヘラー=ローゼンの指摘によっても明らかであるように思う。
固定化した「わたし」なんてものはなく、それをあるように考えはじめるから具合が悪くなるのだ。
ギリシャ語の「わたし[エゴ-]」は、インド=ヨーロッパ諸語のそれに相当する言葉がそうであるように、中性名詞eg[h]omから派生しているが、これは単に「ここにあること」(Hierheit)を意味している。元々、「わたし」は、特に実体を持たない、「ここ」にあるもの全てを指していた。生物無生物を問わず、人間であろうとなかろうと適用され、口語でも書き言葉でもそう示すことができる。
つまり、そして、またしても「共生体」という概念が必要だということだ。
自分のなかに何か確固とした「わたし」を探そうとするから間違える。
そうではなく、外部を含めて「ここにある」ということ、変化し続ける環境に埋め込まれて自分自身も変化する共生体としてここに在るということを、「わたし」であると認識しない限り、わたしは持続可能性を持ち得ない。
砂に書かれた文字
変わり続ける不確定性をもつからこそ、持続可能なのである。それは自覚することが死とともにあるということにも関係しているのだろう。
変わることで持続可能性をもつということで、ヘラー=ローゼンが紹介しているイオの物語が象徴的だ。
オウィディウスの『変身物語』にも出てくるニンフの娘イオに、ユピテルが恋をし、妻のユノーに見つかりそうになって、咄嗟にイオを雌牛に変えてしまう話だ。
言葉、そしてアイデンティティとの関係が生じるのは、イオが牛の姿のまま逃げだした後のことだ。イオはその姿のまま、父に出会う。父は牛をみてたじろぐ。イオのほうは声を出そうにもモーとしか出ない。父の方に差し伸べる手もない。「思うままに言葉を発することさえできれば、助けを求め、自分の名や、わが身の不幸を知らせられるだろうに」。
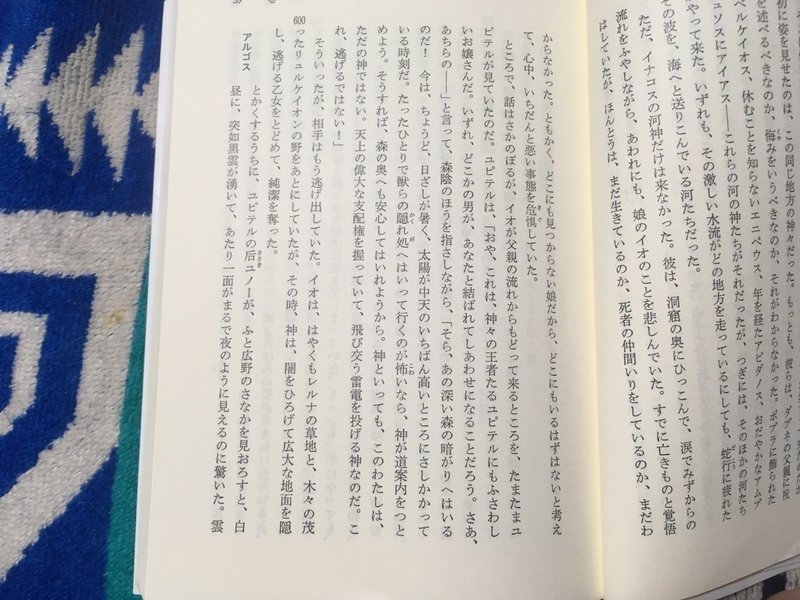
イオは砂の上に蹄で「IO」と書く。
父はようやくその牛が娘のイオであることに気づいて嘆く。
「足で砂に書いた文字が、言葉の代わりに、変身の哀しい知らせを語ってくれたのだ」。
もしも言語が話者がいなくても生き延びるというのなら、それは言語が話者を顧みないからではなく、むしろ、言語が話し手を通じ常にその姿を変えられ、その性質上「さらなる変容が可能だから」である。このようにして、言語は、それを話す者がいようといまいと、時を通じて残る、同じ言語として残ることはないにしても。言語は、別の言語としてのみ生き続ける。そう主張することで、オウィディウスの物語には究極の意味が与えられる。言語は、その変身の中でしか存在しない、そして、あらゆる言葉は、いなくなったニンフの蹄によって砂に記された文字にほかならないのだ。
また、ヘラー=ローゼンは、バベルの塔を建てようとしたことで人間は神の怒りを買い、それまで使っていた同じ言語を失い、バラバラで互いに通じ合わない言語を使わざるを得なくなった混乱について語りながら、言葉と変化の関係について、こう述べている。
「原初の言語の忘却」と解釈されたこの混乱は、言語の多様性の起源となる伝説を示すだけではない。時間的にも空間的にも言語の多様化を引き起こした要素としての「混乱」は、その混乱が生んだ複数の言語と切り離されることはなく、わたしたちが言語と呼ぶこの著しく変わりやすい存在の変わらない核、言語の変化の中で変わらずにいる中心を構成していると言ってもいい。
混乱そのものが言語というものの中心的な核だということだ。そのことだけは、言語がどんなに変化しようと変わらぬ核としてあり続ける。それは統一され、ひとつに収束していく傾向よりも、常に分裂して多様化して、混乱状態を生むような性格を持っている。それが言語というものであり、同時に人間というものなのだろう。
言語は、その変身の中でしか存在しない
その言語を使う人間そのものもまた、そうなのだろう。人間は変身の中でしか存在しない。そして、同時に、その変身を忘れ続けることによって成り立っている。
そんなことを視点の異なる多様なエピソードを通じて感じさせてくれる、とても面白い一冊だった。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
