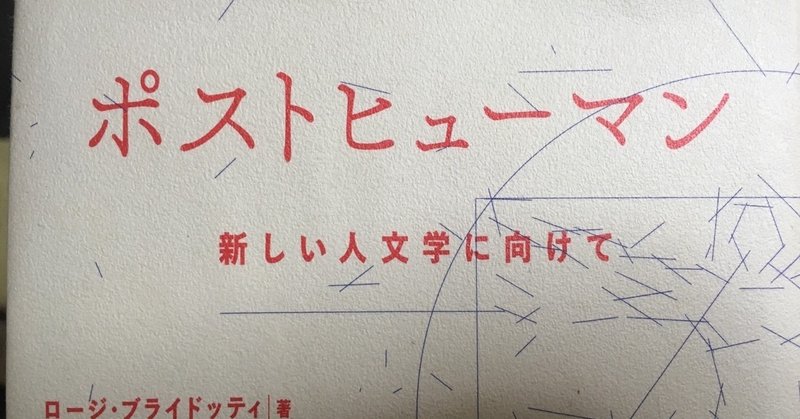
ポストヒューマン/ロージ・ブライドッティ
"わたしたちは実際にポストヒューマンになっている。あるいはわたしたちはポストヒューマンでしかない。"
しばらく前から明確に、いまの時代にあったことをしたいし、いまの時代が必要とすることをするべきだと思うようになっている。そんななか、このロージ・ブライドッティの『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』は、いまの時代に何を考え、何をなすべきかを問うための1つの方向性を提示してくれる1冊だった。
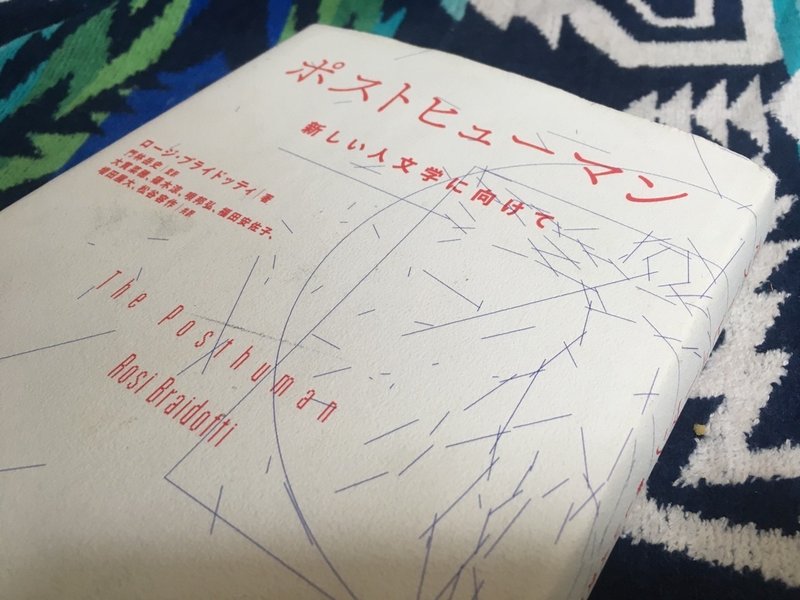
「人間」という時代遅れの枠組み
いまや「人間」というあり方がゆらいでいる。
技術によって高度化された義肢や、VRやARなどをはじめとする人間の感覚・認識を拡張するツールなどにより、従来の人間の身体的な限界は更新され続けている。AIやロボットの技術革新は人間と機械の境界をぼやかしつつあるし、彼らに人間の権利であった仕事も奪われつつある。人間と人間が作りだす機械の境界はますます曖昧になり、たがいに融合している。
人間と非‐人間である動物として、従来なら明確に分けられていた境目も見えなくなりそうだ。これまでも擬人化という形で動物を人間の側に寄せてみる見方はあったが、いま起こっているのはむしろ逆だ。人間のほうが非‐人間と同様のものとして扱われる場面が増えている。
例えば、動物の権利(アニマルライツ)が主張される一方で、人間はドローンなどの新たな戦争兵器の登場により、人知れず虫けら以下の殺され方をするような、これまでとは異なる死の危機にさらされている。はたまた発達した遺伝子技術はゲノム編集による身体の治療や制御を可能にしようとしているし、身体の一部という知性を帯びたマテリアルがグローバルに「取引し利潤をあげるための商品へと」変わろうとしている。
とはいえ、その動物たちもブライドッティが「遺伝子工学的資本主義」と呼ぶこのグローバル経済の環境下においては、人間同様に「取引し利潤をあげるための商品」として扱われることは免れ得ない。
クローン羊のドリーが6歳の羊を遺伝元として生まれ、6年経って死んだが、死因はごくごく普通の肺疾患だった一方で、狂牛病(BSE)という死に至る病を生みだしたのは牛を動物飼料で肥育するというカニバリズム的展開だと言われている。
その動物たちの遺伝子工学的商品として扱いは、人間の身体にも少なからず影響を与えていて、太らせて高く売るために抗生物質を投与して育てられた豚や鶏は、それを食べた人間も同じく肥満になるなどの影響が抗生物質による腸内の微生物環境の荒廃によって起こることが判明すると、ヨーロッパでは飼育時に家畜に対して、病気の治療以外での抗生物質の投与が禁止されたりもしている。
いまや動物と人間の関係はデカルトが両者を明確に切り離したときのようには明確に分け隔てることはできなくなっているわけだ。
そもそも、微生物学の発展が、胎内の微生物と人間の心と体との切っても切れない共生関係を明らかにすることで「わたし」とは何か?の再考を迫ったり、人新生という人間活動が地質学レベルで地球という惑星に影響を与えてしまっていることはマイクロプラスチックや温暖化などの気候変動の問題を持ちだすまでもなく明らかで、そうした観点においても、人間は微生物とも惑星とも切り離せない状態になっている。
この『ポストヒューマン』と題された本で、著者のロージ・ブライドッティが示してくれるのは、こうした現在を生きる僕らにとって、もはや伝統的な「人間」という枠組みのなかで考え、行動しようとすることがまったくの時代遅れだし、もはやそのフレームワークは機能しなくなっているということだ。
排外主義のアイデンティティを捨てて
伝統的な枠組みとしての「人間=ヒューマン」に代わるものとして、ブライドッティが提示するのが「ポストヒューマン」だ。
フェミニズムの研究家でもある著者は、従来の「人間」という装置のもつ排他性や規範性を指摘する。
ヒューマニズムにおける人間なるものは、ひとつの理想でも、客観的な統計上の平均や中庸の立場でもない。それが詳らかにしているのはむしろ、識別可能性――すなわち〈同一性〉――についてのある体系化された基準であり、それによって他のすべてのものが査定され統御され、所定の社会的な場所に割り当てられるということである。人間なるものはひとつの規範的な約束事である。そのこと自体は悪いことではないが、ただそれが人間を高度に統御的なものにし、またそれゆえに排除や差別の実践に加担するものにしている。人間的規範は、正常性、常態性、規範性を意味するのである。それは人間であることのうちのあるひとつの特殊な存在様式を一般化された基準へと転移させることで機能し、その基準が人間なるものとしての超越的な諸価値を獲得するのだ。
この規範的な役割をもった「人間」という物差しが、男性中心主義、白人中心主義、ヨーロッパ中心主義や、健常者と障害者、富めるものと貧しいものなどの区別を生む。
しかし、グローバルに境界なくネットワークが張り巡らされて、いつでもモバイルを介してソーシャルな場にアクセスできるポストヒューマンな時代においては、そうした差は容易に飛び越えることができる。飛び越えるというより混ざり合ってきれいに区別するのが不可能な状況が世界のあちこちに出現しているというほうが正しいか。しかも、そこには人間だけではなく、そこにはbotやエージェントがいる。
そうした世界に対する反応として排他的な自民族主義が生まれている。
だが、ポストヒューマンはそうした反動的なヒューマニズムに陥ることなく、従来の個人主義的なアイデンティティの放棄を引き受ける。一箇所に自己を固定することなく、ノマド的に常に自身とまわりの非‐人間とのあいだに新しい主体を立ち上げる。
それはドゥルーズとガタリのいう「生成変化」だ。それは絶対性や常態性へと陥りがちなものから距離を置き続ける。それは外部に対して、他者に対して排他的で攻撃的な態度を示さず、寛容な態度で外との関係を結ぶ。
一方にグローバル化し文化的に多様なヨーロッパがあり、他方でヨーロッパのアイデンティティをめぐって偏狭な排外主義的定義がある。ヨーロッパのノマドへの生成変化は、ナショナリズム、排外主義、人種差別といったかつての帝国的ヨーロッパの悪癖に対する抵抗となる。かくして、それは過去の壮大で攻撃的な普遍主義とは対置されるものであり、そうした普遍主義は、状況に根ざしており説明責任を果たせる視座によって取ってかわられる。ノマドへの生成変化は、「要塞ヨーロッパ」症候群に対しても決然とした態度をとり、社会的正義のツールとして寛容性を生き返らせることで、新たな政治的・倫理的企図を取り入れるのである。
ノマドとなったものはもはや自らのアイデンティティなどを守るために外部を排除しようとしない。自らを中心と考え、そのほかのものを排外的に外へと追いやったりはしない。
ヨーロッパのマイノリティへの生成変化、あるいはノマドへの生成変化のプロセスが含意するのは、自らを世界の中心だと捉え、伝道師を買って出るヨーロッパの役割を拒絶することである。多民族、多メディアの社会に向けて社会的・文化的変異が起こっているのが事実ならば、そうした変容が作用するのは「他者」という極のみではありえない。それはかつての中心である「同一なもの」の位置やその特権も同様にずらすにちがいないのである。
ポストヒューマンの時代における主体性
こうした個人のアイデンティティ、民族としてのアイデンティティ、そして、何より人間中心主義などを捨てたとき、主体とはどうなるのだろうか?というのが、著者の問いである。
「わたしたちの時代の複雑性や諸矛盾に適した批判的ツールを作りあげるためには、唯物論的かつ関係論的、つまり「自然‐文化」的かつ自己組織的なものとしての主体性の理論が欠かせない」と著者はいう。「わたしたちには、「現在にふさわしい」主体観が必要なのである」と。現在に何がふさわしいのか?ははじめに書いたとおり、僕自身の問いにリンクする。だからこそ、この本を僕は興味深く読んだ。
「自己組織的なものとしての主体性」といわれるとおり、それは従来のような個として閉じた主体ではない。
個人でもなければ、個別のアイデンティティをもった法人でも、国や民族のような固定化した枠組みをもつものでもない。
それは従来の主体と客体というように分かれていた外部と積極的に関係をもった上で生成変化してくる新たな主体である。それは「非単一的な主体」である。
非単一的な主体のためのポストヒューマン的倫理は、自己中心的な個人主義という障害を排除することによって、自己と他者――非‐人間ないし「地球〔=大地〕」の他者を含む――の拡大された意味での相互連結を提示するのである。先にみたように、現代の遺伝子工学的資本主義は、人間以外のものを含むあらゆる生命組織が反動的に相互依存しあう状況を世界規模で引き起こす。こうした統一性は、脆弱性を共有しあうというネガティブなたぐいのものになりやすく、それは言うなれば、人間にとっての環境と非‐人間にとっての環境が同じ脅威に直面して相互に連結するというグローバルな感覚なのである。〔それに対して〕人間の相互作用をポストヒューマン的に再編成するというわたしの提案は、脆弱性という反動的な絆とは同一のものではなく、多数の他者との関係の流れのなかに主体を位置づけるアファーマティヴな絆である。
流れうつろう他者との関係のなかに位置づけられるノマド的な主体。
それが著者がイメージするポストヒューマンにおける新たな主体性のあり方だ。
ポストヒューマンな主体は、ほかのものとの関係のなかにつくられる。
それは従来の個であることを拒絶し、アイデンティティを放棄して、他者とのあいだに流れ動く関係性をつくる。
ポストヒューマン的な主体の関係を織りなす能力は、わたしたちの種だけに限定されるものではなく、あらゆる非-擬人主義的な要素を含んでいる。生ける物質は――肉も含めて――知性をもち自己組織化するものであるが、それはまさしく、生ける物質が残りの有機的な生命から切り離されていないからなのだ。
自然‐文化の連続体
だからこそ、わたしたちは技術によって進化した義足やVRゴーグルも受け入れるし、マイクロプラスチックの海にも温暖化する環境にも向き合い、レジ袋を断り紙製のストローを通して飲み物で喉を潤すだろう。
「わたしはつねに、解放的で越境的ですらある技術のポテンシャルの側に断固として立つつもりでいる」と著者はいうが、同時に「これらの技術を、予測可能で保守的な側面や個人主義を助長し膨張させる営利志向のシステムへと指標づけようとする人たちの側につくつもりはない」とも宣言する。
「人新世の時代、つまり地球の生態バランスが人類によって直接統御されている時代に生きているという事実をはっきり分かっている」状況において、ポストヒューマンであるわたしたちは、わたしたち自身が生みだす機械も、身体に住まう微生物を含めた非-人間的な生物も、そして惑星自体もまとめて1つの主体として感じることができるはずだ。なにしろ、実際、そのような状況にわたしたちはなっているからだ。その事実を古い「人間」だとか「個人」だとか「わたし」だとかという枠組みを無理やり適用して捻じ曲げる必要はどこにもない。しかも、わたしたちはそうしたさまざまなものとの関係を常に更新しながら多様な主体となりうる。
わたしが提起しているのは、ポストヒューマン的主体性を再定義するためのもっとアフォーマティヴなアプローチである。たとえば、この章ですでにみた横断的で関係を織りなすノマド的なアッサンブラージュという対抗モデル、あるいは、前章でみた古典的な人文主義主体とは別の選択肢としての拡張された自然‐文化的自己だ。もっと多くのモデルが考えられるし実現可能である。
この多様なモデルの実験はいままさに始まったばかりだと、著者はいう。そして、その実験的プロジェクトをどんどん実践的に積極的(アファーマティヴ)に推し進めてみればいいのだ、と。
そのためには、「わたしたち」――人新世の時代に多様な場所をもつポストヒューマン的主体--が何に生成変化できるのかというプロジェクトを、わたしたち皆が体系的に実験すればよいのだ。わたしたち皆の利益になるのは、これらの身体化された非‐人間的主体――かつては人間中心主義的でヒューマニズム的な〈人間〉にとっての「他者たち」として知られていたもの――の位置に、ポスト人間中心主義的で横断的な構造上のつながりが存在するのを認めることである。このプロジェクトの倫理的な部門は、新しい社会的結合の創造、そしてこれらのテクノ-他者との新しい社会的な連結のありかたにかかわる。技術に媒介された有機体の自然‐文化連続体のなかではどのような種類の紐帯が確立されうるのだろうか、そしてそうした紐帯はどのようにして維持可能なのだろうか。親族関係と倫理的な説明責任の両方を再定義する必要がある。そうすることで、情動性と応答責任の結びつきを、非擬人主義的で有機的な他者たちのためだけでなく、技術に媒介され、新しく特許化されているが、わたしたちと地球を共有している生き物たちのためにもなるように考えなおす必要があるのだ。
ちょっと難解な言い回しが多い本ではあるが、書かれていることはきわめて実践的で現実的な取り組みへの誘いだと思う。「ドゥルーズとガタリが教えてくれるように、思考することとは、新しい概念や新しい生産的な倫理的関係を発明することである」と著者はいうが、まさにこのポストヒューマンの時代に求められるものが、従来の個人主義やニヒリズムのようなものに陥らず、積極的に現実の世界に埋め込まれた自身や、その状況においてつながりをもったさまざまなものと一体化した新しい主体性において考えることなのだろう。
「ポストヒューマンになるということは、人間たちに無関心になるとか、脱人間化されるとかいったことではない」と著者はいう。そして、こう続けるのだ。
それとは逆に、ポストヒューマンになることは、むしろ倫理的な諸価値を、領土的ないし環境的な相互連結を含む広い意味での共同体の福利へと、新たに結びつけなおすことを含意するのである。こうした倫理的紐帯は、古典的ヒューマニズムにおいて正典となった系譜において定義されるような個々の主体の自己利益とはまったく異なる種類のものであるし、カント主義者たちによる道徳的普遍主義――人権を、すべての種やヴァーチュアルな存在物、分子的な合成体へと拡張することに彼らが寄せる信頼――とも異なる。ポストヒューマン理論はまた、倫理的関係の根拠を共同のプロジェクトや活動といったポジティブな基盤におくのであって、脆弱性の共有というネガティブないし反動的な基盤におくのではない。
気候変動やらさまざまな種の絶滅、あるいは人間や国家などの危機にさらされている時代だからこそ、ネガティヴに変動やら絶滅やら危機の前に戻ろうと考えるのではなく、いまあるこの状況を認めたうえで、僕らがどうあるべきかを考え、いま必要とされるべきことを、あとであの時代にああしておいて良かったと思えるような生成変化を起こすべきなのだろう。
そのとき、僕らは「実際にポストヒューマンになっている」のだろう。
そして、僕たちはもはや「ポストヒューマンでしかない」のだから。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
