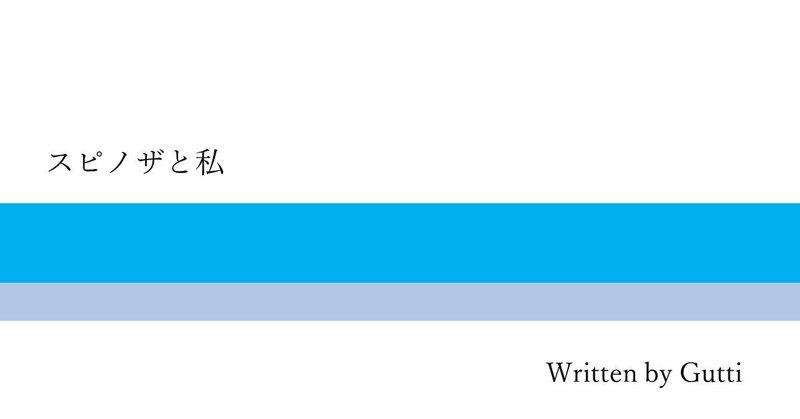
エッセイ:スピノザと私~「私」不在の哲学をめぐって~
●スピノザという哲学者
バルーフ・デ・スピノザは、17世紀、オランダの哲学者である。教科書通りの説明をすれば、デカルト、ライプニッツと並ぶ17世紀の近世合理主義哲学者として知られ、その哲学体系は代表的な汎神論と考えられてきた。また、カント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルらドイツ観念論やマルクスにも影響を与えている。
最新の研究によれば、スピノザの影響はドイツ観念論のみならず、ヒューム、ロックといったイギリス経験論、モンテスキューやディドロ、そしてルソーといったフランス啓蒙思想にも影響を与えていることがわかっており、西洋における近代自由思想の祖、源流ともいうべく存在であることがわかっている。
そして、スピノザ再評価の火付け役ともいうべきドゥルーズらを中心に、フランスの現代思想において二度目のスピノザルネッサンス(一度目は18世紀のドイツ)が起こり、今日に至っている。
日本においても、國分功一郎によるNHK番組でのスピノザ紹介をきっかけに、関連本、研究本が次々と刊行され、ついには待望の新日本語訳による『スピノザ全集』が岩波書店から刊行開始となる。日本におけるスピノザルネッサンスとも呼ぶべき事象が起きているといってもよいのではないだろうか。
●『エチカ』はなぜ躓いてしまうのか
私はといえば、スピノザとの出会いは、遡る事二十数年前、大学生だった頃である。中上健次や武田泰淳、坂口安吾などを読む文学青年だった私は、哲学への関心は一切なかったといってよい。
だが、敬愛する作家、中上健次の盟友でもあり、同時代において圧倒的な影響力を誇っていた批評家、柄谷行人の著作を通して、間接的にスピノザを知ることになった。
そこで、スピノザの代表的な著作である『エチカ』を読むことになった。むろん、誰もがそうであるように、その難解さに面食らったというのが正直なところではあった。
なぜ『エチカ』は、面食らってしまうのか。國分功一郎などの「スピノザ入門」的なものを読めても、いざスピノザ自身の著作に向き合っても、のっけから躓いてしまい、最後まで読み通せない、心が折れてしまう、という人が多いのではないだろうか。
このエッセイのタイトルは、「スピノザと私」なのだが、じつはスピノザ哲学に、「私」という考え方は一切出てこない。と言い切ってもいいくらいに出てこない。
普通、哲学といえば、「私」をめぐるものだというのが通念であろう。なぜ私は生きるのか? なぜ私という存在はあるのか? この私とは何か。逆にいえばなぜ哲学は「私」をめぐる学問だというイメージがあるのか。
これは哲学史上、もっとも有名なテーゼによる影響が大きいと思われる。すなわち、「我思う、故に我在り(Cogito ergo sum)」。フランスの哲学者、ルネ・デカルトが提唱したものである。
デカルトは、スピノザと同じ17世紀を代表する哲学者だが、スピノザよりも先輩である。当時の哲学界隈において、デカルトの影響力は圧倒的であった。デカルト思想を学ぶ、ということが哲学をやること、といってもいいくらいのものであった。
デカルトの生きた時代。それは、私という主体の概念のなかった中世から、個人の主権、国民国家の主権という考え方が出てくる近代への移行にもリンクしている。近代哲学、私という主体の哲学は、デカルトから始まったと言ってもよい。
しかし、スピノザはデカルトは明らかに異なるアプローチをとることとなる。スピノザはライプニッツに、自身の哲学をこう説明していた。
世間一般の哲学は被造物から始め、デカルトは精神から、私は神から始める
そう、スピノザはデカルトを師事していたにも関わらず、デカルトのように精神(=私)から始める哲学ではなく、「神」から始めると宣言しているのである。
これは、スピノザ哲学に最初にアプローチするにあたり、われわれを躓かせてしまう原因の一つである。なぜ「神」なの? 私は私のために私のことを知りたいから哲学をやりたいのに、なぜスピノザ哲学に「私」は出てこないの?となってしまうからである。
このあたりの詳細については、以下の記事でも書いているので、こちらもご参照頂きたい。
●スピノザ哲学に「私」はない?
さて、『エチカ』に戻ろう。上記にも書いたように、スピノザ哲学に「私」という主体の考え方、概念は出てこない。『エチカ』のあまりにも有名な冒頭は以下のような感じである。
第一部 神について
定義
一 自己原因とは、その本質が存在をふくむもの、いいかえれば、その本性が存在するとしか考えられないもののことである。
二 同じ本性を持つ他のものによって限定されるものは、自己の類において有限といわれる。たとえば、物体は有限であるといわれる。なぜなら、われわれは常により大きな物体を考えることができるからである。同じように思想は、他の思想によって限定される。だが、物体は思想によって限定されないし、また思想は物体によって限定されない。
三 実体とは、それ自身において存在し、それ自身によって考えられるもののことである。いいかえれば、その概念を形成するために他のものの概念を必要としないもののことである。
とまあ、こんな感じで「定義」が書かれ、次に「公理」があり、「定理」と続く。『エチカ』はこの冒頭から終わりまで、すべてがこのような数学の証明のための記述形式で書かれており、これが哲学? 倫理学? ということで、のっけから読む者を躓かせてしまうのである。
なぜスピノザがこのような叙述をとっているのかは、さまざまな研究本にも書かれているが、身近なところでは以下のような記事にも説明があるのでご参考まで。参考3分でわかる! スピノザ『エチカ』
スピノザはまず「神について」を第一部で説明し、それから第二部「精神の本性および起源について」、第三部「感情の起源および本性について」、第四部「人間の隷属あるいは感情の力について」、第五部「知性の能力あるいは人間の自由について」と続ける。
「私について」という主題は一切出てこない。読んでみるとわかるが、実際に「私」とは何か、という主体の問題も出てこない。『エチカ』で語られるる主語とは、神から始まり、物体とは・・とか、運動とは・・、知性とは・・、存在とは・・、精神とは・・、身体とは・・、感情とは・・、徳とは・・、といったように、この世界の事象、運動の一つ一つを定義し、説明し、これらすべては神から産出され、神の表現として存在するという感じなのである。
したがって、われわれが通念として抱いている哲学のイメージのまま『エチカ』に向かってしまうと、読者は裏切られたような気分になってしまうことであろう。われわれは、あまりにも近代的思考に慣らされすぎているのだ。すなわち、「私」というものが絶対であり、私という主体があって、この私が関わる世界が、私の周囲にあるという考え方である。
そのような意味での「私」という考え方を求めるのであれば、スピノザ哲学は一切無縁である。國分功一郎が言っていたように、スピノザ哲学は、OSがまったくこれまでのものと異なるのだ。今の私たちが当たり前のようにして使用しているOSのまま、スピノザ哲学を読み解こうとするのであれば、スピノザ哲学は不具合を起こしまくるわけで、場合によっては「起動」すらしないかもしれない。
●スピノザは「この私」をどう考えていたのか
それでも、やはり私たちはこういうだろう。そうは言っても「この私」というのは紛れもなくあるではないか。こうやって記事を書いている私、コンビニに行く私、職場で働く私、映画を見て涙する私、恋愛してどうしようもなく傷ついてしまう私、ケガをする私、死んでしまう私・・・ デカルトが言うように、この私は、現に、あるのだ。
もちろん、スピノザとて、この私は存在しないなどと言っているわけではない。何よりスピノザ自身が、著作の中で、<私は・・・こう考える>と書いているのだし、人間の存在、身体と精神についても詳細に書いているわけで、「私」自体を否定しているわけではない。
そうではなく、スピノザの観点でいくと、「私」という存在は、われわれが考えるような「主体」であるとか、「個人」という「最小単位」ではないということであり、その個としての人間があるから、世界があるわけでは決してない。そのような「私」中心の考え方、自由な個人や主体という考え方をスピノザは採用しないのである。
言うまでもなく、「私」とは、さまざまな関係性の所産として存在する。父と母の存在があり、そのまた父と母の存在があり・・と出生においてもそうであるし、親族、友人、他人、学校の先生、職場の同僚・・・・とさまざまな他者との関わりにおいて、はじめて存在することができるものである。これは誰においても同様であり、他者無しに自身の存在はありえない。
これくらいはまあ、よくある考え方ともいえるが、スピノザはさらに、この私の身体も、細胞や細菌のような単位でのさまざまな個物の集合として成り立っているのであり、今、ここに存在する「私」は、それら集合体が織りなす生成、運動の、一側面、「現れ」の一つというように考えている。
その現われの、ある側面が、今、自分が自覚している「私」にすぎず、私が自覚できていない「私」もあるし(無意識)、コントロールできない「私」もある(身体作用)。でも、私の知らない私も含めて、「私」なんだよね、ということである。
さらには、この私を取り巻くあらゆる環境、あらゆる生命、あらゆる物質が、すべて私に関わり、今この現実として「現れている」のであり、そういった関係の因果が、無限に広がっている。この無限に連続する関係性のすべてが、世界、すなわち「神」なのであるとするのである。
だから、私も、猫も、蚊も、机も、石も、道も、道端に生えている植物も、誰かの汚物も、ゴミも、すべて「神」なのであり、この「神」以外に、主体もくそもないよ、神のみが絶対なのだよ、と。
スピノザはデカルトのテーゼを、こう書き換えるわけである。
「我は思いつつ存在する(Ego sum cogitans)」
私が考えるから私があるのではない。世界があるのではない。私は考えるが、考えながらもすでにもう、存在しているのだ。存在と思考は同時である。存在の証明に精神のプロセスがあるのではなく、存在=精神は同時並行的である。これは証明の問題ではなく、神の認識において「必然」である。それがスピノザ思想の神髄ではなかろうか。
●私ってなに? もっと楽に考えたい
ここまでつらつらと書いてしまったが、最後に、私がスピノザを読むことで得ている身近な実践ということでいけば、「私」とは何か、「私」という存在の価値は何か、などという自己の観念を持たないようにしている、ということが挙げられる。
「私」という表象がある限り、他人と比較してしまい、優劣をつけたくなり、勝った負けたの観念を持ってしまう。そんなものに捉われていると、経済力であるとか、自分の境遇であるとか、受けてきた教育とか、生まれ持っての能力だとかを基準にしてしまうため、自ら息苦しい状況を招いてしまう。
比較や競争というものは、今の社会が、資本主義や国家のようなシステムが作り上げている制度的なもの、その中での価値観や尺度でしかない。
「私」とは、さまざまにある他者との関係性の中の一つの「現れ」と考えれば、自分とか他人とかそのような観念に囚われることから解放されていくのである。そう、スピノザ思想においては、私も含めてすべては他者=世界なのである。
私も、他者も、それらすべて、有限でしかない人間という生の現れ、もっといえば、世界の様態の諸相。そう考えるだけで、肩の力は一気に抜ける。
大谷翔平やアインシュタインンの突出した才能とは、われわれ人類の才能である。比較するものではない。
他者の喜び悲しみは、すべてわれわれの喜び悲しみである。同時に、他者の暴力、弱さは、すべてわれわれの狂気、弱さ、なのであるから、暴力や差別、あるいは争いといった社会課題は、常に自分と無関係であることはない。
とはいえ、現実的にあるこの私の有限な身体は、すべての他者に関心を向けるということが不可能なので、やはりまずは、この私という一人の他者を満足させられるくらいの喜びの最大化に取り組んでみよう。それは仕事であり、家族といることであり、自分の好きな創作をやることであり、食べることであり・・・といった具合に考えてみるのである。
私という他者を満足させられるのは、私だけであろう。まずは、そかから「他者」と向き合ってみる。
今あるこの私、この身体(能力)において、今の私自身の生を最大限に楽しめるものは何か。今できる私自身のベストは何か。そう考えるだけで、何一つ背伸びすることなく前を向くことができるようになる。たったそれだけのことではあるが、スピノザ思想に出会った価値があるというものである。
なにせ世の中にはそれとは真反対の価値観、教えがいまだに溢れ返っているのだから。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

