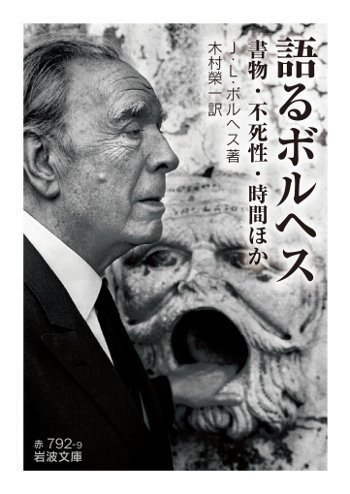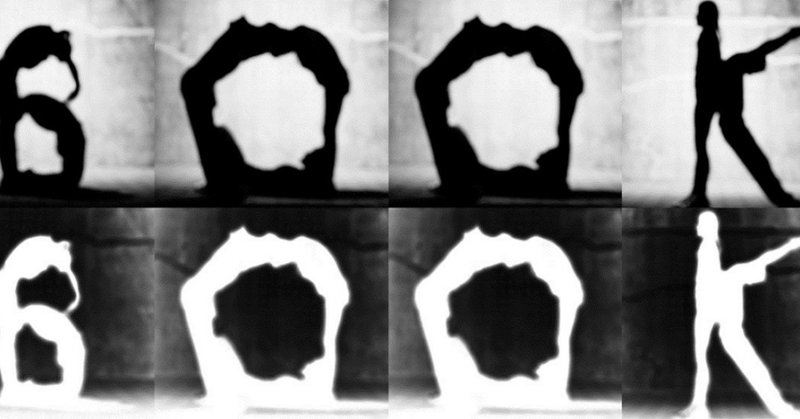
【読書備忘録】エロマンガ表現史からマイタの物語まで
春らしからぬ寒風が吹いているこの頃、春眠どころか冬眠しそうです。皆さまも体調にお気を付けてください。さて、前回からやや間隔はあきましたが、この間にもたくさんの良書に出会えました。その中から特に気に入った書籍を紹介します。
エロマンガ表現史
*太田出版(2017)
*稀見理都(著)
面白かった。エロスの代表格である「おっぱい」の表現方法、乳頭に躍動感を与える「乳首残像」、古くは葛飾北斎もとり入れた「触手」、グロテスクでありながら濃厚な交接を展開させられる「断面図」、絶頂を強調してインパクトを高める「アヘ顔」、さらには「くぱぁ」「らめぇ」といったオノマトペ、そうした今では馴染みのあるエロマンガの表現が生まれた時期・経緯を綿密な調査の上、ときおり考察やインタビューを交えながら概説。新たな表現方法を模索する漫画家たちの野心、規制にも負けない情熱には頭がさがる。また、外国での反響に触れている点も興味深かった。エロマンガを描く人は言わずもがな、読む人にも発見をもたらしてくれる力作だ。本書を通じてエロマンガに対する理解が深まることを切に願う。
追記。後日『エロマンガ表現史』が北海道で有害図書指定された。本書はエロマンガの歴史や工夫をかさねられてきた表現を丁寧に説明し、エロマンガの文化に対する理解を深める立派な研究書であり、青少年の健全な育成を害するものではない。この件に関して小生は青少年健全育成審議会および北海道知事を批判する。誠に遺憾である。
まっぷたつの子爵
*岩波文庫(2017)
*イタロ・カルヴィーノ(著)
*河島英昭(訳)
トルコ人との戦争にキリスト教徒陣営の騎士として参戦したテッラルバのメダルド子爵は敵兵の大砲を受けて無惨にもまっぷたつになる。ところがメダルド子爵はまっぷたつになりながらも命をとりとめる。ここからメダルド子爵の甥にあたる〈ぼく〉の視点で不可思議な物語が始まる。まっぷたつになったメダルド子爵はまるで精神が分離したように善人と悪人にわかれ、悪逆非道な振る舞いを繰り返す〈悪半〉と修行者さながら善行をなしてまわる〈善半〉がおなじ町に居着くことになるのだ。まっぷたつにこめられた意味とは何か。それは物理的・肉体的な分離だけではなく、精神的な意味合いもあるのではないだろうか。ここにもカルヴィーノならではの示唆的な幻想性が表現されている。また語り部である〈ぼく〉の存在感のなさも面白い。一応実在し、実際メダルド子爵や彼に振りまわされる人々と接触もするのだが、どこか浮遊感をただよわせ、物語の外側から概観するような立場を維持している。童話的な雰囲気、グロテスクな情景、現実から乖離した奇妙な世界がそこにある。
圧力とダイヤモンド
*水声社(2017)
*ビルヒリオ・ピニェーラ(著)
*山辺弦(訳)
圧力。圧力。圧力。この小説には「圧力」という単語が何度出てくるのだろうか。数え忘れたのが悔やまれる。熱い日光に照らされる日常で、影のように付きまとってくる圧力。ある紳士に「圧力についてのお考えをお聞かせ願えますか?」と質問されたときから、物語の登場人物たちはあらゆる事柄に圧力を感じ、圧力を恐れ、圧力から逃るためヒステリックに他人と関わらずに済む流行に乗り始める。それはトランプゲームのカナスタであり、最小限の空間にとどまろうと体を縮小させることであり、氷の塊にとじこもって人口冬眠するという時間旅行であったりする。やがて大勢の人々はとんでもない行動に出てしまう。こうした集団パニックとも言える状況に翻弄されながらあくまで流行に逆らう存在として、主人公は孤軍奮闘する。本作品における圧力は複合的で解釈の幅が広い。それは騒動を起こすダイヤモンドのデルフィの扱われ方にも現れている。たびたび強迫観念に囚われ、切羽詰まった状況下に置かれるという不条理。しかし、こうした〈圧力〉は社会が抱える病でもあり、不気味な説得力が認められる。
※水声社さんはAmazonと取引していないので注意。
家宝
*水声社(2017)
*ズウミーラ・ヒベイロ・タヴァーリス(著)
*武田千香(訳)
ズウミーラ・ヒベイロ・タヴァーリスの名前は二〇一八年現在日本ではあまり知られていないが、ブラジルでは高評価を受けている現代文学作家だ。お恥ずかしながら小生も本書を読むまでタヴァーリス氏の名前を知らなかった。サンパウロ美術館付設の映画学校、大学院の芸術コミュニケーション研究科で映画研究を続け、おもに詩集を刊行してきた氏は小説家よりは広範な芸術活動に勤しむ人なのかも知れない。こうした経歴は作品の随所に認められる。娘時代は純真で大人しかったマリア・ブラウリアはヴィーダ(〈生〉と表記される)の導きとピジョン・ブラッドのルビーの効果により、快活で豪胆な老女に変貌する。彼女はくだんのルビーに関わる謎に迫る。物語自体面白いのは言うまでもない。しかし地の文や対話が分割されたように用いられたり、台詞に心中の言葉を挿入したり、戯曲的な構成をとったりと変幻自在、あるいは自由奔放に変化する表現方法に惹かれる。これは解説でも述べられている特徴でもある。テクスト自体に妙味がある。
※水声社さんはAmazonと取引していないので注意。
壁の中
*つかだま書房(2018)
*後藤明生(著)
本書を「短評」形式で紹介するのは無理。できるとしても相当な批評眼と筆力を備えていないとできない。なので、ここでは散文的に書かせていただきたい。ドストエフスキー、ゴーゴリ、カフカ、聖書、永井荷風、アミダクジ式。この帯に記されているキーワードは作中でとりあげられるテーマであり喩えではない。『地下室の手記』『鼻』『変身』『聖書』といった世界的に読まれている本、そして永井荷風と永井荷風に関わる人物の著作をあらかじめ知識として持っている方が物語に入りこめそうだが、仮にすべて未読だったとしても大した問題ではないだろう。どのみち読者はアミダクジ式に脱線をかさねる物語の迷宮をさまようことになるのだから。主人公は高校の英語教師と大学の非常勤講師を務めた後、専任講師になる。舞台は自宅である十二階建てマンションの九階、仕事場に使わせてもらっている九階建てビルの九階、薬剤師を務める女性が住む十五階建てマンションの九階。しかし主人公が〈贋地下室〉と喩えるコンクリートの壁に囲われた部屋は物語の枠を超越し、批評的とも空想的とも戯曲的とも言える奇怪な現場に変わる。読む人を選ぶ小説ながら奇妙な魅力があり、それを味わえたことは僥倖だった。
語るボルヘス 書物・不死性・時間ほか
*岩波文庫(2017)
*ホルヘ・ルイス・ボルヘス(著)
*木村榮一(訳)
一九七八年ベルグラーノ大学で五回に渡っておこなわれたホルヘ・ルイス・ボルヘスの講演の記録。講演で掲げられたのは「書物」「不死性」「エマヌエル・スヴェーデンボリ」「探偵小説」「時間」という博覧強記のボルヘスにふさわしいテーマであり、頭の中に巨大な図書館を持っているボルヘスの果てしなき書物愛、ソクラテスの死を始めとする哲学者や文学者が語り・見せた死の意味、博学多才にして天国と地獄を語るエマヌエル・スヴェーデンボリに依拠した死生観、エドガー・アラン・ポーと探偵小説の歴史に自分自身の解釈を加えた独自の探偵小説論、そしてボルヘスにとって永遠の主題とも言える時間についての考察。次から次に偉人賢人の軌跡を追想し、論説する様子は辞書が語るようでもある。洞察と省察に裏打ちされた観念は、それ自体が壮大な物語のかたちをなしている。
闘争領域の拡大
*河出文庫(2018)
*ミシェル・ウエルベック(著)
*中村佳子(訳)
当初ミシェル・ウエルベックは詩人・評論家として認知されており、一九九四年『闘争領域の拡大』刊行をもって小説家の道を歩み始めた。そういう意味でウエルベック氏の出発点と言える。著者の観察眼は時評的な性質を有する本作品でも発揮されている。ソフトウェア・サービス会社に勤める主人公〈僕〉は仕事の都合で同僚ティスランと地方出張することになる。常に社会や人物にシニカルな感想を抱く〈僕〉と、無類の女好きながら不細工ゆえ運命的に異性と繋がれないティスラン。このおかしな交流が契機となり〈僕〉は経済システムに通じる性愛論を強固にしていく。セックスも自由化する。しかしセックスにおける自由主義は致命的な、金銭とは別種の差異化を起こすシステムでもある。そして彼は〈闘争〉の概念をセックスにも広げ、市場の法則に喩えながら持論を展開する。もしかすると本作品の主題は一二六~一二七頁の独白に集約されているのかも知れない。彼の哲学的にして神経症的な思索の日々、哀れな道化役であるティスランの人生に哀愁を感じる。性愛・世相を追及するウエルベックの原点がここに認められる。
偉人たちのあんまりな死に方 ツタンカーメンからアインシュタインまで
*河出文庫(2018)
*ジョージア・ブラッグ(著)
*梶山あゆみ(訳)
冒頭から「血なまぐさい話が苦手なら、この本を読んではいけない」と意味深長な文言が出てきて尻込みしそうだが、本書は堅苦しさとは無縁の軽快な読みものであり、構える必要はない。ただし医学的な言及が多いため内臓の話を見聞して身震いする人は、著者の警告に従うのが吉だろう。ようするに本書はツタンカーメン、カエサル、クレオパトラ、コロンブス、ヘンリー八世、エリザベス一世、ポカホンタス、ガリレイ、モーツァルト、アントワネット、ワシントン、ボナパルト、ベートーヴェン、ポー、ディケンズ、ガーフィールド、ダーウィン、キュリー、アインシュタインの具体的な死に方、死後の扱われ方に焦点を当てた悪趣味(褒め言葉)な物語なのだ。歴史に名を刻む超有名人たち。彼らの名は教科書にも記載されているが、経歴優先で死因や歴史の裏側は後まわしにされがちである。その後まわしにされがちな、蓋をかぶせられた臭いものをとりだし香りを楽しむわけだ。悪趣味で結構。しっかり楽しませていただいた。
黄金の壺/マドモワゼル・ド・スキュデリ
*光文社古典新訳文庫(2009)
*ホフマン(著)
*大島かおり(訳)
エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマンの短編小説を収録した作品集。特に印象的なのは『黄金の壺』だ。大学生アンゼルムスは文書管理官のもとで筆写係を務めるが、そこには霊界の王フォスフォルスより追放された火の精霊サラマンダーの切なる願望があった。アンゼルムスもサラマンダーの娘に恋を抱いており、利害一致した二人は良好な関係を築いていく。ところがアンゼルムスに恋心を寄せる娘とサラマンダーの宿敵である占い師が手を組み、恋の成就、霊界への帰還、黄金の壺をめぐる熾烈な争いが幕をあける。近代ヨーロッパで繰り広げられるファンタスティックな展開。現実性と幻想性の入り混じり具合が面白く、例えば現実に染まった人々は不可思議な現象にたびたび動揺させられる。このバランスが愉快でもある。そのほか、ルイ十四世時代の作家マドレーヌ・ド・スキュデリが探偵役として冤罪事件を解決に導く『マドモワゼル・ド・スキュデリ』、音楽評論的な小品『ドン・ファン』『クライスレリアーナ』といった短編にも独自の味わいがある。
マイタの物語
*水声社(2018)
*マリオ・バルガス=リョサ(著)
*寺尾隆吉(訳)
まさしく本作品は「マイタの物語」である。一九六二年、社会主義革命を企て農民指導者と学生を含むわずかな面子で反乱を起こすも即鎮圧された、アンデス高地の町ハウハにおける事件を原点とするマリオ・バルガス=リョサ(本書ではバルガス・ジョサ表記。小生は寺尾隆吉氏のバルガス・ジョサ表記に反対しているため意固地になってバルガス=リョサと書かせていただく)の長編小説。著者の分身とも言える主人公はマイタの軌跡を小説にしたためるため取材をかさねる。ところが当事者の記憶が薄れていたり、ときにはぐらかされたりすることにより対話をかさねるごとに事件の様相は虚構の膜に覆われていってしまう。混迷の時代にて革命を成功させるため武装蜂起するマイタ、その血生臭い活動の真相を追い求める作家。絡み合う史実とフィクションのはざまにおかれた二つの物語が接近していく展開は緊迫感に満ちており、過去と現在が同時進行する文体ともども一分の隙もない。フィクションとして、メタフィクションとして丹念に練り込まれている『マイタの物語』は、現代世界文学を代表するペルー発の作家バルガス=リョサ氏の魔術によって顕現した第二の史実と表現したい。
※水声社さんはAmazonと取引していないので注意。
〈読書備忘録〉とは?
読書備忘録ではお気に入りの本をピックアップし、感想と紹介を兼ねて短評的な文章を記述しています。翻訳書籍・小説の割合が多いのは国内外を問わず良書を読みたいという小生の気持ち、物語が好きで自分自身も書いている小生の趣味嗜好が顔を覘かせているためです。読書家を自称できるほどの読書量ではありませんし、また、そうした肩書きにも興味はなく、とにかく「面白い本をたくさん読みたい」の一心で本探しの旅を続けています。その過程で出会った良書を少しでも広められたら、一人でも多くの人と共有できたら、という願いを込めて当マガジンを作成しました。
このマガジンは評論でも批評でもなく、ひたすら好きな書籍をあげていくというテーマで書いています。短評や推薦と称するのはおこがましいかも知れませんが一〇〇~五〇〇字を目安に紹介文を付記しています。何とも身勝手な書き方をしており恐縮。もしも当ノートで興味を覚えて紹介した書籍をご購入し、関係者の皆さまにお力添えできれば望外の喜びです。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。