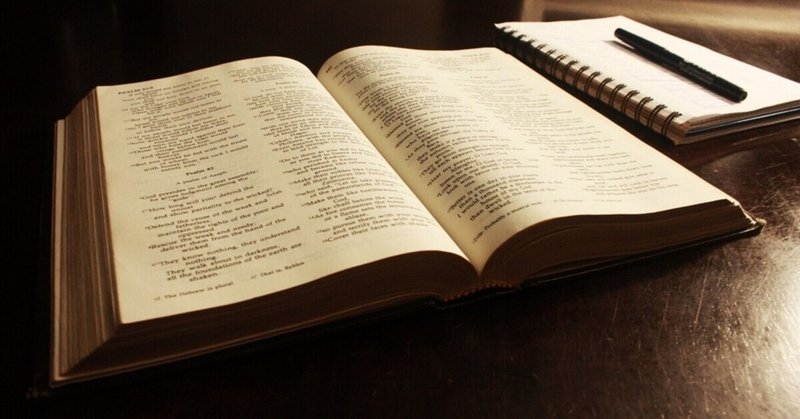
深井智朗 『聖書の情景』 : 二階建ての神学者 : 深井智朗小論
書評:深井智朗『聖書の情景』(春秋社)
深井智朗は、私がもっとも信頼する日本のクリスチャン学者だ。
しかしこの評価は、日本のキリスト教業界では、かならずしも褒め言葉にはならないだろう。なぜなら、私は無神論者であり、呵責のないキリスト教批判者(の嫌われ者)だからである。
しかしながら、私は「キリスト教」を批判しはしても、「キリスト教徒(クリスチャン)」をひとまとめに全否定しているわけでもなければ、その立場で否定しているわけでもないことは、私が殊に厳しく批判することの多いカトリックの場合でも、例外的にではあれ、現ローマ教皇フランシスコを最大限に高く評価していることからも明らかであると思う。
深井が「神学者」であるか「キリスト教学者」かといった分類は、すくなくともその「信仰」においては、ほとんど意味がない。
「神学者」と「キリスト教学者」の違いとは、「神学者」は「キリスト教は真理である」という「信仰」を前提として学問をする人にことであり、一方「キリスト教学者」とは、自身の「信仰」はいったん脇に措き、学問の対象としてのキリスト教を可能なかぎり客観的に研究(学問)する人のことだ。
つまり、どちらも個人的な内心では「キリスト教は真理である」という「信仰」を持っているのだが、自身が他者に向けて「キリスト教」の評価を語る場合に、「結論ありき」で語るのか、それとも「事実分析を前提として」語るのかの違いである。当然、前者は「信仰を共有する身内向けの議論」であり、後者は「内外を問わない開かれた議論」であると言えよう。
このような分類からすれば、深井智朗は間違いなく、後者の「キリスト教学者」なのであるが、深井が「神学をする者」つまり「神学者」ではない、とは言えない。深井智朗は「職業的神学者」ではないだけで、当然のことながら自身の中で、否応なく「神学」をしている人なのだ。
そして、さらに言えば「神学者」として有能か否かは、その肩書きには拠らない。
優れた神学者とは「(キリスト教の)神の意図を、正確に読み解いて伝える人」であるからだ。したがって、深井智朗を「神学者」と呼ぶのも、間違いではない。問題は「職制上の分類」ではなく、その「行ない」なのである。
さて、「キリスト教学者」として数々の業績を残してきた深井智朗の著作の中では、本書は最も「神学者」寄りの仕事だと言えよう。だからこそ「学者」である深井は、「はじめに」において、次のように慎重な断りを入れている。
『 キリスト教会の礼拝で、聖書を朗読し、そこで読み上げられた言葉を解き明かす習慣があります。「説教」と呼びます。しかし、本書は「説教集」ではありません。また、歴史家や神学者は、聖書に登場する人物を調べて、聖書を読む助けになるようにと、「人名事典」や「神学事典」の項目を書きますが、ここに収録された文章は、学問的な事典項目でもありません。もちろん、これを読んだことで聖書の全体像や概略がわかるという意味での啓蒙的な「聖書の入門書」であるわけもないのです。
(中略)
(※ 詩人の)八木重吉の詩のように、聖書を読んでみたいと思ったのです。(中略)彼と同じように「ことばのうちがわにはいりこみたい」という願いを持って読み、感じた情景を描いてみました。もちろんそれは、私自身の読み方、見方に過ぎません。』
この「断り書き」は、いったい何を意味するのか。
もちろん、本書の文章が、著者の「個人的な聖書理解=信仰理解」であると言っているのである。
ここに書かれたことは、キリスト教の「公式見解」でもなければ「正解」である保証も無いと、あらかじめ断っているのだ。
しかしまた、ここに書かれたことは、深井個人にとっての「信仰」の姿を描いたものだとも言えるし、その「信仰」に自信を持つからこそ、他の「神学者」のように、あたかも自分個人の「解釈」を「キリスト教の公式見解」であるかのように語る気もない、という宣言だとも言えよう。そもそも自信が無ければ、単なる「自身の個人的解釈」をわざわざ公刊したりはしないのだから、これは当然のことなのである。
さて、深井智朗の「自身の信仰」に対するこのような自信と「学問に対する厳格さ」は、いったい何に由来するのだろうか。それは、自身の「信仰の純粋性」に対する自信の表れだと、私は見る。
つまり「私は、信仰に不純なものを紛れ込ませていない。信仰さえあれば、あとは捨てられる」という自信が、深井の「学問的厳格さ」を支えている。どんなに「学問対象としてのキリスト教」を突き放して「分析」しようと「私の信ずるキリスト教信仰はビクともしない」と、そう信じているから、世俗の学者と同様の「客観性」を保てるのだし、「客観性」が保てないような「ひ弱な信仰」に対しては厳しくもなって、「自身の個人的なキリスト教解釈と真のキリスト教信仰を、安易に(自己満足的に)混同してはいけない」ということ(甘え・依存の峻拒)にもなり、あのような厳格な「断り書き」を付すこともしたのである。
では、深井智朗の「学問的厳格さ」とは、どのようなものなのであろうか。
私はそれを、本書の「ヘロデ」の章で深井が紹介している『ヴィルテップ』という人形劇の形式に、読み取ることが出来るように思う。この人形劇の特徴は、舞台が「二階建て」になっており、上では「天上の神のドラマ」が、下では「地上での人間のドラマ」が、同時進行で演じられるという形式になっている。
『 この人形劇では、上の舞台ではつねに神の人間救済の計画や努力が演じられるのです。いわば神の世界が演じられるのです。下の舞台では地上の人間の姿が演じられます。ですから、崇高な天上の世界と、生々しいこの世の裏切りや混乱、血が流れ、傷つき、慰められることを拒否したくなるような衝撃の両方を同時に見ることになるのです。
信仰とは、下の舞台を捨て、それから離れ、上の世界に逃れることではありません。下の世界がなくなり、上の世界だけになるように努力することでもありません。信仰とは生きている間、逃れることの出来ない下の世界で、上の世界があることを確信できることです。
信仰をもって生きている人でも、信仰がゆらぐ時があります。上の舞台で、天で起こっていることが、すなわち神が私たちのためになさろうとしておられることが見えないから不安になります。しかし上の舞台は、下からは見えないのだけれども、そこにあるのです。下の世界で地を這うように生きながらも、上の世界を信じるのです。上の世界と下の世界が決して別物ではなく、繋がっていることを示すために、神の独り子は上から下へと向かい、上と下がひとつであることを明らかにしたのです。それがクリスマスの出来事でした。』(P65〜66)
ここで重要なのは、深井が『信仰とは、下の舞台を捨て、それから離れ、上の世界に逃れることではありません。下の世界がなくなり上の世界だけになるように努力することでもありません。信仰とは生きている間、逃れることの出来ない下の世界で、上の世界があることを確信できることです。』と言い切っている点であろう。
と言うのも、下の世界である地上から『上の世界に逃れること』すなわち「天国へ行く」ことがキリスト教信仰の目的だとする教派もあれば、『下の世界がなくなり上の世界だけになる』ことも信じて『努力』している教派も少なくないからだ。つまり、ここで語られているのは、深井自身も認めているとおり、深井自身の「キリスト教信仰」の姿なのである。
こうした深井智朗の「二階建てのキリスト教信仰観」からすれば、もっぱら「上の世界」を論じるのが「神学」であり、下の世界を論じるのが「キリスト教学」だということになるだろう。
したがって、「キリスト教学」の世界では『生々しいこの世の裏切りや混乱、血が流れ、傷つき、慰められることを拒否したくなるような衝撃』を直視して、それに正面から取り組まなくてはならない。つまり「生々しい地上の現実」から目を逸らすことで『上の世界に逃れ』ようとしたり、「生々しい地上の現実」を『消し去って』まるで『下の世界がなくなり上の世界だけにな』ったかのような「現実逃避」に陥ってはならないのだ。
たしかに「キリスト教学」は、もっぱら「生々しい地上の現実」を扱うのだけれど、それは決して「非信仰」を意味しはしない。なぜなら、「下の世界」で人間が何をやっていようと、「下の世界」は「上の世界」と繋がっており、「下の世界の研究」が「上の世界=神」と無縁だなどということはあり得ないし、「神はすべてを見守っておられる」と信じられるのが「キリスト教信仰」だからだ。
したがって、クリスチャンの「キリスト教学者」もまた、何者をも怖れず、何者の「顔色」をうかがう必要もない。ただ神を信頼して、人として誠実に「真理を追究」していけば、その先に神が立っていると確信することができるできるはずで、それこそが「信仰」なのである。
つまり、深井智朗の「キリスト教信仰」は、「信仰」と徹底した「リアリズム」が、矛盾しないのである。
だからこそ、一般的には「矛盾」だと考えられることも、彼の信仰では矛盾にはならない。それが矛盾に見えるのは、「キリスト教信仰」を誤解しているからであり、要は「神を信頼していない」からなのだ。
『 神に救われるというのは、悪人がこの世からいなくなるということではないのです。またこの私が神に救われるというのは、この私の中から悪い部分が全部なくなって、完全な、悪などおこなわない人間になれるということでもないのです。
この私の中にあるどうしても取り除けない部分、なんどでも繰り返してしまう過ちを神がすべて知っていて、その神が、それでも、あなたを愛する、それでもあなたを滅ぼさない、それでもあなたが生きてゆくためにあなたを支えると言って下さるのを知ること、これが救いなのです。
(※ 同様に「創世記」で描かれているとおり)ノアだけが救われて、その後世界には悪がなくなり、ノアは生涯無垢で、罪をおかさず生きたのではないのです。神は(※ ノアの家族と一部の動物以外を、地上からぬぐいさった)洪水の後に決心してくださった。決して無垢であるだけではないノアがいて、このノアが愚かなことをして、救いようがないような状態であっても、それでもノアを滅ぼさないのです。見捨てないのです。そのノアを救うことが神の決心なのです。どんなことがあっても、どんなみじめなことになっても、それでも神はそれをすべてご存知で、この私を救ってくださる。これが聖書の救いです。この私の愚かな部分によりそってくださるのです。』(P113〜114)
だからこそ、神の前で、人は「罪」を隠す必要がないだけではなく、人の前でも「自身の罪」を隠して「聖人君子」ぶらなくてもいい。むしろ「人の前でだけ聖人君子ぶる偽り」こそ「世俗的な過ち」であり「神への信頼欠如」なのだ。
深井は、十二使徒の中でも、イエスによって厳しく叱責されることの多かったペテロが、しかし最も信頼され、後事を託されたという事実(P125)と、にもかかわらず、なぜ「ペテロの失敗譚」が後世に数多く残ったのかという疑問の、一見矛盾した事実を提示した上で「それはパウロ自身が、自分の失敗譚を語ることで、イエスへの信仰の素晴らしさを語ったからではないか」と推測してみせる。つまり「ダメ人間」でも(イエスにサタン呼ばわりされた人間でも)「イエスは救ってくださる」と、ペテロは自身を実例にして、この信仰の力と素晴らしさ語ったのではないか、と推測したのだ。
こうした深井の信仰理解からすれば、「不都合なこと」を隠蔽するような信仰は「偽物」なのである。どんな人間でも救ってくださる主イエス・キリストを信用し切っておらず、世俗的な「体面」を取り繕っているだけ、ということになるからだ。
『 人間が、人生の問題を隠蔽したり、遠ざけたり、放棄したりするのではなく、真の意味で方向転換し、悔い改めるために、ヨハネの首のみならず、神の独り子イエスのいのちまでも必要としたのだと聖書は私たちに語っているのではないでしょうか。』(P158〜159)
そんな贖いきれない犠牲を、決して無駄にしてはならないのだ。
当然、ペテロの末裔を名乗るカトリックが、しばしば「異端審問」や「十字軍」といった問題を、過去の話あつかいにし、無かったことにしたがるのも、同じ誤ちである。そうではなく、カトリックこそペテロのように生きなければならない。
『ペテロは生涯同じことを繰り返したのです。立ち上がっては、また倒れる。正しく理解しては、また誤る。しかしそのたびに彼は立ち上がるのです。なぜなら彼の救いのために祈るキリストがいるからです。伝承に拠れば、最後にはローマに戻り、ローマ皇帝ネロのキリスト教大迫害の中で「逆さ十字架」につけられ殉教したのでした。』(P132〜133)
これは「惨めな死」「無意味な死」「敗北」なのだろうか。否、少なくとも「信仰」的には、そうでないはずなのだが、こうした生き方を選べない信仰者は多い。
例えば「教会を守るため」と称して、上手に「政治的に立ち回る」聖職者の如何に多いことか(例えば、独裁者と政教協定を結ぶなど)。しかし、言うまでもなく、そんな生き方は「信仰」としては間違いである。なぜなら「キリスト教の信仰」は、罪人をも無条件に受け入れる「無償の愛」であって、小利口にも愛の多寡を計算する「ユダの愛」ではないからだ。
「ヨハネによる福音書」に描かれた「マルタとマリア姉妹の家をイエスが訪れた際、マリアが極めて高価な香油でイエスの足を洗った」という有名なエピソードで、このマリアの行ないを非難して「なぜ、この香油を三百デナリで売って、貧しい人々に施さなかったのか」と叱りつけた人がいた。イエスに随行していた弟子の一人である、イスカリオテのユダだ。
深井も認めるとおり、ユダの意見は、世俗的には至極もっともな常識論だろう。三百デナリとは、当時の労働者の年収にあたるというのだから、マリアの突拍子もない行ないを、善意ではあれ浪費と見て「貧しい人に施した方が良かった」と考えるのは、決して間違いではないリアリズムだ。
しかしながら、と深井は指摘する。「キリスト教の信仰」とは「キリストの愛」とは、そういうものではないのだ。
『確かにそうです。正しい意見です。年収ほどのお金があれば、多くの貧しい人を助けられるでしょう。これも愛です。そしてそれはもしかすると私たちがよく知っている愛かもしれない。
この愛は計算するのです。計算された、数値化された、合理的な説明がつく愛なのです。それがイスカリオテのユダの愛で、彼はそのような人でした。その意味で彼は正直な人間だったのです。あの人と付き合うと得かどうか、あの人の友人になると人生にプラスになる。あの人とつきあっているとみんなからうらやましがられる。そうやって愛を計算するのです。そういう心が私たちにもあります。また愛が見えないので、具体的な形を求めてしまうのです。お金に換算したくなるのです。』(P78〜79)
例えば、このまま「お国の方針」に従わないと、弾圧されて「教会」が潰されてしまうから、ここはひとつ「教会を守り、信者を守り、この信仰を守るため、ひいては人間の救いのために」方便的に、お国の方針に従っておこう、などという考え方は『計算された、数値化された、合理的な説明がつく愛』なのである。
このように、深井智朗の「信仰」とは「神の愛への絶対の信頼」であり、だからこそ「地上的な損得(忖度)抜き」で地上的なことにも取り組めるのである。また、だからこそ深井には「絶対的な自信」があるのだ。「たとえそれで自分が間違っても、それでも神が救ってくださる。だから、自分は突き進める」と。
そして、そんな彼の生き方を示す言葉が、佐藤優との対談(形式の講義である)『近代神学の誕生 シュライアマハー『宗教について』を読む』(2019・春秋社)のなかで語られている。
『佐藤一一組織神学については、東京神学大学が圧倒的に強い。そもそも日本の神学界は一九七〇年前後の大学紛争でガタガタになり、同志社と東神大もほとんど交流がなくなってしまった。それ以降、おたがいの生態系はまったく別の発展をしています。いまでもほとんど交流はないでしょう?
深井一一私は(※東神大を)卒業後ほとんど疎遠になってしまったので、そのあたりの事情はあまりわかりません。』(P8)
『深井一一(略)ここまで書くと自分の教会での立場が危うくなるかもしれないような箇所を修正したのが(※『宗教について』の)第三版。だから第三版はつまらない。第一版で「ここまで言っちゃうんだ!」とみんながびっくりしたことを、シュライアマハー自身が修正してしまう。シュライアマハーってそういういう人なんですね。
佐藤一一保守化したらみんなそうですよ。エスタブリッシュされた場所を確保したらおとなしくなるものです。それが普通です。
深井一一そうですか。
佐藤一一ヘーゲルなんて若いころは凶暴ではないですか。たとえば『キリスト教の精神とその運命』のときは凶暴です。『精神現象学』もまだまだ過激ですが、『エンチュクロペディ』になると、相当つまらなくなっている。
深井一一思想は必ず前衛から後衛になる。守りに入ってしまうものでしょうね。
佐藤一一加齢もありますからね(笑)。』(P132)
『佐藤一一しかし、道徳の授業で習熟度をチェックし、評価した上で単位も与えるというのは異常な話ですよ。もっとも学習指導要領では、評価は文章で行い、点数はつけないということになっていますが。
深井一一ただキリスト教の学校も、たとえば聖書の授業で試験をして点数をつけています。これも問題といえば問題ですから。』(P143)
『佐藤一一日本の神学は東西で大きくふたつにわかれていて、圧倒的なシェアは東の東神大系です。関西には細々と同志社と関西学院(関学)がありますが、関学はどちらかというと社会活動のほうに重点を置いている。そうなると、教会形成の神学という観点からは、同志社と東神大が重要になります。
ところが、同志社と東神大はたがいに口も利かない仲(笑)。五〇年くらい全然接触がない。だから勉強していると、全然別の生態系で発達しているからおもしろい。
私が東神大出身の人と仕事をしているというと、みんなびっくりするんですよ。交流があったのって、一九六八年ぐらいが最後じゃないかと思います。
深井一一たぶん私は東京神学大学の人たちからえらくきらわれていると思うので、東京神学大学を代表しているとは、とうてい言えません(笑)。』(P219)
こうした会話の意味は、現在の東京神学大学の神学が、シュライアマハーが批判した「プロテスタント・スコラ主義(プロテスタント正統主義)」と同様に「保守的」である、ということを知っていれば、けっして理解困難ではないだろう。
また、深井が語るとおり、シュライアマハーの『宗教について』が、「宗教を侮蔑する教養人のための講話」というサブタイトルを付して、キリスト教批判者にむけて書かれたかのような体裁を採りながらも、じつはそれを煙幕にして「教会の保守性」を批判した本であった、という点を考え合わせれば、深井智朗の日本の神学界における立場と、その自己認識も自ずと明らかになろう。
要は、現在の東京神学大学の神学的立場からすれば、深井の学問的あり方は「世俗的」でありすぎ、その意味で「教会批判的=初期シュライアマハー的」でありすぎると見られている、ということなのだ。
同様に、なぜ同志社大神学部出身の佐藤優が『東神大出身の人と仕事をしているというと、みんなびっくりする』のかと言えば、それは、日本の神学界の主流に君臨する誇り高き『東神大』出身の人が、傍流の「同志社大学神学部出身」であり、かつ「本職の神学者でもない」佐藤優という「キワモノ」を相手にするとは、とうてい思えないからなのである。
つまり、深井智朗は「地上=現実の生活」において、現に『あの人と付き合うと得かどうか、あの人の友人になると人生にプラスになる。あの人とつきあっているとみんなからうらやましがられる。そうやって愛を計算する』ことを潔しとしなかったが故に、「東神大」系の主流神学者にはならず、逆に『東京神学大学の人たちからえらく嫌われ』ることにもなったのであろう。
このように「日本のキリスト教神学業界」において、嫌われようと、傍流におかれようと、深井は「ペトロ」のように「キリスト教界の失敗の歴史」を語ることを怖れなかった。
私のような外部の人間から「隠すな」「誤摩化すな」「それは詭弁だ」などと批判されることのない公正さで、「キリスト教の歴史」と取り組んできた。だからこそ私は、深井智朗を信用するし、高く評価もするのである。
もちろん、だからと言って、まったく注文を付ける隙がないとまでは言わない。なにしろ、神の実在を信じているという段階で、私にすれば「(無意識ではあれ)どこかに誤摩化しがある」し「弱さもある」という、基本的な評価は変わらないからだ。
本書においても、と言うか、自身の「信仰」を語るという、その意味で神学的な(二階部分に属する)著書である本書においては、いつもの研究書では見えにくい「弱さ」や「不十分さ」の見てとれるところも少なくはない(当然、クリスチャンが読めば、そこは弱点には見えないだろう)。
しかし、深井がクリスチャンであろうとなかろうと、そもそも人間には誰しも「弱さ」や「不十分さ」はあるのだし、深井の、キリスト教徒であるが故の「弱さ」や「不十分さ」、つまり「不完全性」は、決して「非クリスチャン」のそれよりも大きいとは言えないのであるから、本書における細かな弱点を、ここでいちいち指摘するのは止めて、深井には「より厳格であれ」と望むに止めておきたい。
ともあれ、神の存在を信じ、それとの紐帯を常に感じているからこそ、この地上で「強く正しく美しく」生きることが出来るという理想を、精一杯生きようとしている深井智朗という人を、私は最大限に高く評価したい。たとえ、彼の信じる「神」がフィクションだとしても、それに「逃げる」のでもなければ、それを「嵩に着る」のでもなく、その信仰によって、この地上をより良く生きようとするのであれば、その生き方を肯定するのに、私も決して吝かではないのだ。
そして、その上で、個人的には「それでも、貴方は神なんて実在すると思います?」と問うてみたい。
無論、その答は「貴方が納得できるようには説明できませんが、実在します」だろうし、所詮、人の内的確信は、他者には検証のしようもないのだから、最後は「そうですか」と言う他ないのだろう。けれど、それでも私は、世間に蔓延る多様な「信仰という現象」を、キリスト教も含めてそれらすべてを、自身が納得できるまで疑わずにはいられないし、その意味でも、歯ごたえのある信仰者であるからこそ、かえって深井は注目に値するし、私の研究対象となり得るのだ。「地上にあることを怖れない信仰者」であるからこそ、深井智朗は、私の地上的研究の対象に値する「本物の信仰者」なのである。
○ ○ ○
【補論・東京神学大学の保守性について】
現在の日本のキリスト教神学界で、もっとも有名なプロテスタント神学者の一人が、森本あんり(1956年10月19日〜)であろう。森本は「アメリカキリスト教史」の専門家で、その成果の一つである『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体』(2015・新潮社)はベストセラーにもなったので、同書で森本を知った一般読者も少なくないはずだ。
森本は、1979年国際基督教大学(ICU)人文科学科卒、1982年東京神学大学大学院組織神学修士課程修了という経歴を持つ「東京神学大学系の神学者」であり、1991年国際基督教大学牧師、97年同準教授、2001年教授、という経歴を経て、2012年からは同大学学務副学長となり「宗教学」を講じている(Wikipedia)。
国際基督教大学(ICU)と言えば、最近、秋篠宮夫妻の次女である佳子さんの卒業が話題になったばかりであるが、今の天皇家の子女が入学することからもわかるとおり、国際基督教大学(ICU)は、一般的には「リベラル」な学風として知られている。言い変えれば「宗教保守」とは無縁のように感じられるし、その国際基督教大学(ICU)の現副学長が森本あんりなのだから、私も当初は、森本にリベラルのイメージを持っていた。
実際、森本は前記の『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体』で「アメリカの宗教保守派」を詳しく紹介しているが、そのスタンスは学者らしく客観的で、「アメリカの宗教保守派」にシンパシーを示すものでも、世間的で薄っぺらなアンチ「反知性主義」に与するものでもなかった。同書は「アメリカの反知性主義」を、歴史的かつ客観的に紹介する好著であったのだ。
しかし、問題はその次に刊行された一般向け書である『異端の時代 正統のかたちを求めて』(2018・岩波書店)である。私は、この本について、『ねじれた二項対立』と題するAmazonレビューをすでにアップしているが、このタイトルの意味するところは「森本の中で、リベラル性と保守性が捻れをおこしたまま共存しているために、本書は内容的に破綻している」というものであった。
要は、森本は、国際基督教大学(ICU)の副学長という社会的立場からも明らかなのように「社会的にはリベラル」なのであるが、神学的・思想的には「東京神学大学出身者」らしく、意外に「保守的」なのである。だから、表面的には、現安倍政権を批判するような「反保守」的リベラルのスタンスを示しながらも、考え方の本質自体は「保守」なので、どうしてもそこで「無理矛盾が生じている」というのが、森本の『異端の時代 正統のかたちを求めて』に対する、私の診断なのである。
で、こうした、国際基督教大学(ICU)関係者の「二面性」について指摘した、井上章一の極めて興味深い文章があるので、下に紹介しておこう。
『 二〇一五年一一月二八日のことであった。私は国際基督教大のアジア文化研究所にまねかれ、報告をおこなっている。当日は、同大学でシンポジウムがひらかれた。「日本の大学とキリスト教」と題された研究集会である。副題には「戦前・戦後の教育改革と宣教師団体」とある。集会には、キリスト教の学校に籍をおく研究者たちが、多くつどう予定であるという。その基調講演をたのまれ、私は同大学をおとずれた。
(中略)
戦時下にこうむった抑圧が、各会派ごとに報告されるのではないか。国際基督教大での研究報告は、おおむねそんな私の予想どおりに、すすんでいった。キリストと天皇の、どちらをよりうやまうのかと問いつめられ、屈服をしいられる。以上のような発表がつづいたことを、おぼえている。
しかし、夕方以後の懇親会では、まったくちがう話もくりひろげられた。その場では、国際基督教大の関係者たちが、うらやましがられていたのである。秋篠宮家のお姫様がご入学されて良かったですね。おめでとうございます。主催者は、他のキリスト教校からきた研究者に、そう声をかけられていた。国際基督教大側は、これにまんざらでもなさそうな表情で応対していたものである。
昼間にかわされた天皇制の重圧をめぐるやりとりは、いったいなんだったのか。天皇制が研究の場ではけむたがられ、懇親の席では親しみをこめつつ語られる。その現象じたいが、天皇制とキリスト教をめぐるべつの研究テーマになる。以上のようにも、想わされたしだいである。
まあ、戦後の天皇制は、かつてほど威圧的でなくなったということかもしれないが。』
(井上章一・郭南燕・川村信三『ミッションスクールになぜ美人が多いのか 日本女子とキリスト教』2018・朝日新聞出版、P63〜69)
キリスト教徒と言えども、また大学教授と言えども、所詮は「人間だもの」仕方がないと言ってしまえばそれまでなのだが、これがクリスチャンの口からは絶対に語られない「今のクリスチャン研究者・大学人」の実際だろう。
この場には、国際基督教大学の副学長である森本あんりも、たぶんいたはずだ。
ちなみに、井上章一という人は、『霊柩車の誕生』『つくられた桂離宮神話』『アート・キッチュ・ジャパネスク 大東亜のポストモダン』といった著書が示すとおり、建築史・意匠論を専門とする人だが、『美人論』や『京都ぎらい』といった著書もあって、要は「世の常識」や「主流派の思考」を挑発するというスタンスの、ユニークで反権威的な研究者だと言えよう。
そんな彼は、いつでも「意匠と本質」という点に注目して、そこに伏在している欺瞞やホンネを暴くのだが、そんな彼の慧眼にかかると「反権力リベラルという意匠(仮面)」の下に隠された「保守的権威主義という本質(素顔)」も、容易に透視できてしまうという、これはとてもわかりやすい実例なのではないだろうか。
まあ、キリスト教では「三つのペルソナ」(三位一体説)という根本教義があるのだから、それも当然ということなのかもしれないが。
---------------------------------------------
【深井智朗の捏造・剽窃問題について】(2019.5.20 追加)
『深井智朗は、私がもっとも信頼する日本のクリスチャン学者だ。』と、深井の単著『聖書の情景』のレビューに書いた。それだけに、今回の事件は、残念と言うよりも、驚きを禁じ得ない。
何かの間違いではないのかと思いたいところだが、指摘された事実は動きそうにない。事実は事実として受け入れるしかないだろう。
深井のやったことは、もちろん「学者として」「人間として」許されないものなのだが、彼の場合はそれに「クリスチャンとして」「牧師として」という条件が加わるので、通常の場合よりも、ずっと風当たりがキツくなるのは避けられないだろう。
それも自業自得だと言ってしまえばそれまでだが、彼への批判は世間に任せて、私はここで「なぜ」と問うことの方を選びたいと思う。
私は今でも、深井智朗の「人柄」を信じている。それはたかだか数冊の彼の著作から読み取った印象に過ぎないけれども、読書家の自負として、それが間違っていたとは、今も思っていない。
ただ、それだけで、人のすべてが分かるものではないというのも、また事実である。私は、彼が学者としての倫理について、甘いところある人間だとは思わなかった。そこまでは読み取れなかったのだ。
それにしても、そもそも彼はなぜ、存在しない神学者をでっち上げたり、人の意見を剽窃したりしなければいけなかったのだろうか?
わざわざ存在しない神学者をでっち上げなくても、彼はその自著をそれほど遜色なく完成させることができたのではないかと思うし、人の意見を剽窃しなくても「と誰某が書いているが、私もそれに賛成で、さらに言うなら、こういう論点もあろう」といったような書き方もできたはずである。なのになぜ、学者としての致命的行為に手を染めてしまったのか?
私にはこれが、損得の問題ではなく、なにかしら「悪徳の魅力」的なものに憑かれてのものであったように思えない。
「学者として」「クリスチャンとして」「牧師として」という、並外れた「禁欲」「清廉」が求められる立場にあり、すくなからずそんな期待に応えて、そんな人間を演じなければならないからこそ、その無理の代償として、こっそりと「悪徳」に手を染めるという、倒錯的に「甘美な誘惑」を、排除できなかったのではないだろうか。
むろん、これは私の想像に過ぎないけれども、彼の「犯罪」をして、彼の人格を全否定するような評価の仕方は、やはり間違っていると思う。それでは、彼の「犠牲」は無意味になってしまう。
いわゆる「いい人」が破廉恥罪を犯すことは、決して珍しいことではない。
カトリックの方で問題となった「司祭の性的な児童虐待事件」の犯人たちの多くも、決して単純に「非人間的な悪党」などではなかったはずだ。彼らも、司祭になっていなければ、独身の時には風俗店に通ったり、彼女を作ったりして、性的欲求を満たしていただろうし、結婚して普通の性生活を送ったであろう。そのようにしていれば、常習的な性的児童虐待に手を染めることもなかった蓋然性が高いのではないか。
もちろん、こうした「性犯罪」と深井智朗の「学術的不正行為」を同列には扱えない。なぜなら、仮に深井が「クリスチャン」でも「牧師」でもなく、無宗教の歴史研究家であったとしても、「本人の性格」の問題として、今回のような「不正行為」を行った蓋然性は低くはないからである。
しかし、それでも、深井智朗の場合には「学者」であることは無論、「クリスチャン」であること「牧師」であることが、人並み以上の「歯止め」とならなかったのは、やはり、そこに倒錯的な罠があったからではないかと思えてはならない。
人並み以上に「やってはならない」「自制しなくてはならない」という意識こそが、逆説的に「悪魔の誘惑」となったのではないか。そんなふうに思えてならないのである。
ともあれ、深井智朗がクリスチャンであろうとなかろうと、実際に不正行為を行ったのであれば、その事実を認め、悔い改めるべきだろう。
深井が今回のことで、キリスト教会や神学界でその立場を失おうと、存在するのであれば、主イエス・キリストは、決して深井を見捨てはしないだろうからだ。
「罪ある男」を石打ちにしろとは言わず、そこから生まれ変われと言うはずだからである。
初出:2019年3月29日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
