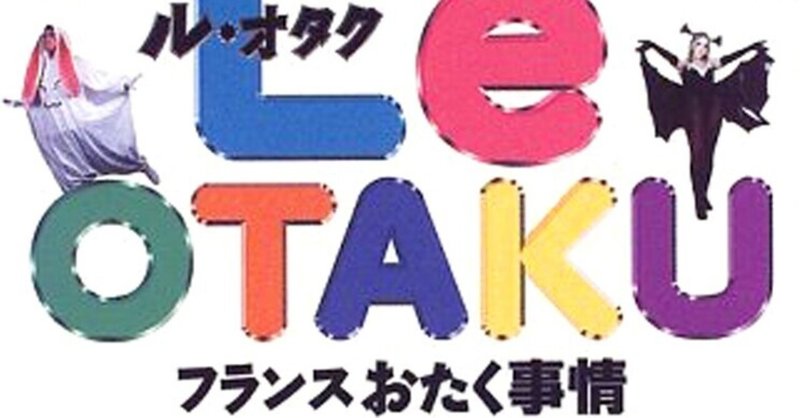
読書感想文 ル・オタク フランスのオタク事情/清谷信一

さーて今回はミーの心の古里、フランスの話題をするザ~ンス! ミーの古里だからと~ぜんみんなミーのことが大好きで、挨拶代わりに「シェー!」をするのが当たり前なんザンス! おそ松6兄弟ザンスか? あいつらはダメザンスね。あーまったくダメダメザンス! なぜって、あいつらの格好を見るザンス。なんザンスか、だっさいパーカーばっかり着て! 区別が付かないザンス! フランスはお洒落発信国なんザンス! ミーみたいな最先端のフランス的ファッションを理解してない連中が、人気者になれるわけないザンしょ! ミーが一番人気に決まってるザンス! フランスはミーの心の古里、いわばミーの国ザンス! だからフランスではタイトルも『おそ松さん』とかじゃなくて『IYAMI』というタイトルで主人公はミー、ミーの登場時間は23分中45分あって、ミーだけフルコマ作画! 全カット付けPANザンス! フランスではあまりにも人気で週12回再放送されているに違いないザンス! あーあー人気者はつらいザンスねー! 毎日毎日放送権利料だけでマグロ食べ放題ザンス! この使い切れないお金、どうすりゃいいザンしょ!
おお、この本には、フランスで放送されたアニメのリストが載ってるザンス! さぁて、フランスでは『おそ松くん』はなんていうタイトルで放送されてたでザンスかね~……。
あれ? ない? ウソざんしょ? 『おそ松くん』はフランスで放送されてない……? シェーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!
というわけで、今回の話題はフランスにおけるアニメザンス……(くそぅ、移った)。日本のアニメがフランスでどのように受け入れられ、定着していったか……という話をしよう。
そうそう、イヤミのやつがうるさいので最初に注釈しておくが、フランスで『おそ松くん』は放送されていない。繰り返す、『おそ松くん』は放送されていない。
(『おそ松さん』は放送されていたかどうか知らない)
フランスの前に、まずアメリカの話をしよう。
米国では70年代後半は若年層の犯罪が増加し、その原因がテレビにあると考えられたため、規制が厳しくなっていった。その当時、とある犯罪で逮捕された少年が、「『刑事コニャック』をマネして犯罪を思いついた」と供述し、そのドラマの主演俳優テリー・サバラスが法廷に呼ぶように求めたことが話題になった。そうした事情があり、アメリカドラマから銃撃戦やカーチェイスといった暴力的なシーンはなくなっていき、その影響はアメコミにも向けられていった。
そこで日本のアニメだった。米国は規制を受けまくってアメコミもドラマもつまらなくなっていったところに、自由なスタイルで制作されている日本のアニメが注目されるようになっていった。
日本とアメリカの西海岸は、太平洋を挟んだ「隣国」である。日本とアメリカ西海岸は飛行機で10時間ほどの距離だ。ヨーロッパになると最短ルートでも16時間掛かったし、金のない学生などは24時間以上かけて何度も乗り継ぎしてようやく日本到着だった。そういう事情もあり、アメリカは日本のビデオの調達が比較的容易だった。
おまけに日本とアメリカはVTRの方式が同じ、NTSC方式であった。アメリカのアニメファンが日本へ行きビデオを買い、それを本国に持っていってそのまま視聴することができた。
一方のヨーロッパではビデオの規格が違っていたので、日本のアニメを見たいと思ったら、まずビデオデッキを取り寄せなければならないし、そのデッキを繋ぐために日本製TVも必要だった。それだけの投資はなかなかできず、ヨーロッパのアニメブームはなかなか広まらなかった。
だから漫画やアニメはまず米国に渡り、英語に翻訳されて、それからヨーロッパに入ってきていた。そうした流通が始まったのは、80年代末頃からだ。
ヨーロッパでのマンガ・アニメの広がり方を見ると、最初にフランス、ベルギー、スイスといったフランス語圏に入ってきた。この辺りはバンドデシネ文化があったから、漫画文化もすんなりだった。続いて90年代に入ってイタリア、スペイン、ギリシャのラテン語のエリア。その後に、英国とドイツというゲルマン系エリアとなる。
そうそう、はじめのほうに注釈しておかねばならないが、日本では「アメコミ」も「バンドデシネ」も一緒くたにして「漫画」と呼ぶが、日本以外の国では呼び分けられている。日本で生まれたもの、あるいは日本風のスタイルで描かれたものが「漫画/MANGA」、日本で制作されたアニメが「アニメ/ANIME」。世界的には、漫画とアメコミとバンドデシネは「違うもの」と認識されている。まとめて「漫画」と表記・表現されることはないし、そもそも欧米の人々にとって『MANGA』は外国語だ。この先、「漫画・アニメ」と表記してあった場合、特に注釈がなければ日本のアニメのことを指す。
漫画≠コミック
漫画=MANGA
が正しい。
(ジャパニメーション?? それは日本でしか使われていない言葉だ)
では次に、フランスでアニメがどのように放送されていったか……という話をしよう。
フランスで初めてアニメが放送されたのは1974年。国営第2チャンネル(A2)で『リボンの騎士』が放送されたのが最初である。当初は『サファイア王子』というタイトルで放送されていたが、89年の再放送の時『サファイア王女』とタイトルが変更された。
フランスの子供達にとって衝撃的だったのは、1978年に放送された『UFOロボ・グランダイザー』である。男子視聴率100%の伝説的なアニメである。
当時のフランスでは、テレビ番組の主要な司会者達は、バカンスシーズンになると番組を休んでしまうので、その穴埋めに日本のアニメが放送されていた。その時に放送されていた『ゴールドラック』が子供達の間で大人気だった。『ゴールドラック』とは『UFOロボ・グランダイザー』や『マジンガーZ』といった東映・ダイナミックプロのロボットアニメの総称だ。
『ゴールドラック』はフランスで一大ブームというくらいの人気になり、初回放送後10回以上も再放送されたし、原作者永井豪のもとに「弟子にして欲しい」というフランス語の手紙が多数届いたという。この当時を過ごした子供で『ゴールドラック』を知らない者など、まずいないくらいの人気だった。
1978年にドロテを司会者とする『レクレ・ア・ドゥ』が始まり、この番組は1987年まで続く長寿番組となった(フランスでのアニメ専門番組には司会者がいた)。ここで『キャプテン・フューチャー』『ガッチャマン』『ベルサイユのばら』『キャプテン・ハーロック』といった番組が放送された。その中でも特に人気のアニメが『コブラ』だった。
1986年、フランスのテレビ局が大きく変わる年となった。テレビ局の民営化である。フランスには国営チャンネルしかなく、しかもチャンネル数は3つ。日本でいえば、NHKしか放送局がなかったような状態だった。こういったことはヨーロッパでは珍しいことはなく、例えばイギリスでは2チャンネルのみ。他の国々でも1~2チャンネルしかなかった。むしろ、戦後間もない時期から7チャンネルもあった日本は、世界的に見てかなり異質な方である。ついでにフランスのテレビは昼になると放送を休むし、バカンスシーズンになるとやはり放送を休む。フランスでは今でも時間通りに番組が始まらないことがある。番組制作力の話にしても、日本はやはりかなり特殊だったわけである。
ともかくも、86年にフランスのテレビは民営化したことによって、多チャンネル化が進んだ。その中でも注目が、ドロテ率いるアベ・プロダクションだ。アベ・プロは積極的にアニメの紹介をし続けてきたが、ほとんど米国から独自ルートで供給してもらっていたものだ。ところがチャンネルとして独立し、週25時間もの枠を作ってしまったために、米国経由で入ってくる番組だけでは、対応しきれなくなっていた。

そこで、ドロテとアベ・プロは日本からの直接買い付けに踏み切った。アベ・プロが買った番組を紹介すると『うる星やつら』『シティーハンター』『キューティー・ハニー』『北斗の拳』『聖闘士星矢』『めぞん一刻』『ドラゴンボール』といった作品群である。日本での放送とのタイム・ラグも1年ほどに縮まった。
ドロテが司会をするアニメ番組『クラブ・ドロテ』は超人気番組となり、専門雑誌『ドロテ・マガジン』が創刊されたほどだった。この時代、ドロテはもっとも成功した女性の一人と呼ばれるほどだった。
米国経由で入ってくるアニメはほとんどが米国で再編集されていた。だから例えば『宇宙戦艦ヤマト』は宇宙警察の話になり、毎回違うエイリアンが現れてそれを倒す話になっていたし、『機動戦士ガンダム』ではジオンが宇宙からやってきたインベーダーということになった。『勇者ライディーン』『超電磁ロボ・コンバトラーV』『超電磁マシーンボルテスV』の3作品は一つにまとまって『ショーグン・ウォーリアーズ』になっていたし、『超時空要塞マクロス』『超時空世紀オーガス』『超時空騎団サザンクロス』も一つにまとめられて『ロボテック』というタイトルで放送されていた。
これは現地のプロデューサーが再編集することで、自身のものであるという著作権を主張するためである。日本のアニメを転売する場合、翻訳しただけでは自分たちにお金は入らないが、多少でも手を加えれば、自分たちも著作権を主張し、利益を要求することができるわけである。
フランスでも改竄されていた。フランスで放送されるアニメのエンドクレジットからは日本人の名前は消えて、番組スタッフやその家族の名前が代わりに載っていた。そういった事情もあって、確かにヨーロッパ中で日本のアニメが放送されていたが、アニメが日本制作だったとは誰も知らなかったし、その後も知らないままの人は結構いる。特にスイスで放送された『アルプスの少女ハイジ』は、日常描写があまりにも完璧すぎたために、あの作品が日本制作だと言っても誰も信じないどころか、失笑されるほどであった(今でも日本制作だと知らない人はいるんじゃないだろうか)。
ではどうして日本のアニメがそこまで欧米で取引されてきたのだろうか?
簡単に答えを示そう。安かったからだ。
テレビアニメ1本の権利料はだいたい10万円(これは1話10万円なのか、シリーズで10万円なのか判然としない)。すでに書いてきたように、ヨーロッパはどの国に行ってもチャンネル数は1~3ほどしかなく、番組制作力も低い。こういった時代にあって、日本ほどクオリティの高いアニメを制作し、かつ生産数も多かった国など、世界中どこを探してもなかったのである。実は日本の独占市場だった。
でも当時の日本人は、アニメが世界の独占市場だったことを知らなかった。権利を売ったアニメが外国でどのように手を加えられ、放送されているのかも知らなかった。作り手達はコンテンツが知らない間に売られている事情も知らなかったし、海外で視聴されていることも知らなかった。権利を売っていたのは放送局で、売ったお金は現場に下りることはなく、どうやら担当者の個人的なお小遣いになっていたらしかった。そもそも版権ビジネスがなんなのかも誰も理解していなかったから、言われるままに安い金で売っていた。
世界から見れば、制作に時間とお金がかかるアニメを自分たちで負担するなんてそうそうできるものではなかった。実際に日本以外で日本のようなアニメを制作しようとすると、数倍の予算がかかったし、クオリティも日本レベルまではなかなか追いつけない。世界からしてみれば、「安く大量に売ってくれる日本という国があるというなら、そこから買えばいいじゃない」、でどんどん買う。当時は「権利」の問題とかよく理解されいなかったから、日本人が知らない間にそこから転売されてどんどん拡散されていくという現象が生まれた。実際に、ヨーロッパ中に日本無許可のアニメグッズが大量に出回っていた。もちろん、それらの利益は1円たりとも日本に入ってくることはなかった。
日本のアニメはアメリカに、次いでヨーロッパ中に拡散していくわけだが、その理由は安かったからだ。日本は権利ビジネスで儲けるというチャンスを失ったが、安く売って拡散していったことによって、世界的な「第1オタク世代」の誕生を促したのだった。
ところが、日本のアニメはいつまでも人気……というわけにはいかなかった。
まず1989年『キン肉マン』がバッシングを受けた。問題になったのは「プロレス」そのものを題材にしたことだった。プロレスは日本人にとっては普通にテレビ放送されているものだからなんとも思わないが、フランスではあの格闘シーンは衝撃的なほどに暴力的に映ったのだ。
次いで問題になったのはブロッケンマンの存在。ブロッケンマンのコスチュームは明らかにナチスドイツを元ネタとし、しかも腕にハーケンクロイツの入った腕章を巻いていた。ヨーロッパではナチスに関するモチーフを、公の場で使用することを禁止されているのだ。
『キン肉マン』のプロレス描写に批判が上がり、さらにブロッケンマンの登場で大バッシングが始まった。ここから、日本のアニメは「社会問題」として取り上げられるようになった。
『キン肉マン』の事件以降、アニメは放送前に精神科医によるチェックが入り、有害なシーンは削除された。そういった事情もあって『聖闘士星矢』では格闘シーンの大部分がカットされ、2話分を1話にして放送されるようになった。
『北斗の拳』も暴力シーンが問題となって、放送中止だった。どうにか放送しようと、台詞をコメディ調にアレンジするという方法を採ったが、それでも放送中止を免れることはできなかった(「お前はすでに死んでいる」に対して「死なないよ~ん」という掛け合いをやったりしていた。これが不評だった)。
『めぞん一刻』にはいつも一升瓶を抱えている一ノ瀬という住人が登場するが、フランスでは公衆の面前で飲酒シーンを見せるのは良しとしない。だから一升瓶はレモネードに変更された。それで視聴者は「日本人はレモネードで酔っ払えるのか?」と不思議な目で観られることになってしまった。
(フランスではお酒を飲みに行っても、酔いを醒ましてから店を出るという)
さらに池田理代子原作『おにいさまへ……』は近親相姦を描いているため、やはり問題となって放送中止になった。
日本のアニメはフランスで高い視聴率を獲得していたわけだが、フランス人全員が純粋に支持していたわけではない。特に地位の高い人や文化人といった人々はアニメを非難し、「日本のアニメは文化侵略を行う敵である」と攻撃の対象にしていた。フランスには日本が大好きで、日本文化を研究している「タタミゼ」と呼ばれる人々がいる。こういった人々も、アニメに関しては「あれは私たちが愛する日本の文化ではない」と非難した。フランスのマスコミも、この流れに追従した。アニメの粗探しをして、少しでも変なところや問題を見付けると、ネチネチと批判的な報道をし始めた。
フランスの国立科学研究センターの児童心理学者リリアヌ・リュサは次のように語っている。 「日本製テレビアニメの中に見られるのは性別役割の固定化です。男は皆戦う存在であり、それは日本の伝統、すなわち戦争に基盤にした文化です。一方、女の子は、服従することになっています。暴力があふれ、スポーツの場合勝つことが目的とされます。そこにあるのは野蛮さだけです」
……ツッコミどころだらけすぎて、逆に何も言えない。
実際の話、ヨーロッパでは日本から送られてくるアニメやゲームのイメージだけで、「日本ではとんでもなく犯罪発生率が高い!」のだと思い込んでいる有識者様は一杯いる。データを見て語らない人々、というのはどこの国にもいるのだ。これについては、面倒くさいので突っ込まない。
このようにアニメは「人気があった」というのは事実だったが、しかし放送すればマスコミによるバッシングを受けるようになっていた。放送局としてはアニメ放送は視聴率を稼げる一方、面倒くさいお荷物になりかけていた。アニメの放送枠は次第に減っていったし、新規でアニメを買うことも少なくなっていった。
アニメ放送枠が衰退していく中で、1987年大ヒット作が生まれた。『ドラゴンボール』だ。それに続いたのが95年から放送を開始した『セーラームーン』だった。『ドラゴンボール』と『セーラームーン』はアメリカでも大ヒットしたが、フランスでも大ヒットしていた。この2作はヨーロッパ中で大ヒットした。
しかしやはり問題が起きた。『ドラゴンボール』でピッコロ大魔王が孫悟空の腕と脚を折るシーンが過激として、高等視聴率会議は放送局に20万フラン(400万円相当)の罰金を支払うように命じた。
一方の『セーラームーン』は「猥褻だ」と非難され、「セーラームーンを見るとレズビアンになる」という見解を示した学者も現れ始めた。
90年代後半に入ると、人気作だったが同時に問題作でもあった『ドラゴンボールZ』の放送が終了した。これを機会に、フランスの放送局はアニメを放送することはほとんどやめてしまった。フランスアニメブームの終焉である。
感想文
本書の紹介はここまで。ここからが、私の感想文だ。
本書の前半部分、フランスのアニメブームとその終焉までをかなりざっくりと紹介した。『ドラゴンボールZ』のアニメ放送を終えた後は、アニメはメジャーな文化ではなく、地下化していくことになる。この先のフランスに起きる現象がなんであるかというと、漫画ブーム。意外に思われるかも知れないが、フランスにおける日本の漫画の普及は、アニメブームの後に始まった。というのも、アニメブームが落ち着いた後、子供の頃アニメを見ていた人に、「あの作品の原作を買ってもらおう」という発想から、漫画を買い付け、翻訳し、書店で販売するという試みが始まったのだ。
また漫画になると、文字を読まなくてはならないという問題が発生する。アニメは台詞を吹き替えるだけでいいが、漫画の翻訳のハードルは高い。おそらく一番大きな問題は、文字の縦書き横書き問題。この問題を乗り越えるのに、漫画の翻訳は長年苦心することになる。
この辺りは、本書を読んでいただくといいだろう。
日本のアニメが世界的に人気というのは正しい。しかし、「言葉」がもたらす問題のせいか、そのイメージはいつも微妙にズレている。確かにアニメは人気だが、それは「マニアックでマイナー」な産物だ。
「マイナーな人気」と書くと、イメージとしては「じゃあせいぜい10人とか多くても100人くらいかな?」みたいに考えてしまうが、実際はフランスでアニメイベントを開催すると、会場を数千人が埋め尽くし、日本語でアニメソングを合唱するという光景が生まれる。アニメイベントにやってこない、サイレントファンを含めるとさらに数万人という人数になるだろう。
これは国家規模で人数を考えてもらいたい。「会場を数万人のファンが埋め尽くす」と聞くと大変な人気のように聞こえるが、しかし国家単位で見ると、国民のうちの数パーセント程度の規模でしかない。そういう規模で言うと、やっぱり「マイナー」なんだ。メインカルチャーと呼ぶほど誰もが熱狂しているような文化じゃない……ということだ。言葉がもたらすイメージと、数字がもたらすイメージのギャップをきちんと捉えるところからはじめて欲しい。
(マスコミは「大人気」という言葉イメージだけで語ろうとするし、一方で批判したい人は「フランスの数パーセント程度だから人気じゃない」という数字イメージだけで語ろうとする。これを言い始めたら、日本のアニメファンだって日本人口の数パーセントだ。もっと具体的な数字感や人々の熱気で考えて欲しい。こういう数字の見方はビジネスをやっている人じゃないとなかなかわからないかも知れない。マスコミは頭が悪いから数字が読めないのは仕方ない)
フランスでのアニメファンおそらく十数万人程度だろう……とこれだけ聞くと少なく思えるかも知れないが、ヨーロッパのどこの国でもそれくらいの人数が潜在的にいると考えて欲しい。トータルした数字にすると、結構な数になるぞ……というイメージを持ってもらいたい。日本のアニメがヨーロッパでそこそこ以上に人気というのは事実なんだ。
この辺りは言葉から来るイメージが微妙にズレてしまうから、誤ったイメージを持ってしまう。当たり前の話だが、フランスの道行く誰もがアニメの熱狂的なファンな訳がない。
日本のマスコミは基本的にアホだからこれがわかっておらず、フランスへ行き、道行く人に「あなたの好きなアニメはなんですか」と突然尋ね、何も答えられないのを見て、「日本のアニメがフランスで人気というのはウソ! 誰もアニメのことなんか知らないし、見てもいなかった! 世界のアニメブームはもう終わっている!」なーんて記事を出したりする(これ本当にあった記事だよ)。日本のマスコミは本当に頭が悪い。当たり前だろ、そりゃ、という話だ。
上に書いたように、フランスのアニメブームというのは90年代後期に一旦終了して、以降アニメの放送はほとんどないような状況になっている。おじさん世代は子供時代に見ていたが、しかし大半は日本のアニメだった、ということも知らない。今でも熱心に日本のアニメを見ているのは、フランス国民の中でもせいぜい数パーセント程度の十数万人くらいの話だ。
どんな国でもそうだが、フランスにも「お国柄」というものがある。当然、その国意識に対するプライドもある。というか、フランス人の愛国心は非常に強い。
フランスでアニメが放送されていた頃、子供達は夢中になって観ていたが、大人達も同じような気持ちで観ていたというわけではない。むしろ苦々しく観ていた、というのが実際だった。日本では大人達も子供時代にアニメを観ていた、という記憶があるが、フランスのアニメ放送が始まったというのは70年代半ばのことで、文化的な基盤なんてものは全くなかった状態だった。外国から来たなんだかわからない文化を見て、警戒するのは当然の心理だ。
しかも80年代に入ると日本はバブル期に入り、ヨーロッパ中のアートや土地を買いまくっていた。これに対して、ヨーロッパの人々による日本への悪感情は猛烈に高まっていた。自分より劣っていると思っていた「極東の黄色い猿」が、ものの価値もわかっていないくせに、その国の歴史的意義の高い土地を買収し、精神性やアイデンティティを示すアートを買いあさるのだ(日本人だってヨーロッパ人が日本のお寺から仏像を買いあさって持ち帰ったら、怒るでしょ。日本人はまさにそれをやったんだ)。これに対する強烈な反発があり、そこに「アニメ」というわかりやすいターゲットがあれば当然叩かれる。アニメは当時の「日本人憎し」の当て馬にされていた……という背景もあったのだ。
(今は中国が欧米諸国の敵として認定されている。これは相手が「共産国家だから」という以前に、やはり「アジア人が気に食わない」という心理が深層にはある)
それに、フランスにはアニメ・漫画の前にバンドデシネが文化としてある。当然ながらバンドデシネの世界にも流儀や格式というものがあって、いくら人気があるからといっても誰もが純粋に日本の漫画を受け入れているわけがない。バンドデシネの権威的な世界に入ると、日本の漫画はむしろ「格下」の扱いで、クオリティの高いものは「まあバンドデシネの仲間に入れてやってもいいよ」みたいな感覚だ。
そういった中で、フランスの漫画界最高賞であるアングレームを受賞した『AKIRA』はそれだけ凄いって話だ(2015年1月)。『AKIRA』はあの「プライドが服着て歩いている」みたいなフランスの権威ですら、黙って賞をあげたくなるような作品なのだ。
(余談。日本のオタクナショナリズムにのめり込んでいる人は、「漫画は9番目のアートだ」なんて語ったりする。これはちょっと待って欲しい。バンドデシネの描き手は「漫画家」というより「アーティスト」で、アートだから一冊の制作で平気で5年や10年をかける。アートという認識が強いからだ。そういったものが「9番目のアート」と名乗っているのであって、日本の漫画について「9番目のアート」と言っているわけではない)
どんな国でも同じだが、外国の文化がものすごい勢いと数で入ってきたら、それに対して警戒し、反発するという動きが必ず起きる。
例えばアメリカでは90年代後半から突如アニメブームが失速するという現象が起きている。人気はあったはずなのに、なぜか市場から姿を消したのだ。日本の漫画・アニメがアメリカ市場に対してあまりにも支配的になったために、これを反発し、排除しようというナショナリズムが刺激されてしまったからだ。板越ジョージはこういった現象を「カルチュラル・エコノミック・ナショナリズム」と名付けた。
ゲームもやはり日本が強かったが、2000年代頃に入ると欧米市場から日本のゲームが姿を消した。人気がなくなったから? いや、人気はあったし特に任天堂のゲームは売れ続けていた。しかしお店からは棚が消えたし、話題にすら上げなくなったし、取り上げるときは批判的に取り上げるようになった。どうやらゲームメディアが共謀し、日本のゲームを外そうと画策したからだった(この話はまだ確認が取れてないので、そういう話があったらしいくらいに考えておいてくれ)。ゲーム業界でもカルチュラル・エコノミック・ナショナリズムは起きるのだ。
この辺りの事情を理解していないマスコミが、表面的な現象だけを捉えて、嬉々として「世界の漫画・ゲームブームは終わった!」と記事を書いて煽ろうとする。日本のマスコミは本当にアホである。
日本だって例外ではない。日本のテレビ局はある時期から極端すぎるくらい韓国ドラマを盛り上げるようになった。これに反発するデモが2011年、フジテレビを前に起きた。これもカルチュラル・エコノミックナショナリズムだ。日本ですらこういう現象が起きるのに、日本以外の国ではこういったことが起きない……とどうして思えるのか。
なんの無策で「素晴らしいものですよ」とゴリ押しすれば売れるというものではない。外国文化が一斉に押し寄せて、その国に元々ある文化を押しのけようとするような動きがあったら、どんな国でも良い気はしない。そういうときは、どんな国でも「文化的侵略」と言いはじめる。フランスの場合、バンドデシネの作家達は猛烈に反撃してくる。おそらくほとんどの国で、そういう反応があるだろうというのは想像するけど、日本人だけはそんなふうに反発されることを想像できない(それぞれの国にも特有の文化とそれを支えるクリエイターがいる……という認識がない)。これも島国で閉じこもって過ごしてきたゆえの弊害だろう。いいコンテンツを作れば、いくらでも外国人が買ってくれるというわけではない。勢いが強すぎると、それは同じ勢いで反発になって返ってくることがある。これは心得ていていたほうが良い。コンテンツを売れば良い……だけではなく、「反発を生まないように」という注意は必要なのだ。
(またまた余談。日本は自国ような性文化、つまりエロ漫画文化が西洋やその他にないと思い込んでいる。そんなわけないでしょ。アメコミにもバンドデシネにもエロはある。しかもあちらの国には規制がないので、性器も結合部もばっちり描かれている。日本人がびっくりするようなエグいエロはいくらでもある。どうして欧米にはエロコンテンツがないんだ、という話を信じられるんだ? ところが海外の「有識者様」という連中は、日本を批判する時はそういう自国のエロ産業については一旦なかったようにとぼけて語る。それを真に受けた、頭の悪い日本のマスコミは「日本のエロ漫画文化は異常だ!」と紹介し、規制派が嬉々として活動をはじめる。どんな国でもエロコンテンツ文化・産業はある。日本人だけが、日本しかないんだと思い込んで、「世界に合わせよう」と言って自粛や規制をかけようとする。海外の文化人もプライドが高いから、相手国について語る時は自国に対するナショナリズムと相手に対する見下しを持って語る。そういう連中にとっては日本人は相変わらず「黄色い猿」という認識なんだから、そういう認識で語っている、という前提を持って聞かなければならない。なぜか日本人は、「西洋の人は知的で公平な見解を下してくれる」と思い込んでいるが、そんなことは絶対にない)
日本人は海外の事情を、日本と同じだとつい考えてしまう。どんな国でも「お国柄」というものがある。基盤となっている歴史というものが必ずある。
日本はかなり特殊で、戦争による断絶があるとはいえ、漫画文化がずっと子供達の間にあって、それがやがて大人の文化にまで波及していき、ここまで多様で奥深い漫画文化を育んでいった。同じような文化的な基盤は、日本以外のどの国にもない。かなりユニークなものだ。
海外の人は、日本人が大人でも漫画を読むことに不思議に思っている。そこまでの奥行き感のある漫画文化を作っているのは日本だけで、そういった事情を知らない海外の人から見ると、不思議と通り越して奇異に見えてしまうのだ。
すると海外の漫画事情も、日本とまるっきり違ってくる。漫画がどのように受容されていったのか、その経緯すら、国によって形が違う。
例えばアメリカは、広大な国ということもあって、それでも国民が読書ができるようにと定期購読がかなりお安く利用できるように制度が作られている。それでアメリカでは漫画雑誌は家に直接送られてきて、家で読む習慣がある。
対する日本は、学生や社会人が通学・通勤前のコンビニなんかで漫画雑誌を買い、電車内の空き時間に読んだりする。
日本の批評家様はこの辺りの文化的差異を知らず、「日本人は電車で漫画雑誌を読んでいる。おかしい! 欧米では誰も電車内で漫画なんて読まない!」なんて言う。漫画をどこで読むのか、ということすら習慣が違うんだから、当たり前だろという話だ。
日本人は海外の状況について、知らないことや勘違いしていることがあまりにも多い。よくわかっていないで、軽々しい言葉で「海外で日本のアニメ・漫画が大ブーム」なんて書いたりしている。こういった言葉だと、どの地域でどの程度の規模なのか、具体的数字や傾向がわからない。わからないで、大雑把な言葉で喜んでしまう。その波に乗ってコンテンツを売り出そうとして、なぜか売れない……「ブームは失速したのか!」みたいな繰り返しをやり続けている。いい加減、学習してもらいたいものだ。
どんな国でも事情や文化的基盤の差異というものはある。まずそこを知ることからはじめ、その次にどんなコンテンツが売れているのか、どんなコンテンツが受け入れられやすいのか、そういったことを慎重に考えてから海外戦略を練って欲しい。どうやら日本の企業は、「リサーチ」が大嫌いらしいから。漫画業界も、リサーチせず、闇雲に漫画雑誌をとりあえず出しては失敗するを繰り返している。そのたびに「失速した」とか言っている。リサーチが重要……という知識から身につけてほしいものだ。
関連記事
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
