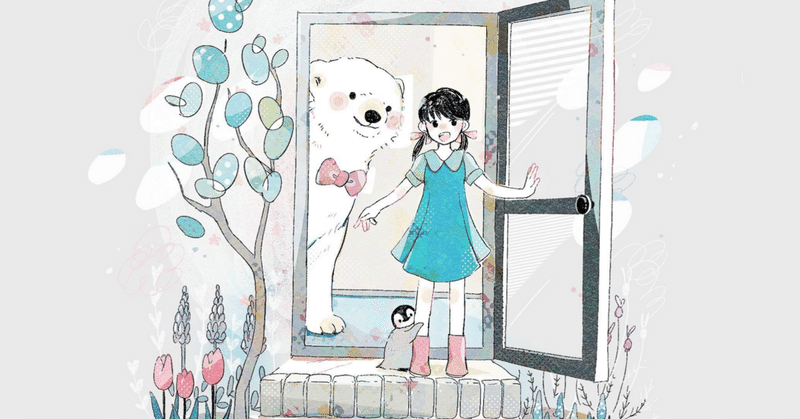
7つの習慣を簡単に復習|「終わりを思い描くことから始める」の実践
7つの習慣における「終わりを思い描くことから始める」
7つの習慣を読んだことがない人のためにも、少し復習をしたいと思います。簡単に概要を説明しますね。①②③で自分の成功を掴み、次のステップ④⑤⑥では皆での成功を目指します。⑦ではその習慣を回していきます。
①主体的である(=自らの価値観に沿って行動を選択する)
人は元来面倒を嫌う習性を持つ。だから、楽な道へ楽な道へと進もうとし、自分の責任を他の存在に預けるべく、より大きなものに包まれようとする。歴史上では、宗教的な権威や力を持った国家、経済的な基盤を作ってくれる企業に頼りきりでも良かったり、誰かが自分たちを管理・支配してくれることで「自由の刑に処されている人間」としての責任を自分は最低限背負うだけで良かったりという場合もあった。
最近のことを言うと、持続的に存続できる企業は少数で、会社の寿命は短い。長い間会社に人生を預けられる「終身雇用制度」も崩壊しつつある。だから、自分の人生を管理してくれる人はいない。だから、自分の人生を主体的に、自分自身で経営していく必要がある。そのためには、自らの価値観に沿って自分自身で方向性と行動を選択していくこと。
②終わりを思い描くことから始める(=人生を通じて何をしたいか・どのような人間でありたいか)
次の説明、「死と夢」で説明します。
③最優先事項を優先する(=自分にとって重要なことを優先する)
タスクを「重要性」と「緊急性」で分けたマトリクスを考えると、最優先事項は「重要性の高いもの」。直近で絶対に片付けなければいけないタスクを終わらせながら、一番時間をかけたいのは「人生を通じて何をしたいか」「どのような人間でありたいか」という重要なことを満たすもの。自分が人生のどの要素に対して価値を感じるのか、仕事・家族・恋愛・成長・遊び・健康・一人でいる時間など自分が何を求めているのか考え、行動に落とし込む。自分にとってのゴールは何か考え、その達成に向けて行動を起こす。
④win-winを考える(=お互いの利益になる結果を目指す)
マイナスサム(誰かが損をして誰かが得をする)ゲームはしないと決めること。協力・共同してプラスサム(全員が得をする)ゲームを作り出す。具体的に言うと、どちらかが敗北する議論をせず、何か新たな価値を生み出せるような建設的な話し合いをするなど。ヘーゲルの弁証法(アウフヘーベン)のイメージ。(テーゼにアンチテーゼをぶつけて第三の道を開く)
⑤まず理解し、そして理解される(=まずは自分から相手に興味を示し、それからお互いに相手に耳を傾け合う)
D・カーネギーの「人を動かす」における、相手の自己重要感を満たすための行動を徹底する。自分本位のコミュニケーションではなく、「相手に感謝を伝える」「励ましの言葉をかける」「相手に体を向けて関心を示しながら、相手のする話を最後まで熱心に聞く」「相手の名前や相手の話の内容を忘れないように記憶・記録しておく」「信頼している証に自己開示をする」などのアプローチをしていくこと。
⑥シナジーを作り出す(=1+1が3以上になるように相乗効果を発揮)
一人としてのパフォーマンスの最大化を追求するなら、誰かと協力する意味はない。お互いに自立・独立した存在として違う価値観を受け入れ、お互いの相対的な長所を活かしていく。そうすることで、個々の足し算を超える成果を望むことができる。
鈴木祐さんの著書から引用すると、「優位なかたより(全体最適を考えたときにそれぞれ担うべき強い役割)」をお互いに対しての理解を深めた上ですり合わせていくこと。
⑦刃を研ぐ(=人格を成長させるために上記の習慣を回し続ける)
7つの習慣の中では違う言葉で言われているんですが、いつも私がnoteで書いている言葉を使うと、「人的資本と社会資本、金融資本を育てること」。
人的資本に関して言うと、まずは自身の心身の健康を軸として、その土台の上に蓄積された次の2つの能力が資本として働く。対人力(コミュニケーションスキルや言語など)と対課題力(学習力や目標達成能力)。
社会資本は、自身の社会的な立ち位置や、現在の仕事をできる環境、周りの人とのつながりなど。金融資本は、現金を含む、交換価値を持つ資産のこと。(人的資本が最も重要だと考えているので、この2つを合わせて付随資本と呼んでいます。)
死と夢「自己啓発の目指すところは成功?」
死守するもの(最期の瞬間、今までの人生を振り返ってわりと良い人生だったと言える人生)
スティーブン・コヴィー氏の7つの習慣における第二の習慣「終わりを思い描くことから始める」では、人生を通じて何をしたいか・どのような人間でありたいかという部分に焦点を当てて考えます。
思い描くべき「終わり」というのは、「死」の瞬間に他なりません。自分の命が尽きるその時に、自分の人生を「〇〇な人生だった」と評価する。その理想のイメージを持つことが、「終わりを思い描くことから始める」ということなんです。
まずは自分の価値観を見直すことです。価値観というのは、それぞれの人で相対的に変わる「何の要素に対して価値を感じるか」という基準。例えば、自分が価値を認め大事だと思っている人生の構成要素は、「仕事・家族・恋愛・成長・遊び・健康・一人でいる時間」のうちのどれか?自分が大切だと思っているものの中で、最も優先順位を高くしたいものはなにか?を考えます。絶対に譲れないその要素だけは、死の瞬間まで文字通り「死守」し通す決意をします。
夢の実現=成功へのアプローチ
本を読んでいる中で、結構現実離れしたようなことを言っているものが多くて、たまに混乱してしまうことがあります。ただ、自分の性質上、せっかく学んだことをそのままにしておきたくないので、その混乱した知識をここに置いておかせてください。「何を言ってるんだ?理解不能だ。」っていう内容があるかもしれませんが、もし肌に合わなそうだったら一番最後のまとめのところに飛んじゃってください。ということで、ちょっと非科学的な「成功」を目指す方法について書いていきます。話がまとまっていないところも多いかと思いますが、温かい目で読んでくれたら嬉しいです。
夢について議論するとき、自己啓発系・スピリチュアル系の本で必ずと言っていいほど言及されるのは「引き寄せの法則」です。「夢を強く願えば波動が伝わって結果が引き寄せられる。はっきりとした願望や目標を持つことで思考は現実化する。」というような主張です。
論文などから得た知識をアウトプットして、生活に役立つ発信活動をしているメンタリストDAIGOさんは、このようなスピリチュアルな主張にかなり否定的です。科学的に検証されていないし、多くの文献の中で「明確な目標を持つこと」の効果が疑わしいという結果が示されているということだと思うんですが、「明確にしたせいで柔軟性がなく凝り固まった、ハードルの高い目標設定は効果が疑わしい」という主張なら、個人的にそれは「思考は現実化する」という話とそこまで衝突しないのではないかと考えています。
(ただし、「思い描くと勝手に夢が叶う」とか「100%、必ず願いは叶う」というような主張は苦しく、逆に「願わなければ99%叶わない」「最終的には行動ありきで目標達成を目指す」という立場だと思ってこの話を聞いてほしいと思います。)
メンタリストDAIGOさんが目標設定に関して大事だよと言っていたのは、「①視野が狭くならないように曖昧で柔軟な目標を立てること②ハードルが高すぎるかつ明確な目標を立ててしまうと、なかなか達成できずにやる気を保てず諦めてしまう。これを避けるべき」という2点。このポイントを覚えておいてください。
他方で、「成功」を目指すコーチングなどの分野では「現状と目標(夢)の大きなギャップが、ピンと張った輪ゴムのようにやる気や充実感を高めてくれる」ということを言っています。現状があって、高いゴールがある。山登りで言うなら、自分が今標高いくらの地点に居て、頂上は一体どこにあるのかということが分かっている状態です。このことで、「どこかに向かって突き進んでいる」という感覚を持つことが出来ます。言い換えると、やる気という方位磁針の針が目的地を指してくれている状態。
さらに、高いところを目指していれば目指しているほど、その夢のような景色を想像してワクワクするもの。少し視覚的に考えてみると、やる気や充実感は時間を横軸に取ったグラフにおける、下から右上に向かっていく関数の現時点で微分した(傾き)と言えます(図1)。夢を願うことで、憧れや理想像・目標を見上げて、充実感を感じながら行動することができるんです。シンプルに、普段の生活にハリが出てきます。「まだゴールに到達するための経験も知識も少ない」というように不足感が大きいことで、遠くを目指すワクワク感や楽しみが大きくなってきます。なれる根拠もないのに「海賊王に俺はなる!」と言っている感じです。

(傾きを可視化するために)現時点で微分すると?
棒ほど願って針ほど叶う
ゴール地点では、大体どんな空間が広がっていて、どんなことができるようになるのか。理想の自分を中心に置いたとき、ゴール達成によって周りの関係の深い要素はどう変化するのか(図2)。それに対して自分はどう思っているか。その感情をありありと臨場感を持って思い描くことが必要です。周りにはどんな人たちがいるか、ぼんやりとどんな感じの環境の中にいるのか、これらを思い描きます。これが「終わりを思い描くことから始める」の終わり、自分にとってのゴールです。

先程のメンタリストDAIGOさんとスピリチュアルの話の続きをすると、今言及したのは曖昧で柔軟な夢なので、明確で凝り固まった目標設定にはなっていませんよね。期間や数値目標を厳格に設定しているわけではありません。なので、両者の衝突は避けられる可能性があるのではないかと考えます。
個人的には、コーチングのような目標設定の仕方は、アドラー心理学が心理学というよりは個人の哲学とか思想と言った方が近いみたいな感じで、科学的に検証されてはいないけれど取り入れると役に立つ考え方だと思うんです。
それに、「棒ほど願って針ほど叶う」という言葉をご存知でしょうか。イメージした範囲でしか人は夢を叶えられないし、大抵の場合、100を目指したら80くらいまでしか行けないということです。一方、すぐ先に見えているような、達成できそうな目標(スモールゴール)であるならば、忘れないように何度も思い出したりする必要はありません。具体的にゴールを設定し、「困難は分割せよ」に則って、多段階の小さな目標を中継点として挟みながら、突き進んでいくだけです。目標達成のために何をすればよいかタスクを洗い出してメモ帳に書き、一つ一つ片付けていけばいいだけ。確実に目的地に到達できます。
しかしながら、現状の延長線上では考えられないくらい、実現の困難な大きな夢だったら話は別です。まずはやる気が持ちません。長期的なモチベーションを保つためには、強い願いが必要です。道のりが遠すぎて、普通はモチベーションが保てない。そして、得るものが大きい代わりに失うものが多すぎて絶望してしまいます。
今持っているもの、人間関係や居場所、役割を失ってしまう可能性も考えなければなりません。先程の、自分のゴール達成に伴って変化する周辺の要素を見ればわかるように、自分が変われば、周りのものも一緒に変わっていきます。失うものは大きい。だから、別に夢を持ったほうが良いわけではありません。大きなゴールがなくても、日々何か小さな目標を達成しながら生活することでとても楽しい日常を過ごすことが出来ます。
でも、本気で人生を180度変えたいなら、強硬策を取らなければいけないことを覚悟しておいてください。条件は、社会資本のリセットです。自分が今持っている人間関係を失う。今やっている仕事を失う。今住んでいる環境を失う。そのようにして、自分が心地よいと感じる「慣れ親しんだコンフォートゾーン」から抜け出し、上へ上へと強制的に引っ張り上げる必要があります。猛烈な努力と苦痛・内外の精神的な抵抗が必ず伴います。不安になったり、心配が尽きなかったりするでしょう。
そして、周りの人たちは、今の居心地のいい空間・環境が変わってしまうかもしれないことへの抵抗で、反対してきたり離れて行ってしまったりもするかもしれません。急に遠くへ行こうとするんですから、そうなってしまいます。
色々と述べてきましたが、叶えたい大きな目標があるならば、「終わりを思い描くことから始める」べきということです。結局、成功への過程は、地道な行動の積み重ね、習慣の形成によってスモールゴールを達成していくしか無いんですが、その前段階で、必ず思い描くことが必要なんです。そうしなければ夢は針ほども叶いませんから。
やる気は「目標にワクワク」していること
度々記事の中で、「やる気」「モチベーション」なんてものは湧くのを待っていたら日が暮れるから、とにかく手を付けること。とにかく最初に、数分でも良いからタスクを始めてみると、行動に一貫性が働いて「始めたあとからやる気が湧いてくる」。だから、「やる気があったらやる、やる気がないからやらない」なんていう基準は絶対に持たない方がいいという話をするんですけれども、内発的動機づけ(やる気)の話はあまりピンとこないという人向けに少し違う観点からの説明をしたいと思います。
「到達したい地点を忘れないで思い出し続ける」ことで、たとえダラダラであっても「とりあえず続けていられる」ということが、成功を掴むためには大事になってきます。
例として株式投資を考えてみてください。S社の株は、去年と今年の間で150%株価が上がりました。でも、その株価は2/10から2/18の間だけで一気に100%ほど上がっていた。ということは、一年の中でその一週間の間だけは絶対に相場に居座っていないと利益が取れなかったということです。これが、長期投資の利点の一つです。
つまり、チャンス(機会)が訪れるのはとても短い期間であるけれども、そのチャンスがいつ訪れるのかは予測はできないので、ダラダラでもいいから継続して取り組んでいないとチャンスを掴むことができないということです。このために、夢を思い描いて忘れないようにリマインドし続けるということが大事になってきます。
夢を思い描き、忘れないようにすることで、現状よりも夢の臨場感の方が高くなる。そして、「自分が重要だと思っていて意識が向いている情報しか見えない」というスコトーマの原理(またはカラーバス効果・カクテルパーティー効果)により、望む達成のために必要な情報を集めるアンテナが立ち、将来のゴールに近づいて行ける。チャンス(機会)を掴むための行動に役立つ情報が入ってきやすくなる。
補足程度で、こんな説明もあるんだということを知っておいてください。とりあえず、「叶えたい夢がある、もしくは大きく変えたい現状があるなら、ゴールを思い描いて現状との綱引きでゴールの臨場感が負けてしまわないようにする。」というのが重要です。
コンフォートゾーンをずらす/違う環境に飛び込む
ここまで色々なことを言ってきたんですけれども、結局はコンフォートゾーン(心地よく感じる環境)のことを言いたいだけなんです。
現状を大きく変えたいなら、「強く夢を願うことでコンフォートゾーンを上に引き上げて、現状にとどまっている現状を気持ち悪く感じるようにしてしまう。結果的に目標達成のための決断・行動をすることになる。」もしくは「居心地の良い空間を抜けて、違う環境に飛び込んで適応する。そこは新たなコンフォートゾーンとなる。」(例えば、人生を最速で変えるためには住む場所を変えるか人間関係を総入れ替えする。価値観を広げたいなら海外へ行ってみたり、一人旅をしてみたりする。みたいな感じで)
補足:WOOPとPDCAは共通項「Plan」で繋がる
夢を思い描いたなら、あとはWOOPとPDCAを意識的に回していくといいかもしれません。ここまで何をしてきたかというと、単純にWOOPの中のWish(願望・夢・目標 = 内側からの気持ち)を考えてきただけなんです。
それに合わせて、Outcome(願望が実現した際の具体的な効果)・Obstacle(成果達成への障壁となる具体的な問題)・Plan(問題を解決するための計画)・Ꭰo(実行)・Check(検証)・Action(改善)を積み重ねていければ夢実現は見えてきます。
簡単に言うと、ゴールはどこに行きたいのか、そこで何を得たいのか考える。現状でゴールに届きそうならやるべきことを洗い出して実行し、改善していく。現状でゴールに届かなそうなら、何の問題が障壁となっていて、それに対してどんなアプローチをすれば解決できるのか考える。その障壁を取り除くことができたら、やるべきことを洗い出して実行し、改善していく。というサイクルを回していくと成果が出やすいと考えられます。
また、さらに成果を上げるためのポイントとして、現実的に達成可能な目標であれば「明確で具体的な目標を定め、逆算してプロセス・行動を実行する」ということを意識しましょう。例えば、20キロ痩せたいなら、まずは3キロ痩せることを明確な目標とし、確実にスモールゴールを達成していくこと。食事を減らし、運動を増やすプロセスを明確化し行動に移します。
やる気は「自分はできる」という自己効力感
先程、やる気・モチベーションの話をしましたよね。少し違う見方をしてみると、やる気は「自分がタスクをこなせている」「自分の能力は通用している」という自己効力感から湧いてくると言うこともできると思います。
また、課題をこなしていくことで、「前に進んでいる」「自分は成長してる」といった前進している感覚を感じることができます。言い換えると、毎日工夫・改善をして少しずつ上手くいくようになっている感覚です。このように、自己効力感や前進している感覚がモチベーションとなるんです。前に進んでいる感覚を感じられると、「自分ならできる」「自分ならやり遂げられる」という自信がついて、やる気が湧いてきます。
だから、絶対に達成できる目標(スモールゴール)が大事になってくる。小さな勝利(成功)を繰り返していくことで、継続して頑張ることができるからです。今日はこれだけできるようになろう、今日はこれだけ達成しようというスモールゴールを設定して、小さな達成感を毎日感じられるようにするんです。今日は漢字を10個だけ覚えようみたいな感じで。
もっと身近な話をしてみると、「部屋を片付ける」ってかなり気が重いですよね。だから、例えば「今日は本棚だけ整理してみよう」「今日はファイルに入ってる書類を断捨離するぞ」というようなスモールゴールを設定してみる。このように、かなりの確率で達成することができ、片付けることのできる小さな目標を意識的に立てていくことで、日々自分が能力を発揮している感覚を得ることができるんです。
これをアクションプランに落とし込んでみると、一日の初めに、今日取り組みたいタスクを一通り書き出してみる。そして、タスクを片付けることができた段階でメモ帳の中で消していくようにする。このように記録していくことで、自分が終わらせられた仕事を可視化できるので、毎日のモチベーションや充実感が桁違いに変わってきます。見返すことで、自身の目指している場所やしなければいけないことをリマインドできる効果もあります。
総括(本論が上手くまとまらなかったので、見るのはここだけでもOKです!)
7つの習慣は多くの成功者がバイブルとして掲げている本なので、第一から第七の習慣をぜひ参考にしてみてください。それを土台として、特に「終わりを思い描くことから始める」に言及して、大事だと思うことを述べたいと思います。
まず1ステップ目として、死を迎えるときに「いろんなことがあったけど、振り返ってみるとわりと良い人生だったなあ」と思える人生はどんな人生か?を思い描きます。これが7つの習慣の「終わりを思い描くことから始める」ということ。生活の中で最も重要視しているもの、最優先事項だけは死の瞬間まで必ず「死守」します。次はフローチャートにしてみました。
"大きな成果を上げたい" or "夢がある" か?
YES
→ 将来夢(現状の延長線上に無い大きなゴール)を叶えたことでできるようになることを思い描き、忘れないようにリマインドし続けます。棒ほど願って針ほど叶うなので、苦労の末にそれなりの成果を上げることができるでしょう。そして、困難は分割せよ。夢までの中継地点となるスモールゴールを設定しながら、着実にタスクをこなしていって最終的にはゴールに到達することを目指します。
"大きな成果を上げたい" or "夢がある" か?
NO
→ 毎日を楽しく過ごしながら(自分でも達成できるような)スモールゴールを達成し続けます。毎日こなすタスクを何個かメモ帳に書いて、達成できたら消してあげましょう。こうすることで、達成感と充実感を感じながら生活できます。
ここまでの文章の中で、なにか一つでも参考にできそうなものがあれば、ぜひ行動に移してみてください!まとまりの無い文章だったかと思いますが、ここまで読んで頂き、本当にありがとうございました!☺
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
