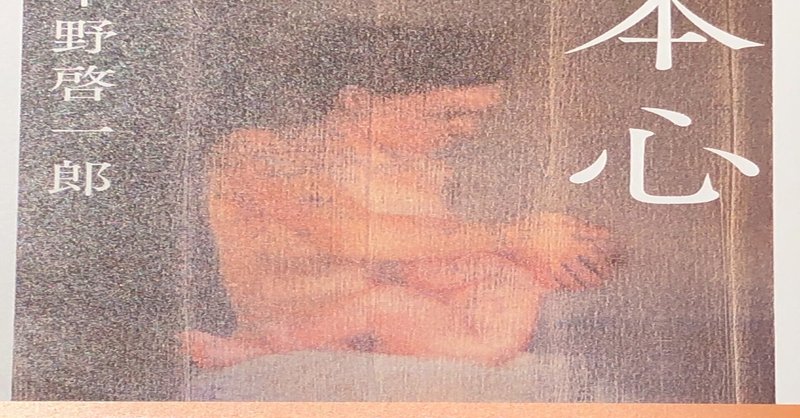
本心 精神の還元
「本心」
著者 平野啓一郎
出版 文藝春秋(2021/05/26)
はじめに
「本心」を読むきっかけは、2021年5月、4回に渡り放映された、NHK「100分de名著シリーズ 金閣寺」である。番組の解説担当:作家 平野啓一郎を僕は名前しか知らなかった。しかし、彼の真摯な三島由紀夫愛がどことなく熱を持って伝わってきて、彼の新作に興味が湧いたのである。※1
こうして、今回の作品で初めて平野啓一郎の小説を読んだ。
素直に、僕が著者の主義主張を受け入れられるかどうかに関係なく、「今」を生きている作家たちで、日本国内に、まだ熱をもって社会への問いかけを物語る人々がいるのが嬉しい。
ちょうど、僕はマルクスガブリエルのいくつかの新書(世界はなぜ存在しないのか、私は脳ではない、新実存主義)を読み終えたり、大好きなカミュの異邦人の感想をアウトプットした後でもあった。
そのため、僕は気づくと本書を読む際、本書を知るきっかけとなった三島由紀夫よりも、ガブリエルのテーマ:人の心、精神は、短絡的に脳へと還元できないものであり、それならば、どこに存在するのか?存在とは何か?という事柄や、カミュの不条理といったテーマを共通点として意識して読んでいた。
以降、少々ネタバレを含む長い文章が続くので、ここで感想の結論を書いておく。
国内でも社会問題に目を向けて疑問を投げかけてくる作品であった。
それと同時に、人の心やアイデンティティのしなやかな生きるというベクトルは前へと向かいつづけると著者が訴えている点には共感を覚えた。
結末に対して、やや寸詰まり感を僕は覚えたが、それでもポジティブで楽観的な思想を根底に感じとり、有意義な読書となった。
※本書のテーマは多岐にわたっており、細かく感想をきちんと書くならば、いくつか記事を分けるべきかもしれない。今回は一読後の所感で書いているためその辺りはお許し願いたい。
※ここで断っておくが、僕は実存主義でも新実存主義者ではない。僕がサルトルに傾倒しているとしてもだ。ひとつの〇〇主義といったレッテルを張られたくない。それと同時に、マルクスガブリエル信者でもないということだ。
分人主義に関して
著者は分人主義を提唱しているようだ。それについては著者による著作物があるのでそちらを参照したほうがよい。
私とは何か 「個人」から「分人」へ (講談社現代新書)
たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて「本当の自分」である。
(私とは何か――「個人」から「分人」へ 講談社現代新書)
僕は、この本の分人主義テーマを、「他者のまなざしを通した<私>の在り方の変化とその精神の還元」として置き換えて、本書を読んでいる。※2
注意:以下からネタばれになり得る文章や考察もあるためこれから読む方はとばしてください。
あらすじ
舞台は、2040年の近未来の日本。
母子家庭で生まれ育った29歳の主人公、石川朔也。
たった一人の肉親である母親を事故で亡くし、母親の面影=生前の母をパターン認識させたAI搭載のVRの中での<母>と向き合い始める。
向き合いの中で、朔也視点での母だけではなく、他者視点での母の側面や他者視点での自分自身の人格の評価が、朔也視点のそれらとは異なるものであることを知ったり体験してゆく。
この「他者が介在する」精神との向き合いを通じて、朔也は母の精神が朔也自身に還元されているのを他者によって知らしめされる。
こうした過程を経て、朔也が自立し社会に主体性を持って関わろうとしていくまでを描いた作品となっている。
「本心」のテーマ
人間の生への問いかけ=死生観
自由への問いかけ=主体性、倫理観
現代社会が掲げる問題=超少子高齢化社会、日本の国力低下
戦後教育
愛
精神の他者性
など、実に多岐にわたる重いテーマが散りばめられている。
こうした重いテーマを主人公、石川朔也の一人称視点で投げかけ、語り、時には熱量を持って他者に語らせている。
また、語らせる際にどことなく、三島由紀夫が差し込まれている気がしなくもなかった。(これは著者が解説者を担当していたNHKの番組を最近見ていたせいで、僕の単なる気のせいかもしれない)
またキーワードとして以下が挙げられる。
著者から提示されたキーワード
他者性
母
心
自由
言葉
生と死
死の一瞬前
もう十分(ポジティブでもありネガティブでもある両局面)
役に立つ/立たない
経済格差
教育格差
僕の本書を読みながら念頭に置いたキーワード
心を包摂する心的語彙としての精神
死者の精神
関心
傍観者
死生観
自由
経済格差
教育
実存
登場人物
石川 朔也
29歳 この物語の主人公 リアルアバターという職業に就いている。
母 石川朔也の実母 旅館の従業員 自由死を目前に事故死する
<母> AIによって再現された朔也の実母のヴァーチャルフィギュア(VF)
野崎 VFの営業担当者
三好 彩花 年齢不詳 母と親交の深かった母の同僚
岸谷 朔也の同僚
ティリ 朔也がメロン事件の一件で助けたコンビニの女子店員。在日ミャンマー2世。
イフィー 下半身不随の車いすの青年
藤原亮治 母が生前、ファンだった作家であり、母と親交があった。カラマーゾフの兄弟のゾシマ的スタンス
吉川先生 <母>が介護する自由死を希望する老人ホームの文学好きな老人
本心とは
本書で著者は「本心」というが、僕は、これを「人間の心を含む精神」の一部と考える。心は状況/時間に応じて変化する。ガブリエルが自然主義を批判するように、僕は、脳に心は還元するものではなく、脳は心の必要条件にすぎないと僕は考えている。
そして心の変化をベクトルの方向に例えるならば、そのベクトルは他者との関係性や経済/年齢あらゆるものを含めて作用され、方向はある程度一定かもしれないが、僕は、ゆらぎのあるものだと考えている。(心のみならずアイデンティティもそうだ)
では、本書でいうところの精神とはいったいどういうものなのだろうか?
精神とは
プロローグを読みながら、ふと懐かしいキルケゴールの序文を思い出した。
「人間は精神である。しかし、精神とは何であるか? 精神とは自己である。しかし、自己とは何であるか? 自己とは、ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である。あるいは、その関係において、その関係がそれ自身に関係するということ、そのことである。自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係するということなのである。人間は無限性と有限性との、時間的なものと永遠なものとの、自由と必然との綜合、要するに、ひとつの綜合である。綜合というのは、二つのもののあいだの関係である。このように考えたのでは、人間はまだ自己ではない」
—『死にいたる病 (ちくま学芸文庫)』セーレン・キルケゴール著
キルケゴールの言う「死にいたる病」とは絶望であるが、絶望するからこそ人間であり、そこには精神がある。人間=精神であり、人間とは自己として他者に認められるものだ。と、僕は解釈している。
さらにその先にサルトルの言葉が脳裏によぎる。僕は、サルトルの言う通り「実存は本質に先立つ」からこそ他者と主体性を持って積極的に、そして、己の主義主張に責任を持って社会と関わりながら、自分自身を作り上げ、希望を持って前へ進むべきだと考えている。
ヤスパースはこう言う。
「過去というものは、人間がいかなる態度をとるべきかを教える力がない。そのことは、人間が自分の回想する過去の光の中で覚醒し、自分自身で決断しなければならないことを意味する。」
「希望喪失はすでに敗北の先取りである。人間にできることがなお残されている限り、希望を失うことは許されない。」
僕は、生と死は連続性を持っており、他者の精神活動の中で、肉体が土へ返っても、精神は生き続けると考えている。
そして、自己の中での死者の精神たちは、時には前進する出発地点や、分岐点で背中を押してくれることもある。
そうやって誰かの心は他者の心に再構築されその精神に干渉しながら縁起し世界=無へ戻る。
本書の感覚的に伝えてくる精神とは、そのようなものを指し示しているように思えて共感した。
自由とは
また、自分自身の周りで起こっているあらゆる事に無関心でいてはいけない。
傍観者的であることは、真の自由ではないのだと考えている。そして、自由とは自ら自立し社会と穏やかに干渉しながら勝ち取れるものであり、意思を前へ向けて表明し行動することだと考えている。そして不条理に意志をもって自己欺瞞に陥ることなく主体的に抗うことも自由とも定義できる。
こうした僕のスタンスでは、生を全うせよというのが信念であるから、「死ぬべきか、死なないべきか」(「本心」平野啓一郎 p338)という「べき」=shouldという言い回しに対して非常に敏感になる。
それは方向性としても「言ってはならぬ」というのが僕の信念だ。
だから、自由死(安楽死含めて)という他者が意図的に介在する死を僕には受け入れがたいものがあった。
戦前戦後の死生観や教育
「死ぬべきか、死なないべきか」は主人公の死生観の希薄さからくるのかもしれない。
本書で戦争体験を聞いた平和活動家60代の男性VFが登場する。
手榴弾で自爆する戦友たちが、決して「天皇陛下万歳!」とは言わず、「お母さーん!」と絶叫しながら死んでいったという証言
中略
教育された通りに、「天皇陛下万歳」と言って死んだ人もいただろうが、”死の一瞬前”にどうしても、日本兵の自分ではなく、母親と一緒の時の自分に戻りたかった人もいたに違いない。
「本心」平野啓一郎 p226-227
本書では「違いない」としているが、僕の曽祖父は最前線でそうした光景を見てきたから、そうなのだ。と断言できる。
戦時下を生き抜いて、中国から日本へ帰ってきた曽祖父が僕ら家族に話してくれた話を例に出す。
「突撃のラッパと同時に敵の顔が判るくらいの距離から、皆「ワー」と叫び、突撃して行く。
躊躇すると後ろに控えている上官に銃殺される。
突撃前後、大部分は「天皇万歳」と叫んで銃身の下にサーベルを装着し、銃を構えて走っていく。
敵からの機関銃や手榴弾の中、隣の友が倒れると、死の間際、胸の裏に家族の写真を持っているものが多く、その写真を見て、家族によろしく頼みます、か、お母さんによろしく頼みますと言っていた。
そうした中、指を4本飛ばされて、腹を撃ち抜かれても、
「日本に残した家族の元に、絶対に生きて帰る」
と決意し、日本へ帰ってきた。
だから、何があっても、生き抜くんだよ」
と、祖父や父に時々語っていた。
天皇万歳や敵を目の前にしても躊躇するなといった全体主義的な教育がされていても、死の一瞬前では家族や母を思うのだ。そうした戦時下の最前線を「生き抜いて」日本へ戻ってきた彼らの表立って言わない「生への讃歌」。それは戦争に負けた絶望から這い上がる我々日本人の精神の原動力ともなったといえよう。
話がだいぶ逸れたが、僕は曽祖父の生き抜くという信念の強さを幸運にも聞いて知っている。それは曽祖父らの精神のほんの一部かもしれないが、僕の中に還元され、僅かながらに宿っている。
しかし現代の教育ではこうしたことをどう教えているのだろうか?
何故、教育で歴史的事実と生き抜くことを教えないのか。
算数よりも大事なことだ。
最愛の人だけでなく、こうした忘れてはならない歴史を背景にもつ(日本人だけではなく)人々の精神もまた、還元されてゆくべきだろう。
格差の拡がった超少子高齢化社会像
主人公朔也は母子家庭で生まれ経済的に決して楽だとは言えない状況で育った。
彩花もおそらく育成環境の経済面は楽ではなかったであろうと推測できる。
一方、体は不自由であっても富裕層のイフィー。
まるでチグハグなこの三者で決定的なのは心を表現して相手に伝える手段でも出てくるところだ。
イフィーはお金で感謝を伝える。
そして、コンビニ店員の女の子ティリ。
ティリは在日ミャンマー人2世だ。
日本語もミャンマー語も不自由な彼女もお金で感謝を伝える。
最大の格差を見せつけられるのは、忖度して「自由死」を「もう十分」と言って選んだ「かもしれない」母だ。
経済・資本が神であり、民主主義が絶対とされる現代から20年後の姿の一コマを垣間見るようでもある。
そこには物質的なものが優先され一見豊かそうに見えていた過去の(2020年代)ハリボテがはがされた結果、経済においても精神においても貧困が拡がっているだけのようにも見える。
エマニュエルトッドらが「自由の限界」(鶴原 徹也 中公新書ラクレ 715)で述べているように、超高齢化すると、すべてが硬直化してしまう。その前に、日本はもっと移民に対して、彼らが根付いて、2世、3世と住んでもらえるよう、そして格差なきよう政策を打ち出すべきではないかとも思った。そうすることが、この少子高齢化社会を打破することにもなりうる。
藤原=優しさとゾシマと三島
物語のなかで登場する藤原が、どことなく三島由紀夫がこちらを向いて穏やかに語っているのを、僕は想像した。
母との思い出の中で登場する三島由紀夫の短編の一片
これほど透明な硝子もその切口は青いからには、君の澄んだ双の瞳も、幾多の恋を蔵すことができよう、
「花ざかりの森・憂国ー詩を書く少年ー」三島由紀夫 新潮社p126
母と藤原、彩花とイフィー、彩花と朔也の純粋な愛情をどことなく彷彿させる。
「”心の持ちよう主義”というのは、僕が自分で言ったことじゃないんです。僕への批判ですが、僕自身は、さすがにもう少し複雑なことを書いてきたつもりです。
中略
何度も戦って傷つき、『もう十分』という人もいますね。僕の文学は、もし、そういう人たちのための、ささやかなものだったと見做されるならば、それは喜びです。」
「本心」平野啓一郎 p411
僕は、あなたのお母さんとの関係を通じて、小説家として、自分は優しくなるべきだと、本心から思ったんです。
「本心」平野啓一郎 p412
これは著者から読者へのメッセージなのかもしれない。
分人主義、〇〇主義というのはどうでもよいのだ。文学のみならず、芸術は誰かの心の糧になりうる。それはとても賛同できる。
「最愛の人の他者性と向き合うあなたの人間としての誠実さを、僕は信じます。」
「本心」平野啓一郎 p417
これを読んだとき、僕は、三島由紀夫と東大全共闘の映像を思い出した。
画面の中で、はっきりと三島はこう言っていた。
「私は諸君らの熱情これだけは信じます」
三島由紀夫vs東大全共闘
時代が変わっても人の精神に揺さぶりをかけるものはたしかに、熱情、敬意、言葉だ。
そして平野啓一郎の熱量のある言葉に僕は何かしら考えこうして長文を書いている。
こうした精神と人間の生への讃歌をテーマにした小説を読むと、いつもカラマーゾフの兄弟を思い出す。
一粒の麦が地に落ちて死ななければ、
それはただ一粒のままである。
しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる
(ヨハネによる福音書 第十二章)
これに対しては病床にてゾシマが明確にアリョーシャへ答えている。
「人生はお前に数多くの不幸をもたらすけれど、お前はその不幸によって幸福になり、人生を祝福し、ほかの人々にも祝福させるようになるのだ。
これが何より大切な事だ。」
「カラマーゾフの兄弟」第二部ドストエフスキー
僕は文学、そして精神とはこのゾシマのいうように生を讃歌しながら他者へと還元していくと考えている。
おわりに
朔也は、亡き母のコピーを再現し<母>を通して過去にフォーカスしながら生きようとしたともいえる。しかし、最後には、最愛の人の他者性と真摯に向き合うことによって、あることを悟る。
朔也の言葉に触れた最愛の人の内なる心の反応こそ求めているものだったのだと。
そして、希望と夢を胸に前へ進む。
社会と主体性を持って身を投じる決意ともいえる。
この決意は、「嘔吐」サルトルの中で登場する主人公ロカンタンともどことなく似ている。ブーヴィルの街を決意し旅立ち、自身を作る。物語の中では100%の理想でいられるが、自分自身の在り方を作る。
生きる希望、夢、光の当らない中でも強くあれ。 小説には終わりがあるが、人生には終わりはない。 誰かの記憶、精神の中で、人の精神は、時には希望の灯の出発点として、生き続ける。 そして、他者を通して自分の在り方をもがきながらも主体性をもって作り上げていくのが人生だろう。
「本心」を読んでいてそう思った。
僕が朔也へ贈るのはお金ではなく吾一が黒崎からもらった言葉。
艱難汝を玉とす
「路傍の石」山本有三
苦労しながら汗水垂らしてみっともなくとも不条理に抵抗しながら生き抜く人々にしか見えない世界もある。そして、そうした人々は死ぬべきか死なないべきかなどと言わないだろう。
朔也らが、希望の中で、その世界を自分自身の目で見れることを願う。
※1
僕は三島由紀夫はエキセントリックスーパースターだとは思うがそこまで好きではない。なぜなら自ら命を絶つことに関して僕は極めて批判的なスタンスだ。僕はカトリックを信仰しており、こうした事には信仰をベースと少なからずともする。
※2
僕は分人主義に関しては賛同できる部分もあるが懐疑的でもある。
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
