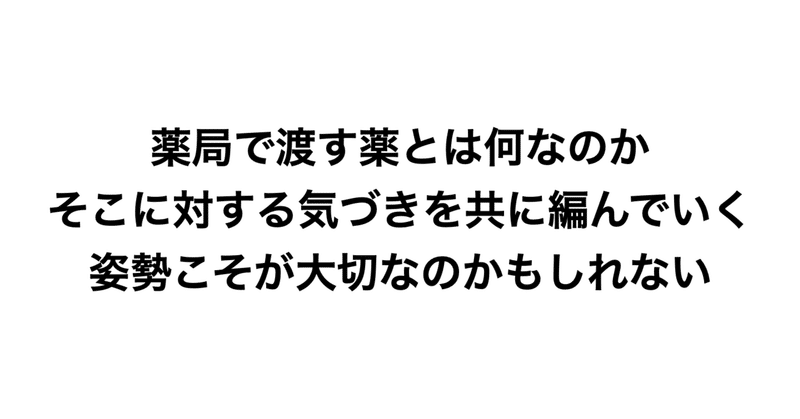
『世界は贈与でできている』を読んでは独り言・其の二
薬局の現場で薬剤師が患者さんに
渡しているものは薬なのだろうか
もちろん薬は渡している
何をそんな当たり前のことを?
と訝しげに思われる方もいるかもしれない
患者さんの立場からしたら
薬局の窓口で支払う金額は
薬の代金だと
薬のみの代金だと
思うかもしれない
そんなことはないのだ
純粋な薬の金額だけではなく
保険調剤の中での
あれやこれやの点数が入っている
それを知り少しでも
薬局での支払いを少なくしたいと
思う方がいる
その気持ちはわかるが
果たしてそれは可能なのか
そんな風にも思ってしまう
結論から言うと
それは無理なのだろう
それはもはや
単なる交換に過ぎず
それはもはや
何も会話するな
と言っているに等しい
薬の自動販売機があったとして
それで薬を買うようなものだ
人を一切介さない
そんなことができれば
いいのだろうか?
おそらく
そんなことを
望んでいるわけでは
ないのだろう
街のあちこちにある
自動販売機にだって
人が飲料を補充している
それに気付けば
一本の飲み物を買う際にも
人のありがたみを感じることができる
物の裏側は得手して見え難いものだ
いや見え難いように
してしまっているのかもしれない
そこに気づくことができないほど
余裕もないのかもしれない
色々な可能性はあるだろう
そんなことを思い浮かべては
今日もまた
読んだんだか読んでいないんだか
積んだんだか積んでいないんだか
といった本達の中から一冊紹介し
心の琴線に触れた一節を取り上げ
ゆるりと書き記していきたい
今回はこちらの本を読んでは独り言
この本を取り上げるのも二度目である
著者の新刊『利他・ケア・傷の倫理学』
既に購入済であるが
まだ読まずに積んでいる
読み始める前に
前作である本書を
再読してから読もうと
自分の中で決めているのだ
読み返す中で
内容をほとんど覚えていないことに気付く
それも本書のメッセージと言ってもいいほど
重要な部分を忘れているのだ
そんな自分に嫌気がさしつつ
いつものように
引用する必要があるんだかないんだか
本来の意義を考えては
自己ツッコミを入れつつ
noteの引用機能を用いて
引用させていただきたい
先ほど、僕は、この映画は贈与の失敗の物語だと述べました。
これまでの議論を通して、もう少し正確な言い方が可能になりました。
贈与の物語でなかったのなら、「ペイ・フォワード」は一体何の物語だったのか。
それは供犠(sacrifice)の物語だったのです。
トレバーは自分の命を犠牲にし、捧げることによって、この世界に良きものを代わりに与えた。そういう物語だったのです。
残念ながら、これは贈与ではありません。供犠という形式の「交換」です。
被贈与という「元手」を持たないトレバーは未来(つまり自分の命)と引き換えに、他者へと善意のパスを渡したのです。
裏を返すと、聖人ならぬ俗人の僕らには、受け取った贈与に気づき、その負い目を引き受け、その負い目に衝き動かされて、また別の人へと返礼としての贈与をつなぐことしかできないのです。
つまり、被贈与の気づきこそがすべての始まりなのです。贈与の流れに参入するにはそれしかありません。
薬を渡す行為が
贈与であるとか
そんなことが言いたくて
引用させていただいたわけではない
気づきについて語りたくて
この箇所を引用させていただいた
何気なくアクセスできる日本の医療
だからこそ
患者さんは交換の論理で
医療に対して考えてしまう
私が思うに
医療は交換の論理で語るには
語り得ないものがあるのだ
だとすると
それは贈与の流れなのだろうか
それもまた違う気がするが
どちらにせよ
医療従事者側にも
患者さん側にも
気づきを出発点として
共に医療の糸を編んでいく必要があるのは
間違えないのではなかろうか
そんなことを考える私は
変人なのかもしれないが
どうしても考えてしまうのだった
こんなポンコツな私ですが、もしよろしければサポートいただけると至極感激でございます😊 今後、さまざまなコンテンツを発信していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします🥺
