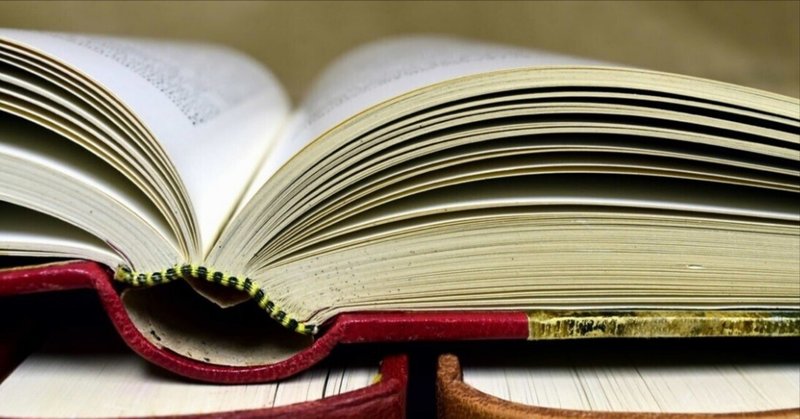
『海がきこえる』氷室冴子著(徳間書店):図書館司書の読書随想
この本は、今まで何度読み返したことか。爽やかな青春を追体験でき、読了したそばから、また再読できる日を心待ちにするほど好きな本だ。
はじめて読んだのは、私が高校三年の時。物語は主人公が大学に進学し、それからの一年と高校二年の時に転校して来たヒロインとの関わり合いを思い出す形で進んでいくので、まさに自分と同年代の話と言えた。
ただ、私が通っていた学校は男子校だったので、同じクラスに女子がいるという状況は、乏しい知識と旺盛な想像力で補うしかなかった。
きっといいものなんだろうな、と思いつつ。
高知で暮らしていた主人公が大学進学と共に上京し、東京の街でヒロインと再会して、すったもんだがありながら小さな恋を育んでいくという筋書きは、受験生だった私にとって極め付きと言えるほどの勉強へのモチベーションとなった。
繰り返しになるけれど、男子校出身なので大学で誰かと再会しても、それは男であるのだけれど。
だから、空想の女子との再会という空しくも哀しい想像でモチベーションを維持していた。
では、そのモチベーションを以て勢いよく入学した大学で(浪人したけれど)、私が物語のような青春を遅れたかというと、下を向いた沈黙するしかない。
文学部へ進んだので、確かに女子は多かった。けれど、それだけだ。
特別仲良くなれた女性というのは、いなかった。
とはいえ、少し、ほんの少しだけ仲が深まった女性が一人いる。
そして、彼女との関りにおいて、この小説にまつわる思い出があるのだ。
『海がきこえる』には、印象的なシーンがいくつもちりばめられており、「ああ、青春だなぁ」と甘酸っぱい気持ちが湧いてくるのだけれど、際立って私の胸に残っているのは、高校三年生の時に主人公と傷心のヒロインがホテルで一夜を共にする場面だ。
健全な男子高生、心が弱った女子高生、ホテル、夜といった道具立てが揃っているのだ。並みの作家ならば、生々しい性描写、あるいはそこはかとない仄めかしの後で朝を迎えさせるだろう。
けれど、この著者はそのような安易な道には流れない。
ヒロインをなだめた主人公は、彼女にベッドを譲ると、自分は毛布を持って規格外に大きな浴槽の底で寝ることにしたのだ。
ここで私の話に戻る。
私が大学四年生の時、微細ながら仲良くなった同級生の女性と喫茶店で話し、その後夕食を共にし、更に場所を変え、友人に教えられたバーで飲んだのだけれど、波長が合うらしくいつまでも話題が尽きなかった。
時計を見ると、十時近くになっていた。
「まだまだ話したいけど、時間大丈夫?」
彼女は、夜遊びをするタイプには見えず、門限が設定されていたら都合が悪いのではないかと、そう尋ねてみた。
「うん。うちは両親が離婚して、母は実家に帰っちゃったし、父はよく外泊するから自由なの」
彼女はそのように答えた。私が、「そうなんだ」と応じた後、この家庭の内輪話をきっかけに、会話はより親密さを増したものになっていった。
彼女の複雑な家庭環境、それによるのか独特な人生観、価値観、交遊観などを聞いているうちに、夜は深まり終電が近くなってきた。
恋愛経験も女性経験もない私は、このまま電車がなくなってしまったらどうなるのだろう、ホテルに泊まることになるのだろうか、だとしたらどういうことになるのか。
よからぬこと、けしからぬことが頭の中を巡り、会話が疎かになってきた。
そこで彼女も夜が遅いのに気付き、「そろそろ帰ろうか」と口にした。
それを聞いてうぶだった私は、残念と思うよりむしろほっとした。
バーを出て駅まで歩いて行く途中、「もし電車が止まっていて、二人とも帰れなかったらどうする?」と訊いてみた。
特に何か企みがあったわけでなく、単なる興味本位の質問だ。
「その時は、ビジネスホテルに泊まればいいのよ」
彼女がそう答えたので、随分大胆なことを言うな、と内心驚いていた。
けれど、話はそこで終わっていなかった。
「そうなった時、私はベッドで寝るから、河合さんはバスタブの中で寝てね」
彼女は悪戯っぽく笑ってそう続けたのだ。
どう考えても、『海がきこえる』を下敷きとした回答に思えた。
たくさん話はしたけれど、私がこの小説を好きで、何度も読み返したということは彼女に言っていなかった。
それなのに、まるで狙ったかのように私が望んでいた、いや切望していた青春シーンを現実に落とし込んでくれたことで、彼女との間に運命的なつながりがあるように錯覚させられたほどだ。
念のために、「バスタブにバスタオルを敷いて、毛布だけ持っていくんだよね」と、小説をなぞった言葉を口にしてみると、彼女は我が意を得たりといった満足げな笑顔で、「そうそう」と答えた。
やはり、『海がきこえる』を知っているからこその反応だと思った。おそらく彼女の方も、同じ物語を二人で共有していると気付いていただろう。
だから、もしそうでなかった場合、肩透かしによる受けるダメージが甚大になりそうで、私たちはそれを口に出して確認し合うことはなかった。
その夜に、それ以上何かがあったというわけではない。電車は通常通りに動いていたので、彼女は上り方面、私は下り方面のホームに向かい、それぞれ帰宅しただけだ。
そして、少し親しくなった彼女とも、私が奥手だったためか次第にすれ違いが増え、その日の夜が幻で合ったかのように疎遠となり、卒業の時を迎えてしまった。
それ以後この小説を読むたびに、主人公たちの爽やかな恋心と、私自身の淡い恋心とが重なり、余計に切なく、より強い憧憬をもって、二重の青春が胸に迫って来るようになった。
だから、私にとってこの『海がきこえる』という物語は特別であり続けるのだろう。
#読書感想文
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
