
中村隆文 『世界がわかる比較思想史入門』 : 〈客観的で柔軟な私〉という陥穽
書評:中村隆文『世界がわかる比較思想史入門』 (ちくま新書)
私の場合はこれまで、「宗教」の素人研究(宗教の批判的研究)として、キリスト教に取り組んできたから、キリスト教とユダヤ教についてはおおよそのことを知っていたが、イスラム教はかじった程度だったので、その部分はとても参考になったし、面白かった。また、これもごく最近になってだが、「仏教」の勉強も始めたので、「インド思想」や「日本思想」の章は、大まかな見取り図(今後の叩き台)として、とても参考になった。一方、まったく手をつけていなかった「中国思想」の章は、ぼんやりとしたイメージしかなかったものについて、明確な整理を与えられて、とても興味深かった。「西洋哲学」についても、ひとつの見取り図としてわかりやすく、とても良かった。
つまり、これまでバラバラに(非体系的に)勉強してきたことに、大まかな見取り図として関連づけてもらえ、とても面白く、ありがたい一冊だった。これが、私個人の率直な感想である。
一一ただし、注文をつけておきたい点もある。
まず、本書を「入門書」として読んだのでは、あまり面白くないのではないか、ということだ。
入門書というのは、平易だが、だいたい面白くない。というのも「神は細部に宿る」と言うとおりで、本当に面白いのは、簡単には整理することのできない、細部であり、矛盾を孕んだ複雑微妙な部分だからだ。
例えば、キリスト教であれ仏教であれ、「この宗教は、こうだ」という大筋での説明は、わかりやすいし間違いではないのだけれども、それだけではぜんぜん面白くない。
同じキリスト教と言っても、いろいろな教派があり、意見の対立矛盾があるからこそ、その矛盾点において、その宗教宗派の「(絶対神の真理ならぬ)人間的な側面」が浮かび上がり、その隠された本質も浮かび上がってくる。
だから、これから、宗教を含む思想というものを勉強しようという人は、こうした入門書から入ろうとするのではなく、ひとつ狙いを定めて、それをある程度研究した後に、それとは立場を異にする思想を対比的に学び、それから本書のような「見取り図」本を読むと、きっと面白いだろうし、研究対象の理解も深まるのではないだろうか。
一番いけないのは、こうした「入門書」で、全体的な「本質」をいっきにつかんだ気分になってしまうことなのだ。「便宜的な簡易図式」が、その後の研究の「先入主」となってしまうことなのである
さて、そうした観点から、本書で注目すべきは、それまでの各種思想を紹介した本章とは違って、著者自身が前面に出てくる最終章「おわりに」と「あとがき」における、著者の「思想」である。
著者はこの二つの章において、「比較思想史」を学ぶことで、どのような視界が開けたかを紹介し、自身の「思想」を語っている。
簡単に言えば、「おわりに」では、
(1)色々な思想的立場を、フラットに俯瞰することで、思い込みや偏見から自由になる。
(2)特定の思想に依り頼んでそれを護持するのではなく、そこから自由になることで、自分の思想が持てる。
(3)「私の思想」とは、他者の価値観に縛られない、自身の見出した価値を信じる(かと言って、独善でもない)思想だと言える。
(4)そうした「私の思想」を生きることこそが、そのまま「行」なのだ。
といった、著者の考える「思想における生き方」が、ハイデガーの「死に先駆する」という考え方に準拠して語られる。
そして「あとがき」では、その具体的な姿として、自身の「父親の死」という体験を通して知った、「特権的な、私個人の体験に生きる」という、著者の「思想」を語っている。
だが、私は、この「あとがき」で示された、「著者の思想」に引っかかった。
一一「えっ、最後はそこなの?」という、どこか裏切られた感じがしたのだ。
結局、本書著者が言うのは、色々な立場を俯瞰して独善を排するならば、「独善にならない個人主義」が最も正しい、というような話になのではないか。しかし、その立場には、どうにも無理が感じられる。
と言うのも、著者はいろんな「思想(宗教を含む)」を研究し、その一長一短を比較考量した上で、どれにも没入(全肯定)しないかわりに、どれも否定しない、という「バランスのとれた立場」を選択した。ここまでは、常識として誰もが納得できるだろう。
しかし、そのあとに、「どれでもないから、残るは、私個人の思想」一一というのは、おかしいのではないか。
というのも、どんなに偏頗な信仰や思想に凝り固まった人でも、その人本人の主観としては「私は、客観的かつ公正に判断した結果として、この立場を選んだ」と感じているだろうからだ。つまり、そうした「無自覚に依存的な立場」もまた「私の立場」と主観されているのである。
では、こうした「主観的に、客観的かつ公正に選択された(と信じている)立場」と、本書著者の「全体をフラットに鳥瞰した上での、客観的かつ公正な判断としての、私個人の思想」とは、どれだけ違っているだろう。
例えば、著者は、自身の「父の死」を普遍化し得ない「特権的な(私的)体験」として、そのような「特権的な体験」に生きることこそが「正しい」と主張してしまっている。また、そうした立場から「他者の生にも関与する」と言っているが、これでは「個人的に神の啓示を受けた私は、その立場から、他人に関与している」というのと、どれだけ違うと言えるだろう?
一一私は、同じだと思う。
つまり、著者の「全体をフラットに鳥瞰した上で」というのは、実際のところ、極めて「個人的なアリバイ作り」にしかなっておらず、そんなことは、どんな宗教者や思想家でも、多かれ少なかれやっていることなのだ。ただ、それに「比較思想史」という学問形態が与えられていないだけなのである。
だが、本書著者は、その見えやすい「形式」に、自ら目を眩まされ、そこに安住してしまったのではないか。
著者が、在籍する「神奈川大学」のホームページに「神大の先生」というページがあり、本書著者はそこで、自身の考える「哲学」の意義と学びの姿勢を、学生に向けて、次のように語っている。
『現在の担当講義「哲学」では、さまざまな観点から人間や生き方について掘り下げ、自分を知ることの重要性を考えていきます。哲学に難解なイメージを持つ人もいますが、哲学は、自分の中に生じたさまざまな「問い」について、深く考えることで答えを導き出していく学問です。私自身の経験から言えば、その過程で多くのことを勉強しながら知見を重ね、柔軟な思考力を身に付けられたように思います。』
という部分があるのだが、ここには著者の考え方が、とてもよく表れているように、私には思えた。
特に『さまざまな観点から』『多くのことを勉強しながら知見を重ね』『柔軟な思考力を身に付け』られた、としている部分だ。
言うまでもなく、ここに表れているのは「全体をフラットに鳥瞰した上でなら、既成の何物にも縛られない(反硬直=柔軟)で、穏当な「私の思想」を手にすることができる。これが正解だ」という「哲学」観である。
しかし私は、ここに「比較思想史」という「鳥瞰視」に立つ人の、「虫の視点」あるいは「細部に宿る神」という視点のへの軽視、ハイデガー風に言えば「投企」の軽視を感じずにはいられない。
またその結果として、著者は「特権的な私の経験」の思想という、ごく「当たり前に主観的な思考」の、個人的な自己正当化に陥ってしまったのではないかと感じずにはいられないのである。

繰り返すが、どんな「権威」に寄りすがっているように見える人の「(党派的な)思想」だって、その人の主観では「私が、私の実感に従って、客観的かつ公正に選んだ、私の思想」なのだし、その意味で本書著者は、安易に自分の立場(だけ)を、特権化しているだけにしか見えないのである。「自分は、比較思想史をやっており、客観的で公正に判断し(え)ている」と。
つまり、私が言いたいのは、「客観的で公正」であるように努めるというのは「当たり前」のことであり、誰しもそれなりにやっていることでしかない、ということなのだ。
しかし、それでも、そうしたものの多くは、客観的には(他者から見れば)しばしば「主観的・独善的」に見えてしまうという事実があるし、だからこそ「比較思想」なんてものだって可能になる。
したがって、ここで必要となるのは、人はいくら「客観的かつ公正」であろうと努力しても、他人から見れば、それは「その人の(個人的)思想」でしかない、という事実を認め、それを「他者の(そして自身の)現実」としてその重みを引き受けた上で、それでも是非善悪「判断」を語るという「責任」を引き受けなければならない、ということなのだ。
主観的に「公正中立」であろうとすることと、客観的に「公正中立」であることとは、同じではあり得ないということを、我がこととして肝に命じていれば、著者のような「比較思想史」をやってますから「客観的で公正」であり、だから「私の思想は、(他の人たちとは違って)独善ではない」といったような語り方にはならない、ということである。
そして、こうした著者の「独善的」な「私の思想」が、なんとなく成り立っているようにも見えるのは、結局のところ、著者が「自身を特権化して、結果的に他者の立場を下げる」ことはしても、他者に向かっては「それもいいですね」みたいな、無難な物言いに終始するからであろう。
「どの立場にも、一長一短がある」という主張は、どんな立場もすべて「不完全だ」と内心ではそう思いながらも、口では「どれも素晴らしい長所を持っていますね」などと耳障りのいいことを言える、世渡り上手な(ずるい)立場だとも言えるのである。
しかし、そんな「安全圏からマニュピレーターを使って、無難に研究する」ような態度(鳥瞰的観察評価)で得られるものとは、所詮は「解説屋の思想」にしかならないのではないか。
「自分の(個人的)立場」というものを、さも選択していないかのごとく語って、「個人的立場の責任の引き受け」を回避しているような者の思想とは、自ずと、その程度のものに止まらざるを得ないのではないのか。「遠巻きにして感想を語る」ような思想が、「参考」にはなっても、実存の重みを欠いた、軽い思想にならざるを得ないのは、理の当然なのではないだろうか。
「神は細部に宿る」というのは、「細部にまで没入する」危険に、一度は身をさらす覚悟において、真に「私の思想」というものが得られる、ということなのではないか。
著者自身の「無難かつ優等生的で、ごく当たり前の思想」に、良くも悪くも「魅力」がないのは、そういうことなのではないだろうか。
初出:2021年2月12日「Amazonレビュー」
(同年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年2月25日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
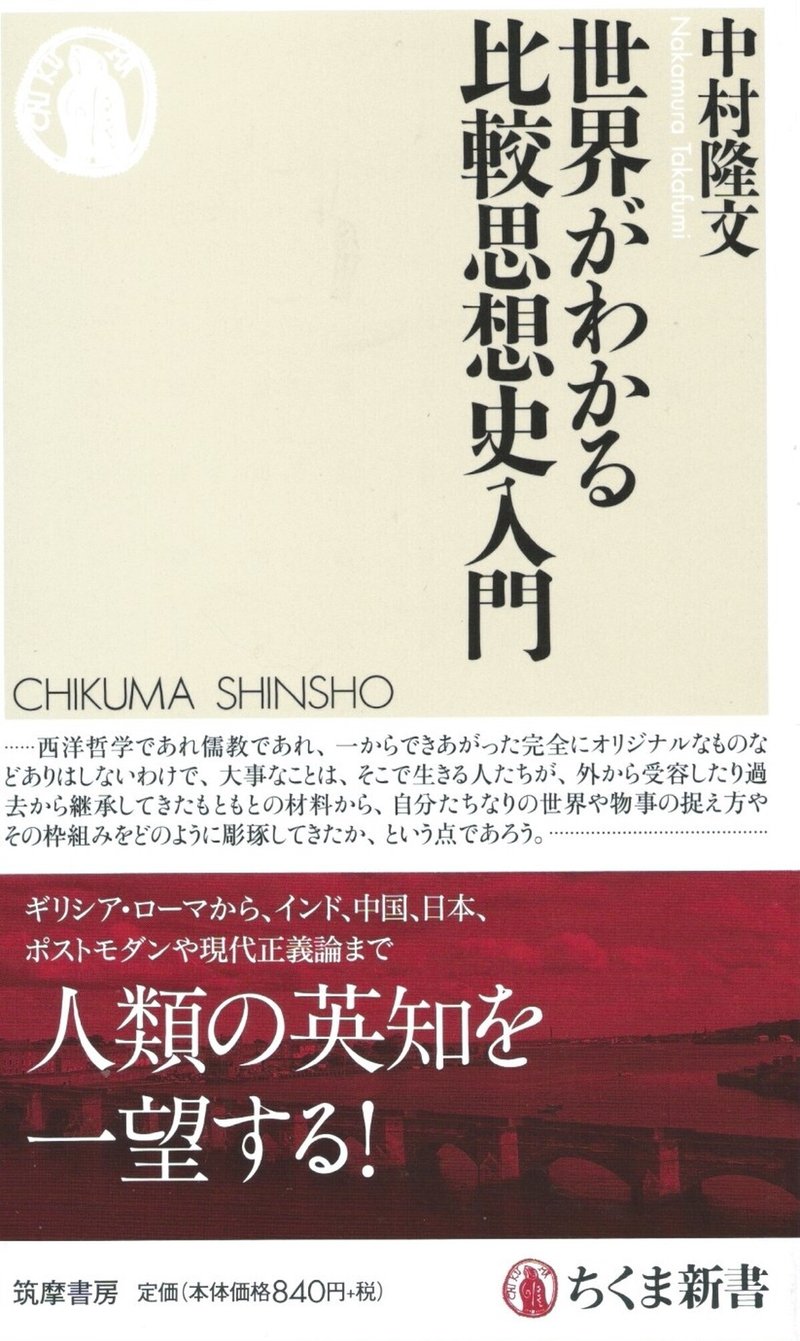
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
