
渡辺照宏 『仏教 第二版』 : 学問の陰の〈信仰〉的無自覚
書評:渡辺照宏『仏教 第二版』(岩波新書)
仏教学者による「仏教」の概説書で、当然のことながら、著者は「学者」として本書を執筆した、と主張している。
『 仏教とは何か、という問いに答えるのが本書の仕事である。仏教について語るべきことはあまりにも多いから、答え方もさまざまであってよいが、あらたに執筆するにあたって「岩波新書」の読者を予想して次のような方針を立てた。
本書を通読すれば仏教についてひととおりの基本的な知識が得られるように工夫する。どうしても必要なテーマを落とさないように注意する。叙述をできるだけ平易にして、予備知識なしに読めるように気をつける。それと同時に、内容については専門学者の批判に耐え得る水準を保ち、学問的に責任の持てることのみしか書かない。仏教において人生の指針を求める人びとの手引ともなる。学生や研究者の参考書としても役に立つ。
ところで、過去二千年以上にわたってアジアの広い地域で行なわれ、現在も生きた宗教である仏教の種々相を満遍なく述べることは不可能であるし、また、その中の特定の立ち場を擁護することも許されない。』(「まえがき」より)
このように、著者は、自身を「信仰者」ではなく「学者」であり、「学者」として、本書を「公正中立な立場」から書く、と言明している(『特定の立ち場を擁護することも許されない。』とは「特定の立ち場以外の立ち場を、意図的に批判することも許されない」ということになる)。そして、そうした「自制」を十分に為し得なかったとも書いてはいない。
つまり、著者に嘘をつく意図ないのであれば、著者は本書を「公正中立な立場」で書き得たと信じていた、ということになるのだが、果たして現実にはどうであったか。
結論としては、ぜんぜん「公正中立」になってはおらず、自覚的にか無自覚にかはわからないが、とにかく、自身の「信仰」に偏った説明を開陳展開してしまっている、と言えるだろう。
わざわざ「まえがき」に「公正中立」たらんことを言明していながら、それが実際には出来ていないのであるから、これは学者として「恥ずべき仕事」だと評価せざるを得ないし、著者はそれを恥ずべきである。
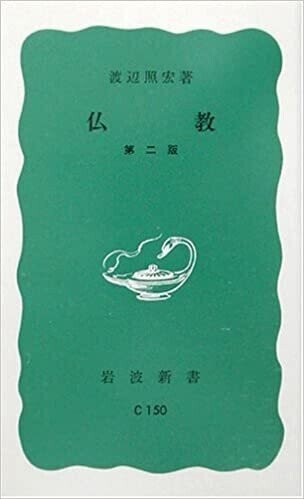
しかしながら、著者はすでに鬼籍に入っているから、自らの不明を恥じて訂正し、学者として責任を取ることもできないので、ここでは生きている者の務めとして、著者の「不適切」な仕事ぶりを指摘して、厳しく批判しておきたい。
『 日本人の生活の中に仏教はどのように生きているのであろうか。あるいはむしろ、いったい今でも生きているのかどうか、と問い直すべきかも知れない。もし肯定的に答えるとすれば、大多数の日本人が死ねば仏教の儀礼によって葬られ、遺族が定期的に墓参し法事を営むという事実を第一に指摘すべきであろう。あるいはまた、大部分の家庭に仏壇が設けられ、必要があればいつでも百貨店でそれを購入することができる、というのも事実である。さらにまた、仏教に関する単行本や雑誌が多く刊行されて、相当に売れているし、寺院及び寺院以外における説教や講演の集会も盛んである。また、座禅やその他の実践に参加する人びともいる。
これに反して、仏教は現代の日本人の生活の中に生かされてはいない、という見方も不可能ではない。たとえば日本には仏教の立場に立つ政党というものはない。特定の宗教団体を背景とする政党があるとしても、実際の政治活動からみて、仏教の理想を実現するための政党であるとは思われない。それ以外の仏教団体でも組織的に票を集めれば政治的な一勢力となり得るはずではあるが、現実には仏教を政治に生かすという試みはない。』(P1〜2)
本書冒頭の一文だが、果たしてこれを「公正中立」な評価を語った文章だと言えるだろうか。
後半部分の『日本には仏教の立場に立つ政党というものはない。特定の宗教団体を背景とする政党があるとしても、実際の政治活動からみて、仏教の理想を実現するための政党であるとは思われない。』という「意見」は、明らかに「(創価学会=)公明党」の仏教政党としての性格を、真っ向から否定するものだが、その根拠は示されておらず、単なる「断言(決めつけ)」だけである。
「公明党」を「仏教政党」と評価するか否かは、それぞれの価値観だから、著者が「個人的な意見」を述べること自体は否定されるべきではないし、私もそれを批判しているのではない。
私が批判しているのは、著者がわざわざ「まえがき」で「公正中立」を宣言しておきながら、開巻早々それに反していることの方なのだ。(そもそも、象牙の塔の仏教学者である著者が、創価学会や公明党の現場を、どれだけ研究し、知った上で、このように断言したのであろうか)
もちろん、いかなる価値判断も語らずに、事実だけを記するというのは、実のところ容易ではないし、不可能に近いことだとさえ言えるだろう。だから、著者が「公正中立」をわざわざ宣言していたとしても、それでもある種の価値判断を語ることを、私は必ずしも否定しない。だから、著者が「公明党」を「仏教政党と認めない」という意見を、本書において表明することも、否定する気は無い。
ただし、批判否定するのであれば、「論理的な根拠提示」が是非とも必要だろうし、それをしてこそ「学問」であり、「公平中立」性も担保できるのではないか。
ところが、前述のとおり、著者は「公明党」を「仏教政党」と認めないという自身の「意見」について、何の根拠も示してはおらず、ただ「断言しているだけ」であり、さらに悪質なのは、誰が読んでも、この文章で批判されているのが「創価学会=公明党」であると気づくかたちで書いていながら、批判した相手を「名指し」しないという「誤魔化し」によって、公的な批判的言論としての責任を回避をしている点である。
言うまでもないことだが、批判するのであれば、正々堂々と相手を名指しし、根拠を示して批判するのが、「人間」としての(さらには「言論人」としての)倫理ではないか。「学者」であることを云々する以前の問題として、著者のこの姑息な批判は、単なる「あてこすり」や「陰口」の類いでしかなく、これは人として恥ずべき行いなのではないだろうか。
そして、この部分を「創価学会へのあてこすり」であると判ずるならば、その前の部分、すなわち『日本人の生活の中に仏教はどのように生きているのであろうか。』と問うた上でなされる、
(1)『大多数の日本人が死ねば仏教の儀礼によって葬られ、遺族が定期的に墓参し法事を営む』
(2)『大部分の家庭に仏壇が設けられ、必要があればいつでも百貨店でそれを購入することができる』
(3)『仏教に関する単行本や雑誌が多く刊行されて、相当に売れているし、寺院及び寺院以外における説教や講演の集会も盛んである。また、座禅やその他の実践に参加する人びともいる。』
といった「事実」に関する指摘もまた、単なる「客観的な事実」の指摘などではなく、著者の「個人的な仏教観」によって、暗になされた「批判」としての「あてこすり」や「皮肉」の類いだと解して、間違いないだろう。
要するに、(1)は「葬式仏教」批判、(2)は「商業主義仏教」批判、(3)「カルチャー教室仏教」批判である。
「仏教」をインドにまで遡って研究した、渡辺照宏先生には、創価学会は無論、こうした通俗文化化された仏教など「仏教ではない」ということなのだ。
しかし、あえて問うが、「源流遡行の恣意的な切断」なくして「本当の仏教」などというものが存在し得ると、著者渡辺は、本気でそう考えているのであろうか。
私が思うに、実際に存在する「仏教」とは、時代につれ場所につれて変化していった、いろんな仏教しかないのではないか。
もちろん、相互の比較において、宗教や哲学や倫理としての優劣はあるかもしれないが、特権的な「本当の仏教」などというものが、特定できるものなのか。また、あえて特定したとすれば、それはどんな「資格」において可能なことなのであろうか。
私としては「本当の仏教」などというものは、客観的には存在しない、としか思えないのだが、いかがなものであろう。
もちろん、何度も言うように、どんな「意見」があってもかまわない。一一と言うか、今となっては、渡辺照宏先生のご意見は、ごく常識的なものであり、いっそ通俗的なものであると言っても過言ではなかろう。そして、そうした意味では、大西巨人言うところの「俗情との結託」による「他宗批判」だと言ってもいいだろう。
著者の渡辺照宏は、「学者」という「肩書き」とその「権威」において、自身の「他宗批判」を、「公正中立」で「客観的な根拠」にもとづいた「学問的な批判」であるかのように見せかけている。
しかし、実際のところはそれは、そんなご立派なものではなく、良くて自覚的、悪ければ無自覚な「御用学者」の仕事でしかない。
そうした現実は、著者の経歴と、その著作の内容を突き合わされば、自ずと明らかとなる。
『成田山東京別院深川不動尊監院渡辺照叡の子として生まれる。1930年(昭和5年)3月に東京帝国大学文学部インド哲学科を卒業する。卒業と同時にドイツに留学し、エルンスト・ロイマン(Ernst Leumann)らに師事し、1933年5月帰国。
1935年(昭和10年)3月に東京帝国大学大学院を修了する。
教授歴は1935年4月 - 1943年3月智山専門学校教授(現:大正大学)。1943年9月 - 1945年10月、文部省民族研究所所員。1946年4月 - 1948年3月連合国軍最高司令官総司令部民間情報局宗教調査課勤務。1948年4月 - 1953年3月九州大学文学部助教授(ただし病気のため赴任せず)。1956年4月 - 1969年3月東洋大学文学部教授。1975年10月成田山仏教研究所参与・理事・主席研究所員。
インド哲学・仏教学を専攻。語学にも非凡な才能をあらわした。1948年2月発病、その後も闘病生活を送りつつ研究と著作を続けた。『私の読書法』(岩波新書、初版1960年)の収録エッセイに、病床での読書の様子がしのばれる。弟子の一人宮坂宥勝の『密教への誘い』(人文書院)に追悼評伝がある。
弟にホフマンの「胡桃割りと鼠の王様」(『ホフマン全集』三笠書房、1936年)を翻訳した永井照徳(1945年にミンドロ島にて戦死)、息子に編集者・智山派僧侶渡辺照敬や、インド哲学研究者の渡辺重朗、書家の渡邉真観がいる。』
(WIKIpedia「渡辺照宏」の「略歴」)
ここで問題になるのは、もちろん、渡辺が『成田山東京別院深川不動尊監院渡辺照叡の子』であり、『息子に編集者・智山派僧侶渡辺照敬』がいる、といった事実だ。
では、『成田山東京別院深川不動尊』の宗派はというと、
『成田山 東京別院 深川不動堂(なりたさん とうきょうべついん ふかがわふどうどう)は、東京都江東区富岡にある真言宗智山派の寺院』
(wikipedia「成田山東京別院深川不動堂」)
ということになる。

つまり、本書著者の渡辺照宏は、弘法大師「空海」を開祖とする「真言宗」の寺院の息子だったのだ。
だが、本書「奥付け」の著者紹介に、そんな事実は一言半句書かれてはいないし、著者自身もそれを明らかにしてはいない。
もちろん、著者が「真言宗の寺院の息子」であろうと、学者になったからには、自他の信仰について「中立公正」で「客観的」な態度を保っているかぎり、それはそれで「学者として当然の義務」ではあるものの、立派な態度だと褒めてさしあげてもかまわない。
私は、「宗教」というもの関しては「キリスト教」を選んで研究をしたのだが、キリスト教の学者というのも、その多くはクリスチャンであるし、それは西欧世界においては、ある程度はやむを得ないことだとも思う。しかしながら、問題なのは、彼らの多くも、自分の信仰を明示することが少ないという事実なのだ。
無論、ある程度、読み慣れてくれば、この学者はカトリックだな、この人はプロテスタントだなといったことが見えてくるようにはなるのだが、それにしても読者に対して、学者として「公正」たらんとするのならば、問われる前に、きちんと自分の「宗教的出自」を読者の前に提示して、評価の用に供するべきなのではないだろうか。そして、自身が、学者として「公正中立」で「客観的」な態度を保持し得ているという自信を持っているのであれば、自身の「宗教的出自」を読者に隠す必要などないのではないだろうか。
しかし、実際には、彼らの多くはそれを明示しないし、それが「宗教学」業界の「悪しき慣例」ともなっているようで、キリスト教研究だけではなく、仏教研究の場においても、本書著者のように、自身の「宗教的出自」を明示しないまま、「学者」という「肩書きの権威」のみにおいて、いかにも自分が「公正中立」であり「客観的」であるかのように、偽っているのである。
実際、本書における「真言宗」の扱いがどのようなものであるかを確認すれば、著者が「真言宗の御用学者」だと謗られても仕方のない記述をしていることが、容易に確認できるだろう。
もちろん、前述のとおり、著者は「学者」という立場上、「公正中立」「客観的」であるかのように見せかける努力をしてはいるのだが、それは「欺罔行為」の域を出るものではないし、だからこそ、私のような素人にすら、見透かされてしまうのである。
ちなみに、本書『仏教 第二版』よりも後に刊行された、同著者の『日本の仏教』では、忌憚なく「他宗批判」がなされているようで、同書のAmazonレビューを見てみると、それを「痛快」だと喜んだ読者もいたようだが、しかし、果たしてそういう読者は、著者の「真言宗の寺院の息子」をいう「宗教的出自」と、著者自身の「(内心の)信仰」を勘案した上で、著者の「意見」が「学術的客観性」に基づいてなされたものであると「確認確信」して、そのように高く評価したのであろうか。
言うまでもなく、カトリック信者の学者が書いたキリスト教の研究書は、どうしてもカトリックに好意的なものになっているし、プロテスタント信者の学者が書いたキリスト教研究書もまた、カトリックほどではないにしても、党派的な偏りがないわけではない。少なくとも「無神論者のキリスト教研究者」の書いたものの方が、比較的「価値中立的」なのは間違いのだが、そうしたことは、「仏教研究」においても全く同様なのだということを勘案し、読者は「逆の立場の意見」を突き合わせてみた上で、判断したのであろうか。
一一しかし、そんなことをする読者なら、研究書に「痛快さ」を求めたりはしないだろうし、そうした点を、高評価の要素とはしなかったはずなのである。
ともあれ、本書著者である渡辺照宏が(公然たる真言宗信徒であれば無論)「隠れ真言信徒」なのであれば、真言宗への評価が、他の宗派に比較して「甘い」というのは、わかりやすい話でしかないし、まして「真言亡国」などと言った日蓮への評価がことさら厳しくなり、創価学会への評価が辛辣になるのも、「人間」的なものとして、いかにも理解しやすいところであろう。
しかしながら、それが、「学者」としては「恥ずべきこと」であるというのも、論を待たない事実なのだ。
本書のレビューをチェックしてみたところ、誰も著者である渡辺照宏の「宗教的出自」に触れてはいなかったのだが、果たして誰も渡辺の「ポジショントーク」に、違和感を感じなかったのであろうか。それとも、自分の立場に近いと感じたから、疑問も持たずに、それで共感支持したのであろうか。
だが、学問というのは「そんなものではない」と私は考えるのだが、読者諸兄はどうお考えなのであろう。
ちなみに、私自身について書いておけば、私は元創価学会員である。
しかし「だから、日蓮や創価学会に厳しい著者に厳しかったのか」と早合点した人は、人間というものがわかっていない。
私は、創価学会のダメさを知ったからこそ、創価学会を批判して辞めた人間なのだから、その意味では、外野のアンチ創価の方より、よほど本質的に反創価である。
しかし、私は創価学会の信仰の誤りを知ったればこそ、単なるアンチ創価であるに止まらず、「信仰とは何なのか」という本質的な問いへと向かい、無神論者になっても、「宗教らしい宗教」としての「キリスト教」の、批判的研究を始めたような人間だ。
つまり、私の「宗教研究」は、「宗教(信仰者)内党派闘争」などではなく、「人間学」なのである。だからこそ、著者のような、「学者」を騙る、中途半端な「信仰者」には我慢ならないのである。
○ ○ ○
私が本書を読もうと思ったのは、著名な宗教学者である中沢新一と、伝奇アクション小説家の夢枕獏、真言宗の僧侶で「中沢新一の弟子」を名乗っていた宮崎信也の3人による、対談・鼎談本『ブッダの箱舟』を読み、その中で宮崎が「仏教の勉強を始めるのなら、渡辺照宏先生の『仏教』や『日本の仏教』などから入れば間違いない」という趣旨のことを語っていたからである。
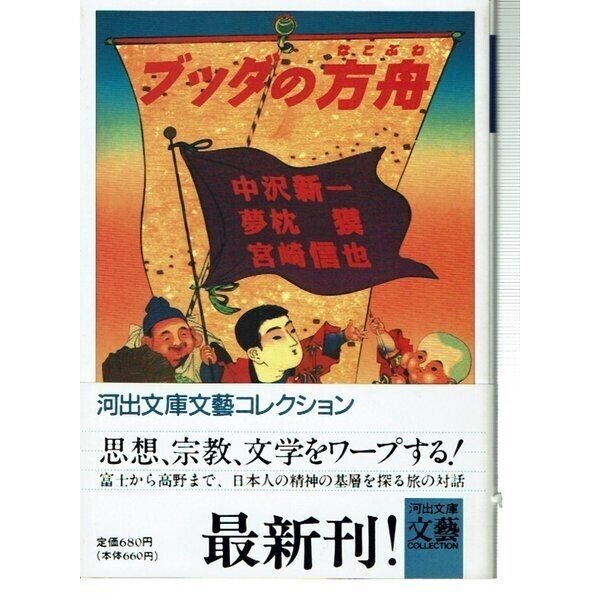
しかしこれは、宮崎の言葉を真に受けたということではなくて、空海に好意的な3人の鼎談において、中沢と宮崎が、半ば当然のこととは言え、日蓮について否定的だったのを見て「この人(宮崎)が推奨する学者とは、どんな学者なんだろう」と、興味を持ったからである。
そして、読んでみれば予想どおりに、渡辺照宏もまた日蓮に批判的であり、さらにあろうことか「真言宗の寺院の息子」であることまで判明した、という次第。一一結局、宮崎信也の渡辺照宏に対する高評価も「党派的な評価」でしかなかった、のである。
そして、この『ブッダの箱舟』が刊行された頃、若手宗教学者でありポストモダン批評家として人気の絶頂にあった中沢新一は、同じ頃「オウム真理教の麻原彰晃」を高く評価していたことが、数年後に問題とされ、厳しい批判にさらされることになる。
中沢は、チベットで密教の修行をした人なので、同じ系列と言えなくもない麻原彰晃の超能力宗教に対しても、比較的好意的だったのであろう。

しかし、言うまでもなく、「党派的な評価」というものは、「中立公正」でも「客観的」でもない、「非学問的」あるいは「反学問的」な、感情的評価(身内褒めの一種)だと言わなければならない。
世間の人は、「学者」というものが「中立公正」で「客観的」だと思い、その「権威」を信じがちだが、実際のところ学者も「人の子」であれば、「党派的恣意性」に流され「身内褒め」に走ることも、決して珍しくないのだという事実を、私たちは肝に銘じて知っておくべきだし、まして「オウム真理教事件」を通過した日本人は、「宗教」に対して、(その「研究」も含めて)もっと慎重であるべきなのではないだろうか。
初出:2020年12月24日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
