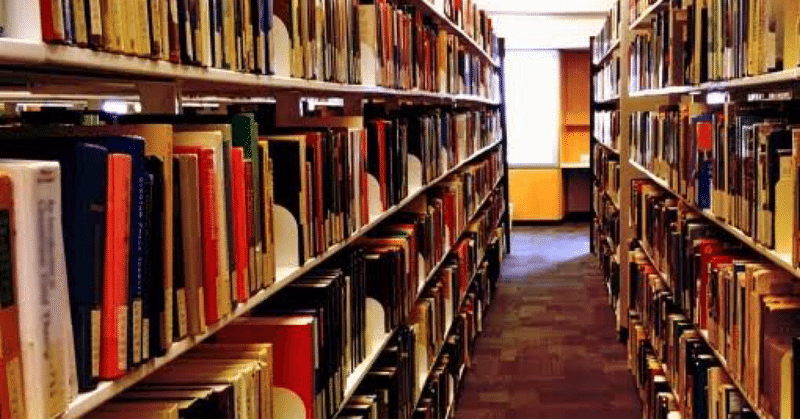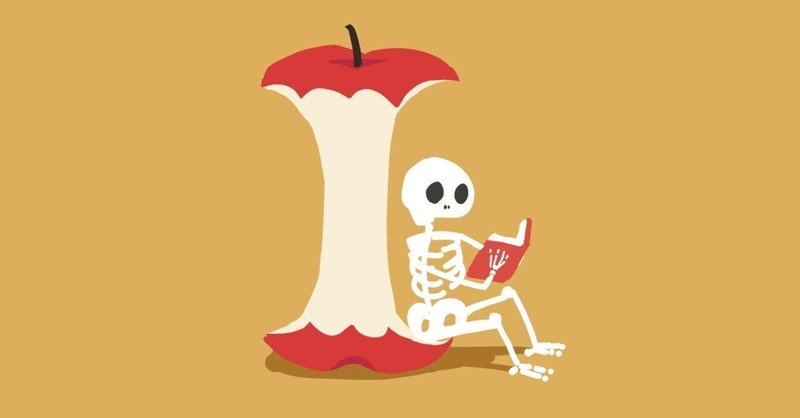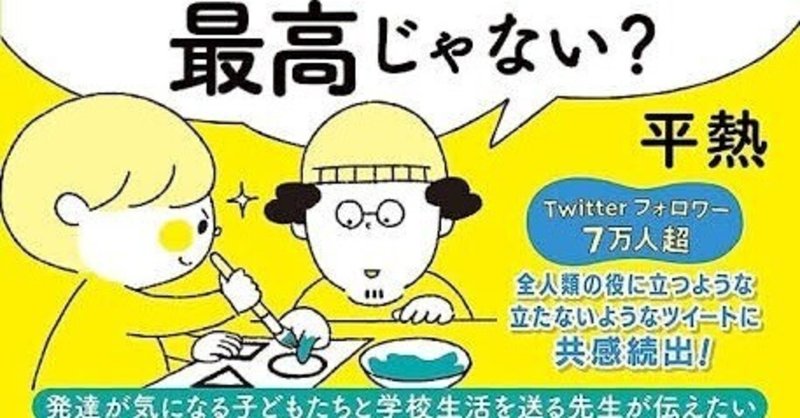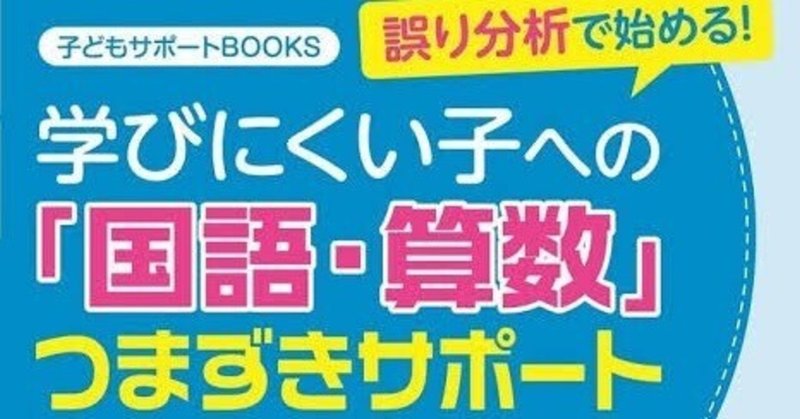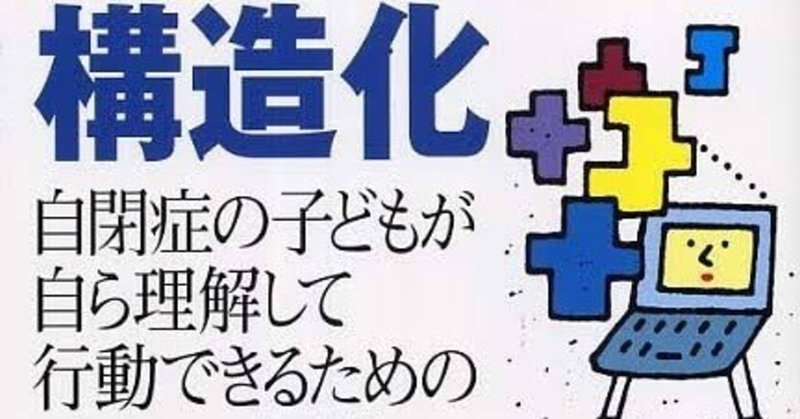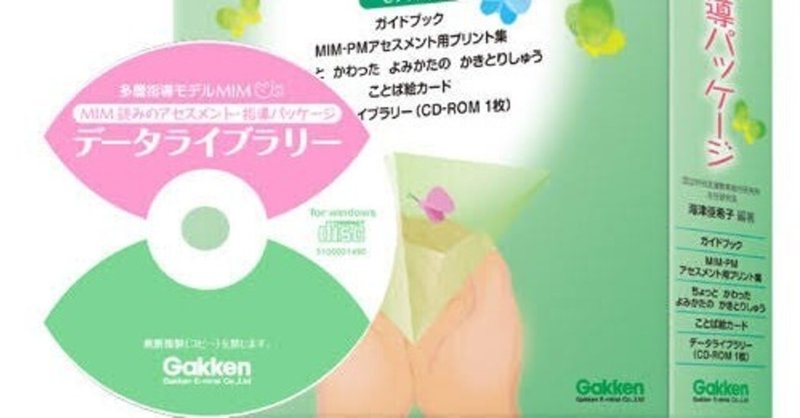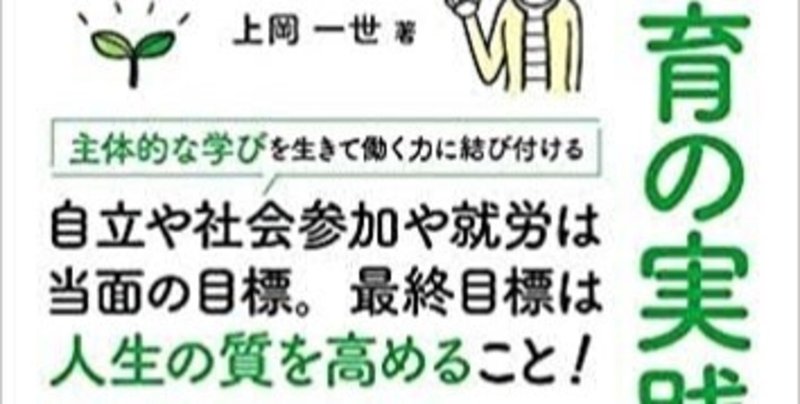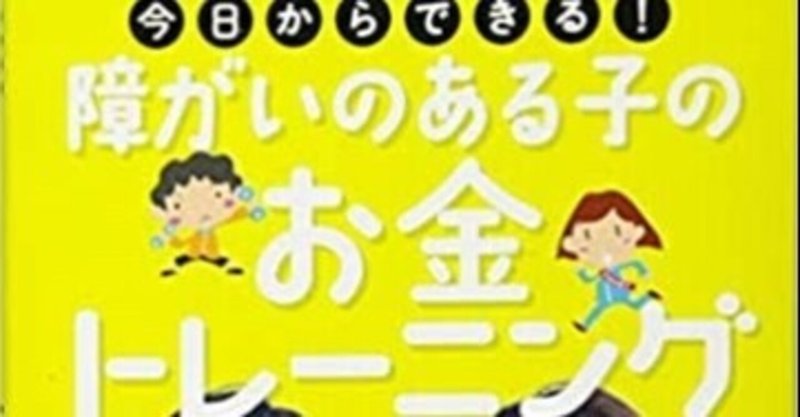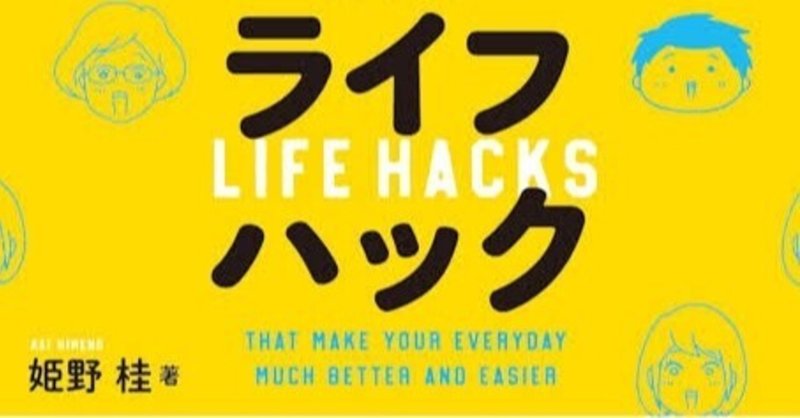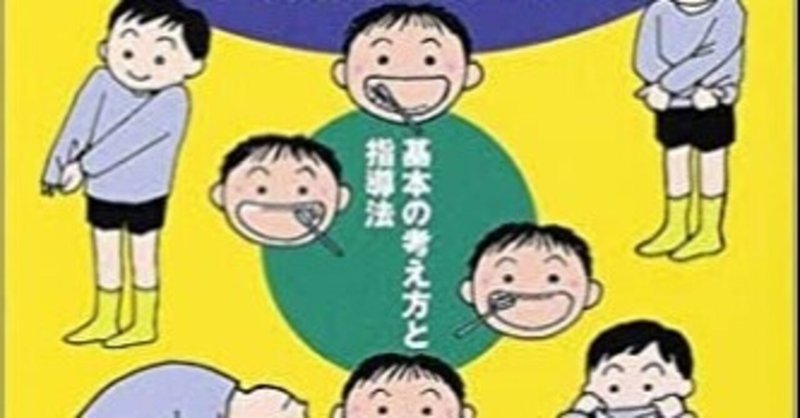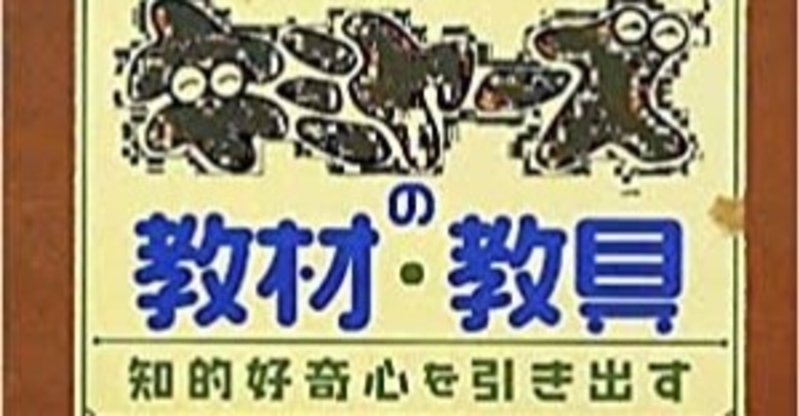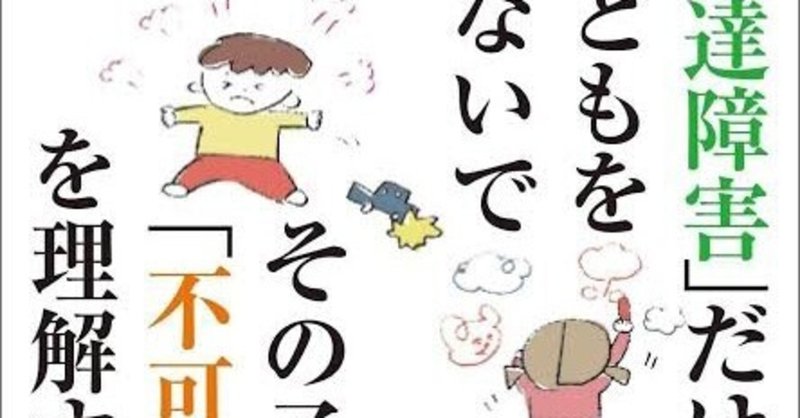#特別支援教育
書籍紹介『「ここ塗ってね」と画用紙を指差したわたしの指を丁寧に塗りたくってくれる特別支援学校って最高じゃない?』
『「ここ塗ってね」と画用紙を指差したわたしの指を丁寧に塗りたくってくれる特別支援学校って最高じゃない?(平熱)』という本の紹介です。
平熱先生の2冊目の本が出ましたよー以前に平熱先生の処女作『特別支援教育が教えてくれた 発達が気になる子の育て方』について記事で紹介しました。
その記事からもわかるように僕は平熱先生の大ファンです。2冊目の話を耳にしてすぐにAmazonで予約しました。もちろんです
書籍紹介『誤り分析で始める!学びにくい子への「国語・算数」つまずきサポート』
『誤り分析で始める!学びにくい子への「国語・算数」つまずきサポート(村井 敏宏/山田 充)』という本の紹介です。
間違いは発見の宝箱以前から研修会で「子どもたちの間違いは宝物です」「間違いを見ると、その子がなににつまずいて、なぜ間違えたのかがわかります」とよく聞く機会がありました。
僕自身も子どもたちに関わる中で「この子の中ではどういう理解をしていて、なににつまずいているのか」「この子がわかる
書籍紹介『自閉症児のための絵で見る構造化』
『自閉症児のための絵で見る構造化(佐々木 正美/宮原 一郎)』という本の紹介です。
構造化とは?構造化とは、主に自閉スペクトラム症(ASD)の子どもやその家族の支援を目的として開発され、広く世界中で実践されている生活全般における総合的・包括的なプログラムであるTEACCH(Treatment and Education of Autistic and related Communication-
教材紹介【国語】『多層指導モデルMIM 読みのアセスメント・指導パッケージ』
『多層指導モデルMIM 読みのアセスメント・指導パッケージ』という教材の紹介です。
多層指導モデルMIMとは?「音読はできるのに意味を理解していない」「読み間違えが多い」「文字を抜かして読んでしまう、書いてしまう」など「学習につまづきのある子」のための「予防的支援」の多層指導モデルで、特殊音に特化した教材です。
図1 通常の学級における多層指導モデルMIM(Multilayer Instruc
書籍紹介『発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ』
『発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ(武田 鉄郎)』という本の紹介です。
この本も職場の先輩に貸していただきました。毎度毎度ありがとうございます。
子どもへどんな関わり方をしていますか?本では家庭や学校で比較的よく目にする3つの対応が紹介されています。
でもこれらの関わり方ってどうなのでしょうか?
確かに叱ったり、怒ったりといった力による指導(罰)によっては子どもた
書籍紹介『特別支援教育新学習指導要領を踏まえたキャリア教育の実践』
『特別支援教育新学習指導要領を踏まえたキャリア教育の実践(上岡 一世)』という本の紹介です。
この本も職場の先輩に貸していただきました。いつもいつもありがとうございます。
キャリア教育ってなんだ?キャリア教育やキャリアプランニング・マトリックス、キャリアパスポートなど、巷ではキャリア教育という言葉が溢れているように感じます。
(画像は国立特別支援教育総合研究所より)
まずそんなキャリア教育
書籍紹介『発達障害かも? という人のための「生きづらさ」解消ライフハック』
『発達障害かも? という人のための「生きづらさ」解消ライフハック(姫野 桂)』という本の紹介です。
(画像はDiscoverより)
2019年3月31日に開催されたイベント「生きづらい けど生きのびたい!『発達ハック』コンテスト」にて、事前にTwitterで募集された、発達障害当事者や傾向がある方が「苦手なことをどうやって工夫して乗り越えているのか」というアイデアをコンテスト形式で紹介されまし
書籍紹介『発達につまずきを持つ子と身辺自立 基本の考え方と指導法』
『発達につまずきを持つ子と身辺自立 基本の考え方と指導法(湯汲 英史/武藤 英夫/田宮 正子)』という本の紹介です。
身辺自立という言葉を聞きなれない人もいるでしょう。食事、排泄、更衣、整理、手洗い、入浴、歯磨きなどなど身の回りのことを、必要なら支援や便利な道具を使ったり工夫したりしながら、自分ですることです。
当たり前のことは当たり前のことじゃない本のタイトルにあるような発達につまずきを持つ
書籍紹介『キミヤーズの教材・教具 知的好奇心を引き出す』
『キミヤーズの教材・教具 知的好奇心を引き出す(村上 公也/赤木 和重)』という本の紹介です。
この本はTwitterで紹介されているのを見かけて購入しました。
読んでみて…その内容は、衝撃の一言でした。
一見するとわけのわからない、イロモノと呼ばれてもおかしくない教材・教具の数々。そして毎度仮装姿の村上公也先生…でも読み進めていくと止められなくなる。
その理由はいくつかあるのでしょうが、
書籍紹介『「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する』
『「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する(田中 康雄)』という本の紹介です。
その行動ってなんなんだろう?発達障がいと呼ばれる子たちの、友だちに手が出てしまう、授業中座っていられない、生活習慣がなかなか身につかない、問題行動とされるそんな行動に対して「なんでそんなことするの!」「駄目でしょ!」と叱責してしまうことがあるかもしれません。
周りの大人もどうしたらいいのかわ